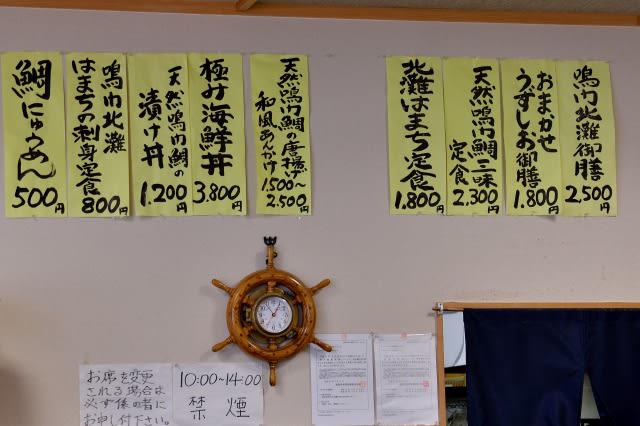草津温泉の一番の見所はこの湯畑である。畑と名がついているからには何か生産物が収穫できるのだろうか、何が取れるのだろうと思って検索してみた。
“湯畑(ゆばたけ)とは、温泉の源泉を地表や木製の樋に掛け流し、温泉の成分である湯の花の採取や湯温を調節する施設のこと”と書かれていた。そう
いう意味だとすると各地の温泉地にもあるはずだが、私は、ここ草津温泉のこの湯畑しか知らない。他の所はあってもこれほど大掛かりではないのかも知れない。



熱い温泉が流れている樋の下につららがある。気温が低い証拠?


撮影していた写真の中に草津町が作成した湯畑の説明板があった。
“湯畑(ゆばたけ)とは、温泉の源泉を地表や木製の樋に掛け流し、温泉の成分である湯の花の採取や湯温を調節する施設のこと”と書かれていた。そう
いう意味だとすると各地の温泉地にもあるはずだが、私は、ここ草津温泉のこの湯畑しか知らない。他の所はあってもこれほど大掛かりではないのかも知れない。



熱い温泉が流れている樋の下につららがある。気温が低い証拠?


撮影していた写真の中に草津町が作成した湯畑の説明板があった。