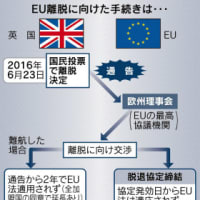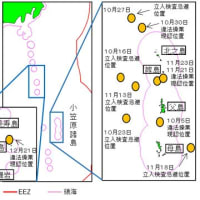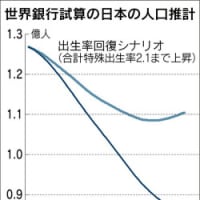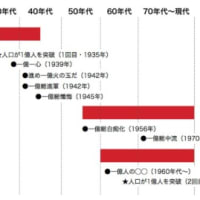手元に残した氏の著作は『評論集 詩的乾坤』(国文社(1974年)だけであった。読んで印象に残った本は他にも沢山あるはずだ。『詩集』『高村光太郎』『宮沢賢治』『西行』『源実朝』『共同幻想論』『評論集』…しかし、押入捜索はムダであった。そこで、残された一冊の評論集のどこが?と言えば、
「都市はなぜ都市であるかー都市に残る民家覚え書」(P312-321)なのだ。
この本の口絵として、手製の「谷中地帯変形略図」がカラー版の絵(表)とモノクロの手書き地図(裏)、として掲載され、続いて、<格子>戸、<格子>窓付きの民家の写真が4ページにわたって掲載されている。写真付きとは氏の諸作には珍しい。それ故、写真を示すことによってしか表現できないこだわりがあったはずだ。それは、この<格子>戸や窓付きの民家こそが、氏にとっての“都市”の原像だからだ[上掲書、口絵より]。
本文での締めくくりの言葉、「みずからは何ものも意味しないのに、存在すること自体が価値であるといったものがこの世界にたしかにありうる」(P321)。
これが「手製の略図」と「<格子>戸や窓の写真」と響きあっている。
<格子>戸や窓は、住人が自らと戸外とを連絡する意識を持っていることを象徴する。しかし、今、<格子>戸は開閉扉にとって代わられ、家族が孤立空間を欲していることを示している。これが民家の破壊度の尺度になる。
<格子>から始まり、<低い二階>、<袋小路>、<イエ・ヤシキ>をたどり、玄関先、軒端に置かれたみかん箱の<植込み>を<庭>と見なす知恵をいわゆる<名園>と拮抗せしめるべき、と指摘する。これが民家の様式である。
筆者の勤務先はJR浜松町駅から大門側へ少し入った近くにある。大小のビルが並ぶ合間に、旧い建屋の店なども細々と残っているが、個々に孤立して存在する程度である。また、とあるビルの脇に小学校があった旨の碑が建っていたりする。
ともあれ、当時も都市の膨張と機能が民家の様式を押し潰すことは止められない。それでも、「都市の民家が、高層ビルの窓の一個または数個に転化してしまうことをきみは肯定するか?」(P317)と問いかける。何故なら、氏がそれを愛惜するのは、懐古、伝統再発見の理念ではないからである。
「近代の展開がもとらした諸悪と諸善が、これらの民家とその住人の真うえをとおりすぎたにもかかわらず、いかなる意味でも爪跡をのこすことができなかったという証拠を、これらの民家が提供しているからである。」
「そこには不羈の貌と慰安と、ある意味でわたしが思想の基底とみなしているものとの合致する構えが存在している。」(P321)
ここには、氏が“大衆の原像”と表現した幻想の住人がいるのだ。「改めて近代という考え方を紹介した」という冷泉彰彦氏の解釈は、あったとしても、派生的なことである。
川崎市にはJR登戸駅近くの生田緑地に「民家園」がある。但し、ここには農村的風景にマッチする民家が並ぶ。土間があり、その一角に馬の居場所もある。薄暗く、藁の匂いが漂う。ここは生活・労働そのものが家の構えと合致しており、およそ都市の民家とは異なる。そこからみれば、<格子>の存在は文化的であり、生活の匂いは希薄である。吉本氏が描く都市の民家は、当然ながら氏にとっての生活の場であり、子ども時代の記憶に結びつくものである。
この巨大都市に残された民家に関する論考は、昭和44年(1969年)の年末近くに雑誌『都市 創刊号』に掲載された。高度経済成長のさなか、大学紛争の時期である。氏の生まれ育った月島、佃島辺りは、その時、遙かに変貌をとげていたはずである。
東京が巨大都市へ変貌した、その第一歩は昭和39年(1964年)の「東京オリンピック」である。筆者は神宮外苑にある高校へ入学した年で、新幹線が開通しただけでなく、京王線が新宿駅近くで路面電車から地下鉄に変わり、あるいは、明治神宮と隣り合わせていたワシントンハイツ(米軍家族宿舎)が、選手村に変貌した。
佃大橋ができて佃渡しが廃止になったのが昭和39年8月(東京さまよい記)。詩「佃渡しで」が作られたのはそのころだ(「吉本隆明全著作集1 定本詩集」(勁草書房))。以下、上記ブログから「佃渡しで」を転載させて頂きます。
佃渡しで娘がいった
<水がきれいね 夏に行った海岸のように>
そんなことはない みてみな
繋がれた河蒸気のとものところに
芥がたまって揺れているのがみえるだろう
ずっと昔からそうだった
<これからは娘に聴えぬ胸のなかでいう>
水はくろくてあまり流れない 氷雨の空の下で
おおきな下水道のようにくねっているのは老齢期の河のしるしだ
この河の入りくんだ堀割のあいだに
ひとつの街がありそこで住んでいた
蟹はまだ生きていてそれをとりに行った
そして泥沼に足をふみこんで泳いだ
佃渡しで娘がいった
<あの鳥はなに?>
<かもめだよ>
<ちがうあの黒い方の鳥よ>
あれは鳶だろう
むかしもそれはいた
流れてくる鼠の死骸や魚の綿腹(わた)を
ついばむためにかもめの仲間で舞っていた
<これからさきは娘にきこえぬ胸のなかでいう>
水に囲まれた生活というのは
いつでもちょっとした砦のような感じで
夢の中で堀割はいつもあらわれる
橋という橋は何のためにあったか?
少年が欄干に手をかけ身をのりだして
悲しみがあれば流すためにあった
<あれが住吉神社だ
佃祭りをやるところだ
あれが小学校 ちいさいだろう>
これからさきは娘に云えぬ
昔の街はちいさくみえる
掌のひらの感情と頭脳と生命の線のあいだの窪みにはいって
しまうように
すべての距離がちいさくみえる
すべての思想とおなじように
あの昔遠かった距離がちぢまってみえる
わたしが生きてきた道を
娘の手をとり いま氷雨にぬれながら
いっさんに通りすぎる
「佃渡しで娘がいった〈水がきれいね 夏に行った海岸のように〉…」から始まるなんとも言えない書き出しに、氏の叙情豊かな感性が柔らかく表現されている。娘の言葉から過去が蘇り、回想の叙情が、河、蟹、泥沼、堀割、橋、欄干…と展開される。しかし、回想の中で過去と現実の距離は縮まり、「…わたしが生きてきた道を娘の手をとり いま氷雨にぬれながら
いつさんに通りすぎる」。
通りすぎたあとの5年後に、谷中にみた現実の姿を都市民家論として描いているのだ。ここでは、回想のなかからではなく、現実に残された姿から自らの思想の基底を探り当て、都市と共に生き続けた民家の様式を位置づけている。
巨大都市・東京は新たなオリンピック開催に名乗りを上げ、リニア中央新幹線の計画も進めている。その中で、僅かに残る民家も壊される運命にあるが、それが吉本隆明という語り部を失った今、本当に消滅したと言えるのかも知れない。
「都市はなぜ都市であるかー都市に残る民家覚え書」(P312-321)なのだ。
この本の口絵として、手製の「谷中地帯変形略図」がカラー版の絵(表)とモノクロの手書き地図(裏)、として掲載され、続いて、<格子>戸、<格子>窓付きの民家の写真が4ページにわたって掲載されている。写真付きとは氏の諸作には珍しい。それ故、写真を示すことによってしか表現できないこだわりがあったはずだ。それは、この<格子>戸や窓付きの民家こそが、氏にとっての“都市”の原像だからだ[上掲書、口絵より]。
本文での締めくくりの言葉、「みずからは何ものも意味しないのに、存在すること自体が価値であるといったものがこの世界にたしかにありうる」(P321)。
これが「手製の略図」と「<格子>戸や窓の写真」と響きあっている。
<格子>戸や窓は、住人が自らと戸外とを連絡する意識を持っていることを象徴する。しかし、今、<格子>戸は開閉扉にとって代わられ、家族が孤立空間を欲していることを示している。これが民家の破壊度の尺度になる。
<格子>から始まり、<低い二階>、<袋小路>、<イエ・ヤシキ>をたどり、玄関先、軒端に置かれたみかん箱の<植込み>を<庭>と見なす知恵をいわゆる<名園>と拮抗せしめるべき、と指摘する。これが民家の様式である。
筆者の勤務先はJR浜松町駅から大門側へ少し入った近くにある。大小のビルが並ぶ合間に、旧い建屋の店なども細々と残っているが、個々に孤立して存在する程度である。また、とあるビルの脇に小学校があった旨の碑が建っていたりする。
ともあれ、当時も都市の膨張と機能が民家の様式を押し潰すことは止められない。それでも、「都市の民家が、高層ビルの窓の一個または数個に転化してしまうことをきみは肯定するか?」(P317)と問いかける。何故なら、氏がそれを愛惜するのは、懐古、伝統再発見の理念ではないからである。
「近代の展開がもとらした諸悪と諸善が、これらの民家とその住人の真うえをとおりすぎたにもかかわらず、いかなる意味でも爪跡をのこすことができなかったという証拠を、これらの民家が提供しているからである。」
「そこには不羈の貌と慰安と、ある意味でわたしが思想の基底とみなしているものとの合致する構えが存在している。」(P321)
ここには、氏が“大衆の原像”と表現した幻想の住人がいるのだ。「改めて近代という考え方を紹介した」という冷泉彰彦氏の解釈は、あったとしても、派生的なことである。
川崎市にはJR登戸駅近くの生田緑地に「民家園」がある。但し、ここには農村的風景にマッチする民家が並ぶ。土間があり、その一角に馬の居場所もある。薄暗く、藁の匂いが漂う。ここは生活・労働そのものが家の構えと合致しており、およそ都市の民家とは異なる。そこからみれば、<格子>の存在は文化的であり、生活の匂いは希薄である。吉本氏が描く都市の民家は、当然ながら氏にとっての生活の場であり、子ども時代の記憶に結びつくものである。
この巨大都市に残された民家に関する論考は、昭和44年(1969年)の年末近くに雑誌『都市 創刊号』に掲載された。高度経済成長のさなか、大学紛争の時期である。氏の生まれ育った月島、佃島辺りは、その時、遙かに変貌をとげていたはずである。
東京が巨大都市へ変貌した、その第一歩は昭和39年(1964年)の「東京オリンピック」である。筆者は神宮外苑にある高校へ入学した年で、新幹線が開通しただけでなく、京王線が新宿駅近くで路面電車から地下鉄に変わり、あるいは、明治神宮と隣り合わせていたワシントンハイツ(米軍家族宿舎)が、選手村に変貌した。
佃大橋ができて佃渡しが廃止になったのが昭和39年8月(東京さまよい記)。詩「佃渡しで」が作られたのはそのころだ(「吉本隆明全著作集1 定本詩集」(勁草書房))。以下、上記ブログから「佃渡しで」を転載させて頂きます。
佃渡しで娘がいった
<水がきれいね 夏に行った海岸のように>
そんなことはない みてみな
繋がれた河蒸気のとものところに
芥がたまって揺れているのがみえるだろう
ずっと昔からそうだった
<これからは娘に聴えぬ胸のなかでいう>
水はくろくてあまり流れない 氷雨の空の下で
おおきな下水道のようにくねっているのは老齢期の河のしるしだ
この河の入りくんだ堀割のあいだに
ひとつの街がありそこで住んでいた
蟹はまだ生きていてそれをとりに行った
そして泥沼に足をふみこんで泳いだ
佃渡しで娘がいった
<あの鳥はなに?>
<かもめだよ>
<ちがうあの黒い方の鳥よ>
あれは鳶だろう
むかしもそれはいた
流れてくる鼠の死骸や魚の綿腹(わた)を
ついばむためにかもめの仲間で舞っていた
<これからさきは娘にきこえぬ胸のなかでいう>
水に囲まれた生活というのは
いつでもちょっとした砦のような感じで
夢の中で堀割はいつもあらわれる
橋という橋は何のためにあったか?
少年が欄干に手をかけ身をのりだして
悲しみがあれば流すためにあった
<あれが住吉神社だ
佃祭りをやるところだ
あれが小学校 ちいさいだろう>
これからさきは娘に云えぬ
昔の街はちいさくみえる
掌のひらの感情と頭脳と生命の線のあいだの窪みにはいって
しまうように
すべての距離がちいさくみえる
すべての思想とおなじように
あの昔遠かった距離がちぢまってみえる
わたしが生きてきた道を
娘の手をとり いま氷雨にぬれながら
いっさんに通りすぎる
「佃渡しで娘がいった〈水がきれいね 夏に行った海岸のように〉…」から始まるなんとも言えない書き出しに、氏の叙情豊かな感性が柔らかく表現されている。娘の言葉から過去が蘇り、回想の叙情が、河、蟹、泥沼、堀割、橋、欄干…と展開される。しかし、回想の中で過去と現実の距離は縮まり、「…わたしが生きてきた道を娘の手をとり いま氷雨にぬれながら
いつさんに通りすぎる」。
通りすぎたあとの5年後に、谷中にみた現実の姿を都市民家論として描いているのだ。ここでは、回想のなかからではなく、現実に残された姿から自らの思想の基底を探り当て、都市と共に生き続けた民家の様式を位置づけている。
巨大都市・東京は新たなオリンピック開催に名乗りを上げ、リニア中央新幹線の計画も進めている。その中で、僅かに残る民家も壊される運命にあるが、それが吉本隆明という語り部を失った今、本当に消滅したと言えるのかも知れない。