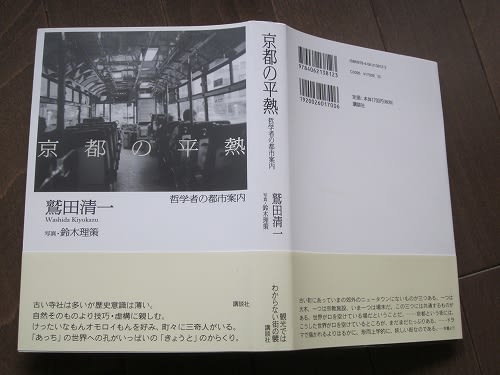伊勢丹新宿店から、京都に住む私のところにダイレクトメールが定期的に届きます。
新春一番の案内は、伊勢丹新春祭「伝統とモダンの競演 京都展」(1/11~1/16)でした。

ここからわざわざ、新宿まで買い物に行く気持ちはありません。
ですが、東京のお客さんにどの様にアピールしているか興味が湧いたので、子細に見てみました。
”舞妓さんがよう来はる 祇園切通し 老舗京フレンチの おもたせなんやわぁ”
>> 祇園おくむら「ビーフステーキサンドセット」15品目の野菜とトリュフソース添え(かにのフラン・ドリンク付き)1,890円”
※本物の舞妓さんは、たぶん、私服に着替えて食べにくるのでしょう。店内で見かけるのは、コスプレ変身舞妓かな
ビーフカツ・サンドイッチは、しかし、確かに京都名物です。
~~
”お店では出されへん 食べきりサイズやから 嬉しいわぁ”
>> 新福菜館「ミニミニミニセット」ミニラーメン・ミニ焼きめし・ミニ餃子 1,050円

”あの有名女優も こういうの 食べはったんかなぁ”
村上開新堂「ロシアケーキ」も出品するようです。
新春一番の案内は、伊勢丹新春祭「伝統とモダンの競演 京都展」(1/11~1/16)でした。

ここからわざわざ、新宿まで買い物に行く気持ちはありません。
ですが、東京のお客さんにどの様にアピールしているか興味が湧いたので、子細に見てみました。
”舞妓さんがよう来はる 祇園切通し 老舗京フレンチの おもたせなんやわぁ”
>> 祇園おくむら「ビーフステーキサンドセット」15品目の野菜とトリュフソース添え(かにのフラン・ドリンク付き)1,890円”
※本物の舞妓さんは、たぶん、私服に着替えて食べにくるのでしょう。店内で見かけるのは、コスプレ変身舞妓かな
ビーフカツ・サンドイッチは、しかし、確かに京都名物です。
~~
”お店では出されへん 食べきりサイズやから 嬉しいわぁ”
>> 新福菜館「ミニミニミニセット」ミニラーメン・ミニ焼きめし・ミニ餃子 1,050円

”あの有名女優も こういうの 食べはったんかなぁ”
村上開新堂「ロシアケーキ」も出品するようです。