年末、家族で加賀・山代温泉に出かけた。この「メモる2007年」シリーズの10回目の締めくくりに何を書こうか迷っていたので、ちょうどよい気分転換になった。ところで、この旅館のことを書いてもブログが3本は立ちそうなほどサービスがよい。就寝前には「羽毛、ソバ殻、低反発の3種の枕がありますが、お好みはありますか」と仲居さんが尋ねてくる。そして食事のメニューは女将さんが描いたイラスト付きである。経営者が料理の細部までマネジメントしている。だからサービスが行き届いていると実感できる。その旅館の窓から見える加賀の山里の景色を眺めながら、金沢大学が能登で展開しているプロジェクトについてこの1年を振り返ってみた。そして、このプロジェクトはどこへ行こうとしているのか自問自答してみた。
どこへ行こうとしているのか
 能登半島の先端にある珠洲市三崎町。廃校となった小学校を再活用した「里山マイスター能登学舎」で、2007年10月6日に「能登里山マイスター」養成プログラムは開講式を迎えた。開講式のあいさつで、金沢大学の橋本哲哉副学長は「能登に高等教育機関をという地元のみなさんからの要望があり、きょうここに一つの拠点を構えることができた。環境をテーマに能登を活性化する人材を養成したい」と感慨を込めた。ここで学ぶ1期生は19歳から44歳までの男女16人。金沢から2時間半かけて自家用車で通う受講生もいる。開講式では、受講生も自己紹介しながら、「奥能登には歴史に培われた生活や生きる糧を見出すノウハウがさまざまにある。それを発掘したい」「能登の資源である自然と里山に農林水産業のビジネスの可能性を見出したい」などと抱負を述べた。志(こころざし)を持って集まった若者たちの言葉は生き生きとしていた。
能登半島の先端にある珠洲市三崎町。廃校となった小学校を再活用した「里山マイスター能登学舎」で、2007年10月6日に「能登里山マイスター」養成プログラムは開講式を迎えた。開講式のあいさつで、金沢大学の橋本哲哉副学長は「能登に高等教育機関をという地元のみなさんからの要望があり、きょうここに一つの拠点を構えることができた。環境をテーマに能登を活性化する人材を養成したい」と感慨を込めた。ここで学ぶ1期生は19歳から44歳までの男女16人。金沢から2時間半かけて自家用車で通う受講生もいる。開講式では、受講生も自己紹介しながら、「奥能登には歴史に培われた生活や生きる糧を見出すノウハウがさまざまにある。それを発掘したい」「能登の資源である自然と里山に農林水産業のビジネスの可能性を見出したい」などと抱負を述べた。志(こころざし)を持って集まった若者たちの言葉は生き生きとしていた。
あいさつと看板の除幕という簡素な開講式だったが、かつて小学校で使われていた紅白の幕を学舎の玄関に張り、地元の人たちも見守ってくれた。5年間に及ぶ金沢大学の「能登里山マイスター」養成プログラムはこうして船出した。では、このプログラムは何を目指して、どのようなビジョンを描いているのか述べてみたい。まず、能登の現状認識について、いくつか事例を示す。
能登半島の過疎化は全国平均より速いテンポで進んでいる。とくに奥能登4市町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の人口は現在8万1千人だが、8年後の2015年には2割減の6万5千人、65歳以上の割合が44%を占めると予想される(石川県推計)。この過疎化はさまざまなかたちで表出している。能登半島では夏から秋にかけて祭礼のシーズンとなる。伝統的な奉灯祭はキリコを担ぎ出す。キリコは収穫を神に感謝する祭礼用の奉灯を巨大化したもので、その高さは12㍍に及ぶ。黒漆と金蒔絵で装飾されたボディ、錦絵が描かれた奉灯、何基ものキリコが鉦(かね)と太鼓のリズムに乗って社(やしろ)に集ってくる。華やかな祭りのなかにも能登の現実をかいま見ることができる。キリコは本来担ぐものだが、キリコに車輪をつけて若い衆が押している。かつて集落には若者が大勢いてキリコを担ぎ上げたが、いまは人足が足りずそのパワーはない。車輪を付けてでもキリコを出せる集落はまだいい。そのキリコすら出せなくなっている集落が多くあり、社の倉庫に能登の伝統遺産が眠ったままになっている。
2006年5月、能登半島を視察に訪れた小泉純一郎首相(当時)は、国指定の名勝である「白米(しらよね)の千枚田」(輪島市)を眺望して、「この絶景をぜひ世界にアピールしてほしい」と賞賛した。展望台から見渡す棚田の風景は確かに絶景であるものの、小泉首相が眺望したのはざっと4㌶で、展望台からは見えにくい周囲の10㌶の田んぼは休耕田や放棄田となっている。高齢化と担い手不足、そして予想以上に放棄田が広がる背景には、棚田は耕運機や田植え機などが入りにくく手間がかかるという現実がある。輪島市では棚田のオーナー制度を打ち出すなど手を尽くしているが、名勝の棚田ですら耕作を持続するのは難しい。さらに、ことし2007年3月25日の能登半島地震。マグニチュード6.9、震度6強。この震災で1人が死亡、280人が重軽傷を負い、370棟が全半壊し、2000人余りが避難所生活を余儀なくされた。自宅の再建を断念し、慣れ親しんだ土地を離れ、子や孫が住む都会に移住するお年寄りも目立つ。能登の過疎化に拍車がかかる。もはや能登、とくに奥能登の地域再生は「待ったなし」の状態となっている。
こうした奥能登の現状に、金沢大学は「能登里山マイスター」養成プログラムを投入することになった。奥能登に拠点を構えるにあたって、このプログラムに連携する輪島市、珠洲市、穴水町、能登町の4市町と、それにブログラムに講師派遣というかたちで参画する石川県立大学を交え、「地域づくり連携協定」を結んだ(2007年年7月13日)。地域の現状を好転させたいと心底から願っているのは当該の自治体である。しかし自治体にとって、課題の解決に向けて大学に協力を求めようとしても大学といのは敷居が高い。そこで、連携協定を結ぶことで敷居を払うという効果につながる。協定内容はごく簡単に地域再生、地域教育、地域課題の3点について協力するというものだ。調印を終え、林勇二郎学長はそれぞれの自治体の首長とがっちりと握手を交わした。その後、この連携協定が単なる文面上の約束事から、求心力へと高まっていくことになる。
 能登の自治体と金沢大学の動きに機敏に反応したのは意外にも石川県議会だった。県議会企画総務委員会の7人の議員が「金沢大学が能登でやろうとしていることを説明してほしい」とわざわざ珠洲市の里山マイスター能登学舎を視察に訪れた。総務企画委員会というのは各会派のベテラン県議、いわゆる「うるさ方」が集まる委員会である。県の局長、部長クラスを伴って、一行がバスで訪れたのは8月22日のこと。議員が動いたということで、今度は県庁内での動きにつながる。庁内で部局を横断的につないだ「里山マイスター連絡会」が組織された。8月31日の初会合には企画振興部地域振興課、環境部自然保護課、商工労働部産業政策課、観光交流局観光推進課、農林水産部企画庁調整室、同部中山間地振興室の関連セクションから課長や課長補佐、主幹、専門員といった中堅クラスが集まった。いわば県庁内での支援組織である。
能登の自治体と金沢大学の動きに機敏に反応したのは意外にも石川県議会だった。県議会企画総務委員会の7人の議員が「金沢大学が能登でやろうとしていることを説明してほしい」とわざわざ珠洲市の里山マイスター能登学舎を視察に訪れた。総務企画委員会というのは各会派のベテラン県議、いわゆる「うるさ方」が集まる委員会である。県の局長、部長クラスを伴って、一行がバスで訪れたのは8月22日のこと。議員が動いたということで、今度は県庁内での動きにつながる。庁内で部局を横断的につないだ「里山マイスター連絡会」が組織された。8月31日の初会合には企画振興部地域振興課、環境部自然保護課、商工労働部産業政策課、観光交流局観光推進課、農林水産部企画庁調整室、同部中山間地振興室の関連セクションから課長や課長補佐、主幹、専門員といった中堅クラスが集まった。いわば県庁内での支援組織である。
大学の研究プログラムにこれほどまでに行政が機敏な動きを見せたのには理由がある。このプログラムは文部科学省科学技術振興調整費の「地域再生人材創出の拠点形成」という課題で金沢大学が申請した。国の第67回総合科学技術会議で採択されたのは2007年5月18日。この課題では全国の大学などから75件の申請があり、12件が採択された。1年間で5000万円、5年継続が可能なのでトータルで2億5千万円の国の委託費だ。科振費の中でも、このプログラムは自治体と連携して地域再生のための人材養成の拠点を形成するというミッション(政策的な使命)を帯びていて、総合科学技術会議の採択を受け、今度は連携する自治体が大学のプログラムを活用して地域再生計画を作成し、内閣府に申請するという「二段論法」になっている。平たくいえば、大学と地域自治体の双方が申請責任者として地域課題に取り組むという仕組みになっている。そこで、石川県と輪島市、珠洲市、穴水町、能登町は「元気な奥能登を創る!“里山マイスター”創出拠点の形成による奥能登再生計画」を国に申請し、7月4日に認定を受けることになる。地域づくり連携協定から県庁内の里山マイスター連絡会まで、大学と行政の連携の動きは一連のものなのだ。
「能登里山マイスター」養成プログラムに先立って、2006年10月、三井物産環境基金の支援を得て、能登半島の最先端にある珠洲市三崎町で「能登半島 里山里海自然学校」を開設した。地域への貢献を条件に、同市から無償で借り受けた鉄筋コンクリート3階建ての旧・小学校の校舎。教室の窓からは日本海が望め、廊下の窓から能登の里山が広がる絶好のローケションが里山里海自然学校に相応しいというのがこの場所の選定理由だった。ここに常駐研究員1人を配して、奥能登における生物多様性調査をオープンリサーチ形式で行なう。山や溜め池、田んぼといったところで生物調査を行なう。この中から、絶滅危惧種であるホクリクサンショウウオの北限を塗り替える発見もあった。このほかに、沿岸集落の里海づくり、食文化調査、マツタケ山の保全活動、ビオトープづくりなどを地域の人たちの協力を得て行なっている。学校のある小泊地区の人たちは「一度明かりが消えた学校に再び明かりがともってうれしい」と言い、里山里海自然学校とは協力関係が築かれている。しかし、社会貢献、地域づくりといいながら、角間の里山自然学校や里山里海自然学校の取り組みだけでは奥能登への貢献は力不足である。大学にできること、それは人材養成ではないのかと自問自答したプランが「能登里山マイスター」養成プログラムだった。プログラムの申請段階から関わった市の泉谷満寿裕市長は「能登には高等教育機関がないので、若い人材が都会に流失していく。この人材養成プログラムがUターン希望者らの呼び水の一つになってほしい」と何度も強調した。七尾市和倉温泉の「加賀屋」、小田禎彦会長は「能登に人づくりの拠点ができることを待ち望んでいた」と話し、若手社員を受講生としてプログラムに送り込んでくれた。地域の期待は予想以上に大きかった。
このプログラムを国に申請書を作成する段階で念頭に置いた、お手本のような地域の事例がある。能登半島の付け根にある石川県羽咋(はくい)市神子(みこ)原(はら)地区という過疎と高齢が進む集落(170世帯500人)がある。山のため池を共有し、人々は律儀に手をかけて稲を育てている。その米が「神子原米」としてブランド化され、高級旅館の朝ごはんに、あるいはその米で造られた純米酒はファーストクラスの機内食として供されるなど高い付加価値をつけることに成功した。生産量は多くないので、決して豊かな村ではない。しかし、目立っていた空き家に、神子原で米づくりをしてみたいと志す都会の4家族13人が入居し、地域は活気づいている。能登はその地形から大規模な河川がなく、平野も少ないことから、生産量を競う米づくりには不向きで、集落が共同でため池をつくり、その水を分け合って水田を耕してきた。個人ベースでは小規模農業であるものの、「ため池共同体」であることを生かし、集落がまとまってブランド米づくりに乗り出すことが可能である。いわば、米づくりが個人ではなく、地域ぐるみのコミュニティ・ビジネスとして成立する素地が能登にあり、神子原地区はその成功例と言える。
追い風もある。食の安全と安心を求める消費者の声が高まり、平成19年度から政府は新農業政策「農地・水・環境保全向上対策」を掲げ、環境保全型の農業へと大きく舵(かじ)を切っている。生産量を誇るのではなく、環境に過度の負荷をかけない、品質の確かな農業への転換である。新しい農業の時代を担う人材を能登の地で育むことができないだろうか。風光明媚な観光資源や魚介類の水産資源にも恵まれている。これらの資源を生かし、農家レストランや体験農業、あるいは食品産業との連携による新事業の展開など、「農」をキーコンセプトとする新しいアグリビジネスを創造する人材が定着すれば、能登再生の展望はほのかに見えてくる。
「能登里山マイスター」養成プログラムが具体化されるまでのいきさつや、どのような人材を能登で養成しようとしているのかについて、これまで述べてきた。ここでお分かりのように、主眼は「農業名人」を育成することではなく、環境配慮をテーマとしたスモールビジネスを行なう若手人材の養成なのである。しかし、里山マイスターを60人育てれば能登を再生できるのか、それは容易ではない。次なる能登のビジョン、あるいは仕掛けが必要なのである。これからがわれわれが目指す里山活動の本題でもある。
 環境配慮型の農業を行なうことで、副次的に水田にはドジョウやタニシといった生物が豊富になる。ある意味で単純なことが実は重要なことであるのに気づくのに半世紀を要している。急減したトキが国の特別天然記念物に指定された1950年代、日本は戦後の食糧増産に励んでいた。農業と環境の問題にいち早く警鐘を鳴らしたレチェル・カーソンは1960年代に記した名著「サイレント・スプリング」に、「春になっても鳥は鳴かず、生きものが静かにいなくなってしまった」と記した。農業は豊かになったけれども春が静かになった。1970年、日本で本州最後の1羽のトキが能登半島の穴水町で捕獲された。愛称は「能里(ノリ)」、オスだった。繁殖のため佐渡のトキ保護センターで送られたが、翌71年に死亡した。解剖された能里の肝臓や筋肉からはDDTなどの有機塩素系農薬や水銀が高濃度で検出された。そして2003年、佐渡の「キン」が死亡し、日本のトキは沈黙したまま絶滅した。
環境配慮型の農業を行なうことで、副次的に水田にはドジョウやタニシといった生物が豊富になる。ある意味で単純なことが実は重要なことであるのに気づくのに半世紀を要している。急減したトキが国の特別天然記念物に指定された1950年代、日本は戦後の食糧増産に励んでいた。農業と環境の問題にいち早く警鐘を鳴らしたレチェル・カーソンは1960年代に記した名著「サイレント・スプリング」に、「春になっても鳥は鳴かず、生きものが静かにいなくなってしまった」と記した。農業は豊かになったけれども春が静かになった。1970年、日本で本州最後の1羽のトキが能登半島の穴水町で捕獲された。愛称は「能里(ノリ)」、オスだった。繁殖のため佐渡のトキ保護センターで送られたが、翌71年に死亡した。解剖された能里の肝臓や筋肉からはDDTなどの有機塩素系農薬や水銀が高濃度で検出された。そして2003年、佐渡の「キン」が死亡し、日本のトキは沈黙したまま絶滅した。
その後、同じ遺伝子を持つ中国産のトキが佐渡で人工繁殖し、107羽(2007年7月現在)に増殖している。環境省では、鳥インフルエンザへの感染が懸念されることから場所を限定しての本州での分散飼育を検討し、08年にも分散場所の選定がなされる見込み。石川県能美市にある県営の「いしかわ動物園」は分散飼育の受け入れに名乗りを上げ、近縁種のシロトキとクロトキの人工繁殖と自然繁殖に成功し、分散飼育の最有力候補とされている。分散飼育の後、人工増殖したトキを最終的に野生化させるのが国家プロジェクトの目標である。
能登の「能里」が本州最後の1羽のトキだったことは前に触れた。途絶えたとはいえ、能登に最後の1羽まで生息したのにはそれなりの理由がある。先に紹介した「能登半島 里山里海自然学校」で行なっている奥能登での生物多様性調査は、珠洲市と輪島市など奥能登の何ヵ所かを重点調査地区に設定し、詳細なデータの蓄積を進めている。調査は途中であるものの、トキの生息環境の可能性を能登に見出すことができる。能登には大小1000以上ともいわれる水稲栽培用のため池が村落の共同体、あるいは個別農家により維持されている。ため池は中山間地にあり、上流に汚染源がないため水質が保たれている。サンショウウオ、カエル、ゲンゴロウやサワガニ、ドジョウなどの水生生物が量、種類とも豊富である。ため池にプールされている多様な水生生物は用水路を伝って水田へと分配されている。
また、能登にはトキが営巣するのに必要とされるアカマツ林が豊富である。昭和の中ごろまで揚げ浜式塩田や、瓦製造が盛んであったため、高熱を発するアカマツは燃料にされ、伐採と植林が行なわれた。さらに、能登はリアス式海岸で知られるように、平地より谷が多い。警戒心が強いとされるトキは谷間の棚田で左右を警戒しながらサンショウウオやカエル、ゲンゴロウなどの採餌行動をとる。豊富な食糧を担保するため池と水田、営巣に必要なアカマツ林、そしてコロニーを形成する谷という条件が能登にある。ここに環境配慮型の農業を点ではなく面で進めたら、トキやコウノトリが舞い生息する里山の環境が再生されるのではないだろうか。
もちろん、机上の話だけでは現実は進まない。かつて奥能登でトキはドゥと呼ばれ、水田の稲を踏み荒らす害鳥だった。ドゥとは「追っ払う」という意味である。トキを野生復帰させるための生態環境的なアプローチに加え、生産者と地域住民との合意形成が必要である。トキと共存することによる経済効果、たとえば農産物に対する付加価値やグリーンツーリズムなどへの広がりなど経済的な評価を行ない、生産者や住民にメリットを提示しながら、トキの生息候補地を増やしていく合意形成が不可欠である。その上で、金沢大学が能登半島で地域住民と協働して実施している生物多様性調査に都市の消費者も加わってもらい、長期モニタンリングにより農環境の「安全証明」を担保していく仕組みづくりができれば、環境と農業、地域と都市の生活者が連携する自然と共生した能登型の環境再生モデルが実現するのではないか。
次世代を担うであろう里山マイスターにぜひ、トキが舞う能登の農村の環境再生の夢を託したい。能登の里山ルネサンス(再興)といってもよい。ここに能登再生の可能性がある。このブログでもすでに紹介したトキの写真がある。昭和32年(1957年)、輪島市三井町洲衛で撮影されたトキの子育て、巣立ち、大空への舞いの当時珍しいカラー写真である。地元の小学校の校長していた岩田秀男氏(故人)がドイツ製の中古カメラを買って撮影した。トキをモノクロの写真で撮影しても意味がないと、カラー写真の撮影に執念を燃やした。岩田氏は最後の1羽を捕獲し佐渡に送ることに反対したそうだ。「最後の1羽は能登で安らかに死なせてやりたいと願っていた」(遺族の話)。わたしはトキが能登に復活することを願っている。本州最後の1羽が能登なら、本州で野生復帰する最初の1羽を能登で実現させたいと。
⇒29日(土)午前・金沢の天気 くもり










 2年前の05年12月31日、私は当時、経済産業省「コンテンツ配信の実証事業」のコーディネータ-として、東京芸術劇場大ホールで岩城さんがベートーベンのシンフォニー1番から9番を指揮するのを見守っていた。演奏を放送と同時にインターネットで配信する事業に携わっていた。休憩をはさんで560分にも及ぶクラシックのライブ演奏である。番組では指揮者用のカメラがセットしてあって、岩城さんの鬼気迫る顔を映し出していた。ディレクターは朝日放送の菊池正和氏。その菊地氏の手による、1番から9番のカメラ割り(カット)数は2000にも及んだ。3番では、ホルンの指の動きからデゾルブして、指揮者・岩城さんの顔へとシフトしていくカットなどは感動的だった。
2年前の05年12月31日、私は当時、経済産業省「コンテンツ配信の実証事業」のコーディネータ-として、東京芸術劇場大ホールで岩城さんがベートーベンのシンフォニー1番から9番を指揮するのを見守っていた。演奏を放送と同時にインターネットで配信する事業に携わっていた。休憩をはさんで560分にも及ぶクラシックのライブ演奏である。番組では指揮者用のカメラがセットしてあって、岩城さんの鬼気迫る顔を映し出していた。ディレクターは朝日放送の菊池正和氏。その菊地氏の手による、1番から9番のカメラ割り(カット)数は2000にも及んだ。3番では、ホルンの指の動きからデゾルブして、指揮者・岩城さんの顔へとシフトしていくカットなどは感動的だった。 何を隠そう私も能登の出身なので、どちらかとうと能登について語る際は概して辛口である。何しろ能登の人は勘違いをしている。民宿、居酒屋、寿司屋などどこで食べても量が多すぎる。たとえば、ブリの刺身はぶ厚い。これが5枚、6枚と皿に盛ってあるので食べきれない。もう少し薄く、量を減らしたらと主人や女将に進言すると、決まって「量が少ないと言われるほうが辛いのです」という。
何を隠そう私も能登の出身なので、どちらかとうと能登について語る際は概して辛口である。何しろ能登の人は勘違いをしている。民宿、居酒屋、寿司屋などどこで食べても量が多すぎる。たとえば、ブリの刺身はぶ厚い。これが5枚、6枚と皿に盛ってあるので食べきれない。もう少し薄く、量を減らしたらと主人や女将に進言すると、決まって「量が少ないと言われるほうが辛いのです」という。 新聞とハサミの格闘が始まったのは、何といっても、新年早々の「発掘!あるある大事典」(07年1月7日放送)の捏造問題だった。番組制作側の関西テレビに対する週刊朝日の「納豆ダイエット」についての質問から端を発した事件だった。関テレ側は社長出席の記者会見で、「制作上のミスであり、お詫びします」と陳謝して逃げ切ろうと思ったのだろう。しかし、新聞記者の追及は甘くなかった。結果的に、納豆ダイエットの番組の中だけで、日本語のボイスオーバー(吹き替え)による捏造4件、データ改ざん4件、そのほか実験方法が不適切であったり、研究者の確認を取ってないものが8件もあった。このほかにも「足裏刺激でヤセる」(06年10月8日放送)などで捏造が次々と明るみとなり、スポンサーの花王が降りて番組は打ち切りとなった。
新聞とハサミの格闘が始まったのは、何といっても、新年早々の「発掘!あるある大事典」(07年1月7日放送)の捏造問題だった。番組制作側の関西テレビに対する週刊朝日の「納豆ダイエット」についての質問から端を発した事件だった。関テレ側は社長出席の記者会見で、「制作上のミスであり、お詫びします」と陳謝して逃げ切ろうと思ったのだろう。しかし、新聞記者の追及は甘くなかった。結果的に、納豆ダイエットの番組の中だけで、日本語のボイスオーバー(吹き替え)による捏造4件、データ改ざん4件、そのほか実験方法が不適切であったり、研究者の確認を取ってないものが8件もあった。このほかにも「足裏刺激でヤセる」(06年10月8日放送)などで捏造が次々と明るみとなり、スポンサーの花王が降りて番組は打ち切りとなった。 境省を訪れた石川県の谷本正憲知事が田村義雄事務次官に対し、トキの分散飼育に「いしかわ動物園」(石川県能美市)もその候補に含めてほしいと陳情したところ、田村氏は「トキを育てている佐渡島の皆さんは、本州最後のトキがいた能登地区にいい思いを抱いている」と告げたという。この記事のポイントは①知事が事務次官に陳情した②上記の言質を得た、というたった2点なのだが、「トキ分散飼育、石川は有力」と5段抜きの見出しが躍った。
境省を訪れた石川県の谷本正憲知事が田村義雄事務次官に対し、トキの分散飼育に「いしかわ動物園」(石川県能美市)もその候補に含めてほしいと陳情したところ、田村氏は「トキを育てている佐渡島の皆さんは、本州最後のトキがいた能登地区にいい思いを抱いている」と告げたという。この記事のポイントは①知事が事務次官に陳情した②上記の言質を得た、というたった2点なのだが、「トキ分散飼育、石川は有力」と5段抜きの見出しが躍った。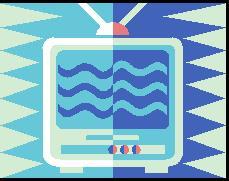 大学の講義でメディア論を担当している。その中で、著作権と放送法の概論は必須なのだが、著作権より放送法の説明が難しく、とくに「県域主義」や「県域免許」などを学生に理解してもらうのにひと苦労する。「県域主義」や「県域免許」とは放送免許は基本的に県単位で与えられており、隣県にはなるべく電波が飛ばないようしてある。しかし、学生はこういうふうに解釈する。「地域のニュースや番組を充実させるためというのは理解できるが、なぜそれが県単位でなければならないのか、電波そのものをブロックできないのに」と。そこでふと考えた。今回の区域外再送信の問題がこじれて、民放局がケーブルテレビ局に「同意せず」を連発すると、テレビ業界の閉鎖性がむしろ世論で問題視され、マイナスイメージが先行するのではないか、と。
大学の講義でメディア論を担当している。その中で、著作権と放送法の概論は必須なのだが、著作権より放送法の説明が難しく、とくに「県域主義」や「県域免許」などを学生に理解してもらうのにひと苦労する。「県域主義」や「県域免許」とは放送免許は基本的に県単位で与えられており、隣県にはなるべく電波が飛ばないようしてある。しかし、学生はこういうふうに解釈する。「地域のニュースや番組を充実させるためというのは理解できるが、なぜそれが県単位でなければならないのか、電波そのものをブロックできないのに」と。そこでふと考えた。今回の区域外再送信の問題がこじれて、民放局がケーブルテレビ局に「同意せず」を連発すると、テレビ業界の閉鎖性がむしろ世論で問題視され、マイナスイメージが先行するのではないか、と。 金沢大学では震災後、医療のほか復興のためのボランティア活動を学生や職員に呼びかけた。避難所生活が長期化し、落ち着かない日々を過ごす人たちを元気づけようと、社会貢献室ではかねてから交流のあった山口県岩国市の「猿舞座」座長の村崎修二さんと連携して開いた。体長1.2㍍のサル「安登夢(あとむ)」が跳び上がって輪をくぐる「ウグイスの谷渡り」などの芸を披露すると、会場は歓声と拍手に包まれた。
金沢大学では震災後、医療のほか復興のためのボランティア活動を学生や職員に呼びかけた。避難所生活が長期化し、落ち着かない日々を過ごす人たちを元気づけようと、社会貢献室ではかねてから交流のあった山口県岩国市の「猿舞座」座長の村崎修二さんと連携して開いた。体長1.2㍍のサル「安登夢(あとむ)」が跳び上がって輪をくぐる「ウグイスの谷渡り」などの芸を披露すると、会場は歓声と拍手に包まれた。 氏のクレジットを必ず入れることを条件に写真の使用許可をいただいた。
氏のクレジットを必ず入れることを条件に写真の使用許可をいただいた。 アンケートの調査は、震度6強に見舞われ、住民のうち65歳以上が47%を占める石川県輪島市門前町で行った。当初は地震発生の翌日に被災地に入り、地域連携コーディネーターとして、学生のボランティア支援をどのようなかたちで進めたらよいか調査するのが当初の目的で被災地に入った。そこで見た光景が「震災とメディア」の調査研究をしてみようと思い立った動機となる。震災当日からテレビ系列が大挙して同町に陣取っていた。現場中継のため、倒壊家屋に横付けされた民放テレビ局のSNG(Satellite News Gathering)車をいぶかしげに見ている被災者たちの姿があった。この惨事は全国中継されるが、地域の人たちは視聴できないのではないか。また、半壊の家屋の前で茫然(ぼうぜん)と立ちつくすお年寄り、そしてその半壊の家屋が壊れるシーンを撮影しようと、ひたすら余震を待って身構えるカメラマンのグループがそこにあった。こうしたメディアの行動は、果たして被災者に理解されているのだろうか。それより何より、メディアはこの震災で何か役立っているのだろうか、という素朴な疑問だった。
アンケートの調査は、震度6強に見舞われ、住民のうち65歳以上が47%を占める石川県輪島市門前町で行った。当初は地震発生の翌日に被災地に入り、地域連携コーディネーターとして、学生のボランティア支援をどのようなかたちで進めたらよいか調査するのが当初の目的で被災地に入った。そこで見た光景が「震災とメディア」の調査研究をしてみようと思い立った動機となる。震災当日からテレビ系列が大挙して同町に陣取っていた。現場中継のため、倒壊家屋に横付けされた民放テレビ局のSNG(Satellite News Gathering)車をいぶかしげに見ている被災者たちの姿があった。この惨事は全国中継されるが、地域の人たちは視聴できないのではないか。また、半壊の家屋の前で茫然(ぼうぜん)と立ちつくすお年寄り、そしてその半壊の家屋が壊れるシーンを撮影しようと、ひたすら余震を待って身構えるカメラマンのグループがそこにあった。こうしたメディアの行動は、果たして被災者に理解されているのだろうか。それより何より、メディアはこの震災で何か役立っているのだろうか、という素朴な疑問だった。 ことし3月25日の能登半島地震で「震災とメディア」の調査をした。その中で、「誰しもが一瞬にして情報弱者になるのが震災であり、電波メディアは被災者に向けてメッセージを送ったのだろうか」「被災地から情報を吸い上げて全国へ発信しているが、被災地に向けたフィードバックがない」と問題提起をした。その後、7月16日に新潟県中越沖地震が起きた。そこには、「情報こそライフライン」と被災者向け情報に徹底し、24時間の生放送を41日間続けた放送メディアがあった。
ことし3月25日の能登半島地震で「震災とメディア」の調査をした。その中で、「誰しもが一瞬にして情報弱者になるのが震災であり、電波メディアは被災者に向けてメッセージを送ったのだろうか」「被災地から情報を吸い上げて全国へ発信しているが、被災地に向けたフィードバックがない」と問題提起をした。その後、7月16日に新潟県中越沖地震が起きた。そこには、「情報こそライフライン」と被災者向け情報に徹底し、24時間の生放送を41日間続けた放送メディアがあった。



