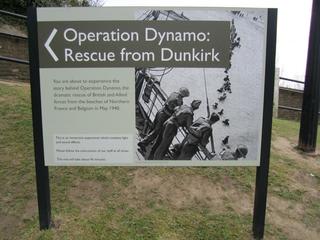ウィットビー・アビーを後にして、次は付近の散策を楽しんだ。
【セント・メリー教会&墓地】
アビーの隣には、セント・メリー教会(St. Mary's Church)という教会が立っている。教会自体も古いらしいのだが、有名なのはこの教会の裏にある墓地。ウイットピーはドラキュラがルーマニアから上陸した地でもあるのだが、この小説の作者ブラム=ストーカーはこの墓地で「吸血鬼ドラキュラ」の着想を得たという。確かに教会の裏に、風化し、誰のお墓だかも分からなくなってしまった墓石が並び、一種独特の雰囲気を醸し出している。小説自体は読んだことはないが、まだ陽の高い時間だから良いものの、これが夕闇だったらいつ墓石が動き出して、棺の中から吸血鬼が出てきてもおかしくなさそう。

この教会と墓地は北海に面した丘の上に立つため、眺めが抜群だ。ウイットビーとはデンマーク語で、現在ある河口沿いの町自体がデンマークからの移住者によって出来たらしいが、この風景を見れば分かる気がする。この海を渡ってデンマーク人が来たのだ。


この丘を下るときには、199段の階段を下る。下りながら見下ろす街が美しい。細い通りに、小さいお店が所狭しと並んでおり、観光客で一杯。家族と一緒なら、ここをそぞろ歩きをするだけで、1時間はあっという間に経ってしまうだろう。一人の私は、ウインドーショッピングの代わりに、河口に面したパブで一杯。


【キャプテン・クック記念館】
ウイットビーにはドラキュラの並んでもう一人有名人がいる。英国史に残る海軍士官であり海洋探検家であるキャプテン・クック(ジェームズ=クック)である。クックは17歳の時からこのウイトッピーで見習い船員として働いていて、そのとき働いていた大船主の家がキャプテン=クック記念博物館になっている。
(博物館の入り口)

家を博物館にした構造なので、こじんまりとした部屋の中にテーマごとにクックに関連する展示がしてある。クックのことは高校時代の世界史で少し触れたぐらいだったが、タチヒ、ニュージーランド、オーストラリア、南極圏、北アメリカ西海岸、ハワイと彼の航海の跡をたどっていくと、改めて世界を股にかけた海軍人であったことが良くわかる。当時の航海といえば、常に死のリスクと向き合ったものであっただろうから、その冒険心にただただ感服する。
(展示室内)




【そぞろ歩き】
なんだかんだで1時間ちょっとキャプテンクック博物館に居た後は、街歩き再開。河口の橋の袂では、子供たちが釣り糸を垂らしている。「何を釣っているか」と訊いたのだが、えらい訛りの強い英語が返ってきて来てまるで理解不能だった。バケツを覗いてみたら、カニが捕まっていた。釣りをする子供の表情は、どこも変わらない。



ずっと歩き詰め、立ち詰めで、少々疲れたので、またもやパブで一杯。

夕方になって、だんだんと陽が傾いてきた。河に沿って、海に出てみる。波の音、鴎の鳴き声を聞いていると、ロンドンとは別世界だ。


対岸の丘の上には、夕陽に照らされてアビーや教会が美しく輝いている。あまりの美しさに、もう一度近くで見たくなって再び、丘を登った。さっきまで混みこみだった細い通りも、人通りが少なくなって寂しくなっていた。

雲が無くなった青空の中、夕陽に照らされる教会は息を飲むほど美しい。陽は傾いてきたものの、あまりにも澄んだ空気の透明感で、墓地からドラキュラが出てくる気配も全くない。


でも、夕陽向かって、教会、墓地、海を眺めると、逆に神秘的な雰囲気が醸し出されるから不思議だ。


アビーは既に閉門しているが、アビー沿いの道から夕陽を背にしたアビーも見えた。思わず、手を合わせ、拝みたく神々しさだった。

(つづく)
【セント・メリー教会&墓地】
アビーの隣には、セント・メリー教会(St. Mary's Church)という教会が立っている。教会自体も古いらしいのだが、有名なのはこの教会の裏にある墓地。ウイットピーはドラキュラがルーマニアから上陸した地でもあるのだが、この小説の作者ブラム=ストーカーはこの墓地で「吸血鬼ドラキュラ」の着想を得たという。確かに教会の裏に、風化し、誰のお墓だかも分からなくなってしまった墓石が並び、一種独特の雰囲気を醸し出している。小説自体は読んだことはないが、まだ陽の高い時間だから良いものの、これが夕闇だったらいつ墓石が動き出して、棺の中から吸血鬼が出てきてもおかしくなさそう。

この教会と墓地は北海に面した丘の上に立つため、眺めが抜群だ。ウイットビーとはデンマーク語で、現在ある河口沿いの町自体がデンマークからの移住者によって出来たらしいが、この風景を見れば分かる気がする。この海を渡ってデンマーク人が来たのだ。


この丘を下るときには、199段の階段を下る。下りながら見下ろす街が美しい。細い通りに、小さいお店が所狭しと並んでおり、観光客で一杯。家族と一緒なら、ここをそぞろ歩きをするだけで、1時間はあっという間に経ってしまうだろう。一人の私は、ウインドーショッピングの代わりに、河口に面したパブで一杯。


【キャプテン・クック記念館】
ウイットビーにはドラキュラの並んでもう一人有名人がいる。英国史に残る海軍士官であり海洋探検家であるキャプテン・クック(ジェームズ=クック)である。クックは17歳の時からこのウイトッピーで見習い船員として働いていて、そのとき働いていた大船主の家がキャプテン=クック記念博物館になっている。
(博物館の入り口)

家を博物館にした構造なので、こじんまりとした部屋の中にテーマごとにクックに関連する展示がしてある。クックのことは高校時代の世界史で少し触れたぐらいだったが、タチヒ、ニュージーランド、オーストラリア、南極圏、北アメリカ西海岸、ハワイと彼の航海の跡をたどっていくと、改めて世界を股にかけた海軍人であったことが良くわかる。当時の航海といえば、常に死のリスクと向き合ったものであっただろうから、その冒険心にただただ感服する。
(展示室内)




【そぞろ歩き】
なんだかんだで1時間ちょっとキャプテンクック博物館に居た後は、街歩き再開。河口の橋の袂では、子供たちが釣り糸を垂らしている。「何を釣っているか」と訊いたのだが、えらい訛りの強い英語が返ってきて来てまるで理解不能だった。バケツを覗いてみたら、カニが捕まっていた。釣りをする子供の表情は、どこも変わらない。



ずっと歩き詰め、立ち詰めで、少々疲れたので、またもやパブで一杯。

夕方になって、だんだんと陽が傾いてきた。河に沿って、海に出てみる。波の音、鴎の鳴き声を聞いていると、ロンドンとは別世界だ。


対岸の丘の上には、夕陽に照らされてアビーや教会が美しく輝いている。あまりの美しさに、もう一度近くで見たくなって再び、丘を登った。さっきまで混みこみだった細い通りも、人通りが少なくなって寂しくなっていた。

雲が無くなった青空の中、夕陽に照らされる教会は息を飲むほど美しい。陽は傾いてきたものの、あまりにも澄んだ空気の透明感で、墓地からドラキュラが出てくる気配も全くない。


でも、夕陽向かって、教会、墓地、海を眺めると、逆に神秘的な雰囲気が醸し出されるから不思議だ。


アビーは既に閉門しているが、アビー沿いの道から夕陽を背にしたアビーも見えた。思わず、手を合わせ、拝みたく神々しさだった。

(つづく)