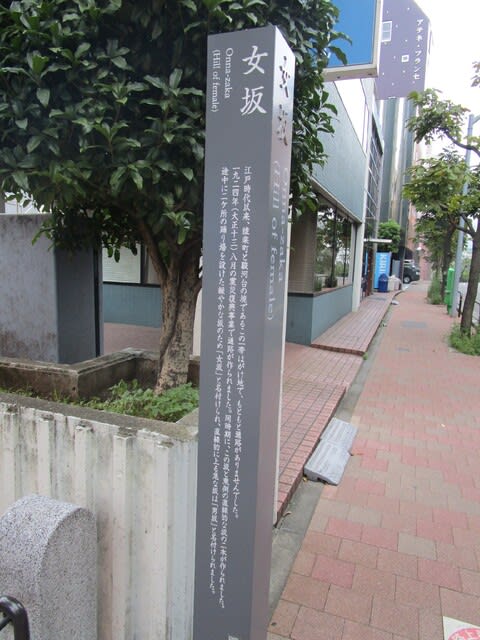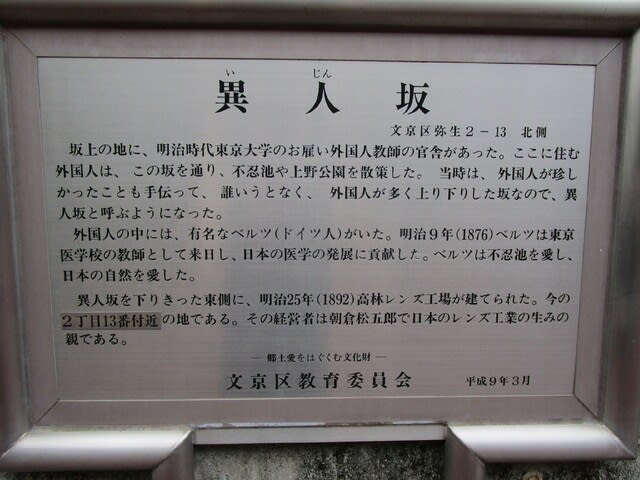今年の夏休み旅行は涙のキャンセルで、仕方なく都内をぶらつくことに。初日は、一度行ってみたかった東京の郊外八王子市にある八王子城址を訪れました。

戦国時代の関東の雄、後北条氏の北条氏輝(氏政の三男)が築城したと言われている深沢山(城山)に築かれた山城です。残念ながら、秀吉の小田原攻めの一環で、前田利家、上杉景勝に攻められ、城兵の奮戦むなしく落城したとのこと。日本100名城にも選ばれています。城そのものは残っていませんが、現在整備が進み、遺構等が発掘され、当時を偲ぶことができます。
ベースとなる案内所に隣接した駐車場に車を停めて、散策開始。山のふもとにある領主の居住エリアと、戦闘の拠点となった要害エリアに分かれています。まずは居住エリアで当時の石垣、復刻された館門、ご主殿跡らを見学。

〈当時の石垣が再現されています>

〈御主殿の入口にある冠木門〉

〈御主殿跡〉
一通り見た後は、要害エリアに移動します。要害エリアはまさに山城に相応しく、本丸に向かっては山登りそのものです。深沢山は標高400メートルちょっとなのですが、久しぶりにちょっとした登山の感覚。これを攻めあがるのは大変だろうなあ。木に覆われていますから、陽ざしを直接浴びることは無いものの、地上35℃の中、高台とは言いつつも、もわっとしたねっとりする空気は避けがたく、山の爽やかな空気には程遠いものでした。

〈本丸への入口〉

〈完全な登山道。ここを攻め上がる豊臣側も大変だ〉
途中には八王子神社があります。殆ど朽ち果てていますが、「現社殿は江戸末期の造営である。またこの社が八王子の市名の起源ともいわれる。」(東京都神社名鑑)だそうです。社殿の向かいにはこれまた朽ち果てた神楽殿が残っています。木の建造物は放っておくとこうなってしまうのでしょうね。まだ明るいから良いものの、蝉の鳴き声しか聞こえない人気のない山の神社の境内は、ちょっと不気味でもあります。

〈八王子神社社殿〉

〈神楽殿。ここでどんな踊りが舞われたのだろうか?〉
暑さの中、フーフー言いながらさらに登ります。兵士たちはこの中、鎧を着て戦ったのかと思うと、それはお気の毒としか言いようがない。ただ、本丸近くになると、広大な関東平野を見下ろす素晴らしい景観が望めます。確かに関東の縁で、南と北を抑える地理的に重要な拠点にあることが良く分かります。なんとか40分ちょっとかけて、本丸跡のある頂上までたどり着きました。

〈方向的には横浜方面〉

山頂部はさほど広くないので、きっと本丸もさほどの収容能力は無かったと思われます。ただ、それでも北条VS前田・上杉の戦いで1000名を超える兵士が命を落としたということですから、その激戦ぶりは容易に想像がつきます。

〈本丸跡〉
帰りは下り道を一気に降りました。すれ違った人は2組のみ。暑さを考えればそんなものと思いますが、この八王子城址、ちょっとした運動も兼ねた歴史と想像の旅としてはもってこいの史跡です。涼しくなったら、史跡好きの方には強くお勧めします。

〈北条氏輝と北条氏家臣の墓〉



























 お寺を出て、寅さんがよく日向ぼっこしている江戸川の土手に出る。土手の手前には、葛飾柴又寅さん記念館・山田洋次ミュージアムや大正・昭和初期の旧邸である山本邸などの観光スポットもある。今回は時間の関係で残念ながら素通りし、江戸川の土手の散歩に時間を使った。さくらが自転車で通ったり、寅さんが昼寝するシーンを回想しつつ、映画のロケにはぴったりのような春を感じる日差しの中、白球を追いかけるユニホーム姿の少年たちを眺め、映画そのままの雰囲気を楽しんだ。
お寺を出て、寅さんがよく日向ぼっこしている江戸川の土手に出る。土手の手前には、葛飾柴又寅さん記念館・山田洋次ミュージアムや大正・昭和初期の旧邸である山本邸などの観光スポットもある。今回は時間の関係で残念ながら素通りし、江戸川の土手の散歩に時間を使った。さくらが自転車で通ったり、寅さんが昼寝するシーンを回想しつつ、映画のロケにはぴったりのような春を感じる日差しの中、白球を追いかけるユニホーム姿の少年たちを眺め、映画そのままの雰囲気を楽しんだ。