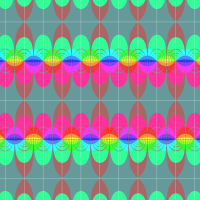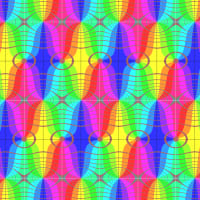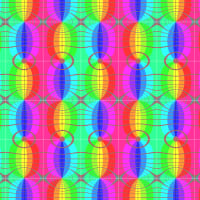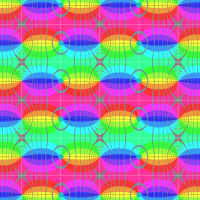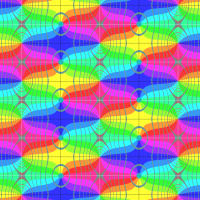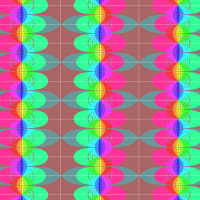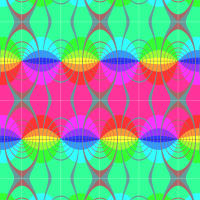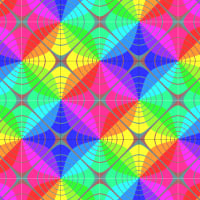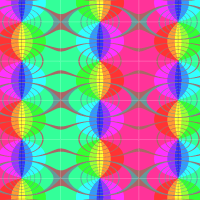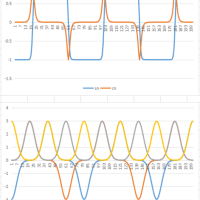本日は日曜日。今年は春に自宅待機があった関係で、夏頃からは仕事が詰んでいて、やっと休息が取れる感じです。幸いにも、正月付近はしっかり休みが取れそうな感じがします。みなさまいかがでしょうか。
世界情勢が急展開しそうな気配で、しかし、大筋はすでに主要国間で決定しているような気がするので、どう後始末するのかな、の感じがします。もちろん現在の主軸は米中対立です。気のせいか、日本人がこよなく尊敬するヨーロッパ諸国が振り回されている感じがします。日本はもろに当事者間のまっただ中にいるので、こちらも御同様と言えばそうなのかも。
元に戻って。と言う訳で、積み上がっている未読書の中の一冊、朝永振一郎の「新版 スピンはめぐる」を…、速読してしまいました。本来ならばこの本は古典としてじっくり読むべきで、多少反省しています。
時代は19世紀末から20世紀初頭の各領域の巨人の時代が終わった直後の時代です。数学は数学で、独自の危機(実数の連続とは何か)が訪れていて、21世紀初頭の今から見ると、解決策はすでにその重厚な古典数学の末裔(無限級数とその収束)に現れていて、しかし根本的な問題は解決不能(ゲーデルの不完全性定理)と解決とされていて、しかし、現代技術を支える実用数学(線形代数)はこの世の春を謳歌していて、まあ、話題には事欠きません。幸せな時代だと思います。
朝永博士のその著書は、現在の観点からはいささか古い部分があるみたいで、この新版では多分お弟子さん(?)が適宜書き換えているようです。その最大のものはCGSガウス単位系から、現在の国際標準のSI単位系への数式の書き換えで、すさまじい作業量で、よくやること。時代はニュートリノが発見された付近で、中性微子の旧名で記述されています。つまり、通常の物質を構成する素粒子はほぼ発見し尽くされていて、しかし、新素粒子がこれでもかと発見されていて、クォーク理論の出る少し前の時期です。
いや懐かしいです。私の小学生の頃の科学啓蒙書はこんな感じでした。ええと、リーダーズダイジェスト関係だったか。μ中間子が発見された頃だったか。
ディラックのブラとケットは出ていないみたいで、その代わりに行列が数式として出てきます。