■Free Live! (Island)
さてさて連日のオリンピックでは各国選手の頑張りが熱い感動と興奮を呼んでいるわけですが、しかし反面、我国絡みで体操や柔道に妙な誤解を憶測させる判定覆り事件が発生しているのは、どういうもんでしょう……。
それは確かに競技ルールの性質上、審判の主観が優先するは人間味ゆえの事かもしれませんが、それを判定後のクレームや観客のブーイングによって逆転させてしまうのは、それだけ競技の本質が曖昧となり、四年に一度の真剣勝負に水を差す結果になっている事は否定出来ません。
直言すれば、それは競技そのものを冒涜する行為に繋がりかねないと思いますし、選手や観客にも失礼じゃ~ないでしょうか?
例え判定にミスがあったとしても、それはそれで勝負は時の運!
きっちり決着をつけられなかった自らの実力の無さを反省するべきであって、そういう潔さこそが、殊更日本人の感性には合っていると思うんですがねぇ……。
逆に言えば、だからこそ勝負が分かり易い競技は面白いし、作為的な手抜きも作戦のひとつとして許容される範囲が認められているわけですよねぇ。
例えば昨夜の女子サッカーでは、我国なでしこの本気度が???
という問題を、何も八百長云々というのは野暮でしょう。
そこで本日は極めて分かり易い歌と演奏を堪能すべく、王道ロックの名盤ライプLPを取り出してきました。
A-1 All Right Now
A-2 I'm A Mover
A-3 Be My Freind
A-4 Fire And Water
B-1 Ride On A Pony
B-2 Mr. Big
B-3 The Hunter
B-4 Get Where I Belong
この熱演を繰り広げたフリーは、1960年代の英国ブルースロックをハードロックに融合発展させた名バンドとして、今や大衆音楽史には欠かせない存在だと思いますし、何よりも解散消滅後でさえ、ファンや信者を増やし続けている現実は直視されるべきでしょう。
ご存じのとおり、フリーは1968年のロンドンで、十代の若者4人によって結成され、そういう経緯は未だ世界中数多のバンドと異なるところはないはずです。
しかしフリーが凄かったのは、ポール・ロジャー(vo,g)、ポール・コゾフ(g)、アンディ・フレイザー(b)、サイモン・カーク(ds) というメンバー各々が、とてつもない個性派であり、自然体としか思えないブルースやソウルに対する感性をロックに結実させる力量を持っていたという事です。
それは翌年に発売され、忽ち名盤認定されたデビューアルバム「トンズ・オブ・ソブス」に明確に記録され、メンバーが全員二十歳前だったという真相を知るにつけても、驚異的でしょう。
う~ん、これは神様の思し召し!?
確かに時代は、既にロックと言えどもアルバムをメインに聴くが当然の流れになっていた状況も、特にヒットチャート向けのバンドでは無かったフリーには幸いしていたと思いますが、もうひとつ、彼等が注目されたのは、そのライプパフォーマンスの実力と凄さ!
本来がギミックを持ちあわせない音楽性であろうとも、強烈なロックビートとソウルフルな歌と演奏をストレートに観客へ伝える手法は、決して若気の至りの紛れ当たりではないはずです。
何故ならばフリーが残したライプ音源は何れも熱く、また1971年の初来日公演を含む当時の巡業ステージの凄さは伝説化しているとおりであって、それが同時期のスタジオ録音セッションに反映され、少なくとも1970年までに制作されていたアルバムやシングル盤は過言ではなく、名唱名演ばかり♪♪~♪
ですから、この4人組によるライプ盤を熱望する声は日増しに高まり、ついに1971年夏に発売されたのが、掲載したアルバムです。
しかも中身は極上の仕上がりで、そのギリギリの緊張感とヘヴィなピートの高揚感、さらには重苦しいばかりの歌と演奏の鬩ぎ合いは、まさに一期一会ですよっ!
なにしろA面初っ端からフリーを代表する人気ヒット曲「All Right Now」が、これぞっ! シンプル&ハードなロックピートで演じられ、サイモン・カークのドラムスがビシバシにキマれば、後は一気呵成の硬派なグルーヴ!
ヘヴィな蠢きとエグミ満点のボーカルがキツイ「I'm A Mover」、一転してスローなパラード風味ながら、実は哀愁ロックのネクラな展開がディープな「Be My Freind」と続く二連発には、汗ダラダラにさせられますねぇ~♪ 特に後者の抑えたギターソロは、ポール・コゾフならではのメロディアスなフレーズがテンコ盛りですし、前者におけるアンディ・フレイザーの朴訥にして饒舌なベースワークのアンバランス感も最高に好きです。
そしてAラス「Fire And Water」は、言わずもがなの代表曲のひとつとして、バンドが十八番のスローでヘヴィな蠢きロックが全開! あぁ……、ここでもフックの効いたメロディアスなギターを披露するポール・コゾフが、本当にたまりませんねぇ~~♪
全くLP片面だけで、フリーという稀代のロックバンドの真髄に触れることが出来るわけですが、言うまでもなく、そこにはポール・ロジャーという、破天荒なボーカリストが揺るぎなく、結局はここに存在する4人でなければ、フリーはフリーにならないという事でしょう。
実は良く知られているように、この当時のバンド内は人間関係の悪さが決定的であり、それは違法なクスリによるメンバーの健康問題や音楽性の相違等々、これからのグループの行く末をマイナスのベクトルにしか導けないほどの酷さだったと言われています。
このライプアルバムを出したのも、既に解散するしかない土壇場において、レコード会社との契約をクリアする目的があった事は、皆様ご推察のとおりなんですが……。
しかしそんなゴタゴタを微塵も感じさせないほどの名演が、ここに残されているのは流石のプロ根性なのか、それとも奇蹟なのか!?
ちなみに録音データを信じれば、ほとんどのトラックが1970年1月と9月の英国巡業から纏められているらしく、こうしたアルバムは通常、他のバンドでは様々な手直しがスタジオで行われるはずが、フリーに関しては、あまりそれも感じられないのは高得点!
まあ、真相は闇の中ではありますが、個人的には好感が持てます。
その意味でB面はさらに豪快にして熱血なフリーの本質が大爆発で、正統派ブルースロックが煮詰められてガチガチになった「Ride On A Pony」、狂おしいギターソロと極みのボーカルが対峙する「Mr. Big」、これまたお馴染みのブルースロックの定番リフを活かした「The Hunter」では、愚直なまでのバンドグルーヴと暑苦しいギターソロが混然一体化しており、これほど鬱陶しい仕上がりも無いっ!
正直、そう思う他はありませんねぇ~♪
ですから、特にメロディアスな歌も無く、またゼップのような構成力やザ・フーのような強引な暴虐もやらず、はたまたストーンズの如き悪魔的快楽性も発散出来ないフリーが、ここまで個性を確立してしまったのは、やっぱり時代の奇跡なんでしょうか??
好き嫌いは別にして、その分かり易さは絶対であり、穿った予断は許されないのが、全盛期のフリーだと思います。
もちろん残念ながら、彼等は直後にバラバラとなり、それでも離散集合を繰り返し、新しいメンバーを交えながら活動は暫時継続されていくのですが、常に哀しいものが付き纏った事は否定出来ません。
そこでオーラスに収められたアコースティックなフォーク系美メロ曲「Get Where I Belong」が、1971年3月のスタジオ録音、つまりは最後の挨拶的な印象に思えるのは、せつないほど……。
う~ん、これは全く名盤アルバムとしての条件も意義も、必要十分以上に満たしていると思います。
最後になりましたが、それでも以後のフリーが全然ダメ!?
という事をサイケおやじは言いたいわけではありません。
きっちりそれなりの良さも、味わいもあって、かなり好きなアルバムも出してくれました。
それは追々にご紹介していく所存ですし、後年になって発掘された音源も含めて、やっぱりフリーは全てがロックファンを夢中にさせるバンドだと思っているのです。
その基本が分かり易い凄さ!
それが万人の称賛を集める、決して覆らない判定だという事は、書いておきます。














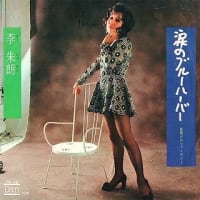

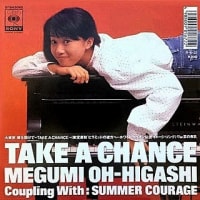








中学時代から友達と言ってたんですが
結局よくわからなかった感じなんです。
このライブも中坊時代、最もよく聞いたアルバムですが
ミスタービッグはベースソロの曲という認識でしたね。
コメントありがとうございます。
全体の意味は分かりませんが、「忍び泣き」とか、「むせび泣き」とか、そういうニュアンスじゃ~ないでしょうか?
また、その意味で、ジャケ写の「ミッキーマウス」みたいなのは???
まあ、サイケデリック時代の残滓でしょうかねぇ~?
それとフリーの魅力は剛直なドラムスと動きまくるペースの対比かもしれません。
「トンズ・オブ・ソブス」だけを買い、後はポールのバンド、バク・ストリート・クローラーを買ったのですが、当時高1の僕には、ちょっと難しい印象で、あんまり聞きませんでした。
その点、バッド・カンパニーは取っつきやすいサウンドで、そっちに夢中でした。
とは言っても、熱心に聴いたのは「ラン・ウィズ・ザ・パック」1枚だけですけど。
実は私、昨日まで「タンズ&ソブズ」だと思っていたのです。
タン(舌、タン塩)とかの関係なのかと。
あとウサギとかが意味深で、へんなデカイ顔とかもあるし、ヘンゼル&グレテル、チルチル&ミチルみたいな御伽噺的な名前関係かなとか思ってました。
まあどっちにしろ棺おけミッキーとは繋がらないですね。
このアルバム(トンズ)のギターは、ライブのナチュラルディストーションとは違って、マクソンのD&S(憶えてます?)使ってるみたいな音ですよね。
ちなみに当時ハンターを演るときは、トレモロアームを使ってデフォルメして演ってました。
コメント感謝です。
ポール・コゾフの訃報が女性週刊誌で報道されていたとは、知りませんでした。
決してルックス優先のギタリストではありませんからねぇ。
当時は、女にロックはわからない!
そんな時代にも、ポール・コゾフが広く女性の心を鷲掴みにしていた!?
それもまた、天才ギタリストに相応しいのでしょう。
バドカンの魅力はズバリ、分かり易さであって、ストレートな爽快感がウケた理由かと思います。
正直、現在でもフリーよりは人気が高いかと……?
コメント感謝です。
ポール・コゾフはデビュー時にはレスポール、フリー解散の頃はフェンダーストラトを使っていたと思います。
所謂「泣き」を演出する強靭なチョーキングとヴィブラートのコンビネーションは、マーシャルのアンプがあってこその魔術であり、腕の力も相当に強くなくては、あのような音は出せないでしょう。
今となっては、「筆を選ばず」の世界かもしれず、どんなギターでも、アンプでも、ポール・コゾフは常に激しくギターを震わせてくれるんじゃ~ないでしょうか。
個人的には真似する時、アームを使うのは同じです(笑)。