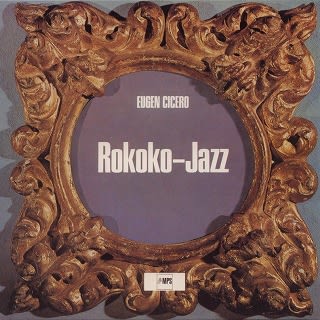■The Complete Quebec Jam Session / Clifford Brown (RLR = CD)
本日も「ブートもどき」のご紹介となりますが、それがクリフォード・ブラウンとあっては、ご容赦願えるものと思います。
内容はクリフォード・ブラウン自らが録音したとされるプライベートなリハーサル音源をメインに、おまけとしてエアチェックされたブラウン&ローチのバンド演奏が収められていますが、「All Tracks Previously Unissued!!」とジャケットに記載されているのは、その真偽は別としても、やはり嬉しいものがあります。実際、先日発見して、迷わずにゲットさせられましたよ♪♪~♪
☆1955年7月28日、カナダのケベックで録音
01 All The Things You Are
02 Lady Be Good / Hackensack
03 Strike Up The Band
04 Ow!
05 Sippin' At Bells
06 Brownie Talks
メンバーはクリフォード・ブラウン以下、Rob McConnell(tb)、そして多分、ハロルド・ランドと推測されるテナーサックスに正体不明のピアニストが加わった練習セッションですが、もちろんクリフォード・ブラウンは真摯に吹きまくりですし、その場の和んだ雰囲気もたまりません。
まず冒頭、日常的な音出しチューニングから、お馴染みのスタンダード曲「All The Things You Are」へと入っていく流れが、如何にもです♪♪~♪ ドラムスやベースが入っていませんから、当然ながらビシバシのビート感は楽しめませんが、クリフォード・ブラウンのハートウォームなトランペットは流石の歌心で、思わずグッと惹きつけられますよ。
気になる音質は、あくまでもプライベートな録音ですから、それなりですが、最新のリマスター技術によりノイズは極力抑えてありますし、音のメリハリも自然です。このあたりは入門者にはキツイかもしれませんが、ある程度ジャズに親しんだ皆様ならば、納得してお楽しみいただけると思います。
それは後の演奏にも同じく言えることですが、その合間の会話等も興味深く、当時二十歳になったばかりだったというトロンボーン奏者の Rob McConnell も大健闘! またピアニストはパド・パウエル直系のスタイルで好感が持てます。
ちなみに「Brownie Talks」では、録音年月日を吹き込むクリフォード・ブラウンのリアルな肉声が、なんとも貴重だと思います。
☆1955年11月、シカゴでの放送録音
07 A Night In Tunisia
08 Billei's Bounce
09 A Night In Tunisia (source 2)
10 Billei's Bounce (source 2)
11 Fine And Dandy
続くパートはシカゴのクラブ「Bee- Hive」からのラジオ放送をエアチェックした音源で、メンバーはクリフォード・ブラウン(tp)、ソニー・ロリンズ(ts)、ニッキー・ヒル(ts)、ビリー・ウォレス(p)、Leo Blevins(g)、ジョージ・モロウ(b)、マックス・ローチ(ds) ということで、時期的なものも勘案すると、アナログ盤時代に「ロウ・ジニアス Vol.1 & 2」という日本盤オリジナルで発掘発売され、後に「Clifford Brown Live At The Bee Hive (Lonehill Jazz)」としてCD化された音源の頃の演奏でしょうが、このブツに収められた上記演目は、そこには入っていませんでしたから、これも嬉しい♪♪~♪
まず「A Night In Tunisia」はクリフォード・ブラウンのトランペットが実に丁寧な、そして歌心いっぱいのアドリブで、もう最高です! 続くテナーサックスは多分、ニッキー・ヒルでしょうが、その古いタイプのスタイルが逆に良い感じですし、Leo Blevins のギターの音色にしても、その真空管の響きがたまりません。
ちなみに音質は、これもそれなりですが、ちょうど歴史的名盤に選定されている、あの「ミントンズ」のジャムセッションと似たような味わいです。ただしバランスがエレキということもあるでしょうが、少しギターが大きめなんでねぇ。このあたりは賛否両論かもしれません。
そして「Billei's Bounce」でのクリフォード・ブラウンが、これまた凄すぎます! 極めて自然体でありながら、全てが「歌」のアドリブフレーズが溢れて止まりませんよっ! あぁ、これを聴いたら、久しくジャズモードには疎遠となっていたサイケおやじも、見事にカムバックさせられましたですよ♪♪~♪
そのあたりがさらに強調されているのが、トラック「09」と「10」で、これは「source 2」としてあるように、演奏そのものは同じみたいですが、クリフォード・ブラウンのソロパートをメインに短く編集され、また音質も軽めになっていますが、メリハリのある明るいものに変えられていますから、結果オーライでしょう。正直、こっちのほうが楽しめるかもしれません。
また、「Fine And Dandy」は終盤のクライマックスのみの録音で、ドラムスとフロント陣のソロチェイス! 短いのが本当に残念ですが、ふっと気がつくと、このパートの音源にはソニー・ロリンズが入っているのか? これは疑問です。
☆1955年春、ボストンでの放送録音
12 Gerkin' For Perkin'
13 It Might As Well Be Spring
これもエアチェック音源で、ボストンの有名店「Storyville Club」での演奏です。
メンバーはクリフォード・ブラウン(tp)、ハロルド・ランド(ts)、リッチー・パウエル(p)、ジョージ・モロウ(b)、マックス・ローチ(ds) という当時のレギュラーバンドですから、名演は必定!
まず「Gerkin' For Perkin'」は、テーマアンサンブルの荒っぽさがハードバップのど真ん中で、もちろんクリフォード・ブラウンのアドリブは素晴らしい限り♪♪~♪ 続くハロルド・ランドも熱演ですし、リズム隊の熱気はリアルタイムの勢いに満ちていると思います。
そして「It Might As Well Be Spring」は説明不要、クリフォード・ブラウンの十八番ですから、その安らぎに満ちたトランペットの節回しと歌心が満喫出来ますよ♪♪~♪
気になる音質は、もっさりしたオリジナルソースを最新の技術で聴き易くしてありますし、これだけの演奏に接する喜びからすれば、文句を言うのはバチあたりでしょう。サイケおやじは本当に、そう思います。
☆1956年初頭、ロスでのテレビ放送音源
14 Lady Be Good
15 Meomries Of You
これはネットでも流れているクリフォード・ブラウンのテレビ出演映像から、音声だけを収録したパートです。
一応、解説書に記載のデータによると、メンバーはリッチー・パウエル(p)、ジョージ・モロウ(b)、マックス・ローチ(ds) というリズム隊をバックにしたクリフォード・ブラウンのワンホーン演奏ですが、流石の完成度は圧巻!
まず「Lady Be Good」での、流れるようなメロディフェイクとアドリブの歌心は素晴らしいとしか言えませんし、それが終わって、間髪を入れずに始まる「Meomries Of You」が、これまた絶品♪♪~♪ 2曲合わせても4分ほどの演奏時間ですが、最後には短いインタビューも聞けますし、これも世界遺産でしょうねぇ。
願わくば、映像の完全復刻も実現しますようにっ!
ということで、音質やソースの出どころがどうであれ、やっぱりクリフォード・ブラウンは凄くて、しかもハートウォームな魅力がいっぱい♪♪~♪
決して万人向けではありませんが、やはり聴かずに死ねるかのブツだと思います。
そしてサイケおやじが、どうにかジャズモードへと気持ちが戻りつつあるのも、この天才のおかげなのでした。