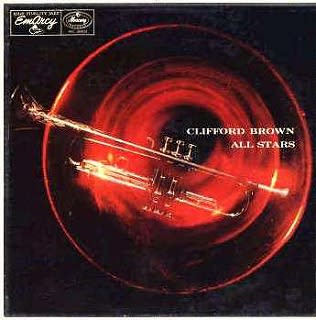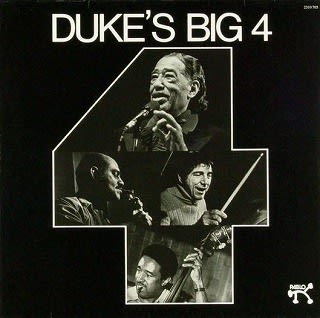■Moonbeams / Bill Evans (Riverside)
ジャズピアノの歴史を振り返れば、その最高峰のひとつが、スコット・ラファロ(b) と組んでいた時期のビル・エバンス・トリオでしょう。異論は無いと確信しています。
しかし、この素晴らしいトリオも1961年7月、スコット・ラファロの突然の悲報によって消滅……。以降、ビル・エバンスは失意の中で幾つかのセッションを行い、もちろんその中にはジム・ホール(g) との奇跡の名演となった「Undercurrent (United Artists)」も残されていますが、やはり……。
そして1962年5&6月、約1年ぶりのリーダー吹き込みから作られたのが、本日ご紹介のアルバムです。メンバーはビル・エバンス(p)、チャック・イスラエル(b)、ポール・モチアン(ds) という、もちろんこれは新生ビル・エバンス・トリオとしての再出発を記録しています。
ちなみにこの時は3回のセッションからアルバム2枚分の演奏が残され、それをスロー系とアップテンポ系に分けて発売した制作者側の意図については賛否両論でしょうが、個人的にはスロー系中心のこちらが、ビル・エバンスの美学や当時の心境が滲み出ているような気がして、かなり好きです。
A-1 Re: Person I Knew (1962年5月29日録音)
A-2 Polka Dots And Moonbeams (1962年6月5日録音)
A-3 I Fall In Love Too Easily (1962年6月5日録音)
A-4 Stairaway To The Stars (1962年6月5日録音)
B-1 If You Could See Me Now (1962年517日録音)
B-2 It Might As Well Be Spring (1962年6月5日録音)
B-3 In Love In Vain (1962年6月5日録音)
B-4 Very Early (1962年5月29日録音)
演目は上記のように、有名スタンダードが嬉しい選曲ですが、最初と最後にビル・エバンスのオリジナルを配置する構成はニクイばかりです。
その「Re: Person I Knew」はリバーサイドの主催者だった Orrin Keepnes の名前を綴りかえした、これから後もライブでの十八番となる抽象的なモード曲ながら、まさにビル・エバンスならではの耽美な味わいが、このアルバムの中では最も力強いテンポで表現されています。ポール・モチアンのブラシ主体のドラミングも、なかなか躍動的でツッコミ鋭く、このあたりはスコット・ラファロ時代の良さが継続されているわけですが……。
残念ながら、そこに拘泥すると、新参加のチャック・イスラエルが惨めになるでしょう。実際、真剣な自己表現とビル・エバンスの意図を理解しようと務める姿勢は好感が持てるのですが、失礼ながら、やはり持っている資質には限界を強く感じてしまいます。
このあたりは当時の誰が入っても、同じだったのは確実な結果論でしょうねぇ、何もチャック・イスラエルだけが劣る存在ではないと思います。
それを百も承知のビル・エバンスは、それゆえに尚更、自己を掘り下げる道を選んだのでしょうか、続く有名スタンダード曲の解釈は、何れも素晴らしすぎます。
素直なフェイクからトリオしての間合いの芸術を披露する「Polka Dots And Moonbeams」、シンプルな表現でメロディとハーモニーの魔法に耽溺していく「I Fall In Love Too Easily」、さらに力強いビートと意外にもグルーヴィな表現が横溢している「Stairaway To The Stars」というA面の美しき流れは本当に良いです。
そしてB面では、まず「If You Could See Me Now」がオリジナルメロディの素晴らしさに負けている雰囲気も否定出来ませんが、それでもビル・エバンスならではの表現は捨て難く、中盤からの疑似ワルツテンポの表現は如何にも「らしい」です。
しかし「It Might As Well Be Spring」での幾分の勘違いは個人的に残念……。ただしこれは、あくまでも私だけの気分ですから、十人十色の好みの問題でしょう。
それを払拭してくれるのが「In Love In Vain」の耽美な名演です。なにしろ原曲メロディよりも素敵なアドリブメロディが出ていますし、どこまでも美意識優先に深化していくビル・エバンスの世界が、完全にビル・エバンス本人を中心に表現されていると感じます。まさに新生トリオの今後の道という感じでしょうか。
締め括りの「Very Early」もまた、ビル・エバンスのオリジナル曲という以上に、「エバンス中心世界」が、それこそ気持良いほどに展開されています。十八番のワルツテンポで愛らしいメロディを綴るピアノには、真摯なベースも小技を駆使するドラムスも、入り込めない世界があるんじゃないでしょうか。そこが尚更にビル・エバンスの魅力となって、耽美な感性が浮き彫りになった気がしています。
ということで、チャック・イスラエルには気の毒な聴き方しか出来ませんでしたし、ポール・モチアンにしても以前の柔軟にして奔放なスタイルを些か封じ込められた結果のようです。その所為でしょうか、ポール・モチアンはほどなく、このレギュラートリオから抜けているわけですが……。
この点に関しては、既に述べたように、同じセッションから作られたもう1枚のアルバム「How My Heart Sings!」を聴いても感じられるところじゃないでしょうか?
しかしビル・エバンスの最も「らしい」美学は、ここから再スタートして次なる安定期へと向かい、多くのファンを魅了していくのですから、このアルバムも裏名盤でしょう。
美女ジャケットとしての人気も抜群♪♪~♪
ちなみに、このジャケットの彼女は、この角度で鑑賞するのがベスト! 試しにジャケットの向きを変えて飾ったりしましたが、これは皆様もご経験があるのでは?