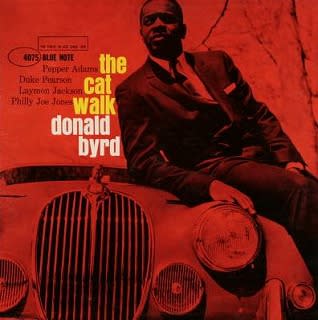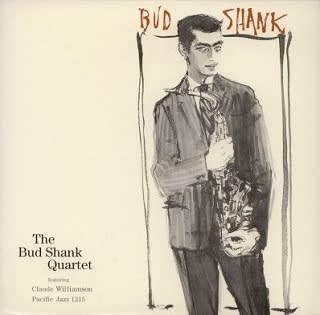■Understanding / John Patton (Blue Note)
所謂コテコテ派とされるジョン・パットンですが、私は基本的に、この人はモダンジャズにどっぷりのオルガン奏者だと思っています。
そのあたりを存分に堪能出来るのが本日ご紹介の1枚♪♪~♪
録音は1968年10月25日、メンバーはジョン・パットン(org)以下、ハロルド・アレキサンダー(ts,fl)、ヒュー・ウォーカー(ds) という実力派を従えたトリオで、あえてオルガンジャズには付き物のギター、あるいはソウルジャズには必須のエレキベースを排除した編成に、その本気度の高さがあるように思います。
A-1 Ding Dong
ハロルド・アレキサンダーのオリジナルで、ポリリズムのラテンビートを使った愉快な曲ですが、小型エルビン・ジョーンズとも言うべきヒュー・ウォーカーのドラミング、さらにヘヴィなベースラインと分厚いコードを提供するジョン・パットンに煽られた作者のテナーサックスが、それこそアグレッシプに爆発する展開が痛快至極!
実際、ヒステリックなフリー寸前にまで昇りつめるハロルド・アレキサンダーは、決して有名ではありませんが、その実力は流石に侮れません。
そして同じくヒュー・ウォーカーの軽くて重い、二律背反のドラミングが、これまた心地良いんですねぇ~~♪
ですからジョン・パットンのオルガンが何の迷いも無く、モード節を基本にしつつも、実に素直にノリまくったアドリブを披露するのは当然が必然だと思います。
A-2 Congo Chant
タイトルどおり、当時の流行だったアフリカ色が強いジョン・パットンのオリジナル曲で、初っ端から不穏な雰囲気を滲ませるハロルド・アレキサンダーのテナーサックスが印象的! そしてもちろん、ジョン・パットンのオルガンは硬派に唸っていますよ。
それをバックアップするヒュー・ウォーカーのドラミングが、これまたモロにエルビン・ジョーンズしているのも、既にして「お約束」でしょう。
肝心のアドリブパートでも、そのあたりの気概は満点! と同時に、些かの煮え切らなさが尚更にモダンジャズの最前線という感じも、かえって好ましいと思います。
つまり極言すれば楽しくない演奏なんですが、こういう真っ向勝負を捨てきれないところがジョン・パットンの資質なんでしょうかねぇ~。繰り返しますが、私は好きです。
加えてハロルド・アレキサンダーが、またまたの暴走フリーモード! しかし決して迷い道ではないところが、流石にブルーノートの底力だと思います。
A-3 Alfie's Theme
そして一転、アップテンポで爽快にブッ飛ばす演奏は、ご存じ、ソニー・ロリンズが畢生のヒットメロディ♪♪~♪ ウキウキするようなテーマ部分は、もう少し緩いテンポが良いと思いますが、そうすれば必然的にロリンズバージョンとの比較が避けられませんから、これで結果オーライでしょうか。
しかし演奏そのものの熱気は素晴らしく、激烈モード節を基本に疾走するハロルド・アレキサンダーが自然とロリンズ節を出してしまうのも、憎めません。正直、ちょいと姑息な感じもするんですが、まあ、いいか♪♪~♪
気になるジョン・パットンのオルガンは、可も無し不可も無し……、なんですが、その安定感はやはり名手の証に他なりません。
B-1 Soul Man
これまた嬉しい選曲で、アメリカ南部を代表するスタックスR&Bのブルーノート的解釈が最高です♪♪~♪ 軽いブーガルービートを活かしたイナタイ雰囲気が、まず心地良いですねぇ~♪ ジョン・パットンのオルガンもダークなムードを演出していますが、やはり基本はモード系ハードバップという趣がニクイところです。
ハロルド・アレキサンダーも、そのあたりを十分に飲み込んだソウルフルなプローを聞かせてくれますが、時折のエキセントリックな節回しに見事に呼応するヒュー・ウォーカーのドラムス! これがジャズ!
演奏全体の些か弛緩したムードと厳しさの対比という、見事な緊張と緩和が実に楽しいです。
B-2 Understanding
アルバムタイトル曲は、またまたユルユルのモードファンクというか、ダサ~い雰囲気が逆に好ましいと感じるのは、レアグルーヴなんて言い訳が出来るからでじょうか……。個人的には辛いものがあります。
ただし妙な心地良さも確かにあって、怠惰な休日、空しいセックスの余韻、あるいは会話の途切れた恋人達の道行き……、そんな感じでしょうか。あまくでも私的な感想ではありますが、そんなこんなも日常生活には必要という演奏だと思います。
B-3 Chittlins Con Carne
オーラスは本当に聴く前から楽しみになってしまう選曲!
ご存じ、同じブルーノートでケニー・バレルがソウルフルに演じきった自作の素敵なメロディですからねぇ~~♪
それをジョン・パットンは軽いボサロックに変換し、ハロルド・アレキサンダーが決して上手くはないフルートでやってしまったという、その味わい深さが、たまりません♪♪~♪
しかし演奏が進むにつれて白熱化していくバンドのグルーヴ、ジョン・パットンのオルガンのツッコミ塩梅が絶妙です。オリジナルバージョンよりもテンポアップしているところも正解だと思います。
そしてハロルド・アレキサンダーのフルートが、ハービー・マンやローランド・カークの得意技を拝借する茶目っ気で、思わずニンマリですよ♪♪~♪ 正直言えば、これまた姑息な手段なんですが、それも楽しいのがモダンジャズの醍醐味じゃないでしょうか。私は好きです。
ちなみに曲タイトルは黒人風モツ煮込み料理と同義でしょう。これがアメリカにしては、なかなか美味いんですよね。ちょっと甘ったるい味なんですが、ここでの演奏は辛口か効いています。
ということで、嬉しい選曲と安定充実した演奏のバランスが良い快楽盤です。
ただし全盛期ジャズ喫茶では完全に無視されていた事実も確かにありましたし、それほど売れたという話も聞きません。実際、1970年代の中古盤屋では捨値の代表格でもありましたから、私はその頃に入手したのが真相です。確か千円、していなかったような……。
しかし内容はイノセントなジャズファンにも十分楽しめるものだと思いますし、それゆえにコテコテ派には些か肩すかしかもしれません。
まあ、そのあたりにジョン・パットンの真髄があると言えば、贔屓の引き倒しではありますが、機会があれば、ぜひともお楽しみ下さいませ。