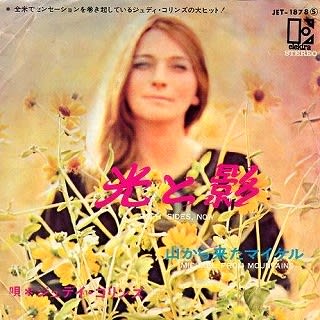■街角のプレイガール / Del Shannon (Big Top / 日本ビクター)
オールディズというよりも、洋楽懐メロのスタアの中で、サイケおやじが殊更好きな歌手がデル・シャノンです。
それはキメのパートで用いる特徴的なファルセットもそうですが、もうひとつ、ソングライターとしての才能がサイケおやじの好みにジャストミートしているんですねぇ~~♪
とにかく歌ってくれるメロディが良い感じ♪♪~♪
1963年にヒットした本日掲載のシングル盤A面曲「街角のプレイガール / Little Town Flirt」にしても、そのメロディラインは所謂黄金律であり、同時進行していた英国のマージービートに与えた影響も少なからずという推測は、後にジェフ・リンが主導していたエレクトリック・ライト・オーケストラ=ELOにカバーされたという状況証拠も出ていますし、パクリという段階においては、例えば我が国では吉田拓郎の自作自演、あるいはモップスのカバーバージョンで大ヒットした「たどりついたらいつも雨降り」とか、大滝詠一の「我が心のピンボール」等々、沢山ありますよねぇ~~♪
ちなみにELOのバージョンは名盤「ディスカバリー」のCDボーナストラックで聴けますが、デル・シャノンのオリジナルバージョンを特徴づけていたリズムパターンを巧みにマージービートに変換させたあたりは、相当に好きなんでしょうねぇ~~。
もちろん、さらに後の1980年代末、ジョージ・ハリスンやボブ・ディランと一緒にジェフ・リンが参加していた覆面プロジェクトのトラヴェリング・ウィルベリーズの構成員だったロイ・オービソンの急逝に伴い、補充メンバーにデル・シャノンを押していたのもジェフ・リンだったという噂も忘れ難いところです。
それと毎度の昔話で恐縮なんですが、サイケおやじが学生時代に入れてもらっていたアマチュアバンドでは、ちょうど洋楽ジャンルでブームになっていたオールディズリバイバルの中、グランド・ファンクがリトル・エヴァの代表曲「ロコモーション / The Loco-Motion」をカバーして大ヒットさせた実績に便乗し、同じ様なアレンジを流用させてもらっては、この「街角のプレイガール / Little Town Flirt」もやっていたんですが、もちろん、その下心はモップスの「たどりついたらいつも雨降り」だったという懺悔の告白をさせていただきます。
あぁ、当時、件のELOのバージョンに接していたらなぁ……。
なぁ~んていう恥ずかしい思いは拭いされないわけですが、それはそれとして、もうひとつ気になるのが、この曲の共作者としてクレジットされているマロン・マッケンジーという人物で、残念ながらサイケおやじは詳しい実績等々、知る由もありません。
しかし、マニアックな世界では有名なのかなぁ~?
と思うばかりです。
最後になりましたが、デル・シャノンと言えば、我が国では「街角男」の異名もあるほど、とにかく発売される楽曲の邦題には「街角」という言葉が用いられているんですが、ど~せならば「街角箱」とかの名称でコンプリートな音源復刻を強く望んでいるのでした。