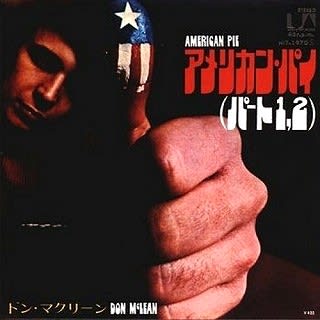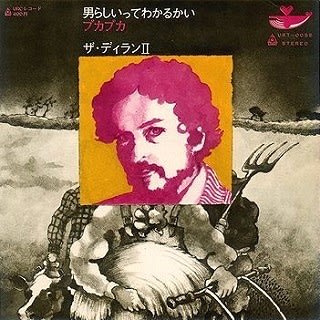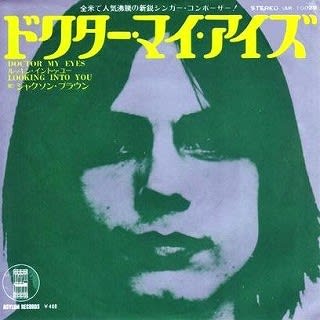■男らしいってわかるかい c/w プカプカ / ディランII (URC)
いゃ~~、
ボブ・ディランがノーベル文学賞!?! という昨夜の報道には驚かされたという気分が半分、同時に昔っから本命が不在の時の穴馬(?)なぁ~んていうジョークめいた話も出ていましたから、ノーベル財団もずいぶんと物分かりが良くなったんだなぁ~~!?
そんな不遜な気持ちも半分はあったんですから、それこそサイケおやじの天邪鬼も極まってしまった証といえば、ミもフタもありませんが……。
ですから、とにかく音楽業界でメシを喰っている連中がそれを悪くいうはずもないし、表立って誹謗中傷でもしようものなら、そんな戯言を放った者が笑われるのは必定でしょう。
もちろん、サイケおやじも肯定派であることに違いはありませんし、近年夥しく、それも膨大な分量のアーカイヴシリーズを出しまくっているボブ・ディランの活動がさらに盛り上がっていくのであれば、歓迎するのは自らの経済状況と相談しなければならないという、所謂嬉しい悲鳴が抑えきれません。
さて、そこで本日掲載したのは、ボブ・ディランについて何か書こうと思い立ち、あれこれとレコード棚を物色していたら出て来たというシングル盤で、何故ならば、それは松平維秋がデザインしたというスリーブがまずは素敵過ぎますよねぇ~~♪
しかし、これは決してボブ・ディランのレコードじゃ~なくて、実は我が国のフォーク系グループで関西を拠点に活動していたディランII(セカンド)のデビュー作として、昭和46(1971)年夏に発売されたシングル盤です。
そして今となってはB面に収録された「プカプカ」がフォークを越えた人気曲として知られているわけですが、しかし、今日のお題はディランですから、このA面収録の「男らしさってわかるかい」がボブ・ディランの人気有名曲「I shall be released」の替え歌であるという事実こそが大切!?
それはディランII(セカンド)が最初は大阪の難波にあった喫茶店「ディラン」の関係者や常連客で結成された経緯があり、当初は大塚まさじ、西岡恭蔵、永井洋が中心となって「ザ・ディラン」と名乗っていたんですが、諸事情からレコーディングの話が来た時には西岡恭蔵が抜けていたために「ディランII(セカンド)」名義で活動する事になったと云われています。
で、この「男らしさってわかるかい」のレコーディングは昭和46(1971)年5月に行われ、大塚まさじ(vo,g) &永井洋(vo,g) のディランII(セカンド)をサポートしたのが鈴木慶一(p)、上村律夫(org)、ピロ(b)、松本隆(ds) というのが定説なんですが、既に述べたとおり元ネタはボブ・ディランの楽曲ですから、メロディはオリジナルに近くとも、歌詞の中味は翻訳、あるいは意訳というよりも、大塚まさじ&ピロによる創作と定義しても差し支えないと思います。
そのあたりは皆様がそれぞれにボブ・ディランの「I shall be released」の英語詞とディランII(セカンド)の「男らしさってわかるかい」で歌われているものを聴き比べ、あるいは読み比べてみれば、おそらくは十人十色の好き嫌いはあろうかと思いますが、個人的にはディランII(セカンド)の「男らしさってわかるかい」の世界も嫌いではありません。
ヤツらは楽な方を 取るのさ
誰とでも 手をつなぎながら
でも 俺は断じて俺の
考え通りに生きるんだ
朝日は もう昇るよ
少しずつだけどね
そのとき その日こそ
自由になるんだ
上記した歌詞のパートは「男らしさってわかるかい」の中でも、特にサイケおやじが好きなところです。
さて、ここまで書いてしまえば、ど~しても触れておかなければならないのがB面収録ながらラジオの深夜放送を中心にヒットして以降、今や我が国の裏スタンダード曲となり、様々な歌手やグループによってカバーもどっさり吹き込まれている「プカプカ」です。
それは今更説明不要かもしれませんが、西岡恭蔵の作詞作曲で、歌の中の中心人物はジャズシンガーの安田みなみ? という真相もあるようですが、その真偽をサイケおやじは知る由もありません。
しかし何があっても「タバコをプカプカ」という歌の世界は、まさに昭和40年代後半のムードであり、これはサイケおやじと同世代の皆様ならば、きっと共感していただけるものと思います。
ちなみにレコーディングメンバーはディランII(セカンド)に加えて鈴木慶一(p)、細野晴臣(b)、松本隆(ds) と云われていますが、このシングルバージョンは後に作られたディランII(セカンド)のLP「きのうの思い出に別れをつげるんだもの」とは異なりますので要注意!
サイケおやじとしては、そのLPバージョンの方がヘヴィなサウンドになっているので好みなんですが、大塚まさじのボーカルに特徴的なある種のネチッコさに微妙な安らぎが滲むシングルバージョンにも捨てがたい魅力を感じてしまいます。
ということで、最後に告白させていただければ、サイケおやじは高校生の頃、校内同好会のバンド組で、この2曲を演奏した事があります。
それは年末恒例の発表会という場の校内ライブだったんですが、これまで拙ブログで度々書いてきたように、その頃にロックを追及していたバンド組は空前の歌謡フォークブームに押されてメンバーも最小限の5人体制だったところから、ドラマーの最上級生が抜けてしまい、ベースの先輩がドラムス、サイケおやじがベースにコンバートされ、後はボーカル&ギターの先輩と無口な上級生女子のキーボードという、本当に苦しい状況でしたから、やれる演目も限られて……。
ついには日本語のフォークをやらざるをえないという窮地(?)から、ボーカルの先輩が選びだしたのが、掲載したシングル盤に収録の2曲でありました。
尤も件の先輩は岡林信康の信者でしたからねぇ~、日本語を歌うことにも、それをロックと認識すれば抵抗はなかったみたいですし、現実的にはバンド組もそれまでに日本語の歌をやっていたのですから、何を今更ってな居直りも確かにありました。
しかし顧問の教師からは、もっと前向きな歌をやるようにっ!
なぁ~んていう、何時もどおりに注意され、相変わらず分かっちゃ~いませんでしたよ。
うむ、ボブ・ディランは今頃何を思っているのかなぁ~~。