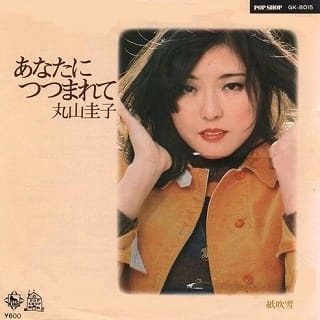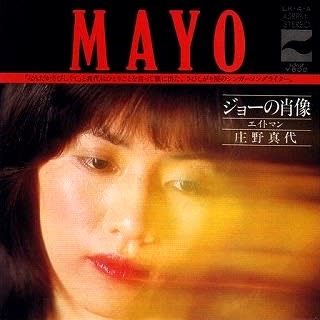■Chicago c/w Simple Man / Graham Nash (Atlantic / ワーナーパイオニア)
ご存じ、ホリーズ~CSN&Yで大活躍したグラハム・ナッシュの、これは1971年に世に出た初めてのソロアルバム「ソング・フォー・ビギナーズ」に収められていた人気曲をカップリングしたシングル盤なんですが、やはりと言うか、案の定と申しましょうか、アルバム収録のトラックよりも音圧が高いところに微妙な別ミックス疑惑(?)を感じるのは、サイケおやじの不遜な独断による偏見でしょうか。
しかし、それはそれとして、グラハム・ナッシュに対する一般的な認識は、個性の強いCSN&Yの中にあっては一番の穏健派というイメージでありましょうが、実はグラハム・ナッシュはホリーズ在籍当時から、かなりの政治的思想を持ち併せていた進歩的なミュージシャンだったという見方も出来るはずです。
ところが自作曲のメロディーにはハートウォームな分かり易さがあるもんですから、それに乗せて披露される歌詞の過激で「前のめり」な中身が、英語が基本的に使われていない我国の洋楽ファンには伝わっていなかった現実がありましたからねぇ~~。
普通にメロディラインやビート感、そして歌詞の語呂のリズム的楽しさだけに親しむばかりであっては、なかなかグラハム・ナッシュの気骨には触れる事が叶わず、だからこそ、我々洋楽ファンはグラハム・ナッシュの歌を気楽に聴けるという利点を大切にしなければならないはずです。
そこで、このA面曲「Chicago」は、ヘヴィな感触を強調したリズムを用い、ピアノやオルガン、そしてギター等々を操りつつ、グラハム・ナッシュが我欲優先の政治家や権力者を糾弾するという、なかなか熱いゴスペルロック!
これを聴くと、ビリー・ジョエルの「Stranger」や西城秀樹の「ギャランドゥ」が聞きたくなるという皆様も大勢いらっしゃるにちがいないほど、キャッチーやメロディのキメとグイノリのロックビートがたまりません♪♪~♪
ちなみに印象的なバックコーラスは当時のスワンプロックには欠かせない人材だったクライド・キングやリタ・クーリッジ等々が参加しているのも高得点♪♪~♪
一方B面の「Simple Man」は、せつなくも愛らしい素敵なメロディとグラハム・ナッシュのナチュラルな歌声がジャストミートした傑作で、その如何にもの「らしさ」こそが、ファンには絶対的なプレゼントなんですねぇ~♪
もちろん、ここでもリタ・クーリッジのハーモニーボーカルが良い感じ♪♪~♪
ということで、本日唐突にグラハム・ナッシュが聞きたくなったのも、PCに入れている様々な音源を整理している最中の寄り道鑑賞でした。
つまり、片づけをやりながら、その都度、それらの対象に気を惹かれては作業が進まないという、サイケおやじの何時もの悪癖が出てしまったというわけです。
やれやれ、ど~にもなりません……、失礼致しました。