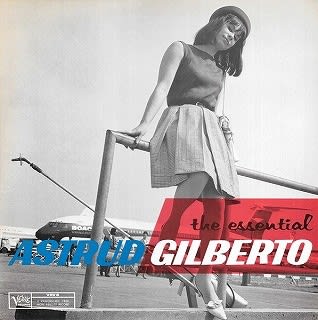■Take It To The Limit / Eagles (Asylum / ワーナーパイオニア)

ポコ ~ イーグルスというアメリカ西海岸ロックの偉大なるバンドに在籍し、大活躍したランディ・マイズナー(vo,b,g) の訃報に接しました。
基本的にアメリカ西海岸ロックが大好きで、学生時代には、そんなこんなのコピーもやっていたバンドに入れてもらっていたサイケおやじとしては、あのハイトーンボイスによる故人のコーラスワークや節回しが大好きでしたねぇ……。
さて、そこで掲載したのは、故人の代表的な名唱が強い印象を残したイーグルスの「Take It To The Limit」をA面に入れたシングル盤で、これは皆様ご存じのとおり、1975年に発売されたイーグルスの傑作アルバム「呪われた夜 / One of These Nights」からシングルカットされ、同年晩秋から大ヒットした人気曲であり、同バンドの中心的ソングライターコンビのドン・ヘンリー&グレン・フライとの共作者として、ランディ・マイズナーの名前がクレジットされているところから、しっかりとリードも歌った哀切のロックワルツ♪♪~♪
その歌詞は、失ってしまった恋愛への未練と高速道路の制限速度を結び付けたとしか、サイケおやじには理解出来ない世界ではありますが、せつないメロディ展開と陰陽が絶妙のコーラスワークを活かしきった故人の歌いっぷりは、正に最終パートでのファルセット&ハイトーンボイスが大団円の素晴らしさ ♪♪~♪
これぞっ! イーグルスならではのサウンドの妙を堪能させてくれる名曲にして、大名唱でありましたですねぇ~~♪
しかし……、これは以前にも拙ブログで書きましたが、この「Take It To The Limit」が大ヒットしている頃からイーグルスは内部で紛糾が続き、まずはバーニー・レドンが脱退、ドン・ヘンリーとグレン・フライの権力闘争、そして……、ついにはランディ・マイズナーも辞めてしまうという流れの中で、発売されたベストアルバムはバカ売れし、畢生のロックアルバム「ホテル・カリフォルニア」が制作されていったのですから、この世は儘なりません……。
つまり、そ~した大成功の最中に、それを捨て去るが如き行動をやってしまった故人は、一般的感覚では理解不能な人物かもしれませんが、しかし、ランディ・マイズナーというロックミュージシャンは、なかなかの苦労人であり、1960年代中頃に高校を中退してまでもバンドマンとしての生き様を選択し、ローカルバンドを転々としながらも結婚して妻子を養い、時には悪いクスリの売人までやっていたと云われるほどでしたが、ついに冒頭で述べたとおり、ポコのスタート時のレギュラーメンバーに決定した事から、後の成功への足掛かりは出来たはずなんですが……。
なんとっ!?
ここで最初のアルバムをレコーディング中にバンドの方針に反旗を翻したというか、件のデビュー作が発売された時にはポコを辞めてしまっていたという頑固者の本領を既に発揮!?
もちろん、忽ち路頭に迷ったところで様々なバイトをやっていたそうですが、ここでカントリーロックに転身していたスタアシンガーのリック・ネルソンのツアーバンド結成に参画し、そのストーン・キャニオン・バンドのリーダー格に収まったところから、再び業界の第一線へ復帰、ついにはイーグルスの結成へと歩みを進めたわけですが、そんなキャリアの持ち主なればこそ、大成功していたイーグルスにさえも納得出来ないものを感じれば、自らの信じる道を選んだのでしょう。
ですから、以降のランディ・マイズナーは些か地味な活動ばかりで、時折にポコの再結成やロック界のレジェンドツアーに参加する他は、それほど表舞台に登場する事も少なくなっていた中で、確か……、20年ほど前から心臓病やアル中で逼塞状態……。
まあ……、故人の様な浮き沈みの激しいスタア芸能人は少なくありませんが、一徹な人生を送ったのだとしたら、それもまたロックな生き様だったのでしょうか……。
サイケおやじは、ランディ・マイズナーを忘れません。
今……、胸中には「Take It To The Limit」を熱唱する故人の歌声が去来しています。
衷心より、合掌。