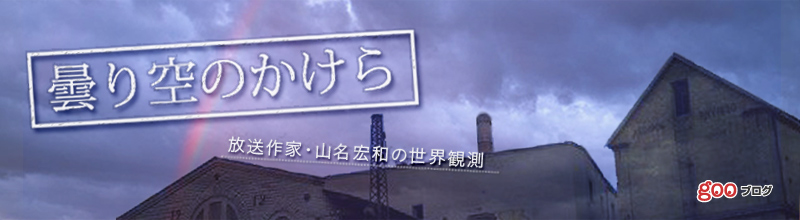ピアノの発表会、といっても、ささやかなものだが、
まあ、それに出かけたのだった。
その会場で、
後ろの席に座った親子が最悪だった。
正確には、父親が。
自分の子どもの演奏が終わった後、
客席で他の子どもの演奏を見ているのだが、
父親がずっと我が子になにやら話しかけている。
子どもが父親にではない。
父親が子どもにだ。
演奏に対する感想ならば、
まあ、それもちょっとどうかと思うが、
1000歩譲って、よしとしよう。
しかし、父親が話しているのは、
目の前で行われている演奏とはまったく別の話だ。
たとえば、
「近所の音大の先生にピアノを教わると1時間50万円」
そんな話を小学校低学年の娘に話してどうする?
さらに、ステージ上のグランドピアノを見て、
「あのピアノ高そうだな」
聞いていると、その父親、金がらみの話しかしていない。
しかも、高価=いい、という価値観の持ち主のようで、
そんな価値観に育てられた子どもは、
将来どんなふうになるのか想像すると、
現実的には怖くもあり、
無責任な空想の上ではコメディの匂いがしてくる。
それにしてもなんであの父親は、
娘にピアノを習わせようと思ったのか。
それが最大の疑問であり、
理解不可能な点である。
まあ、それに出かけたのだった。
その会場で、
後ろの席に座った親子が最悪だった。
正確には、父親が。
自分の子どもの演奏が終わった後、
客席で他の子どもの演奏を見ているのだが、
父親がずっと我が子になにやら話しかけている。
子どもが父親にではない。
父親が子どもにだ。
演奏に対する感想ならば、
まあ、それもちょっとどうかと思うが、
1000歩譲って、よしとしよう。
しかし、父親が話しているのは、
目の前で行われている演奏とはまったく別の話だ。
たとえば、
「近所の音大の先生にピアノを教わると1時間50万円」
そんな話を小学校低学年の娘に話してどうする?
さらに、ステージ上のグランドピアノを見て、
「あのピアノ高そうだな」
聞いていると、その父親、金がらみの話しかしていない。
しかも、高価=いい、という価値観の持ち主のようで、
そんな価値観に育てられた子どもは、
将来どんなふうになるのか想像すると、
現実的には怖くもあり、
無責任な空想の上ではコメディの匂いがしてくる。
それにしてもなんであの父親は、
娘にピアノを習わせようと思ったのか。
それが最大の疑問であり、
理解不可能な点である。