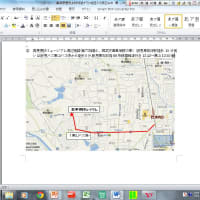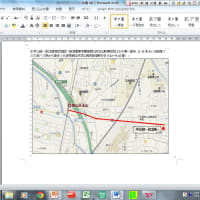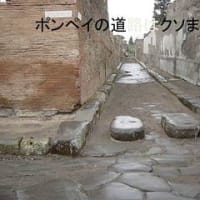慰労詔書を勉強してみなくては、と思ったら よろしくお願いします。
『延喜式』もっと勉強しろ!という激励を受けて??早速慰労詔書の研究状況を確認しました。本当にお恥ずかしい限りですが、あるはあるは山ほどあることが解りました。そしてもっとお恥ずかしいことに自分でその論文の載る雑誌を持っていたのであります。
『延喜式研究第10号』(延喜式研究会1995年3月15日)であります。
丸山裕美子「慰労詔書・論事勅書の受容について」という論文がありました。済みません丸山さん。いかに日頃勉強していないか、雑誌を取っていても積ん読だけかが露呈しました。
早速読みました。するとその引用に中野高行「慰労詔書の「結語」の変遷について」(『史学』55-11985年)という、そのものズバリの論文のあることが解りました。『延喜式』の注釈書はここから来ているのだろうと想像しました。これから大学の図書館に行ってこの論文もコピーしてこようと思っています。
と、ここまで書いて、1月30日に図書館に行きました。『史学』55号があるかどうか不安だったのですが、あちこち探すこと15分。ありました。早速コピーして読みました。
中野氏の論考によると、次のようにまとめられている。
① 慰労詔書の書式には「結語」に注目すると二つの変節点を有していること。
第一変節点:天平宝字年間→中国化強化の時期
第二変節点:延暦年間→書式の確立期=慰労詔書が対蕃国外交意思伝達機能文書として確立
② 日本の慰労詔書式の確立過程に中国の慰労制書の書式がいかなる役割を果たしたのか。
→ 極めて濃厚な影響を日本の書式形成に与えた。
→ 慶雲期である成立期のみならず中国的修正を加えた天平宝字年間も、中国の制書式に強い影響をうけていた。
③ 日本の慰労詔書式がいかなる経緯で受容されたのか。
第一案:中国からもらった文書により経験的に書式を知った。
第二案:中国の慰労制書式を何らかの形で入手し、その内容を理解した人間が定めた。
→山田英雄氏の研究により明らかにされた国書基本構造が、熟知されて表現されていることを大きな理由として第二案を筆者は採用する。
→おそらく具体的には「帰化人・遣隋・遣唐留学生」などが書式解説書などをもたらした結果だと言うのである。
これを読んで一安心した。
どうも中野さんも、他の研究者も書式の成立過程やその変遷上で第一の画期となった天平宝字年間には興味をお持ちだが、確立したと評価される延暦期にはあまり関心をお持ちでないらしいと言うことだ。要するにこの時期以降書式が確立して平安時代を通じて用いられ続けたという事実関係を追認しているだけなのである。
これは有り難い?!
つけいる隙はあるぞ!と思わず手を打った。
もちろん書式の変換点の第1期が天平宝字年間であるというのは強敵(いえいえ、敵などと失礼なことを申しました。私等蚊がブンブンですから・・・)吉川さんの主張するとおりのいわゆる四字元号期であり、延暦期なんて「フン!」という感じではアルのだが、私にとっては大いに有り難い史料である。
なぜ?
私は桓武朝はその後の日本の国境を確立するに大いなる役割を果たした時期だと考えているからである。その際に外交文書がいかに大きな役割を果たすかは言うまでもない。特に渤海や新羅に対する意識は強烈であったろう。それ故、慰労詔書なる国書のスタイルを確立しなければならなかったのである。だからこそ積極的に書式の形成を模索したのではなかろうか。
では誰がその書式をもたらせたのであろうか。
中野さんの論文によれば、宝亀三(772)年二月二八日の慰労詔書の「結語」に初めて新しい表現である「指此示懐」が登場し、宝亀八(777)年五月二十三日の書式は欠けていて判らず、同十一年の詔書で初めて「遣書指不多及」と「遣書」の語が登場し、次いで、延暦十五(796)年五月十七日詔書でその後の書式の基礎になる「略此遣書」の文言が出現するというのである。
こんなにうまくいっていいんだろうかと思うくらい見事に私の想定と一致していたのである。
即ち、私は桓武天皇は皇太子(山部親王)であった光仁朝に既に基本政策の決定に深く関与していたと考えているのだが、その山部親王が、宝亀八(777)年に中国へ王朝として初めての遣唐使を派遣するのである。
東野治之さんの有名な論考によれば、この遣唐使こそ、桓武王権の新政策を演出するために、様々な装置の将来を命じたものだというのである。大学寮の伊予部宅守を派遣し、第一に、皇帝のあるべき姿を述べた『春秋』の新たな注釈書「穀梁伝」や「公羊伝」を持ち帰らせ、新しい『皇帝(天皇)』像を形成しようとしたことであり、第二に、中国語の習得を命じ、中国語を公用語として本格的に習得させようとしたことだ、というのである。
宝亀十一年にその書式の萌芽が認められるというのは実にうまく符合する。そして実際にはこの年、光仁・桓武朝の第二次遣唐使が中国へ向け新たな船を出しているのである。この2度の遣唐使が将来した新たな文書形式を下に実際に作られ、残っているのが、延暦十五年の慰労詔書だったのではなかろうか。いうまでもなく『続日本紀』は延暦十年までしか記録せず、その後を記録した『日本後紀』は多くが失われており、具体的な史料を欠いている。
私は、考古学的にみて、光仁・桓武朝に大きな変換点があると以前から主張しているのだが、まさに慰労詔書の書式形成においても、同様の画期を認めることができるのである。特にこの文書がその後の国書つまり外交文書として確立するものであるだけに、その持つ意味はとてつもなく大きいと考えるのである。
東北蝦夷戦争を経て北の国境を確定し、南方隼人を完全支配下に置くことによって班田を開始し、喜界島まで進出して南の国境確定した桓武王権は、外交文書においても最新の唐の書式に従って「蕃国」に対し国書を発行するという形式を整えるのである。
吉川さんにはそんなこと「お見通し!」といわれるのは判っているのだが、私にとっては『延喜式』研究会のお陰で思わぬ史料に出会うことができた望外の喜びだったのである。
これも執筆中の『桓武朝の考古学』にすべり込ませなければと思った次第である。
研究会直前の忙しい時期に(実際追い込まれると他のことをしたくなるというのが人間心理だが)こんなことを考えていたのである。とても直ぐにはアップできる状態ではなかったので、考古学研究会が終わった今、ちょっと話題として書き込んだ。
『延喜式』研究会、面白そうだなと思ったら・・・参加してみませんか?!よろしく!!
『延喜式』もっと勉強しろ!という激励を受けて??早速慰労詔書の研究状況を確認しました。本当にお恥ずかしい限りですが、あるはあるは山ほどあることが解りました。そしてもっとお恥ずかしいことに自分でその論文の載る雑誌を持っていたのであります。
『延喜式研究第10号』(延喜式研究会1995年3月15日)であります。
丸山裕美子「慰労詔書・論事勅書の受容について」という論文がありました。済みません丸山さん。いかに日頃勉強していないか、雑誌を取っていても積ん読だけかが露呈しました。
早速読みました。するとその引用に中野高行「慰労詔書の「結語」の変遷について」(『史学』55-11985年)という、そのものズバリの論文のあることが解りました。『延喜式』の注釈書はここから来ているのだろうと想像しました。これから大学の図書館に行ってこの論文もコピーしてこようと思っています。
と、ここまで書いて、1月30日に図書館に行きました。『史学』55号があるかどうか不安だったのですが、あちこち探すこと15分。ありました。早速コピーして読みました。
中野氏の論考によると、次のようにまとめられている。
① 慰労詔書の書式には「結語」に注目すると二つの変節点を有していること。
第一変節点:天平宝字年間→中国化強化の時期
第二変節点:延暦年間→書式の確立期=慰労詔書が対蕃国外交意思伝達機能文書として確立
② 日本の慰労詔書式の確立過程に中国の慰労制書の書式がいかなる役割を果たしたのか。
→ 極めて濃厚な影響を日本の書式形成に与えた。
→ 慶雲期である成立期のみならず中国的修正を加えた天平宝字年間も、中国の制書式に強い影響をうけていた。
③ 日本の慰労詔書式がいかなる経緯で受容されたのか。
第一案:中国からもらった文書により経験的に書式を知った。
第二案:中国の慰労制書式を何らかの形で入手し、その内容を理解した人間が定めた。
→山田英雄氏の研究により明らかにされた国書基本構造が、熟知されて表現されていることを大きな理由として第二案を筆者は採用する。
→おそらく具体的には「帰化人・遣隋・遣唐留学生」などが書式解説書などをもたらした結果だと言うのである。
これを読んで一安心した。
どうも中野さんも、他の研究者も書式の成立過程やその変遷上で第一の画期となった天平宝字年間には興味をお持ちだが、確立したと評価される延暦期にはあまり関心をお持ちでないらしいと言うことだ。要するにこの時期以降書式が確立して平安時代を通じて用いられ続けたという事実関係を追認しているだけなのである。
これは有り難い?!
つけいる隙はあるぞ!と思わず手を打った。
もちろん書式の変換点の第1期が天平宝字年間であるというのは強敵(いえいえ、敵などと失礼なことを申しました。私等蚊がブンブンですから・・・)吉川さんの主張するとおりのいわゆる四字元号期であり、延暦期なんて「フン!」という感じではアルのだが、私にとっては大いに有り難い史料である。
なぜ?
私は桓武朝はその後の日本の国境を確立するに大いなる役割を果たした時期だと考えているからである。その際に外交文書がいかに大きな役割を果たすかは言うまでもない。特に渤海や新羅に対する意識は強烈であったろう。それ故、慰労詔書なる国書のスタイルを確立しなければならなかったのである。だからこそ積極的に書式の形成を模索したのではなかろうか。
では誰がその書式をもたらせたのであろうか。
中野さんの論文によれば、宝亀三(772)年二月二八日の慰労詔書の「結語」に初めて新しい表現である「指此示懐」が登場し、宝亀八(777)年五月二十三日の書式は欠けていて判らず、同十一年の詔書で初めて「遣書指不多及」と「遣書」の語が登場し、次いで、延暦十五(796)年五月十七日詔書でその後の書式の基礎になる「略此遣書」の文言が出現するというのである。
こんなにうまくいっていいんだろうかと思うくらい見事に私の想定と一致していたのである。
即ち、私は桓武天皇は皇太子(山部親王)であった光仁朝に既に基本政策の決定に深く関与していたと考えているのだが、その山部親王が、宝亀八(777)年に中国へ王朝として初めての遣唐使を派遣するのである。
東野治之さんの有名な論考によれば、この遣唐使こそ、桓武王権の新政策を演出するために、様々な装置の将来を命じたものだというのである。大学寮の伊予部宅守を派遣し、第一に、皇帝のあるべき姿を述べた『春秋』の新たな注釈書「穀梁伝」や「公羊伝」を持ち帰らせ、新しい『皇帝(天皇)』像を形成しようとしたことであり、第二に、中国語の習得を命じ、中国語を公用語として本格的に習得させようとしたことだ、というのである。
宝亀十一年にその書式の萌芽が認められるというのは実にうまく符合する。そして実際にはこの年、光仁・桓武朝の第二次遣唐使が中国へ向け新たな船を出しているのである。この2度の遣唐使が将来した新たな文書形式を下に実際に作られ、残っているのが、延暦十五年の慰労詔書だったのではなかろうか。いうまでもなく『続日本紀』は延暦十年までしか記録せず、その後を記録した『日本後紀』は多くが失われており、具体的な史料を欠いている。
私は、考古学的にみて、光仁・桓武朝に大きな変換点があると以前から主張しているのだが、まさに慰労詔書の書式形成においても、同様の画期を認めることができるのである。特にこの文書がその後の国書つまり外交文書として確立するものであるだけに、その持つ意味はとてつもなく大きいと考えるのである。
東北蝦夷戦争を経て北の国境を確定し、南方隼人を完全支配下に置くことによって班田を開始し、喜界島まで進出して南の国境確定した桓武王権は、外交文書においても最新の唐の書式に従って「蕃国」に対し国書を発行するという形式を整えるのである。
吉川さんにはそんなこと「お見通し!」といわれるのは判っているのだが、私にとっては『延喜式』研究会のお陰で思わぬ史料に出会うことができた望外の喜びだったのである。
これも執筆中の『桓武朝の考古学』にすべり込ませなければと思った次第である。
研究会直前の忙しい時期に(実際追い込まれると他のことをしたくなるというのが人間心理だが)こんなことを考えていたのである。とても直ぐにはアップできる状態ではなかったので、考古学研究会が終わった今、ちょっと話題として書き込んだ。
『延喜式』研究会、面白そうだなと思ったら・・・参加してみませんか?!よろしく!!