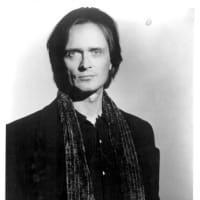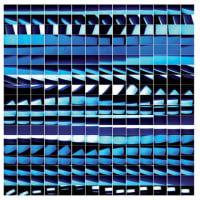ヤフオクの合間に準備してた(逆ですよ:笑)プログラムノートをアップしました!
ヤフオクの合間に準備してた(逆ですよ:笑)プログラムノートをアップしました!
 こちらでごわす → Whta's New?
こちらでごわす → Whta's New?  最近マスターしたPDFをフル活用!
最近マスターしたPDFをフル活用!
原稿は録音時のコンサートのために書かれた原稿を打ち込みました。
打ち込んでいるうちに作曲家の没年とかをアップデートして校正しようかと思いましたが、やめました。
例えば:88年にメシアンを弾いてる時には、まだメシアンは存命中でした。そして93年のプログラムノートでは没年が記載されています。その他、プログラムノートの後に旧帝国大の教授になられた作曲家のセンセー(ダチがエラくなってさ:笑)もいらっしゃいます。プロフィールもアップデートしていません。
こういう記述が:私が弾いてきた曲の『現代性』を表していると思い、何も手を加えたり書き直しを頼んだりしないことに決めました。
今読み返すと、解説も:「当時はこのように考えられていた」という内容で懐古的でもあり、私が書いたワケでもないので このままアップさせて?と了承を得ました。
このままアップさせて?と了承を得ました。
「きゃ~ 懐かしい~ 恥ずかしい~」( ← 柴辻純子氏)
懐かしい~ 恥ずかしい~」( ← 柴辻純子氏)
「・・・・・・・・」( ←佐野光司氏:「許可出来ない場合に限り返信下さい:ヤザワより」)
そうそうたる方たちが情報社会化以前に集成して下さった解説です。打ち込みも大変でした ヤフオクについ走るわけさ。
ヤフオクについ走るわけさ。
そもそもこのような難しい
 解説は:一般のお客さん向きというより、史料ということを念頭に置いて書かれた面もあるので改訂すべきではないのです。
解説は:一般のお客さん向きというより、史料ということを念頭に置いて書かれた面もあるので改訂すべきではないのです。
そして:この分野の後進の方たちが、手軽にウィキとかタダの文献を拾って張り合わせただけで自分の文章として発表することの危険さを先輩として教えて差し上げたい
没年も知らずに拾って使ったら単位落とすよ?
学問とは「定説を疑うこと」から始まるのです。
トリスタン・ミュライユも91年のプログラムノートには:『新ロマン主義』と書かれてました(筆者明瞭:笑)。こちらの録音はリリースしていないので、この解説もお蔵入りのままではありますが、いずれ「お蔵出し」したいと思っています。
これも別に意地悪とか面白がってやってるワケではなく(ちょっとはアルけど:笑)、当時の現代音楽界の様子が分かる文献だと思っているからです。
このように日本で考える学者がいるのも無理はない状況で、当時はアメリカのジョージ・クラムを代表する『新ロマン主義』が脚光を浴びていたこと。フランスの楽壇ではスペクトル楽派はブーレーズに嫌われていて、あまり大きな作品を発表する機会に恵まれていなかったため、その存在と知名度が日本では低かったという背景もあります。当時のフランス楽壇で活躍していた人は:ジルベール・アミのようなブーレーズの亜流が主体だったと思います。
情報社会とはいっても、発信される情報というのは必ず誰かの「意見」「利権」に色付けられてから発信されるものですから、真実は時間が経たないと分からないところがあるのです。そこを 現在の時点で見分けるのが学者の使命だと思うのですが。
現在の時点で見分けるのが学者の使命だと思うのですが。
そういう点でもとてもよく書けているプログラムノートだと思います。
むづかしー  けど読んでみてネ
けど読んでみてネ