
台風が関東方面に上陸し、去って行ったようです。
ぼくの育った東北地方では台風というのはそれほど大きな脅威ではありませんでした。
北上するにつれて勢力が弱まって、普段より雨風が激しいやつが来たという感じでした。
で、そういう時は長靴とカッパを着て、家の前の細い路地に出ます。
舗装されてない路地はまるで小川のようになっています。
石ころや泥をかき集めてダムを作ります。
何を見たいのかというと、できるだけ大きなダムを作って、水がひたひたに増し、臨界点を超え、
泥と石ころのダムが一気に決壊するのが見たかったのです(笑)
カタストロフィというやつですね。
ダムを作っては壊れ、壊れては作ります。
そのうち雨脚が弱まり、決壊の威力がなくなると、面白みを失って、家に帰ってテレビで「巨人の星」やら
「サザエさん」を見るわけです。
破壊というのはある種の魅力を持っています。
創造の魅力と、おそらくは背中合わせなのだと思います。
組織なり体制なりの自律的運動エネルギーが弱まり、組織なり体制なりの維持保存エネルギーだけが残った場合、
破壊衝動が内部より生まれます。
要は、保存維持エネルギーというのは「面白みにかける」のです。
持続が重要なのではなく、何に向かって、何のためにという「目的・意義」が人間の意識にとっては重要です。
重要かどうかという話になると、いろいろ異論も出てきますから、
要するに、持続・保存のためにエネルギーを使うというのは、子供や、特に男の意識から言うと、
「つまらない」のです。
まぁ、個人差がある話ではありましょう。
組織なり体制なりが流動的であり、活動が活発であるうちは破壊衝動は生まれません。
破壊すべき対象が形となって現れてこないからです。
それらが流動性を弱め、固定化してくると破壊衝動が生まれます。
破壊衝動の裏側に、破壊した後に新たな何を作りたいかという創造意欲も大いに沸き起こってきます。
生物のうちで、こういう贅沢ともいうべき意識活動を持つのは人間だけです。
安定が続くとリスクを厭わず改変を望み、不安定な状態が続くと安定を希求します。
幕末の志士たちの徹底的な社会の改革運動は見事でした。
あれだけ少ない犠牲で体制をひっくり返すことができたのは、おそらく世界中に例がないと思います。
ポイントは、自らの属する武士階級というものを、破壊する、捨てる覚悟で改革を断行したことでしょう。
武士という階級を保持しながら改革を進めようとしても、自己矛盾に陥り、体制(旧幕府)側に潰されていたかもしれません。
自らを捨てて、改革を志す人間は強いです。
守りたいものがある人間は、その守りたいところを突かれると、ぐらぐらに揺れてしまいます。
逆に言うと、守りたいものがある人間にとって、すべてを捨てて改革をしようとする人間ほど、
恐ろしく、厄介で、憎らしいものはありません。
彼の改革の意思を挫くすべがないからです。
そして、つまるところ、「今」という時代をどう見るのかという視座が、
その人がどういう人生の選択をしていくかを決定するわけです。
「今」を発展途上の通過点と見るか、行き詰まりの飽和点と見るか。
通過点と見る人は、不安定な状況に陥ることを嫌うでしょうし、飽和点と見る人はガラガラポンを望むでしょう。
さてさて、今はどんな時代だったのかと後世の歴史は記すのでしょうか。
ぼくの育った東北地方では台風というのはそれほど大きな脅威ではありませんでした。
北上するにつれて勢力が弱まって、普段より雨風が激しいやつが来たという感じでした。
で、そういう時は長靴とカッパを着て、家の前の細い路地に出ます。
舗装されてない路地はまるで小川のようになっています。
石ころや泥をかき集めてダムを作ります。
何を見たいのかというと、できるだけ大きなダムを作って、水がひたひたに増し、臨界点を超え、
泥と石ころのダムが一気に決壊するのが見たかったのです(笑)
カタストロフィというやつですね。
ダムを作っては壊れ、壊れては作ります。
そのうち雨脚が弱まり、決壊の威力がなくなると、面白みを失って、家に帰ってテレビで「巨人の星」やら
「サザエさん」を見るわけです。
破壊というのはある種の魅力を持っています。
創造の魅力と、おそらくは背中合わせなのだと思います。
組織なり体制なりの自律的運動エネルギーが弱まり、組織なり体制なりの維持保存エネルギーだけが残った場合、
破壊衝動が内部より生まれます。
要は、保存維持エネルギーというのは「面白みにかける」のです。
持続が重要なのではなく、何に向かって、何のためにという「目的・意義」が人間の意識にとっては重要です。
重要かどうかという話になると、いろいろ異論も出てきますから、
要するに、持続・保存のためにエネルギーを使うというのは、子供や、特に男の意識から言うと、
「つまらない」のです。
まぁ、個人差がある話ではありましょう。
組織なり体制なりが流動的であり、活動が活発であるうちは破壊衝動は生まれません。
破壊すべき対象が形となって現れてこないからです。
それらが流動性を弱め、固定化してくると破壊衝動が生まれます。
破壊衝動の裏側に、破壊した後に新たな何を作りたいかという創造意欲も大いに沸き起こってきます。
生物のうちで、こういう贅沢ともいうべき意識活動を持つのは人間だけです。
安定が続くとリスクを厭わず改変を望み、不安定な状態が続くと安定を希求します。
幕末の志士たちの徹底的な社会の改革運動は見事でした。
あれだけ少ない犠牲で体制をひっくり返すことができたのは、おそらく世界中に例がないと思います。
ポイントは、自らの属する武士階級というものを、破壊する、捨てる覚悟で改革を断行したことでしょう。
武士という階級を保持しながら改革を進めようとしても、自己矛盾に陥り、体制(旧幕府)側に潰されていたかもしれません。
自らを捨てて、改革を志す人間は強いです。
守りたいものがある人間は、その守りたいところを突かれると、ぐらぐらに揺れてしまいます。
逆に言うと、守りたいものがある人間にとって、すべてを捨てて改革をしようとする人間ほど、
恐ろしく、厄介で、憎らしいものはありません。
彼の改革の意思を挫くすべがないからです。
そして、つまるところ、「今」という時代をどう見るのかという視座が、
その人がどういう人生の選択をしていくかを決定するわけです。
「今」を発展途上の通過点と見るか、行き詰まりの飽和点と見るか。
通過点と見る人は、不安定な状況に陥ることを嫌うでしょうし、飽和点と見る人はガラガラポンを望むでしょう。
さてさて、今はどんな時代だったのかと後世の歴史は記すのでしょうか。










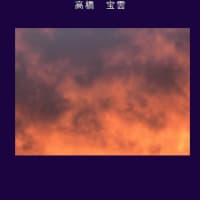









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます