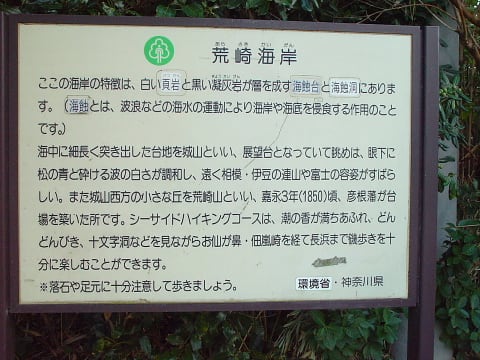木立に囲まれた路を抜けきると中央に位置する湖畔展望館の前に出ます。
バッグから出たがらないトッポと記念撮影です。

ここからの芦ノ湖の眺めは格別で箱根外輪山、富士山が姿を見せると絵画的な光景となるそうですが、富士山は薄い雲に覆われていて残念でした。
でも、雲の流れを見ているだけでも、ここを訪れた価値はありました。

上空は風の流れが速いのか、刻一刻と空の景色が変わります。

暫く待って富士山の浮かび上がりを期待しましたが、途中で雲の切れ間に顔を出した富士山を望遠で撮ってみましたがこれで精一杯でした。

今年の春には雪化粧の富士山を是非撮りに、もう一度来る予定です。
続く...................。
バッグから出たがらないトッポと記念撮影です。

ここからの芦ノ湖の眺めは格別で箱根外輪山、富士山が姿を見せると絵画的な光景となるそうですが、富士山は薄い雲に覆われていて残念でした。
でも、雲の流れを見ているだけでも、ここを訪れた価値はありました。

上空は風の流れが速いのか、刻一刻と空の景色が変わります。

暫く待って富士山の浮かび上がりを期待しましたが、途中で雲の切れ間に顔を出した富士山を望遠で撮ってみましたがこれで精一杯でした。

今年の春には雪化粧の富士山を是非撮りに、もう一度来る予定です。
続く...................。