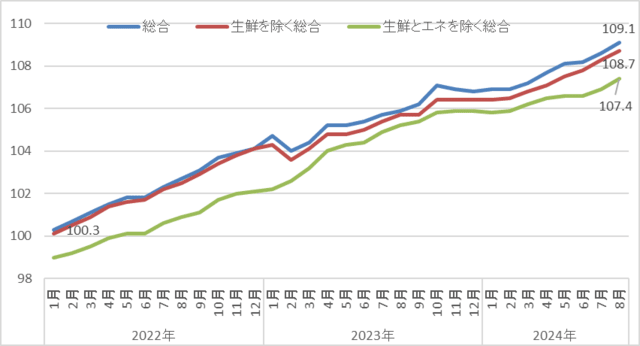今日は文化の日です。11月3日は、明治節の昔から「晴れ」の特異日という事になっているようですが、今日も昨日までの大雨も上がって朝から日本中晴天です。
文化の日には、このブログでは、何か少し変わったことを論じてみようなどと欲張ったことを考えるのですが、そのなかで「競いの文化と争いの文化」「天皇誕生日の祝日」など少し面白い事にも気づいて書いてきました。
そんな事で、今日は「保守と革新」という区別について、在り来たりかもしれませんが考えてみました。
「保守と革新」は主として政治に関連して使われる言葉で、通常、対立概念として使われることが多いようです。
確かに「保守と革新」は対立概念というか、人間の持つ2つの主要な考え方、行動の仕方を表した言葉でしょう。
しかし、ここではこの2つを対立概念としてばかり考えるのは、必ずしも適切ではないのではないという視点で考えてみたいと思っています。
対立概念をあらゆるものに当てはめるというのは欧米流の思想と言いますか、典型的にはキリスト教の教えに根差すのではないかと感じています。
キリスト教は元々「神と悪魔」があって対立抗争が基本になっています。そのせいか欧米では二元論(dichotomy)がよく使われ、「相容れない2つのもの」といった解釈がされています。
これは物事を解り易くするという効果はあるかもしれませんが、いまのアメリカではありませんが、基本的にはどちらが政権をとっても「米国中心という基本」はほとんど変わらないのに民主党と共和党が些少(失礼!)の違いを強調し、国を二分するような状況すら生んでいるようです。
英語にも「wholistic」(全体的、総合的)という言葉もあり、全体を見る視点が重要との主張もありますが、こちらは正しいがマイノリティーといったところでしょう。
ところで、人間の意識や行動、文化の面から見ますと、現代人の性向としては、基本的に保守的な要素と、革新的な要素が共に本来備わっているようです。
もともと人間は、他の動物に比して体力的にはひ弱で、食物を得る事と共に、外界の危険から身を守る事が重要な関心事だったのでしょう。この安全欲求は、身を守ることが最重要ですから危険を避ける「保守的」な意識であり行動だったと思われます。
そうした生活を繰り返し、知識や技術の蓄積が進んだ結果、人類はより豊かな生活をしたいという意識を持つようになったのでしょう。
しかし多くの食料、より良い生活を実現するためには冒険が必要でした。冒険は保守的なものではありません。
例えば、より多くの食料、より美味な食糧を狙って縄文人の先祖はユーラシア大陸や南の島からナウマンゾウを追い、豊かな魚群や橘の実を求めて日本列島にまで移動してきたのでしょう。
これは新たな可能性を求めて保守的な意識を乗り越え、リスクを取って生活の進歩向上を求める「革新」の意識・行動の実践ということで、人間がより高い満足を得るために持っている「革新」という性向の発揮でしょう。
こうして見て来れば、保守と革新は、現生人類が長い進化の歴史の中で備えることになった本能に由来するもので、人間の個体の中に共存する性向で、人間が安定をベースにそこから進歩するという2つの重要な要素という事になるのでしょう。
現実に戻れば、保守と革新は、個人の生活でも、企業経営でも、国家の運営でも、大切に組み合わせて活用すべき2大要素と考えるべきでしょう。