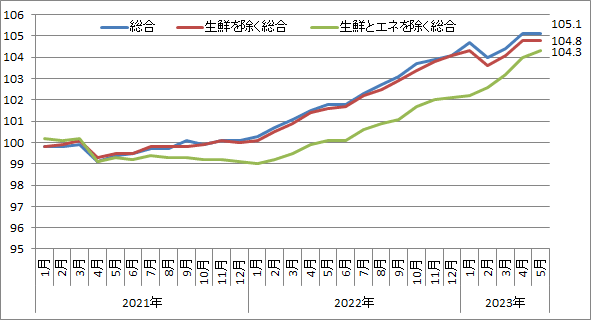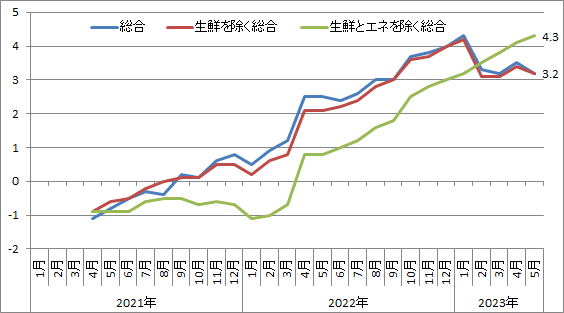変動相場制と日本経済:日銀の認識を問う
戦後の為替システムは固定相場制でした。太平洋戦争で日本国土は灰燼に帰し、終戦の年から2年間は国民所得統計もありません。
そんな日本も国民の真面目な努力で次第に復興し、経済活動も活発になり、アメリカとの取引でも単一為替レートが決められるまでになり、終戦から4年目の1949年にやっとGHQから$1=360円という為替レートを決めてもらうまでになりました。
当時アメリカは、圧倒的な経済力を誇り。第二次世界大戦後の世界を理想的なものに作り上げようと考えていたのでしょう。国際経済は固定相場制の下にあるべきだと考えていました。ドルは金に裏打ちされ、安定した価値を持っていたからです。
この理想は、アメリカの経済力が続くうちは機能しましたが、アメリカが次第に国際収支赤字国になり、アメリカに35ドル持っていけば金1オンスに換えられるという事で、アメリカの金準備は急速に目減りすることになりました。
そして1971年当時のニクソン大統領がドルの金兌換を停止するという、いわゆる「ニクソンショック」で、ドルはペーパーマネーになってしまいました。
そして、ドル安を決めた一時的なスミソニアン体制を経て結局1973年から今の変動相場制にすることになりました。
ドルは金の裏付けのある絶対的価値を持つ通貨から、アメリカの経済力の評価によってマーケットで価値決まる「(基軸)通貨」になったのです。
然しマーケットは常に「正しい」とは限りません。多様な経済的要因、投機資本の思惑などで常に動きます
通貨の取引を徹底的に自由化すれば、プライスメカニズムによって通貨はその国の経済価値を正確に表わすという仮定に立つのが「変動相場制」という事でしょうが、現実にはそうはなりません。
日本に関わる具体的な例を挙げましょう。
それはプラザ合意です。当時石油危機を率先克服、経済好調で円相場は割安という状況の中で、日本経済の一人勝ちを懸念した欧米主要国は日本に円相場の切り上げを要求しました。
経済好調だった日本は、鷹揚に「了解」といったようです。日本は、円安気味だから多少の切り上げも認めようという事だったのでしょう。
しかし結果は2年で240円から120円になり、マーケットは、日本経済の実力は2年で二倍になったという回答を出しました。2年で国民経済生産性が2倍になった計算です。
その後の日本の惨状を見れば、マーケットは誤りを犯すものだと理解できるでしょう。
ここまでは事実の列挙です。
そこで問題ですが、日本の政府、日銀の態度を見ていますと、一貫して「円レートは与えられるもの」という感覚であることを感じます。しかし、それで良いのでしょうか。
唯一例外は、2発の黒田バズーカでしした。あれがなければ、日本は$1=70~80円という為替レートで未だに苦しみもがいていたかもしれません。
こう考えてみますと、変動相場制でも為替レートはそれぞれの国が、自国の経済力に応じたレートを表明、申告し、それを安定的に維持する努力義務を負うという「ディシプリン(縛り)」をベースにすることが必要と考えるのがいいのではないでしょうか。
勿論申告するレートには、IMFなど適切な機関の同意が必要という事になるのでしょう。
世界が、あるいはアメリカが「変動相場制」をマーケットメカニズムが正しく働くという前提で、今の様にマーケット任せにすることは、世界経済の成長発展につい、適切な判断ではないようです。
戦後の為替システムは固定相場制でした。太平洋戦争で日本国土は灰燼に帰し、終戦の年から2年間は国民所得統計もありません。
そんな日本も国民の真面目な努力で次第に復興し、経済活動も活発になり、アメリカとの取引でも単一為替レートが決められるまでになり、終戦から4年目の1949年にやっとGHQから$1=360円という為替レートを決めてもらうまでになりました。
当時アメリカは、圧倒的な経済力を誇り。第二次世界大戦後の世界を理想的なものに作り上げようと考えていたのでしょう。国際経済は固定相場制の下にあるべきだと考えていました。ドルは金に裏打ちされ、安定した価値を持っていたからです。
この理想は、アメリカの経済力が続くうちは機能しましたが、アメリカが次第に国際収支赤字国になり、アメリカに35ドル持っていけば金1オンスに換えられるという事で、アメリカの金準備は急速に目減りすることになりました。
そして1971年当時のニクソン大統領がドルの金兌換を停止するという、いわゆる「ニクソンショック」で、ドルはペーパーマネーになってしまいました。
そして、ドル安を決めた一時的なスミソニアン体制を経て結局1973年から今の変動相場制にすることになりました。
ドルは金の裏付けのある絶対的価値を持つ通貨から、アメリカの経済力の評価によってマーケットで価値決まる「(基軸)通貨」になったのです。
然しマーケットは常に「正しい」とは限りません。多様な経済的要因、投機資本の思惑などで常に動きます
通貨の取引を徹底的に自由化すれば、プライスメカニズムによって通貨はその国の経済価値を正確に表わすという仮定に立つのが「変動相場制」という事でしょうが、現実にはそうはなりません。
日本に関わる具体的な例を挙げましょう。
それはプラザ合意です。当時石油危機を率先克服、経済好調で円相場は割安という状況の中で、日本経済の一人勝ちを懸念した欧米主要国は日本に円相場の切り上げを要求しました。
経済好調だった日本は、鷹揚に「了解」といったようです。日本は、円安気味だから多少の切り上げも認めようという事だったのでしょう。
しかし結果は2年で240円から120円になり、マーケットは、日本経済の実力は2年で二倍になったという回答を出しました。2年で国民経済生産性が2倍になった計算です。
その後の日本の惨状を見れば、マーケットは誤りを犯すものだと理解できるでしょう。
ここまでは事実の列挙です。
そこで問題ですが、日本の政府、日銀の態度を見ていますと、一貫して「円レートは与えられるもの」という感覚であることを感じます。しかし、それで良いのでしょうか。
唯一例外は、2発の黒田バズーカでしした。あれがなければ、日本は$1=70~80円という為替レートで未だに苦しみもがいていたかもしれません。
こう考えてみますと、変動相場制でも為替レートはそれぞれの国が、自国の経済力に応じたレートを表明、申告し、それを安定的に維持する努力義務を負うという「ディシプリン(縛り)」をベースにすることが必要と考えるのがいいのではないでしょうか。
勿論申告するレートには、IMFなど適切な機関の同意が必要という事になるのでしょう。
世界が、あるいはアメリカが「変動相場制」をマーケットメカニズムが正しく働くという前提で、今の様にマーケット任せにすることは、世界経済の成長発展につい、適切な判断ではないようです。