
我々日本人はお正月や受験などの時には神社やお寺へ行ってお参りをするという習慣がありますが、台湾の人もお参り好き。いや、日本よりももっともっと頻繁にお参りをするのですな。お参りや神様にお祈りすることを“拝拝(バイバイ)”と言い、春節はもちろん月に2回訪れる満月の日には各家庭や会社、商店で必ずたくさんのお供えをし“拝拝”するというのは台湾の習わしとなっています。家庭や会社、商店での拝拝についてはまた別の機会に詳しくお話しするとして、今回はお寺での拝拝についてお伝えします。
さて、訪れましたのは龍山寺。大勢の人が拝拝に訪れ、老若男女がお供えや線香を手に、熱心にお祈りをしていました。ここは台湾なんだから台湾式にってことで、周りの人をまねて拝拝に挑戦。


中華圏のお寺にはお祈りする所に両膝をつくための椅子のようなものが置いてあります。ここに膝をついて身をかがめ、半月型をした赤い小さな拝拝の道具(木製。表面が赤く塗られている。二つで一対。)を手に持ち、お願いを唱えます。この道具、台湾の言葉でぶぁっぼぇいといいます。(ぶぁっぼぇいというのは「神様とコミュニケーションをとる」という意味だそうです)よくお願いしたらぶぁっぼぇいをポイッと地面に落とします。
上の写真2枚を見てください。ぶぁっぼぇいには表と裏があり、こんもりと盛り上がった形のほうが表、ぺたっと平べったくなっている方が裏なんですね。(上の方の写真はどちらも表)落としたときに一つが表向き、もう一つが裏向きになるとお願いがかなうと言われています(下の方の写真参照)。こうなったら近くに置いてあるおみくじを引きます。(下の写真を見てください。黄色の服を着た男の子の隣におみくじ棒の束がありますよね。ここから一本引くのです。棒の先には数字が書いてあります。)仮におみくじの数字が「十」だとすると、「十でよろしいでしょうか」と唱えながら再びぶぁっぼぇいを落とします。うまく表と裏が出たらおみくじ箱十番の引き出しをあけてその中に入っている紙に書かれた占いを読みます。(これは日本でも同じですよね。)表と裏が出なければもう一度おみくじを引き、新しい番号を唱えてぶぁっぼぇいを落とします。こうして表と裏が出るまでおみくじを引き続ける
のです。

最初のお願いの時点で表と裏が出なければまたお祈りをしてぶぁっぼぇいを地面に落とせます。しかしぶぁっぼぇいを使えるのは通常3回までなのだそうです。ただしぶぁっぼぇいがどちらも裏向きになった場合は“神様が笑っている”という意味と見なし、もう一度落とすことができるとのことでした。
ここでご紹介したぶぁっぼぇいを使った拝拝は一般的に台湾で言われているやり方なのですが、お祈りの方法については家庭によって、また人によって多少異なるそうです。
・・・と、ここまで読み返してみて拝拝の仕方がうまくまとめられていないようなのでもう一度わかりやすく説明いたします。
─────────────────────────────────
願い事を唱えながらぶぁっぼぇいをポイッと落とす
↓ ↓
表と裏が出た 表どうし、または裏どうしが出た
↓ ↓
↓ またぶぁっぼぇいを落として表と裏が出るまで
↓ お願いできる、ぶぁっぼぇいを落とせるのは3回
まで。但し裏どうしが出たらノーカウント
↓ ↓
おみくじを引いて、その数字を確認するのだ!
↓
この数字でよいかもう一度ぶぁっぼぇいを落とす
↓ ↓
表と裏が出た 表どうし、または裏どうしが出た
↓ ↓
↓ またぶぁっぼぇいを落として表と裏が出るまでおみくじを引き続ける
↓ ↓
↓ 表と裏が出た
↓ ↓
おみくじ箱へレッツゴー!!
──────────────────────────────────
うーむ、うまく説明できたかなー?
拝拝に興味のある方は是非台湾に来て実際にやってみてください。
















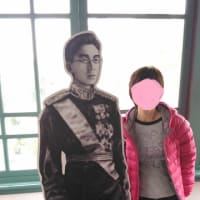



結構、よい事が書いてあったので嬉しかったなぁ~
ほんと、台湾のお寺はカラフルで綺麗ですね☆あと線香なんかもタダでもらえてお金かからないのが嬉しいです。
縁結びの赤い糸とかももらいましたよ!
効き目は・・・まだ大切に持ってます(笑)
なんていうお寺ですかね?ガイドさんは日本で言うところの浅草寺くらい有名な所と言ってました。
輪っかの中に入って、その中の小さな輪っかに頭を入れて願い事を言うってのもありました。