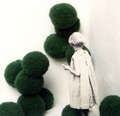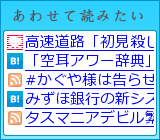本が好き!な、りなっこのダイアリーです。週末は旦那と食べ歩き。そちらの報告も。
本読みの日々つらつら
山之口洋さん、『天平冥所図会』
引き続き、花冷えの一日。
今朝、うすいえんどうの豆ごはんを炊きました。白に黄緑の野暮ったい配色が愛らしかったです。関西に住んで二年目にして知った、うすいえんどう。春の野菜はほんわかと土の匂いがしそうで、嬉しく噛みしめました。桜の季節よ、今年もよろしく…。
さて、読み終えたのは昨日です。図書館に予約して待ちかねていた作品です。
『天平冥所図会』、山之口洋を読みました。
〔 「ひとーつ、琵琶。弦は五本」「ひとーつ、五弦の琵琶」「材は、ええ……紫檀」「紫檀製と」「捍撥(ばちうけ)はたいまい貼り。螺鈿の飾り」「ほいきた。それなら『螺鈿紫檀の五弦琵琶』ではどうだ」「ようし」 〕 129頁
とても面白楽しくて、これ好き…と鼻の下を伸ばしながら読む読む。
主人公は葛木連戸主(かつらぎのむらじへぬし)という、貴族の端くれに引っ掛かっている程度の役人です。そして戸主の周りには、元上司の吉備真備にその一人娘の由利や、由利と一緒に後宮に仕える藤野別真人(和気)広虫、広虫の弟・清麻呂たちがいて、奈良の都を生き生きと闊歩します。
物語は4つの章から成っています。
前半の「三笠山」と「正倉院」では、東大寺の大仏鋳造や正倉院の献納帳作成の現場が舞台になっていて、現場ならではの面白さがみっちり味わえます。私が読んでみたかったのは、この前半に見られる奈良時代の職人や官人たちのこまごまとした仕事の様子や、賑やかな職場の雰囲気、専門職ならではの拘りなどなど、日本史を学んだだけではわからないけれど本当は一番面白そうな現場の話、だったので、その点とても満足でした。
「三笠山」は、大仏鋳造のタタラで働いていた父親を探しにきた少年百世と、百世を助けた広虫と戸主が少年の父親探しをする話。「正倉院」は、献納準備の実務を任せられた戸主が奮闘する話です。
特に「正倉院」は面白かったー。光明皇太后の“捧げようと思います”の一言で、どれだけの役人がどれだけ働かされるんだー!って現場のきりきり舞いとか、まあつまり、聖武天皇のコレクション(御遺愛の品々)が凄過ぎたってことです。
30人の部下が八班に分かれ、さらに外部にも応援を頼んで、巻物班は作り直しに肩を落とし、楽器班は声を張り上げる。そしてその献物帳の存在が、藤原仲麻呂の権力UPに利用されそうになったり、反対派の妨害で完成が間に合わなくなりそうになったり、政治音痴の戸主もやるときはやる!とばかりに活躍します。漢です戸主。
で、後半に入るといよいよ藤原仲麻呂が乱を起こすし、主人公の戸主は〇〇になってしまうしで、「あらら、そういう話になるのでしたか」と、目を丸くする心地で読んでいました。
しかし面白かったなー。藤原仲麻呂や称徳天皇の人となりの描き方には説得力があるし、吉備真備って長生きしたのねーと感心したり(そこにか)。あ、実は道鏡に…(むにゃむにゃ)にはのけ反ったけれど、愉快なお化けも跋扈してて楽しかったです。
| « 稲見一良、『... | 藤枝静男、『... » |