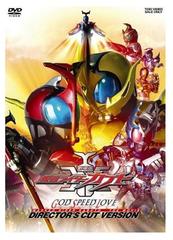 劇場版 仮面ライダーカブト
劇場版 仮面ライダーカブトGOD SPEED LOVE
石ノ森章太郎、東映(2006年)
2006~07年にテレビ放送された「仮面ライダーカブト」の劇場版オリジナル作品。避けて通れない1作です。というのもこの作品、確認できる限り世界初の軌道エレベーターが登場する実写ドラマなのです。TV版も観ないと書けないかも知れないから面倒だな、と思って後回しにしていたんですが、いざ観てみたら色んな意味で楽しめました(ネタバレご注意ください)。
あらすじ 1999年、隕石が落下して地球環境は激変。さらに隕石の中から地球外生命体「ワーム」が現れ、人類は存亡の危機に立たされる。秘密組織ZECTは「マスクドライダーシステム」を開発してワームに抵抗するが、不満分子がネオZECTを立ち上げ、人間同士でも抗争を続けていた。天道総司=仮面ライダーカブトは、ある目的を秘めて両者に近づく。
 1. 本作に登場する軌道エレベーター
1. 本作に登場する軌道エレベーターZECTは「天空の梯子」と名付けた計画を遂行しており、隕石の落下で海が蒸発して(その水分はどこへ行った?)人類はとっくに死滅していていいはずの世界で、わずか7年程度で軌道エレベーターを完成させます。主だった構造は次の通り。
地上基部は日本国内あるいは近辺の模様。ピラーと思われるエレベーターシャフトが中心部にあり、それを取り囲むようにパイプが延びています。ピラーとパイプは、宇宙でステーションにつながっています。ここが末端のような描かれ方をしているのですが、ステーションが画面に映る時は、その上にも細い棒(ただのアンテナか?)が伸びているのが見えるので、中間ステーションかも知れません。
昇降機は、乗員が立ったままベルトで体を固定して乗り、ズドーン!とものすごい勢いで上昇(動力不明)。ステーションに着く頃にはフラフラになっているという代物で、おいおいそんな危険な乗り物みたいに描くなよう。ステーションは宇宙船みたいな形をしており、先端がミサイルになっています。そんなこんなで、分類すれば第2世代以降ということになりましょうか。
最初だけは一応科学的に検証します。まず地上基部を日本の近くに設けるのは無理がありますが、エドワーズモデルが北緯35度まで設定してますし、まったく不可能ではないかも知れません。赤道を挟んでシンメトリー構造を成している可能性もありますから、技術次第で絶対無理とは言い切れない感があります。
昇降機の原理は不明。ステーションの高度もわかりませんが、劇中でライダーたちがステーションから転落(!)する場面があるので、少なくとも高度約2万5000kmより下になければいけません。地球の見かけの大きさから判断しても、低軌道域でなければならんのですが、それに反する描写もあるので、正確なところは不明です。ちなみに内部には「重力装置」なるものがありますが原理は不明。どのみち、ほとんどの場面で1G並みの重力があるような描写しかされてません。
天空の梯子計画は、氷の塊である彗星をこのステーションまで持ってきて、パイプを通じて地上に水を供給し、干上がった海を再生させようというものです。軌道エレベーターを超巨大な水道管にしようというわけですね。いやはやトンデモない発想で、真に受けるのは無粋というものですが、彗星を固定し、液化して状態を保持できる技術があるとすれば、高度によっては水が自然に落ちるし、この計画、力技次第でひょっとしたら可能か? と思わないでもありません(水力発電もできるな!)。
ただし水のような重いものを、海が戻るほど大量に落ちるに任せていたら、コリオリがピラー全体の角運動量に影響して、軌道エレベーターが倒れてしまうかもしれない。とはいえ、「絶対に無理」とは言い切れないのがコワい。
まあどれ一つとってもトンデモないですが、軌道エレベーターをストローにしてしまうとはアッパレな。しかもカブトはこのパイプを侵入路として利用し、中を昇って(!)ステーションへ行くという無茶苦茶な真似を2回もやってのけます(しかもエレベーターで昇った連中より早く着く)。デタラメもここまで大胆にやってくれるとかえって痛快! まあ、結局この計画自体がダミーであり、真の目的があるのですが、私ゃこういうの大好きです。本作はこれでよろしい。
2. 軌道エレベーターで闘うライダーたち
仮面ライダー生誕35周年記念作品の本作は、TVシリーズとは異なる歴史をたどったパラレルワールドのお話。主人公の天道は、天空の梯子計画には何か裏があると疑っています。その秘密をあぶり出そうと、ZECTとネオZECTに自分の腕を売り込み、共食いをさせて計画を前倒しさせ、その過程で色んなライダーと闘います。
この天道が相当な変人で、おばあちゃんの教訓をやたら披露するのは有名な話。劇場版では、
「おばあちゃんが言っていた…強きを助け、弱きをくじけってな。
強い者だけが生き残ればいいんだ」
お前のおばあちゃん鬼畜。
彼を筆頭に、ナルシストなライダーたちが軌道エレベーターを舞台にじゃんじゃん活躍(?)してくれます。極めつけは劇場版オリジナルキャラの仮面ライダーケタロス。カブトエクステンダー(専用のバイク)で軌道エレベーターの水道管を昇ってきたカブトと、ステーションで格闘したあげくに、2人そろって転落。大気圏に再突入して空力加熱で燃え上がりますが、カブトはエクステンダーを呼び出してまたがり(耐熱フィールドでも付いとんのか!?)、ケタロスを助けようとします。以下は、落下中のカブトとケタロスの対話である!
(エクステンダーからケタロスに手を伸ばすカブト)
ケタ「何の真似だ?」
カブ「生き延びたかったら・・・放すな」
ケタ「同情など無用、
俺の情熱の炎は、この熱さにも負けない!」
断熱圧縮による空力加熱よりも自分の情熱の方が熱いということは。。。
おお! 相対的に涼しく感じるってわけだな (゜▽゜*) 。。。って、んなわけあるか。結局人間隕石と化して、変な方向から地上基部に落下して、「我が魂は、ZECTと共にあり~」とか叫びながら爆発。迷惑な奴だ。軌道エレベーターから落ちて、燃え尽きずに地上に激突死したなんて、後にも先にもこの人だけでしょう。
終盤に登場する、これも劇場版のみ登場の仮面ライダーコーカサスは「紫のバラの人」(自然界にそんなバラないぞ)。カブトは仲間の仮面ライダーガタックと共に再びステーションに上がり、ミサイル部に侵入します。クロックアップ(サイボーグ009の加速装置みたいなもの)してるからよくわかんないですが、今度は走って昇ったみたいです。
コーカサスはミサイルの中でカブトとガタックを待ち伏せしているのですが、2人が到着すると、室内にバラの花びらがヒラヒラ舞っている。素晴らしい! 今の日本人が忘れて久しい、もてなしの心を持っていらっしゃる。
「私のバラに彩りを加えましょう。裏切り者の赤い血と、屈辱の涙を」
自分のためかい( ̄□ ̄); どいつもこいつもどんだけ自分好きなんだよう。
カブ「お前はそれでいいのか・・・地球をワームに奪われても」
コー「バラが見つめてくれるのは、最も強く、最も美しい者。私はそのために闘うだけです」
ちょっと何言ってるかわかんない。ていうか、この人天道のおばあちゃんの言いつけ実践してるじゃん。とにかくすったもんだ闘った末、カブトがバージョンアップして、宇宙でコーカサスにライダーキックかまします。いやいやすげえな! そして天道の狙いはもう一つあり、それが終盤で明かされて、TVシリーズに近い世界(でも同一じゃない)とのつながりを匂わせる終わり方をしますが、その辺の演出はなかなか感動的です。
3. 米国学会で紹介された劇場版カブト
実は本作、2008年7月に米マイクロソフト本社の会議場で開かれた"2008 Space Elevator Conference(08'SEC)"で紹介されたのです(写真は08'SECの様子)。
 この年の4月に宇宙エレベーター協会(JSEA)を発足させ、5人が08'SECで研究発表。私もその1人でした。そこで同志のH川さんが、軌道エレベーターの発想を一つのミーム(文化的遺伝子)としてとらえた研究発表を行い、実写映画に初登場した本作を紹介したのです。「バイクでエレベーターを昇っちゃう」なんて言うと会場から笑いが起きていました。
この年の4月に宇宙エレベーター協会(JSEA)を発足させ、5人が08'SECで研究発表。私もその1人でした。そこで同志のH川さんが、軌道エレベーターの発想を一つのミーム(文化的遺伝子)としてとらえた研究発表を行い、実写映画に初登場した本作を紹介したのです。「バイクでエレベーターを昇っちゃう」なんて言うと会場から笑いが起きていました。本作について、軌道エレベーターの扱いがひどいと憤慨?している記述も散見されたのですが、いや、「仮面ライダー」に期待するモノを間違えてるだろ。そりゃツッコミどころ満載なんだけど、本作はそのツッコミも楽しむべき作品でしょう。いくらデタラメでもいいんです、それで面白くなるなら。そして本作は、本作にしかできないことをやってくれました。
軌道エレベーターをストローとして使う
軌道エレベーターをバイクで昇り、次は走って昇る
バイクで大気圏突入
ステーションから転落死
あまつさえ宇宙でライダーキック
このやったもん勝ちな想像力の暴走を見よ! 良くも悪くもこれだけ軌道エレベーターをイジってくれた作品ほかにあるでしょうか? 理屈倒れでお行儀の良い昨今のSF作品は、こういう破壊的な大ボラを吹く気概を失っているんじゃないでしょうか。
そもそも本作で、軌道エレベーターは単なる話題作りのキワモノとして取り上げられたとは思えないのです。TVシリーズで天道は何かと言うと人差し指を高く突き上げ、「俺は天の道をゆき、総てを司る男…」と決め台詞を吐いていました(旧姓日下部のくせに)。その背には東京タワーがそびえていたのです。今ならスカイツリーでしょうが、とにかく天と一体化した姿を象徴していた。その延長として、劇場版で軌道エレベーターが出るべくして出てきた。漠然とした勘ですが、本作の脚本家はけっこうSF好きなんじゃないかなあ。
そして本作は、主人公の心理をちゃんと追えて、しかも、要所々々で大人の鑑賞にも耐える演出もなされている。特撮ヒーローものにしては、アクションが足りないのでは? と感じるんですが、私のような歳くった人間からすれば、冗長さがなくてかえって見やすかったです。ところどころ効果音を消した演出もよろしい。SFとしては反則の部分もありますが、枝葉はともかく、ストーリーの根幹では最低限の筋が通っていますし、終盤には不覚にもグッときてしまったぜ。いい話だ。
長々書いてしまいましたが、深く考えずに楽しめます。軌道エレベーターが登場する世界初の実写作品。その栄誉を奪い取った本作を、ぜひご覧ください。










 果てしなき流れの果に
果てしなき流れの果に 登場するのは
登場するのは 宇宙でいちばん丈夫な糸
宇宙でいちばん丈夫な糸
 銀河英雄伝説
銀河英雄伝説 1. 本作に登場する軌道エレベーター
1. 本作に登場する軌道エレベーター
 iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。
iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。


