「軌道エレベーターが登場するお話」、強化月間中ということで少し趣向を変えたものを掲載します。まあぶっちゃけた話、たまには軌道エレベーターに全然関係ない(けど個人的に好きな)物語を扱ってみようという、いわば「つまみ食い集」です。
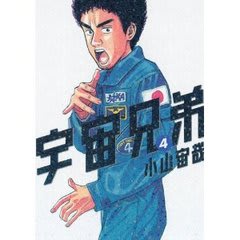 宇宙兄弟
宇宙兄弟
小山宙哉
(講談社 2008年~)
(2011年4月9日付記)映画化が決定したそうです。おめでとうございます!
週刊モーニングで連載中の人気作品。本作のどこに軌道エレベーターが登場するのか? 描かれているんですよ、単行本3巻172頁右上のコマ! 地球から棒のようなものが2本伸びて、中ほどに昇降機らしいものがくっついている。主人公は「そのうち宇宙が近い時代が来て 誰も文句言わなくなるよ」と語っている。これは軌道エレベーターに違いない。ですよね、小山宙哉先生!? ていうかこの絵、SEVGの映像を参考にしていませんか? 間違ってたらごめんなさい。
。。。すみませんこのひとコマだけです。これにこじつけて取り上げます。
あらすじ 南波六太と日々人の兄弟は、幼い頃、共に宇宙飛行士になることを約束する。時は流れ、六太は勤めていた自動車会社をクビになり、一方日々人は本当に宇宙飛行士になり、日本人初の月面着陸に挑む。引け目を感じる六太だったが、日々人にかつての想いを呼び起され、宇宙飛行士選抜試験に挑戦、遥か先で待つ弟を追い越そうと動き出す。
1. シャトル後の宇宙開発
本作の宇宙開発計画では、コンステレーション計画の見直しで、扱いが微妙になっている「アレス」が使われているんですね。月着陸船「アルタイル」なんかも登場して、実物より早く活躍しているわけです。想像というより予想と呼ぶべきですが、設定のベースとなっている宇宙開発の技術は非常にリアルです。
また、宇宙飛行士の選抜過程などは詳しく知りませんが、密室に入ったり、単色のパズルを組み立てたりするなどの課程は「ドキュメント 宇宙飛行士選抜試験」(光文社新書)でも紹介されていますし、しっかりとした取材や作者の理解の深さがうかがえます。
アポロ計画当時、月のレゴリスが飛行士の目や肺に入ってメチャメチャ痛かったらしいとか、月面の望遠鏡構想(太陽─地球系のL2に打ち上げられるはずだったという「ウェッブ」と、どっちが効率的なのだろうか?)などのエピソードや構想も「ほお~」なんて非常に興味をそそられました。
2. 似てない兄弟
しかしこの作品は、やっぱり物語とキャラが面白い。自分が先に宇宙飛行士になって弟を引っ張っていくことを目指していた六太でしたが、宇宙飛行士になったのは日々人の方。六太はサラリーマンとなり(でもってクビになり)、弟へのコンプレックスを抱えながらすっかり宇宙を諦めてぐずぐず病状態になってました。日々人は、遅れてでも兄が宇宙に来ることを信じて(願って?)いて、そんな六太を何かとアオります。
「宇宙行くの夢なんだろ 諦めんなよ
もし諦められるんなら、そんなもん夢じゃねえ」(2巻95頁)
あんまり「夢」と言う言葉を多用したくないのですが、それを捨てたことに負い目やコンプレックスを持つ人には、かなりキツい言葉ですね。うん、あまりにも君は特殊な立場からモノを言ってるよ日々人君。世界で1億人に1人くらいしかいない職業に就いてるんだぞお前は!
しかし、こういうセリフにギクリとする人は、図星の部分があるからこそ琴線に響くのでしょう。日々人の言わんとしているのは、「本当に今のままでいいのか、自分自身に訊いてみろよ」あるいは「本当にやりたいことなら、出来るまでやれよ」と換言できるのではないでしょうか。
この兄弟は全然似てなくて、六太はセンシティブで気にしいで、他者への観察力が豊か。おそらくは他人が気になるからでしょう。時々相反するように大胆になりますが、二面性は感じません。一方日々人は、困難な課題を楽々こなして宇宙飛行士になり、世事に無関心でいつも飄々としている人物。。。という芝居をしているように見えます。マスコミの前ではちゃんと道化を演じ切っているだけに、その印象が強い。それぞれ自覚していないだけで、実は現実に対する割り切りがよく、自分と向き合うことが多いのは六太の方ではないか?
決して物語からそう類推するのではなく、このコーナーは登場人物が本当に存在しているような感じで書くように心がけているので、そんな目で見た時に、日々人は人格や能力の重心がかなり偏っていて、内面の矛盾を未消化の負荷にしたまま隠し持つタイプに見えるんですよね。まあ、兄に対しては虚心になれないのでしょうが。もちろんそんな人格設定はされていないと思います。物語が六太の語りで展開するせいで私にそう見えるだけでしょう。私にはそれが面白かったりするんですが。
3. 作品の空気
そんなこんなで、妙運珍運に背中を押されつつ、宇宙飛行士を目指すようになる六太なのですが、選考終盤でほかの受験者たちと話が弾みます。宇宙や天文学の話題をおそらくは初めて共有でき、「今まで……こんなこと一度もなかった」と感慨にふける六太。
「ここにいたんだ 誘ったら喜んでついて来てくれそうな連中が…」(4巻193頁)
わかる、わかるよ六太! 軌道エレベーターなんてモノを追いかけ続け、どれだけ浮きまくってきたことか。ようやく友人というか同志が増えて、色々語り合えるようになった喜び。やっぱりこの道を捨てずに良かったなあと思うきょうこの頃。宇宙飛行士の選抜なんて世界にはとうてい及びませんが、つい自分たちの経験を重ね合わせてしまいます。もっとも私、軌道派だからその友人たちの中でさらに浮いてるんですけどね。
ところで本作の空気というかノリについて、読み始めた頃からずーっと「この感覚。。。どこかで。。。」と感じていました。大分読み進めるまで気づかなかったのですが、ある日突然思い出しました。。。「スラムダンク」です。
六太が何かとふてぶてしい表情で根拠のない自信を見せては、いつも間が悪くてトホホな表情になるところや、同僚の女性宇宙飛行士候補を「せりかさん」と呼んで憧れたり(スラムダンクでは「ハルコさん」だったっけ。なんか印象も似ているような)するあたり、「スラムダンク」の桜木花道を連想せずにはいられません。4巻では六太が「ホワチャー──!!」と、訳あって選抜試験中にブルース・リーのモノマネをするのですが(今回の書影もそのイラストね)、私は真っ先に陵南高校の福田(「ほわちゃあ」とキレて監督をボコボコにする)を思い出しましたし。。。私だけかなあ? まあ、両作を併せ読んでも全然意味ないですね。
何はともあれ、スペースシャトル後の宇宙開発を描いた作品としても興味深い上、ストーリーは掛け値なしに面白いです。今後も見逃せません。
当初、この「つまみ食い集」は、軌道エレベーターにほとんど、あるいはまったく関係ない3作品をまとめて扱うつもりだったのですが、つい書き過ぎてしてしまいました。番外編として、今月中にあと1回か2回掲載するつもりです。次回も、軌道エレベーターにはそんなに関係ない作品を扱うつもりですが、なにとぞよろしくお願いいたします。
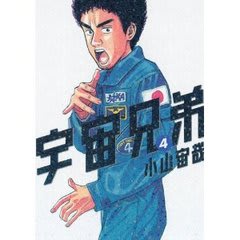 宇宙兄弟
宇宙兄弟小山宙哉
(講談社 2008年~)
(2011年4月9日付記)映画化が決定したそうです。おめでとうございます!
週刊モーニングで連載中の人気作品。本作のどこに軌道エレベーターが登場するのか? 描かれているんですよ、単行本3巻172頁右上のコマ! 地球から棒のようなものが2本伸びて、中ほどに昇降機らしいものがくっついている。主人公は「そのうち宇宙が近い時代が来て 誰も文句言わなくなるよ」と語っている。これは軌道エレベーターに違いない。ですよね、小山宙哉先生!? ていうかこの絵、SEVGの映像を参考にしていませんか? 間違ってたらごめんなさい。
。。。すみませんこのひとコマだけです。これにこじつけて取り上げます。
あらすじ 南波六太と日々人の兄弟は、幼い頃、共に宇宙飛行士になることを約束する。時は流れ、六太は勤めていた自動車会社をクビになり、一方日々人は本当に宇宙飛行士になり、日本人初の月面着陸に挑む。引け目を感じる六太だったが、日々人にかつての想いを呼び起され、宇宙飛行士選抜試験に挑戦、遥か先で待つ弟を追い越そうと動き出す。
1. シャトル後の宇宙開発
本作の宇宙開発計画では、コンステレーション計画の見直しで、扱いが微妙になっている「アレス」が使われているんですね。月着陸船「アルタイル」なんかも登場して、実物より早く活躍しているわけです。想像というより予想と呼ぶべきですが、設定のベースとなっている宇宙開発の技術は非常にリアルです。
また、宇宙飛行士の選抜過程などは詳しく知りませんが、密室に入ったり、単色のパズルを組み立てたりするなどの課程は「ドキュメント 宇宙飛行士選抜試験」(光文社新書)でも紹介されていますし、しっかりとした取材や作者の理解の深さがうかがえます。
アポロ計画当時、月のレゴリスが飛行士の目や肺に入ってメチャメチャ痛かったらしいとか、月面の望遠鏡構想(太陽─地球系のL2に打ち上げられるはずだったという「ウェッブ」と、どっちが効率的なのだろうか?)などのエピソードや構想も「ほお~」なんて非常に興味をそそられました。
2. 似てない兄弟
しかしこの作品は、やっぱり物語とキャラが面白い。自分が先に宇宙飛行士になって弟を引っ張っていくことを目指していた六太でしたが、宇宙飛行士になったのは日々人の方。六太はサラリーマンとなり(でもってクビになり)、弟へのコンプレックスを抱えながらすっかり宇宙を諦めてぐずぐず病状態になってました。日々人は、遅れてでも兄が宇宙に来ることを信じて(願って?)いて、そんな六太を何かとアオります。
「宇宙行くの夢なんだろ 諦めんなよ
もし諦められるんなら、そんなもん夢じゃねえ」(2巻95頁)
あんまり「夢」と言う言葉を多用したくないのですが、それを捨てたことに負い目やコンプレックスを持つ人には、かなりキツい言葉ですね。うん、あまりにも君は特殊な立場からモノを言ってるよ日々人君。世界で1億人に1人くらいしかいない職業に就いてるんだぞお前は!
しかし、こういうセリフにギクリとする人は、図星の部分があるからこそ琴線に響くのでしょう。日々人の言わんとしているのは、「本当に今のままでいいのか、自分自身に訊いてみろよ」あるいは「本当にやりたいことなら、出来るまでやれよ」と換言できるのではないでしょうか。
この兄弟は全然似てなくて、六太はセンシティブで気にしいで、他者への観察力が豊か。おそらくは他人が気になるからでしょう。時々相反するように大胆になりますが、二面性は感じません。一方日々人は、困難な課題を楽々こなして宇宙飛行士になり、世事に無関心でいつも飄々としている人物。。。という芝居をしているように見えます。マスコミの前ではちゃんと道化を演じ切っているだけに、その印象が強い。それぞれ自覚していないだけで、実は現実に対する割り切りがよく、自分と向き合うことが多いのは六太の方ではないか?
決して物語からそう類推するのではなく、このコーナーは登場人物が本当に存在しているような感じで書くように心がけているので、そんな目で見た時に、日々人は人格や能力の重心がかなり偏っていて、内面の矛盾を未消化の負荷にしたまま隠し持つタイプに見えるんですよね。まあ、兄に対しては虚心になれないのでしょうが。もちろんそんな人格設定はされていないと思います。物語が六太の語りで展開するせいで私にそう見えるだけでしょう。私にはそれが面白かったりするんですが。
3. 作品の空気
そんなこんなで、妙運珍運に背中を押されつつ、宇宙飛行士を目指すようになる六太なのですが、選考終盤でほかの受験者たちと話が弾みます。宇宙や天文学の話題をおそらくは初めて共有でき、「今まで……こんなこと一度もなかった」と感慨にふける六太。
「ここにいたんだ 誘ったら喜んでついて来てくれそうな連中が…」(4巻193頁)
わかる、わかるよ六太! 軌道エレベーターなんてモノを追いかけ続け、どれだけ浮きまくってきたことか。ようやく友人というか同志が増えて、色々語り合えるようになった喜び。やっぱりこの道を捨てずに良かったなあと思うきょうこの頃。宇宙飛行士の選抜なんて世界にはとうてい及びませんが、つい自分たちの経験を重ね合わせてしまいます。もっとも私、軌道派だからその友人たちの中でさらに浮いてるんですけどね。
ところで本作の空気というかノリについて、読み始めた頃からずーっと「この感覚。。。どこかで。。。」と感じていました。大分読み進めるまで気づかなかったのですが、ある日突然思い出しました。。。「スラムダンク」です。
六太が何かとふてぶてしい表情で根拠のない自信を見せては、いつも間が悪くてトホホな表情になるところや、同僚の女性宇宙飛行士候補を「せりかさん」と呼んで憧れたり(スラムダンクでは「ハルコさん」だったっけ。なんか印象も似ているような)するあたり、「スラムダンク」の桜木花道を連想せずにはいられません。4巻では六太が「ホワチャー──!!」と、訳あって選抜試験中にブルース・リーのモノマネをするのですが(今回の書影もそのイラストね)、私は真っ先に陵南高校の福田(「ほわちゃあ」とキレて監督をボコボコにする)を思い出しましたし。。。私だけかなあ? まあ、両作を併せ読んでも全然意味ないですね。
何はともあれ、スペースシャトル後の宇宙開発を描いた作品としても興味深い上、ストーリーは掛け値なしに面白いです。今後も見逃せません。
当初、この「つまみ食い集」は、軌道エレベーターにほとんど、あるいはまったく関係ない3作品をまとめて扱うつもりだったのですが、つい書き過ぎてしてしまいました。番外編として、今月中にあと1回か2回掲載するつもりです。次回も、軌道エレベーターにはそんなに関係ない作品を扱うつもりですが、なにとぞよろしくお願いいたします。










 最終定理
最終定理
 Z.O.E Dolores, i(ゾーン・オブ・エンダーズ ドロレス・アイ)
Z.O.E Dolores, i(ゾーン・オブ・エンダーズ ドロレス・アイ) 本作で感心するのは、攻撃を受けたOEVの危機回避システムが、かなり妥当に描写されていることです。物理の基礎をふまえた的確なもので、見ていてけっこうシビれました!
本作で感心するのは、攻撃を受けたOEVの危機回避システムが、かなり妥当に描写されていることです。物理の基礎をふまえた的確なもので、見ていてけっこうシビれました! 妙(たえ)なる技の乙女たち
妙(たえ)なる技の乙女たち
 3001年終局への旅
3001年終局への旅

 iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。
iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。


