土曜ドラマ「ハゲタカ」:NHKオンライン
《番組概要》
バブル崩壊後、「失われた10年」と呼ばれる長いトンネルの闇に包まれていた日本に、風穴を開けにやってきた男がいた。日本経済界で、外資系のファンドマネージャーとして暴れ回る男の名は、鷲津政彦――。ビジネスとして、外資的な合理主義を盾に、次々と日本企業に切り込み、買収していく様は、まさに死肉を漁る“ハゲタカ”であった。
一方、襲い来る“ハゲタカ”に敢然と立ち向かう男がいた。旧態依然とした日本の体制にもがきつつ、懸命に日本企業を支え続けようとするエリート・バンカー、芝野健夫――。日本初のターンアラウンド・マネージャー(企業再生家)として、企業再生の道を模作して行く。
「日本買収」ビジネスを巡る二人の男の野望と挫折を軸に、合理化、弱肉強食が叫ばれる今、日本の会社にとって本当に必要な治療法とは何なのか?を問いかける。
《この一言》
“ 私は44です。人生の折り返し点はとっくに過ぎています。
ですが、残りの人生、自分に言い訳して生きていくには、長過ぎます。 ”
世間での評判の高さは知っていましたが、私がこのドラマを観たいと思うようになったきっかけは、〈プレイステーション3〉の『トロ・ステーション』という番組(というべきなのか何なのか分かりませんが、毎日配信されていた近日発売のゲームや全国の観光案内などさまざまな広告的内容を『どこでもいっしょ』のトロちゃんとその友人クロが紹介してくれる楽しいサービス)でした。トロが「芝野さん役」、クロが「鷲津さん役」で、『ハゲタカ』冒頭の「腐ったこの国を買いたたく! 買いたたく! 買いたたく!」とか「あなたが言ったんじゃないですか…」などの名場面のパロディをやっていて、私はK氏とともに大爆笑したものです。それ以来ちょっと気になっていました。
*その時の『トロ・ステーション』の内容をまとめてくれているブログを発見! 懐かしい!!
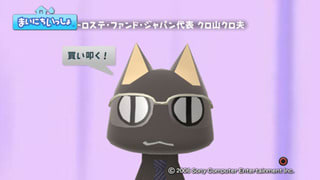
クロ山クロ夫さん
→→
トロステ・ファンドがあなた方を救いに来ました!:days like this
そのパロディの印象があまりに強かったため、私もK氏も『ハゲタカ』は演出の激しいネタドラマだと思い込んでいましたが、第一話を観てすぐに、そんな印象は彼方へと吹っ飛んでしまいました。これはあまりにもシリアス! あまりにも熱いドラマだったのです。
また、タイトルの『ハゲタカ』という言葉から想像していたような、外資ファンドとそれに買い漁られる日本企業との戦いといったような単純な構造の物語でもありませんでした。あまりにも切実で、心に食い込んでくる、激しい物語でした。これは凄い。
このドラマは全6回にわたって物語の緊張感を保ち続け、回を追うごとに少しずつ登場人物の真意を明かしていき、同時に視聴者にはそれぞれの人物に共感させつつ、現在の社会経済の問題点を学ばせ、さらに「では、どうしたら?」と考察させようという、超絶難度のことをやってのける凄まじい出来のドラマです。密度高過ぎ。よく出来過ぎ。
特に第1話の衝撃はもの凄く、私はショックでその日は続きを観られませんでした。第2話からは一息に観てしまいましたが、こんな本気のドラマは久しぶりでしたよ。
本気のドラマ。そう、本気のドラマでした。
即座に心を惹き付ける優れた脚本、キレがありながら抑え目で品の良い演出、抑制をきかせつつも迫真の演技をみせてくれる素晴らしい俳優、感情に訴えかける音楽。隙がありません。
特に主人公の二人は素晴らしかったですね。エリート・バンカー 芝野役の柴田恭兵、ハゲタカこと外資ファンドの日本代表 鷲津役の大森南朋。大森さんは私はこのドラマで初めて拝見しましたが、ちょくちょくCMには出られていますよね。ひょっとしてこれでブレイクしたのでしょうか。頭は切れるんだけど、心根が純粋すぎて極端から極端へと走りがちであるような鷲津役はぴったりでしたね。柴田さんについては、『あぶない刑事』でのお気楽刑事の印象はまったくなく(記憶が古すぎますかね;)、エリート銀行員としての手腕を発揮しつつも理想と現実の狭間で苦しむ芝野役の、ものすごくリアリティを感じる繊細な演技に心を打たれました。
その他のキャストも地味ながら上手い人ばかりで良かったです。第1回の宇崎竜堂さんはとくに凄かった。初っ端からあんなのを見せられたら、そりゃ最後まで観ちゃいますよ。ほんと凄い。あと、栗山千明さん、素敵。この人が唯一華やかなキャスティングで、残りは硬派な役者さんばかりといった感じでしたが、それが良かった! 名脇役をこれでもかというくらいに使ってあって、そのあたりはさすがにNHKといったところでしょうか。贅沢ですねー。
あまりに面白かったので、興奮冷めやらず、しかし考えがまとまりません。「金」の威力を使って人は何を為すべきか。金に使われ、金にひれ伏し、金のために時に人生を踏み誤ってしまう人々。金のために働く、そうだ金は必要だ。でも、金だけのために働くのか? 人が働こうとする動機は金だけによるものだったろうか? 金と人情の間で押しつぶされてしまう人がいる。けれど労働とはそんなものだったろうか。我々は学ばなければならないのではないか、自分で自分の選択や行動にもっと責任と自覚を持たなければならないのではないか。また、果して金は万能なのだろうか? 金の力は人を狂わせるだけだろうか? 金の力は悪なのか?
労働について、資本について、社会活動に参加している全員が一度よく考えてみるべきではないのか。そんな問題を突きつけられるようなドラマだったかと思います。ドラマの結末は必ずしも円満解決というわけではありませんでしたが、よりよい在り方を探していこうとする爽やかな終わり方でした。猛烈な面白さでした。こいつは凄いぜ。
そういうわけで、K氏と『ハゲタカ』ごっこに興じています。台詞が格好良くて真似したくなる感じなんですよね~。「腐ったこの国を買いたたく!(リピート×2)」はもちろんのこと、「あなたは…わたしなんだ」とか「お前は、俺だ!」とか、意味もなく突然「ゴールデン・パラシュート」とか言ってみたりしています。ウヘヘ…。
映画版も観るぜ!
と張り切ってレンタル店に行ったら、全部借りられていました。大人気。わあ~。
*NHKのホームページによると、来月、ドラマ版および劇場版の放送があるようです。
 『ツルバミ』YUKIDOKE vol.2 始めました /【詳しくはこちらからどうぞ!】→→*『ツルバミ』参加者募集のお知らせ(9/13) / *業務連絡用 掲示板をつくりました(9/21)→→ yukidoke_BBS/
『ツルバミ』YUKIDOKE vol.2 始めました /【詳しくはこちらからどうぞ!】→→*『ツルバミ』参加者募集のお知らせ(9/13) / *業務連絡用 掲示板をつくりました(9/21)→→ yukidoke_BBS/ 『ツルバミ』YUKIDOKE vol.2 始めました /【詳しくはこちらからどうぞ!】→→*『ツルバミ』参加者募集のお知らせ(9/13) / *業務連絡用 掲示板をつくりました(9/21)→→ yukidoke_BBS/
『ツルバミ』YUKIDOKE vol.2 始めました /【詳しくはこちらからどうぞ!】→→*『ツルバミ』参加者募集のお知らせ(9/13) / *業務連絡用 掲示板をつくりました(9/21)→→ yukidoke_BBS/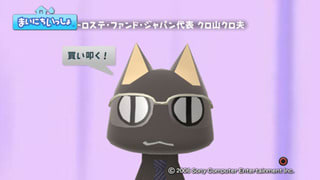 クロ山クロ夫さん
クロ山クロ夫さん 「萌えたら死亡 ラッコ編」:ニコニコ動画
「萌えたら死亡 ラッコ編」:ニコニコ動画

