4月は読まないままだった新書本に取り組み続け、最後に小熊英二の新書を二冊読んだ。やはり興味深かったが、とにかく分厚い。さすがに新書には飽きてしまって、今は違う本を読んでいる。先に読んだ『生きて帰って来た男』(岩波新書、2015)は、ポリープを取った時に読んでた本だった。「あとがき」までいれて389頁。著者にしては薄い方になる本だけど、岩波新書だから結構ズッシリ感がある。刊行当時評判になったが、何となく読まないうちに9年も経ってしまった。ずっと近くに積まれていたのだが、奥の方に入ってしまい探すまで苦労した。しかし、この本は読みやすくて、とても充実した本だった。

小熊英二氏(1962~)は、とにかく分厚い本が多い印象がある。主著が文庫化されてないから、思想史に関心がない人は読んでないだろう。『単一民族神話の起源――<日本人>の自画像の系譜』(1995)で颯爽と論壇デビューした時は、30代前半の新進研究者だった。その後、『<日本人>の境界――沖縄・アイヌ・台湾・朝鮮:植民地支配から復帰運動まで』(1998)、『<民主>と<愛国>――戦後日本のナショナリズムと公共性』(2002)とさらに長大な本を出したが、僕はずっと読んできた。毀誉褒貶もあったが、非常にスリリングな本だった。しかし『1968』上下(2009)になると、持ち歩けないぐらい重い本が2冊で、買ったまま読んでない。『社会を変えるには』(2012、講談社現代新書)も興味深かったが、それ以後読んでなかった。
 (小熊英二氏)
(小熊英二氏)
『生きて帰ってきた男』は著者の父親である小熊謙二氏の生涯をインタビューした本である。小熊謙二(1925~)は一介の市井の人物だが、晩年に戦後補償裁判に関わった。そのためかWikipediaに項目が立っていて、それによればまだ存命である。(更新されていないだけかもしれないが。)刊行当時の書評でも、実の父親の戦争体験、特にシベリア抑留を聞き書きしたことが大きく取り上げられていた。戦争体験、中でもシベリア抑留は非常に重い体験に違いない。しかし、ソ連軍に連行された人は60万人以上と言われ、体験を書き残した本は相当ある。僕もずいぶん読んでいて、そういう目で見ると特に珍しい本ではない。
そもそも題名が『生きて帰ってきた男』である。最初の目次を見ると、徴兵され、シベリアに連行され、帰国後に結核になって療養所に入った。どんな人の人生も語るべきことがあるが、この本の主人公、小熊謙二は結局生還するわけである。生きて帰って来ない限り、著者の小熊英二氏が誕生しない。よって、結末の判っているミステリーみたいな気がして、つい読み遅れたのである。だがその予測は読んでみて間違いだったと判った。実は戦争体験以外のところが抜群に面白く、類書がないのである。
小熊謙二は1925年生まれ。この前読んだ映画監督岡本喜八は1924年(早生まれ)、僕の父は1923年(早生まれ)、僕の母は1927年だから、小熊謙二はちょうど僕の両親の真ん中だ。この世代は戦争と結核で大きな被害を受けていて、僕の父母もそうだった。小熊謙二の兄や姉、そして僕の母の生母や兄は結核で亡くなった。僕の父の兄はシベリアで死んでいて、その場所は小熊謙二と同じチタだった。彼はソ連の実態を知って共産主義に幻想は持たなかったが、戦争責任を認めない保守勢力の「足を引っ張る」ため選挙では社会党や共産党に入れてきたという。これは僕の「左翼というより反右翼」に近い。読んでるうちに何だか親近感が湧いてきた。アムネスティ日本支部に80年代から加入して毎月外国へハガキを送っているのも僕と同じ。
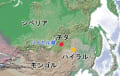 (チタの場所)
(チタの場所)
小熊謙二は北海道で生まれたが、元々小熊家は新潟県中蒲原郡の農家だった。そこの次男小熊雄次が著者の祖父になる。先物取引に失敗して北海道に渡り、札幌で結婚して子どもも生まれたが妻を亡くし網走に移った。そこで代書屋をやり、宿泊していた旅館の娘片山芳江と再婚した。片山家は元々岡山出身だったが、こうして新興の北海道で新しい家族が生まれたのである。しかし、先走って書くと、父方も母方も没落してしまう。芳江は結核で亡くなり、祖父は火事で旅館を失い東京へ出て小さなお菓子屋を開いた。謙二は祖父に預けられ、東京で育ったのである。そして兄の勧めもあって、早稲田実業に進むことが出来た。
子どもを上級学校に進ませる発想は祖父にはなかった。しかし、そこまでである。大学に進むお金があるわけない。何とか小商人としてやって来た祖父は、戦時下に没落し(お菓子屋は休業させられた)、空襲で家も失う。北海道に残った父も欺されて没落し新潟に帰った。両者ともそこそこの老後資金を貯めていたが、戦後のインフレで紙くず同然になった。年金制度もなく戦争で全く生きる術を失ったのである。今まで戦争体験を語るのは、文字を書ける大学出身の知識層が多かった。「農民兵士の手紙」の研究はあるが、地域的に調査がしやすい。没落すれば全国に散らばる小商店主(旧中間層)の戦争体験は極めて珍しいと思う。
親は没落、シベリア帰り、結核回復者の小熊謙二は、いかにして息子(英二)を大学へ入れることが可能な生活を手に入れたか。この本で一番興味深いのは「高度成長をいかに乗り切ったか」である。謙二の妹が東京学芸大の事務をしていて、そのツテで立川ストアという店のスポーツ部門要員に雇われる。社長の拡大方針が失敗した時に、謙二が中心になって整理し自ら立川スポーツという会社を立ち上げ社長となった。自分はスポーツをしないのに、スキー、登山、テニスなどのブームに乗ったのである。さらにベビーブーム世代のための学校増設時代で、新設校に食い込んで体操着や体育館履き、運動用具などを売りまくったのである。
 (不戦兵士の会機関誌「不戦」)
(不戦兵士の会機関誌「不戦」)
そんな小熊謙二の心に、年齢とともに戦争体験、というか戦争責任を置き去りにした戦後日本への憤りが深まっていく。「不戦兵士の会」に参加したのである。さらにシベリア抑留の「慰労金」を「朝鮮人兵士」が貰えないことを知り、補償を求める訴訟の共同原告人にまでなった。ただし一緒に日本国を訴えた韓国人原告には「日本の裁判では負ける」と事前に告げていた。日本国家への幻想もないのである。この小熊謙二という人間の中で、人生の最後に正義を求める心がどんどん高まっていった様は心打たれた。
最後に特に興味深かったこと。学校回りの際には、4月1日に訪ねてはいけない。新設校立ち上げで多忙な教員は、そういう業者を鬱陶しいと思って排除する。学校ごとに体育教員と事務職員と、どちらが主導権を持っているか確かめる必要がある。なるほど。また著者の兄は(一人は祖父の片山家の養子にする約束)輝一、政一だった。これは(片山家の出身の)岡山の殿様池田輝政に由来するという。一方自身の謙二は、(小熊家の出身の)新潟の武将上杉謙信に由来するという。だからもう一人男子が生まれたら、信三だったろうという。当時の命名法はそんなものだと語るのは印象的だ。

小熊英二氏(1962~)は、とにかく分厚い本が多い印象がある。主著が文庫化されてないから、思想史に関心がない人は読んでないだろう。『単一民族神話の起源――<日本人>の自画像の系譜』(1995)で颯爽と論壇デビューした時は、30代前半の新進研究者だった。その後、『<日本人>の境界――沖縄・アイヌ・台湾・朝鮮:植民地支配から復帰運動まで』(1998)、『<民主>と<愛国>――戦後日本のナショナリズムと公共性』(2002)とさらに長大な本を出したが、僕はずっと読んできた。毀誉褒貶もあったが、非常にスリリングな本だった。しかし『1968』上下(2009)になると、持ち歩けないぐらい重い本が2冊で、買ったまま読んでない。『社会を変えるには』(2012、講談社現代新書)も興味深かったが、それ以後読んでなかった。
 (小熊英二氏)
(小熊英二氏)『生きて帰ってきた男』は著者の父親である小熊謙二氏の生涯をインタビューした本である。小熊謙二(1925~)は一介の市井の人物だが、晩年に戦後補償裁判に関わった。そのためかWikipediaに項目が立っていて、それによればまだ存命である。(更新されていないだけかもしれないが。)刊行当時の書評でも、実の父親の戦争体験、特にシベリア抑留を聞き書きしたことが大きく取り上げられていた。戦争体験、中でもシベリア抑留は非常に重い体験に違いない。しかし、ソ連軍に連行された人は60万人以上と言われ、体験を書き残した本は相当ある。僕もずいぶん読んでいて、そういう目で見ると特に珍しい本ではない。
そもそも題名が『生きて帰ってきた男』である。最初の目次を見ると、徴兵され、シベリアに連行され、帰国後に結核になって療養所に入った。どんな人の人生も語るべきことがあるが、この本の主人公、小熊謙二は結局生還するわけである。生きて帰って来ない限り、著者の小熊英二氏が誕生しない。よって、結末の判っているミステリーみたいな気がして、つい読み遅れたのである。だがその予測は読んでみて間違いだったと判った。実は戦争体験以外のところが抜群に面白く、類書がないのである。
小熊謙二は1925年生まれ。この前読んだ映画監督岡本喜八は1924年(早生まれ)、僕の父は1923年(早生まれ)、僕の母は1927年だから、小熊謙二はちょうど僕の両親の真ん中だ。この世代は戦争と結核で大きな被害を受けていて、僕の父母もそうだった。小熊謙二の兄や姉、そして僕の母の生母や兄は結核で亡くなった。僕の父の兄はシベリアで死んでいて、その場所は小熊謙二と同じチタだった。彼はソ連の実態を知って共産主義に幻想は持たなかったが、戦争責任を認めない保守勢力の「足を引っ張る」ため選挙では社会党や共産党に入れてきたという。これは僕の「左翼というより反右翼」に近い。読んでるうちに何だか親近感が湧いてきた。アムネスティ日本支部に80年代から加入して毎月外国へハガキを送っているのも僕と同じ。
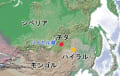 (チタの場所)
(チタの場所)小熊謙二は北海道で生まれたが、元々小熊家は新潟県中蒲原郡の農家だった。そこの次男小熊雄次が著者の祖父になる。先物取引に失敗して北海道に渡り、札幌で結婚して子どもも生まれたが妻を亡くし網走に移った。そこで代書屋をやり、宿泊していた旅館の娘片山芳江と再婚した。片山家は元々岡山出身だったが、こうして新興の北海道で新しい家族が生まれたのである。しかし、先走って書くと、父方も母方も没落してしまう。芳江は結核で亡くなり、祖父は火事で旅館を失い東京へ出て小さなお菓子屋を開いた。謙二は祖父に預けられ、東京で育ったのである。そして兄の勧めもあって、早稲田実業に進むことが出来た。
子どもを上級学校に進ませる発想は祖父にはなかった。しかし、そこまでである。大学に進むお金があるわけない。何とか小商人としてやって来た祖父は、戦時下に没落し(お菓子屋は休業させられた)、空襲で家も失う。北海道に残った父も欺されて没落し新潟に帰った。両者ともそこそこの老後資金を貯めていたが、戦後のインフレで紙くず同然になった。年金制度もなく戦争で全く生きる術を失ったのである。今まで戦争体験を語るのは、文字を書ける大学出身の知識層が多かった。「農民兵士の手紙」の研究はあるが、地域的に調査がしやすい。没落すれば全国に散らばる小商店主(旧中間層)の戦争体験は極めて珍しいと思う。
親は没落、シベリア帰り、結核回復者の小熊謙二は、いかにして息子(英二)を大学へ入れることが可能な生活を手に入れたか。この本で一番興味深いのは「高度成長をいかに乗り切ったか」である。謙二の妹が東京学芸大の事務をしていて、そのツテで立川ストアという店のスポーツ部門要員に雇われる。社長の拡大方針が失敗した時に、謙二が中心になって整理し自ら立川スポーツという会社を立ち上げ社長となった。自分はスポーツをしないのに、スキー、登山、テニスなどのブームに乗ったのである。さらにベビーブーム世代のための学校増設時代で、新設校に食い込んで体操着や体育館履き、運動用具などを売りまくったのである。
 (不戦兵士の会機関誌「不戦」)
(不戦兵士の会機関誌「不戦」)そんな小熊謙二の心に、年齢とともに戦争体験、というか戦争責任を置き去りにした戦後日本への憤りが深まっていく。「不戦兵士の会」に参加したのである。さらにシベリア抑留の「慰労金」を「朝鮮人兵士」が貰えないことを知り、補償を求める訴訟の共同原告人にまでなった。ただし一緒に日本国を訴えた韓国人原告には「日本の裁判では負ける」と事前に告げていた。日本国家への幻想もないのである。この小熊謙二という人間の中で、人生の最後に正義を求める心がどんどん高まっていった様は心打たれた。
最後に特に興味深かったこと。学校回りの際には、4月1日に訪ねてはいけない。新設校立ち上げで多忙な教員は、そういう業者を鬱陶しいと思って排除する。学校ごとに体育教員と事務職員と、どちらが主導権を持っているか確かめる必要がある。なるほど。また著者の兄は(一人は祖父の片山家の養子にする約束)輝一、政一だった。これは(片山家の出身の)岡山の殿様池田輝政に由来するという。一方自身の謙二は、(小熊家の出身の)新潟の武将上杉謙信に由来するという。だからもう一人男子が生まれたら、信三だったろうという。当時の命名法はそんなものだと語るのは印象的だ。















