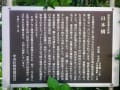いつまで書いていても仕方ないから、銀座散歩は今回で一応終わりにしたい。銀座にはいろいろなものがある。例えば、「画廊」が一番多いのは今でも銀座だという話で、検索すると一覧のようなものが出てくる。でも僕が知っているのは「日動画廊」ぐらい。ここは数寄屋橋交差点から外堀通りを少し行ったところにある。今回歩いていて銀座8丁目に「月光荘」があった。今は画材店だけだけど、昔は画廊もやっていた。(月光荘事件というのがあったので、名前だけ何となく記憶していたのである。)映画の「銀座の恋の物語」では、浅丘ルリコが銀座で「お針子」をしている。銀座には昔はシャレた洋服、帽子などの店(ブティック)がいっぱいあったのではないか。今は多分、表参道や代官山などにいっぱいあるんだろう。並木通りを歩いていて「ヒロコ・コシノ」の店があった。コシノジュンコ(小篠淳子)の姉で、ファッション界のコシノ三姉妹の一番上。漢字で書くと小篠弘子なんですね。



数寄屋橋交差点から有楽町マリオン(旧日劇)へ行くところに「西銀座デパート」がある。東銀座という地下鉄駅はあるけど、「西銀座」は今はない。今村昌平監督に「西銀座駅前」という小品があるけど、どなたかのブログに「今村昌平は映画の中で架空の駅名を使った」などと書いているのを読んだことがある。しかし、東京で2番目の地下鉄、丸の内線が出来た時、銀座駅は西銀座駅と言ったのである。銀座線(中央通り)と丸ノ内線(外堀通り)は並行して走っている。そこに1963年に日比谷線が晴海通りの地下に開通した。この結果、三つの地下鉄路線は全部「銀座駅」に統一されたのである。1957年から1963年までという短い間だけ、西銀座駅があったわけだ。その向かい側には、プランタン銀座(もともと今はなきダイエー系の商業施設だった)、丸の内東映、銀座教会などが並んでいる。この銀座教会というビルも最初に見た時は結構ビックリしたものである。一度だけ迷い込んだときがある。日時も覚えていて、1972年12月24日、つまり降誕祭前夜のことだった。教会ビルから交差点よりに「塚本素山ビル」がある。塚本素山という人は元は軍人、戦後は実業家で、一種の政商のような人だった。創価学会とのつながりが深かった。ここの地下一階に「日本で一番有名なお店」がある。


それは「すきやばし次郎」のことで、もちろんオバマ大統領来日時に安倍首相と行ったところである。というか映画「二郎は鮨の夢を見る」という記録映画の舞台。ホームページを見ると、前月の一日に翌月の予約開始。8月はもう一杯。おまかせコースで3万円とある。お店の前まで行ったけれど「写真お断り」と英語で書いてあった。だから店の写真は止めて、塚本素山ビルの地下入り口の店名だけ撮ってきた。僕は多分行くことはないだろうと思うけど、それは値段や予約の問題ではない。実はお寿司はあまり好きではなく、人生で寿司屋に行ったことが数回しかない。社会勉強としてなら、まず回転寿司に行く方が先なんだろう。
ところで、「銀座で食べる」という題名にしたけど、実は「銀座では食べない」。高いということもあるけど、家に地下鉄一本で帰れるので「デパ地下で買って家で食べるか」になりやすい。有名な店は値段もだけど、どうも敷居が高いので、映画を見た後なんかにくつろげない。だから一時はシェーキーズによく行っていた時がある。中央通り(2丁目か3丁目あたり)にあったのである。村上春樹の「ダンス ダンス ダンス」で五反田君と「僕」がよくシェーキーズで会うのと同じで、バイキングという「匿名性」が気楽だった。歳とると行かなくなったけど。
外で一番食べるのはカレーなんだけど、銀座では2丁目の「メルサ」の4階の「オールドデリー」がお奨め。名前で判るように北インド料理で、ナンが美味しい。サモサもいい。そんなに混んでないのもいい。銀座でカレーと言うと、東銀座の昭和通り沿い、歌舞伎座の近くに有名な「ナイルレストラン」がある。このナイルというのは、ナイル川ではなくて店主の名前から取ったもの。初代は独立運動弾圧を逃れて日本に来た。戦時中は日本軍とも協力した過去があるが、戦後1949年に開店した。昔、池袋西武に店があってよく食べに行ったし、本店にも行ってるけど「ムルギーランチ」ばかりすすめられて「混ぜて混ぜて」というのがちょっと鬱陶しくて最近は行ってない。今回久しぶりに見に行ったら、両隣の高いビルに囲まれ、自分のビルで頑張っていた。他に「カツカレーの元祖」、グリル・スイスもある。巨人の選手だった千葉茂が常連で、その求めで作った。和光裏のガス燈通り。



銀座の「甘いもの」の名物は何だろうか。美味しいケーキ屋なんかが集中してそうだけど、それは昔の話かもしれない。いや、デパートなんかは別。松屋なんか、いくら見てても飽きないようなスイーツが並んでる。洋物はデパートに吸収されてる感じではないか。しかし、和菓子なら有名なものがある。「空也もなか」である。東京のもなかでは最強レベル。僕の中では、上野のうさぎやの「どら焼き」や長命寺の桜もちなどと並ぶ位置にある気がする。でも、これを店で買うのは大変。6丁目7番にある店には、いつも「売り切れ」の紙が貼ってある。もう銀座の風物詩に近い。基本は「予約」が必要なのである。でも、今回探していて、この空也もなかを一個でも食べられる店を発見した。松屋デパートの真裏に花や野草の店があり、そこの2階に「茶房野の花」という、銀座の隠れ里のようなスペースがあるのだ。いや、通り一本隔てただけで、こんなに静かな店があるのか。ここで「空也もなかとお茶(またはコーヒー)」が頼めるのである。非常に小さくて可愛らしい「もなか」だけど、やはり美味しい。



後は銀座の有名な店をピックアップして載せておきたい。行ったことのない店ばかりだけど。新橋寄りに名店が多い。中央通りを8丁目(7丁目交差点)まで行くと、かの有名な「資生堂パーラー」。名前は昔から有名だけど、こういう店は親に連れられて行った経験でもないと、知らずに通り過ぎてしまう。こういう店に入るという文化を身に付けてないので。どこから撮っても自分が映ってしまうので写真が難しい。1902年創業の超有名店。メニューも撮ったので、一応。



もう中央通りが終わるあたりに天ぷらの「天國」。「ハゲ天」とか「天一」とか有名店は多いけど、何しろ1885年開業という歴史がある。中華では「維新號」。1899年神田で創業し、戦後に銀座に開店した。肉まんで有名らしい。どっちも8丁目。7丁目に「銀座ライオン」。1899年創業のビヤホールの元祖である。ここも残念ながら入ったことなし。資生堂パーラーの道向かい、三菱東京UFJ銀行の並びに、「カフェ パウリスタ」がある。この名前は大正時代の文献によく出てきて、大正時代のモダン東京の象徴のような喫茶店だった。震災で焼けて無くなったはずが、同じ経営者のもとで1970年に復活したのだという。そのことを森まゆみさんの本で知っていたけど、今回初めて場所を知った。でも、まだ入ってない。僕のよく行く場所からすると、コーヒーを飲むには遠いのである。いずれ、また。店名はブラジルの「サンパウロ」から来ていて、まあ「パウロっ子」とでも言った言葉らしい。最後に3丁目、和光の裏をずっと道を燃えてしばらく行くと、洋食の「煉瓦亭」。1895年創業の、日本の洋食を始めた店の一つ。カツレツを考案したという。カキフライ、エビフライ、メンチカツなど、皆この店が始まりと森まゆみ「明治・大正を食べ歩く」(PHP新書)という本にある。高いステーキ屋と思い込んでいたけど、銀座にしては手が届く洋食屋と知ったので、いずれ入ってみたいと思う。








数寄屋橋交差点から有楽町マリオン(旧日劇)へ行くところに「西銀座デパート」がある。東銀座という地下鉄駅はあるけど、「西銀座」は今はない。今村昌平監督に「西銀座駅前」という小品があるけど、どなたかのブログに「今村昌平は映画の中で架空の駅名を使った」などと書いているのを読んだことがある。しかし、東京で2番目の地下鉄、丸の内線が出来た時、銀座駅は西銀座駅と言ったのである。銀座線(中央通り)と丸ノ内線(外堀通り)は並行して走っている。そこに1963年に日比谷線が晴海通りの地下に開通した。この結果、三つの地下鉄路線は全部「銀座駅」に統一されたのである。1957年から1963年までという短い間だけ、西銀座駅があったわけだ。その向かい側には、プランタン銀座(もともと今はなきダイエー系の商業施設だった)、丸の内東映、銀座教会などが並んでいる。この銀座教会というビルも最初に見た時は結構ビックリしたものである。一度だけ迷い込んだときがある。日時も覚えていて、1972年12月24日、つまり降誕祭前夜のことだった。教会ビルから交差点よりに「塚本素山ビル」がある。塚本素山という人は元は軍人、戦後は実業家で、一種の政商のような人だった。創価学会とのつながりが深かった。ここの地下一階に「日本で一番有名なお店」がある。


それは「すきやばし次郎」のことで、もちろんオバマ大統領来日時に安倍首相と行ったところである。というか映画「二郎は鮨の夢を見る」という記録映画の舞台。ホームページを見ると、前月の一日に翌月の予約開始。8月はもう一杯。おまかせコースで3万円とある。お店の前まで行ったけれど「写真お断り」と英語で書いてあった。だから店の写真は止めて、塚本素山ビルの地下入り口の店名だけ撮ってきた。僕は多分行くことはないだろうと思うけど、それは値段や予約の問題ではない。実はお寿司はあまり好きではなく、人生で寿司屋に行ったことが数回しかない。社会勉強としてなら、まず回転寿司に行く方が先なんだろう。
ところで、「銀座で食べる」という題名にしたけど、実は「銀座では食べない」。高いということもあるけど、家に地下鉄一本で帰れるので「デパ地下で買って家で食べるか」になりやすい。有名な店は値段もだけど、どうも敷居が高いので、映画を見た後なんかにくつろげない。だから一時はシェーキーズによく行っていた時がある。中央通り(2丁目か3丁目あたり)にあったのである。村上春樹の「ダンス ダンス ダンス」で五反田君と「僕」がよくシェーキーズで会うのと同じで、バイキングという「匿名性」が気楽だった。歳とると行かなくなったけど。
外で一番食べるのはカレーなんだけど、銀座では2丁目の「メルサ」の4階の「オールドデリー」がお奨め。名前で判るように北インド料理で、ナンが美味しい。サモサもいい。そんなに混んでないのもいい。銀座でカレーと言うと、東銀座の昭和通り沿い、歌舞伎座の近くに有名な「ナイルレストラン」がある。このナイルというのは、ナイル川ではなくて店主の名前から取ったもの。初代は独立運動弾圧を逃れて日本に来た。戦時中は日本軍とも協力した過去があるが、戦後1949年に開店した。昔、池袋西武に店があってよく食べに行ったし、本店にも行ってるけど「ムルギーランチ」ばかりすすめられて「混ぜて混ぜて」というのがちょっと鬱陶しくて最近は行ってない。今回久しぶりに見に行ったら、両隣の高いビルに囲まれ、自分のビルで頑張っていた。他に「カツカレーの元祖」、グリル・スイスもある。巨人の選手だった千葉茂が常連で、その求めで作った。和光裏のガス燈通り。



銀座の「甘いもの」の名物は何だろうか。美味しいケーキ屋なんかが集中してそうだけど、それは昔の話かもしれない。いや、デパートなんかは別。松屋なんか、いくら見てても飽きないようなスイーツが並んでる。洋物はデパートに吸収されてる感じではないか。しかし、和菓子なら有名なものがある。「空也もなか」である。東京のもなかでは最強レベル。僕の中では、上野のうさぎやの「どら焼き」や長命寺の桜もちなどと並ぶ位置にある気がする。でも、これを店で買うのは大変。6丁目7番にある店には、いつも「売り切れ」の紙が貼ってある。もう銀座の風物詩に近い。基本は「予約」が必要なのである。でも、今回探していて、この空也もなかを一個でも食べられる店を発見した。松屋デパートの真裏に花や野草の店があり、そこの2階に「茶房野の花」という、銀座の隠れ里のようなスペースがあるのだ。いや、通り一本隔てただけで、こんなに静かな店があるのか。ここで「空也もなかとお茶(またはコーヒー)」が頼めるのである。非常に小さくて可愛らしい「もなか」だけど、やはり美味しい。



後は銀座の有名な店をピックアップして載せておきたい。行ったことのない店ばかりだけど。新橋寄りに名店が多い。中央通りを8丁目(7丁目交差点)まで行くと、かの有名な「資生堂パーラー」。名前は昔から有名だけど、こういう店は親に連れられて行った経験でもないと、知らずに通り過ぎてしまう。こういう店に入るという文化を身に付けてないので。どこから撮っても自分が映ってしまうので写真が難しい。1902年創業の超有名店。メニューも撮ったので、一応。



もう中央通りが終わるあたりに天ぷらの「天國」。「ハゲ天」とか「天一」とか有名店は多いけど、何しろ1885年開業という歴史がある。中華では「維新號」。1899年神田で創業し、戦後に銀座に開店した。肉まんで有名らしい。どっちも8丁目。7丁目に「銀座ライオン」。1899年創業のビヤホールの元祖である。ここも残念ながら入ったことなし。資生堂パーラーの道向かい、三菱東京UFJ銀行の並びに、「カフェ パウリスタ」がある。この名前は大正時代の文献によく出てきて、大正時代のモダン東京の象徴のような喫茶店だった。震災で焼けて無くなったはずが、同じ経営者のもとで1970年に復活したのだという。そのことを森まゆみさんの本で知っていたけど、今回初めて場所を知った。でも、まだ入ってない。僕のよく行く場所からすると、コーヒーを飲むには遠いのである。いずれ、また。店名はブラジルの「サンパウロ」から来ていて、まあ「パウロっ子」とでも言った言葉らしい。最後に3丁目、和光の裏をずっと道を燃えてしばらく行くと、洋食の「煉瓦亭」。1895年創業の、日本の洋食を始めた店の一つ。カツレツを考案したという。カキフライ、エビフライ、メンチカツなど、皆この店が始まりと森まゆみ「明治・大正を食べ歩く」(PHP新書)という本にある。高いステーキ屋と思い込んでいたけど、銀座にしては手が届く洋食屋と知ったので、いずれ入ってみたいと思う。