最近の風潮だが、どうやら「感動」「泣ける」というキャッチフレーズは商売になるらしい。
みんなが泣ける、癒されるというあるピアニストの「ラ・カンパネラ」にちっとも感動できない。おじいちゃん部長の奥様は、テレビで彼女のドキュメンタリーを観て感動し、CDを買って聴いているそうだ。感動というクオリアはその人個人固有のものだから、晩年にわかに脚光を浴びて多くのファンを獲得した元天才少女だったそのピアニストの演奏に水をさす気持ちはないが、あのサントリーホールを満席にする集客力とプロとしての音楽性の差に冷ややかな感情がわいてくるのも、自分なりの正直な感想だ。
篠田節子さんの近作「讃歌」は、そのような現象に疑問を感じている素直になれないやっかいな者への、感動の裏側の核心をついた小説である。そして、受けとめ方によっては、薄っぺらな「感動」への警告を放つ問題作である。
 テレビ製作会社に勤務する小野は、毎日激務に追われ、短い結婚生活の後に別れた妻の願いである幼い娘の面談すらもままならない。そんなある日、良質なCDを制作しているという業界でも定評のある会社の社長、熊谷に誘われて、小さな教会でのコンサートを聴きに行く。クラシック音楽を知らなかった小野は、そのヴィオリストが奏でるシューベルトのアルペジオーネソナタに、我知らず涙を流す。その若くないヴィオリスト柳原園子の演奏に深く感動したのだった。
テレビ製作会社に勤務する小野は、毎日激務に追われ、短い結婚生活の後に別れた妻の願いである幼い娘の面談すらもままならない。そんなある日、良質なCDを制作しているという業界でも定評のある会社の社長、熊谷に誘われて、小さな教会でのコンサートを聴きに行く。クラシック音楽を知らなかった小野は、そのヴィオリストが奏でるシューベルトのアルペジオーネソナタに、我知らず涙を流す。その若くないヴィオリスト柳原園子の演奏に深く感動したのだった。
「成功する女性ヴァイオリニストには二通りある。火のような情熱と腕力で弾ききるタイプと、氷のように冷静で研ぎ澄まされたテクニックと解釈力で自分の音楽を作りこんでいくタイプ」
そう解説する熊谷から聞かされた園子の経歴は、どちらにも該当しなかった。園子はかって学生音楽コンクールで優勝し、天才少女ヴァイオリニストと期待され米国に留学しながらも、文化の摩擦や自己主張の激しい音楽生の集う周囲の環境にもなじめず、孤独を深めて自殺のような事故にあい、失意のうちに帰国。長年、後遺症に苦しむ彼女を救ったのは、楽壇の重鎮である音楽家の「涙とともにパンを食べることによって、音楽は豊かさと深みを増すこともある。君に合うのはヴィオラだ。真の意味でのヴィオラの魅力を表現できる演奏家は限られている。ヴィオラという楽器が、君を選ぶのだ」というアドバイスだった。驚きと感動に震えた園子は、ヴァイオリンからヴィオラに転向した。小野が聴いたのは、そんな彼女の演奏に惹かれて、癒されて集う人々のボランティアが支える、教会での小さな小さなコンサートだったのだ。
小野は、彼女の壮絶な悲劇と清らかな語り口に益々純粋に感動する。そして、この感動をドキュメンタリーとして視聴者に届けたいと企画を練リ始める。
著者である篠田節子さんの女性を見る目は厳しい。残酷なまでに、女の化粧や衣装の舞台裏を暴いていく。バブル時代もてはやされ、三島由紀夫夫人の名前をペンネームにした芸大出身の女流作家の小説を、中身が全くからっぽ、いずれ時代は彼女を忘れていくと思っていたところに、篠田さんの「第4の神話」が登場した。この本を読んで、実業家であるイギリス人の夫の買うヨットのためにもう一冊小説を書くと、その多作の作家の告白に、私は胸をつかれた感情を思い出した。ここまで真実の素顔をさらさなくてもと、すでに亡くなった作家に同情したものだ。勿論この小説は、フィクションだ。しかし篠田さんは、誰もがモデルを想像するこの小説で訴えたかったのは、悪趣味な暴露でなく、そんなひとりの作家を消耗しつくした時代とマスコミへの、同業である作家としての、小説を世におくることへの問いかけだったのではないだろうか。
そして今度は、素人とはいえ長年チェロのレッスンを受けている作家がかいた「讃歌」である。この小説は、受けとめ方によって異なるだろう。安易に感動を視聴者に売るマスコミ、そしてその手口にいとも簡単にのってしまう大衆、下請けプロダクションの劣悪で厳しい仕事ぶり、マスコミをうまく利用して高額なストラディバリウスを手にいれるまでに”経済的に”成長する演奏家と、逆に「讃歌」に登場する”音楽の権威”といういやみなくらいぶあつい壁。そして何よりも、音楽家になることのあまりにも厳しく高い峰。私にとっては、この作品は「第4の神話」を流れをくむ小説という位置付けである。舞台をテレビとクラシック音楽にしているが、なにもこの業界だけの話ではない。真の感動とは何か、今度はそれを真摯に世に問いた作品である。
園子のシューベルトの音楽をCDで聴きながら小野は涙を流して、最後に自問自答する。
「園子の音楽には、心を揺さぶる圧倒的な力があった。数々の試練を経て再生した魂が、他者の苦しみに、哀しみに、共感し、救いへと導く力。あの中傷は、聴衆のこの力への畏れだったのではないか。
いったい音楽とは何か、何のためにあるのか。」
みんなが泣ける、癒されるというあるピアニストの「ラ・カンパネラ」にちっとも感動できない。おじいちゃん部長の奥様は、テレビで彼女のドキュメンタリーを観て感動し、CDを買って聴いているそうだ。感動というクオリアはその人個人固有のものだから、晩年にわかに脚光を浴びて多くのファンを獲得した元天才少女だったそのピアニストの演奏に水をさす気持ちはないが、あのサントリーホールを満席にする集客力とプロとしての音楽性の差に冷ややかな感情がわいてくるのも、自分なりの正直な感想だ。
篠田節子さんの近作「讃歌」は、そのような現象に疑問を感じている素直になれないやっかいな者への、感動の裏側の核心をついた小説である。そして、受けとめ方によっては、薄っぺらな「感動」への警告を放つ問題作である。
 テレビ製作会社に勤務する小野は、毎日激務に追われ、短い結婚生活の後に別れた妻の願いである幼い娘の面談すらもままならない。そんなある日、良質なCDを制作しているという業界でも定評のある会社の社長、熊谷に誘われて、小さな教会でのコンサートを聴きに行く。クラシック音楽を知らなかった小野は、そのヴィオリストが奏でるシューベルトのアルペジオーネソナタに、我知らず涙を流す。その若くないヴィオリスト柳原園子の演奏に深く感動したのだった。
テレビ製作会社に勤務する小野は、毎日激務に追われ、短い結婚生活の後に別れた妻の願いである幼い娘の面談すらもままならない。そんなある日、良質なCDを制作しているという業界でも定評のある会社の社長、熊谷に誘われて、小さな教会でのコンサートを聴きに行く。クラシック音楽を知らなかった小野は、そのヴィオリストが奏でるシューベルトのアルペジオーネソナタに、我知らず涙を流す。その若くないヴィオリスト柳原園子の演奏に深く感動したのだった。「成功する女性ヴァイオリニストには二通りある。火のような情熱と腕力で弾ききるタイプと、氷のように冷静で研ぎ澄まされたテクニックと解釈力で自分の音楽を作りこんでいくタイプ」
そう解説する熊谷から聞かされた園子の経歴は、どちらにも該当しなかった。園子はかって学生音楽コンクールで優勝し、天才少女ヴァイオリニストと期待され米国に留学しながらも、文化の摩擦や自己主張の激しい音楽生の集う周囲の環境にもなじめず、孤独を深めて自殺のような事故にあい、失意のうちに帰国。長年、後遺症に苦しむ彼女を救ったのは、楽壇の重鎮である音楽家の「涙とともにパンを食べることによって、音楽は豊かさと深みを増すこともある。君に合うのはヴィオラだ。真の意味でのヴィオラの魅力を表現できる演奏家は限られている。ヴィオラという楽器が、君を選ぶのだ」というアドバイスだった。驚きと感動に震えた園子は、ヴァイオリンからヴィオラに転向した。小野が聴いたのは、そんな彼女の演奏に惹かれて、癒されて集う人々のボランティアが支える、教会での小さな小さなコンサートだったのだ。
小野は、彼女の壮絶な悲劇と清らかな語り口に益々純粋に感動する。そして、この感動をドキュメンタリーとして視聴者に届けたいと企画を練リ始める。
著者である篠田節子さんの女性を見る目は厳しい。残酷なまでに、女の化粧や衣装の舞台裏を暴いていく。バブル時代もてはやされ、三島由紀夫夫人の名前をペンネームにした芸大出身の女流作家の小説を、中身が全くからっぽ、いずれ時代は彼女を忘れていくと思っていたところに、篠田さんの「第4の神話」が登場した。この本を読んで、実業家であるイギリス人の夫の買うヨットのためにもう一冊小説を書くと、その多作の作家の告白に、私は胸をつかれた感情を思い出した。ここまで真実の素顔をさらさなくてもと、すでに亡くなった作家に同情したものだ。勿論この小説は、フィクションだ。しかし篠田さんは、誰もがモデルを想像するこの小説で訴えたかったのは、悪趣味な暴露でなく、そんなひとりの作家を消耗しつくした時代とマスコミへの、同業である作家としての、小説を世におくることへの問いかけだったのではないだろうか。
そして今度は、素人とはいえ長年チェロのレッスンを受けている作家がかいた「讃歌」である。この小説は、受けとめ方によって異なるだろう。安易に感動を視聴者に売るマスコミ、そしてその手口にいとも簡単にのってしまう大衆、下請けプロダクションの劣悪で厳しい仕事ぶり、マスコミをうまく利用して高額なストラディバリウスを手にいれるまでに”経済的に”成長する演奏家と、逆に「讃歌」に登場する”音楽の権威”といういやみなくらいぶあつい壁。そして何よりも、音楽家になることのあまりにも厳しく高い峰。私にとっては、この作品は「第4の神話」を流れをくむ小説という位置付けである。舞台をテレビとクラシック音楽にしているが、なにもこの業界だけの話ではない。真の感動とは何か、今度はそれを真摯に世に問いた作品である。
園子のシューベルトの音楽をCDで聴きながら小野は涙を流して、最後に自問自答する。
「園子の音楽には、心を揺さぶる圧倒的な力があった。数々の試練を経て再生した魂が、他者の苦しみに、哀しみに、共感し、救いへと導く力。あの中傷は、聴衆のこの力への畏れだったのではないか。
いったい音楽とは何か、何のためにあるのか。」











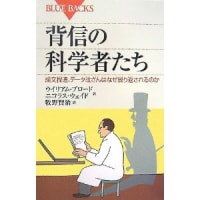

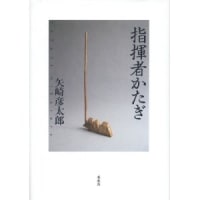
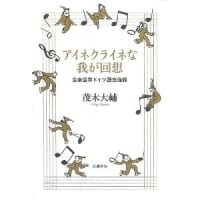
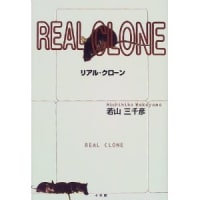
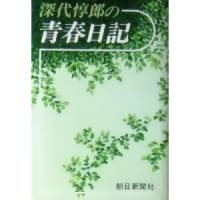
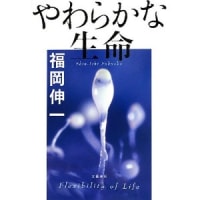
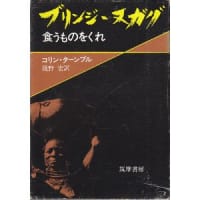
追伸 ブログの背景には驚きました。もしかして今はやりの「翔子さん」かと錯覚したぐらいです。
同作者の音楽作品ということで、「カノン」の記事をトラバさせて頂きました。
「賛歌」は朝日の連載に途中から気付いて読んでいたのですが、「カノン」の天才からかわって、こう来たか~、と思いました。園子は小野の思いもよらぬほど、したたかでもありましたが、「感動」って何だろう、と考えました。小説などにおいても、理論、テクニック的にはなっていなくとも、感動させられるものもあるのだろうなぁ、と思います。理論的にその地位を知らしめられた時(貶められたとき?)、それまで「感動」に乗っていた人たちが、同じように感動できるか、というのはまた別の問題なのでしょうか。刊行されたら読もうと思いつつも、ハードだしなぁ、とまだ通して読んではいません。
「翔子さん」てなんでしょうか?でも、驚きましたか。(笑)こういう冗談が結構好きです。それに叶姉妹タイプではないですし。(今日、本屋のレジで叶姉妹の写真集を見つけました)読みにくいので、すぐに元に戻しますが。
ブログでは書ききれなかったのですが、園子の演奏に感動して涙を流す小野と対照的な位置にあるのが、音大卒のAD、神田です。彼女は、園子の演奏を聴いて、「西洋音楽を理解していない演歌」と評します。そして「バッハやモーツァルトを理解できる日本人は、一握り。日本人が感動するクラシック音楽は、未だに大正音楽。センチメンタルな演奏はプロとして恥かしい」と。この神田の意見に、小野は本質的に真実を感じとり、認めたくない真実に自分は直面せざるをえなくなります。
但し、篠田さんは、小野の感動を否定するものでもなく、だから園子の演奏自体も否定せず、どちらが正しいのではなく、問題定義をして読者に答えを委ねています。そこに、暴露的な下品な印象が残らず、作品の高い質を維持しているポイントだと思います。
モーツァルトを理解できる日本人だ自分のことを思えませんが、calafさまのおっしゃりたいのは、本物の音楽がないがしろにされて(←CD制作におけるこの辺の事情も本作にあります)、安易な商業主義にのった音楽はいかがなものか、ということではないでしょうか。私も全く同感です。
ただ、ヴァイオリニストの川畠成道さんは、本物のヴァイオリニストです。機会がございましたら、一度聴いてください。
にも関わらず、音楽よりも彼のヒューマンストーリーの方がみなさんよく聞かれるようで。残念です。
コメントの返信が遅くなり、申し訳ございません。
(つなさんのブログは、まるでチャットの如くコメントが多いですよね。)
朝日新聞に連載されていたことを読み終わって知りましたが、勇気ありますね。さすが、篠田さん。。。
おじいちゃん部長が以前、篠田さんのことを女性としての魅力に乏しいといっておりましたが(失礼!)、作家としての情念には、充分魅力を感じます。まるで「炎立つ」みたいです。
>理論的にその地位を知らしめられた時(貶められたとき?)、それまで「感動」に乗っていた人たちが、同じように感動できるか、というのはまた別の問題なのでしょうか
個人的な見解を申し上げれば、自分の評価に自信があれば、地位や名声の上昇、下降に関係なく感動は続くと思います。感動するのは、世間的な評価でもなければ、今応援したいという気持ち、原石を発掘した喜びでもなく、創造性と表現における感動だと思うからです。
>ハードだしなぁ
一般的な傾向として、ハードで優れた作品が多くになりました。桐野夏生さんの「グロテスク」なんか、超ハードでした。
反動で「東京物語」のような柔らかい小説を読みました。
読みながら、つなさんのことを思い出しました。
何をおっしゃいまする。中年こそ男盛りです!
出会い系に流れてしまいそうなので、今夜はこれで。
ああ、分かりにくかったですね。追加でも少し、お話させて下さい。「ハード」はハードカバーの意味です。文庫化されないと、何となく食指が伸びない私・・・。「グロテスク」もまた、「他人の評価」が大きなテーマになる本でしたね。
「賛歌」で言うなら、理論的に感動出来ないという神田に代表されるA層、雰囲気で乗せられて感動した一般大衆B層、裏のからくりを知ってなお、その音に感動できる小野のようなC層がいると思うのです。A、C層はいいと思うのですが、B層は問題ですよね。その対象が持ち上げられている間は感動するものの、一転叩かれるとすっかり幻滅してしまう人たち。B層は一体、何に感動していたのでしょう。B層にならないようにしたいなぁ、と思います。
また、私が読んだ「カノン」は、全体のトーンとして、A層を良しとする物語だったのですが、一般大衆から離れた所にある音楽というのも、少し淋しいように思います。音楽も物語りも、素養があるからこそ、噛み砕き、理解する事が出来ることもあるわけで、難しいなぁとは思うのですが。
長くなってしまって、すみません~。
>「マエストロ」という、美貌のヴァイオリニスト
篠田さんのそのあたりの小説は、殆ど読んでいます。考えてみると、音楽のテーマーを盛り込みつつ、おもしろくて内容の充実した小説はあまりないのです。やはり著者ご自身が、チェロを習っているという経験と知識は強みですね。(最近では、天満敦子さんをモデルにした高樹のぶ子さんの「百年の預言」がありました。)
A~C層の分析、わかりやすいですねぇ~。
>B層は一体、何に感動していたのでしょう
”感動したい”という願望に、”たまたまヒットした対象”に感動したのに過ぎないと思います。世にいう浮動票のようなものです。私は、A層に入るかと思いますが、C層のタイプもそれはそれでよいのではないかとも。本当に感動したのであれば。ただ貨幣論にあるような商業ベースにのれない内容の良いCDや演奏会が、売れるというだけのものにとって代わるのであったら、それも問題です。
>一般大衆から離れた所にある音楽
つなさんの感想ももっともだと思います。その点も、篠田さんは「讃歌」で小野の言葉を借りて、読者に伝えたいのではないかと感じます。クラシック音楽そのものは、決して一般大衆と離れた所にある音楽ではなく、もっと身近に生活の中にある音楽です。でも、誰が、何が、クラシック音楽を高みにおいてしまったのでしょうか。いろいろ刺激を受けるコメントをありがとうございました。
TBさせていただきました。またTBありがとうございました。
音楽に感動するって何なのか?って思います。
あまりにヘタなのには感動以前に聴き続けられませんが、クラシックでもポピュラーでもなんだかさほど上手とも思えないのに感動、というかすごく気に入ってしまう曲がありますよね。
つなさんのABC層はわかりやすいですねえ。私はCですねきっと。
篠田節子さんは大好きで出るたびに読んでます。読むきっかけは数年前ドラマ化された「ハルモニア」がきっかけです。
音楽に感動する時、作曲家の作品に感動しているのか、演奏者に感動しているのかわからなくなる時があります。クラシック音楽の場合、Gacktのように作曲家=演奏家ではないですから。
>でもなんだかさほど上手とも思えないのに感動
それはおそらく作品のもつ力なのだと思います。
>ハルモニア
もしかして堂本光一君主演でしたかしら。篠田さんの本はおもしろいので、映画やドラマになる作品が多いようですね。