コロナ禍と資本主義 格差危機③ 先例ない経済縮小 雇用直撃
世界を襲った医療危機は、同時に世界的経済危機を引き起こしました。
「2020年に起こった経済活動縮小の速度とその広がりの同時性は、人々の記憶に残っている範囲では先例がない」。国際通貨基金(IMF)が4月に発表した世界経済見通しは、コロナ禍が直撃した世界経済をこう表現しました。
IMFは、世界経済の20年の成長率は3・3%のマイナス成長だったと推定しています。なかでも深刻な打撃を受けているのは、若者、女性、比較的学歴が低い労働者、非公式経済の労働者たちです。極度の貧困に陥った人が20年には9500万人増加し、新たに8000万人が栄養不良になったとIMFは指摘します。
日本経済は、コロナ対策への迷走ぶりを示す菅義偉政権の下で大きく落ち込み、20年度の国内総生産(GDP)成長率は前年度比4・6%減でした。下落率は08年度(3・6%減)を超え、統計上さかのぼれる1956年度以降で最大でした。
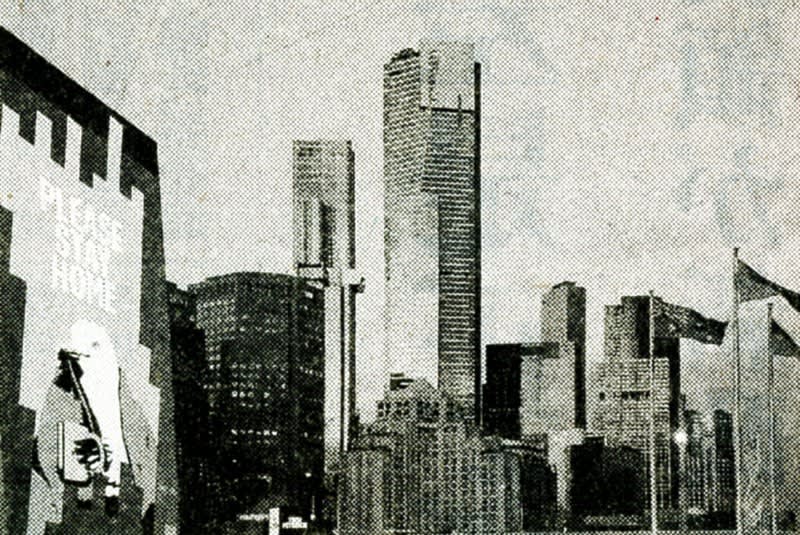
新型コロナウイルス感染抑制のため家にとどまることを求める市中心部の看板=5月28日、オーストラリア・メルボルン(ロイター)
所得8・3%減
コロナ禍が雇用に及ぼす影響は甚大です。国際労働機関(ILO)によると、20年、世界で1億1400万人という前代未聞の規模で雇用が失われました。20年の世界の労働所得(所得支援措置の算入前)は、8・3%減少。世界のGDPの4・4%に相当する3・7兆ドルに達すると推計しています。大規模な労働所得の喪失は労働者の家庭を貧困に追い込みます。
ILOの推計によると、コロナ以前の世界で、就業者の61%以上に当たる20億人あまりが非公式(インフォーマル)経済で生計を立てていました。日本でも18・7%が非公式経済で生計を得ているとしています。
非公式経済は、未登記で法人化されていない零細事業の事業主とそこで働く労働者のほか、安定した雇用契約がなく、各種福利厚生、社会保障の適用対象とならない就業者で構成されます。露天商、靴磨き、自転車修理工、自宅で作った服やお菓子を売る女性たち、日雇い建設労働者、自宅でデータ入力作業を行う人々やアルバイトのヘルパーだけでなく、先進国における非正規労働者など、活動内容・形態はさまざまです。
非公式経済の労働者と生産者は、さまざまなつながりで、グローバル経済と結びついています。ILOも「経済のグローバル化と情報通信技術(ICT)の普及に伴う生産および雇用関係のインフォーマル化と柔軟化は生産の分散、非典型労働の増大をもたらし、その規模は現在、ますます膨らみ続けています」(02年11月6日のトピック解説)といいます。衣料品や繊維、スポーツシューズなど輸出産業の労働力の多くは、非公式経済の下で働いているとも指摘されています。多国籍企業が最低の労働コストを求めて国から国へと移動する「底辺への競争」に伴って、労働者は、低賃金競争にかりたてられ、社会保障などの公的保護や、職場における安全性の欠如にさらされています。
賃下げ圧力
コロナ禍は、多国籍企業主導で拡大した非公式労働者に襲い掛かりました。
彼らは、医療保健サービスを利用することが難しい上、都市封鎖(ロックダウン)によって仕事ができなくなった場合や病気になった場合、ほかの手段で所得を得ることが困難です。ステイホームを強いられ家にとどまることは、露天商などにとっては失職を意味します。
ILOが20年12月に発表じた「世界賃金報告」によると、コロナ危機は多くの国で賃金に大きな下方圧力をかけ、20年上半期にデータがある国の3分の2で、賃金は前年より下落するか、伸びが鈍化しました。「この危機は近い将来、大規模な賃金押し下げ圧力をもたらす可能性が高い」とILOは警鐘を鳴らします。(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年6月3日付掲載
コロナ禍で雇用を失ったという「非公式経済」。
その事態は、露天商、靴磨き、自転車修理工、自宅で作った服やお菓子を売る女性たち、日雇い建設労働者、自宅でデータ入力作業を行う人々やアルバイトのヘルパーだけでなく、先進国における非正規労働者など、活動内容・形態はさまざま…。
経済を底辺で支えてきた人々の暮しを直撃したのです。
世界を襲った医療危機は、同時に世界的経済危機を引き起こしました。
「2020年に起こった経済活動縮小の速度とその広がりの同時性は、人々の記憶に残っている範囲では先例がない」。国際通貨基金(IMF)が4月に発表した世界経済見通しは、コロナ禍が直撃した世界経済をこう表現しました。
IMFは、世界経済の20年の成長率は3・3%のマイナス成長だったと推定しています。なかでも深刻な打撃を受けているのは、若者、女性、比較的学歴が低い労働者、非公式経済の労働者たちです。極度の貧困に陥った人が20年には9500万人増加し、新たに8000万人が栄養不良になったとIMFは指摘します。
日本経済は、コロナ対策への迷走ぶりを示す菅義偉政権の下で大きく落ち込み、20年度の国内総生産(GDP)成長率は前年度比4・6%減でした。下落率は08年度(3・6%減)を超え、統計上さかのぼれる1956年度以降で最大でした。
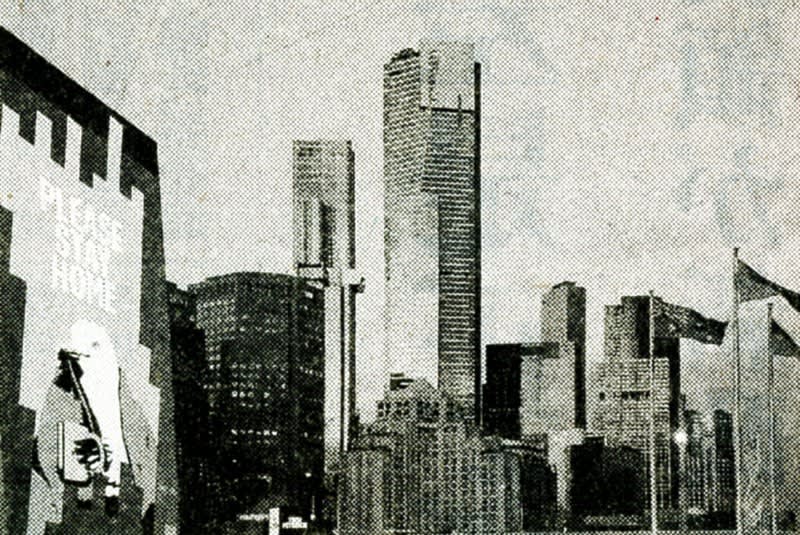
新型コロナウイルス感染抑制のため家にとどまることを求める市中心部の看板=5月28日、オーストラリア・メルボルン(ロイター)
所得8・3%減
コロナ禍が雇用に及ぼす影響は甚大です。国際労働機関(ILO)によると、20年、世界で1億1400万人という前代未聞の規模で雇用が失われました。20年の世界の労働所得(所得支援措置の算入前)は、8・3%減少。世界のGDPの4・4%に相当する3・7兆ドルに達すると推計しています。大規模な労働所得の喪失は労働者の家庭を貧困に追い込みます。
ILOの推計によると、コロナ以前の世界で、就業者の61%以上に当たる20億人あまりが非公式(インフォーマル)経済で生計を立てていました。日本でも18・7%が非公式経済で生計を得ているとしています。
非公式経済は、未登記で法人化されていない零細事業の事業主とそこで働く労働者のほか、安定した雇用契約がなく、各種福利厚生、社会保障の適用対象とならない就業者で構成されます。露天商、靴磨き、自転車修理工、自宅で作った服やお菓子を売る女性たち、日雇い建設労働者、自宅でデータ入力作業を行う人々やアルバイトのヘルパーだけでなく、先進国における非正規労働者など、活動内容・形態はさまざまです。
非公式経済の労働者と生産者は、さまざまなつながりで、グローバル経済と結びついています。ILOも「経済のグローバル化と情報通信技術(ICT)の普及に伴う生産および雇用関係のインフォーマル化と柔軟化は生産の分散、非典型労働の増大をもたらし、その規模は現在、ますます膨らみ続けています」(02年11月6日のトピック解説)といいます。衣料品や繊維、スポーツシューズなど輸出産業の労働力の多くは、非公式経済の下で働いているとも指摘されています。多国籍企業が最低の労働コストを求めて国から国へと移動する「底辺への競争」に伴って、労働者は、低賃金競争にかりたてられ、社会保障などの公的保護や、職場における安全性の欠如にさらされています。
賃下げ圧力
コロナ禍は、多国籍企業主導で拡大した非公式労働者に襲い掛かりました。
彼らは、医療保健サービスを利用することが難しい上、都市封鎖(ロックダウン)によって仕事ができなくなった場合や病気になった場合、ほかの手段で所得を得ることが困難です。ステイホームを強いられ家にとどまることは、露天商などにとっては失職を意味します。
ILOが20年12月に発表じた「世界賃金報告」によると、コロナ危機は多くの国で賃金に大きな下方圧力をかけ、20年上半期にデータがある国の3分の2で、賃金は前年より下落するか、伸びが鈍化しました。「この危機は近い将来、大規模な賃金押し下げ圧力をもたらす可能性が高い」とILOは警鐘を鳴らします。(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年6月3日付掲載
コロナ禍で雇用を失ったという「非公式経済」。
その事態は、露天商、靴磨き、自転車修理工、自宅で作った服やお菓子を売る女性たち、日雇い建設労働者、自宅でデータ入力作業を行う人々やアルバイトのヘルパーだけでなく、先進国における非正規労働者など、活動内容・形態はさまざま…。
経済を底辺で支えてきた人々の暮しを直撃したのです。
























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます