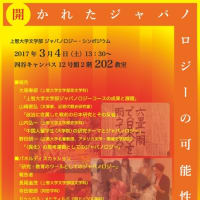昨日の「パブリック・ヒストリー」公開研究会、無事終了。思ったより多くの方々にお越しいただき、懇親会も含めていろいろな話が聴け、得がたい経験をした。菅豊さんの力こもりすぎのイントロダクション、岡本充弘さんの現状を浩瀚に俯瞰する周到な講演があり、自分はあまりコメントすることがないなあと思っていたが、岡本さんのお話の多少分かりにくい部分を明確にするよう、ディフォルメを心がけて質問し、また今後のパブリック・ヒストリー研究の論点になりそうなことも、2〜3指摘したつもり。 ちなみに、ホワイトのいうヒストリカル・パスト(historical past、「歴史的な過去」と訳されている)をプラクティカル・パスト(practical past、「実用的な過去」と訳されている。ぼくは「実践的過去」という訳語を使用)に対置されるものではなく、近代科学主義民族(modern scientism tribe)の歴史実践に過ぎないと規定した議論、特権的なものでもなんでもないのだと主張した点は、それなりに玄人ウケした。
昨日の「パブリック・ヒストリー」公開研究会、無事終了。思ったより多くの方々にお越しいただき、懇親会も含めていろいろな話が聴け、得がたい経験をした。菅豊さんの力こもりすぎのイントロダクション、岡本充弘さんの現状を浩瀚に俯瞰する周到な講演があり、自分はあまりコメントすることがないなあと思っていたが、岡本さんのお話の多少分かりにくい部分を明確にするよう、ディフォルメを心がけて質問し、また今後のパブリック・ヒストリー研究の論点になりそうなことも、2〜3指摘したつもり。 ちなみに、ホワイトのいうヒストリカル・パスト(historical past、「歴史的な過去」と訳されている)をプラクティカル・パスト(practical past、「実用的な過去」と訳されている。ぼくは「実践的過去」という訳語を使用)に対置されるものではなく、近代科学主義民族(modern scientism tribe)の歴史実践に過ぎないと規定した議論、特権的なものでもなんでもないのだと主張した点は、それなりに玄人ウケした。しかし、このところの言語論的転回をめぐる動向で、極めて気になっている点については、あまりこの会の趣旨にそぐわないだろうとは思いつつ、質問せざるをえなかった。すなわち、00年代後期に停滞を迎えた言語論的転回をめぐる議論が昨今また復活してきたこと、それはそれで歓迎すべきなのだが、その方向性やインパクトが、90年代当初と比較して希釈されてしまっている点である。具体的には、「言語の世界構成機能」に関する論点の捨象。ぼくからすれば、バルトの「作者の死」も、デリダの「テクスト外というものはない」というテーゼも、この論点をもとにしてこそ理解できるものだ。歴史学がこれを踏まえてテクストを論じようとすると、さまざまな仮定や想定を幾重にも積み重ねねばならないことになり、極めて面倒くさい。方法論懇話会で議論していた折、これらの難問に立ち向かうために、クリサート・ユクスキュルの議論から始めて、認知物語論に至るまで勉強し、人間が自らの環境を構成するその方法について、自分なりに理論構築していった。いまのぼくの環境文化史は、そのあたりのことが基底になっている。環境史に大きく踏み出せたのも、言語論的転回の「質問状」に、具体的に応えようとしたからだ(このとき書いた論文は、『史学雑誌』回顧と展望で、「北條は言語論的転回を思想史の範疇に押し込めようとしている」と、まったく逆ベクトルの読み方をされて〈というか読んでいなかったのだろう〉一蹴されたけれども)。しかし一般的には、これは「歴史学の議論ではない」。それゆえに歴史学では、言語論的転回を自学の俎上に載せるために、希釈に希釈を重ねてほとんど別の問題に作り変えてしまった。そこでの中心的論点である「言語が対象を正確に把握できるか」なんて、アリストテレス的言語観で、ソシュール以降の考え方にはそぐわないだろう。ヒストリカル・パストの特権性を剥奪し、下位の歴史構成や歴史の担い手をとりあげるなどといった傾向も、むしろ社会史の議論であって(すでに、セニョボス/シミアン論争にみられる)、言語論的転回とは本質的な関係がない。7月の長谷川さんの書評会の際にも、その違和感は拭えなかった。 これについて、岡本さんからは納得のゆく答えを引き出すことはできなかった。会場には鹿島徹さんもいらっしゃっていたので、コメントをいただきたかったが、「疲れたから今日は帰るね」と懇親会にはおみえにならず。懇親会の場でいちばん詳しそうな内田力さんとは、概ね理解が一致したと思うが、「希釈したから扱えるようになったので、そこはポジティヴに評価してもいいのでは」と。まあ、それもそうかもしれないが…結局、言語論的転回は歴史学を開こうとした、ある意味ではその可能性を拡大しようとしたのだが、大部分の歴史学者はその実践の困難に耐えきれず、逆に閉塞し、「強烈な毒ゆえに薬にもなりえた液体を、甘い水になるくらいまで懸命に薄めてきただけではないのか」。まあ、ぼくの議論も到底完成されているとはいえず、水を注いでいるばかりかもしれないのだが。そんなことも考えた1日だった。
なお懇親会では、民俗学その他の関係の方々から、理論や方法論に関するさまざまな著作を頂戴し、新たな課題をみつけだすことができた。感謝、感謝である。また思いもかけず、尊敬する川本喜八郎氏と一緒にスタジオで作品を作っていたという!方にお会いし、かなり長い時間お話を伺うことができた。あの優しげな川本さんが、全身に刺青をされていたとか…! ほとんど聞き取り調査だが、またあらためてきちんとお話を伺いたい。歴史学と映像との関係を考えるうえでも、貴重な体験となりそうだ。
※ 質疑応答での発言のうち、斎藤英喜さんの「保苅実はカスタネダになったのか否か」という議論、上智の学生Y君の「歴史戦における公正さをめぐる議論は、結局事実性を基準とせざるをえないのか」という質問、武井基晃さんの「自分とインフォーマントを同レベルの歴史実践主体と把握した場合、相手の〈誤り〉を指摘し、こちらの〈答え〉を示すのは、保苅的には適切なのか否か?」という議論は、歴史学者としてはかなり本質的な問いと感じられた。cross-culturalizing historyが、実際はどれだけ困難かも指し示しており、その問題意識の幾らかは、ぼくも共有している。今後も、できれば一緒に考えてゆきたい。また、保苅実が本当に目指したこの理想が、日本の関連分野でほとんど言及されないのは、やはりポストモダン民族誌の議論が充分咀嚼されず、定着しなかったからなのかもしれない。すなわち未だ日本では文化相対主義が主流で、それは客観主義的対象把握の裏返しなのだという議論が、歴史や文化を考える際の前提とはなっていないのだろう。