 6日(月)は、会議と学生との面談のため出勤。帰りに立川まで足を伸ばして、『かぐや姫の物語』を観てきた。比べても仕方ないが、『風立ちぬ』より数段よい(しかし、『風立ちぬ』より売れないだろうな)。
6日(月)は、会議と学生との面談のため出勤。帰りに立川まで足を伸ばして、『かぐや姫の物語』を観てきた。比べても仕方ないが、『風立ちぬ』より数段よい(しかし、『風立ちぬ』より売れないだろうな)。アニメーションとしては、高畑勲の敬愛するフレデリック・バックの作風を、日本のデジタルアニメの製作工程でどう再現するか、というのが大変だったのだろう。実験アニメを見慣れている眼には新鮮さはないけれども、アニメートは近年まれにみる出来で非常にしっかりしていた。姫の赤ん坊時代の描写など、画の動きだけで心を動かされたのは久しぶりである。アニメーションとアニミズムの関係性については以前に論じたことがあり、ジブリアニメでは『崖の上のポニョ』の表現に顕著に表れていたが、アニメートする主体とアニマを与えられた画との関係性を考えると、手描きの工程が直接的であればあるほどシャーマニックな営みとなる。それは自分の身体を自覚する作業でもあり、身体のコントロールにも繋がってくる(マンガ家がキャラクターの表情を描くとき、鏡をみるわけでもないのに画と同じ顔を作っていることは、実体験としてよく分かる)。『白蛇伝』『安寿と厨子王』時代の東映動画の風格もあった。絵巻からの引用も随所にみられ、日本史研究者としての楽しみもあったな。
物語の内容としては、まず、時代を超えて受け継がれてゆく古典の力を感じた。原作の『竹取物語』は、もちろん生のさまざまな営みに視線を向けながらも、やはり現実世界の無常と神仏・神仙の世界の永遠性を対比的にみつめ、後者の価値観を中心に持つものだった。しかしこの映画は、環境世代の目線に立って、現実世界のなかに自然/文化の対立軸を組み込み、草木魚虫と人間との営みをより具体的に描き出したうえで、原作の価値観を転倒させる。地上世界に生きるいのちははかなく、互いに殺し合い傷つけ合い、苦しみと悲しみ、虚仮と無常に満ちている。しかしそれゆえに愛おしい。波立つ苦悩はなく平穏で、けれどもそれゆえにほとばしる激情も、沸き立つ喜びもない天上世界を拒否する主人公は、ナウシカに代表されるジブリ・ヒロインの正統な系譜に位置している(でも、星野鉄郎みたいなところもあるか)。『死者の書』の南家郎女とは対照的…と書くと、語弊があるだろうか。まあ、姫の造型を地上化しすぎて、単純化してしまった面は否めない。神仙=他者としての隔絶性、豊かさの方は薄れてしまった。
もっとも価値観の転倒の問題は、思想史的にみれば「本覚思想化」なのだということもできる。映画のラスト、月世界からの聖衆来迎(これは、平安~中世の隠された心性を捉えていて見事)に象徴される神仙・神仏世界の「平和」は、愛憎を超越したその静謐さゆえに否定的に位置づけられるが、そもそもなぜ仏教が現実を苦と捉えそれからの解脱を唱えたのかを考えると、日本列島の環境文化のなかだからこそ可能な「転倒」だといわざるをえない。劇中、姫が再会した木地師の青年に対し、あなたと一緒なら「生きていける!」と繰り返し語る場面があるが、そのとおり、日本の環境でなら生きてゆけてしまうのである。数多繰り返された激甚災害の犠牲となったいのちのことを思うと、簡単には断言できないのだが、それでも日本の環境は生命の生育において極めて恵み豊かなのだ(もちろん、そこに政治的・社会的要素が加わると、とたんに〈生存〉を危ぶまれる情況になってしまうのだが)。現実世界のいのちの営み、その豊かさを具体的に描き出すことに力点を置いたこの映画は、その本当の対立軸である神仙世界・神仏世界の価値観については充分に表現できておらず、それを憧憬せざるをえない人々の心のあり方には目を向けていない(倶会一処を描いた二階堂和美の主題歌「いのちの記憶」が、それを補っているということだろうか)。その意味で『かぐや姫の物語』は、列島の環境文化、列島的価値観に絡め取られた物語なのだといえるだろう。
 暮れに深夜のテレビで『パンズ・ラビリンス』を放映していたのだが、DVDを持っているにもかかわらずじっくり観てしまった。そういえばあの映画も『かぐや姫の物語』と同じ構造を持っているが、スペイン内戦の悲惨な現実のなかで、『かぐや姫』とは逆に楽園を希求する物語になっていた。楽園/現実の間で揺れ動く人間の姿は、シャーマニズム研究の主題のひとつでもある。とにかく、『ハンナ・アーレント』に続いていい映画を観た(しかしまあ、自然と共生しすぎの平安時代であったことよ。もっと開発してるよなー、実際)。
暮れに深夜のテレビで『パンズ・ラビリンス』を放映していたのだが、DVDを持っているにもかかわらずじっくり観てしまった。そういえばあの映画も『かぐや姫の物語』と同じ構造を持っているが、スペイン内戦の悲惨な現実のなかで、『かぐや姫』とは逆に楽園を希求する物語になっていた。楽園/現実の間で揺れ動く人間の姿は、シャーマニズム研究の主題のひとつでもある。とにかく、『ハンナ・アーレント』に続いていい映画を観た(しかしまあ、自然と共生しすぎの平安時代であったことよ。もっと開発してるよなー、実際)。※ 追加。音楽もよかったので、サウンド・トラックほしいな。二階堂和美はもちろんいいのだけど、いちばん印象に残ったのは「天人の音楽」。ゴンチチか!と突っ込んだ。












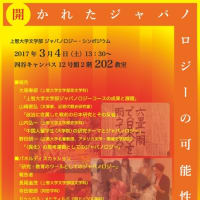












歌詞も、メロディーも、歌声も反則だよ~と思って見てました。
ほうじょうさんのブログを読んでようやく頭を冷やした、というところ。
原作は不死の薬を燃やすところとか、徹底して地上性を重視し異世界を基本的には物語世界に登場させることのないはじめての物語文学とされていますが、たしかに、そういう意味で原作をよく読み込んでいるなと思いました。
でもさすがに、和歌は出てこないよなあ、と思っていたのです、和歌をよむことによって、かぐや姫が地上性に結びついていって亡くなった求婚者や帝に心を動かされるようになってゆくという。。。
ところが、考えてみたら、月の世界で聞いた歌に、かぐや姫はすでに心を動かされてしまっていて、歌が無意識の記憶の鍵になっていて、さらに、月の世界にもどっても、また歌だけは記憶の貯蔵庫になってゆくのだろうと予想されて、和歌はなくとも、和歌以上に歌なるものの働きを上手に生かしているのだなあとあらためて思いました。
今年もお会いしてお話したいですね。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
ちょっと時間が経っていま考えているのは、ジブリにおける「振り向く主人公の系譜」というものです。ラストでの振り返り。それは、物語の終末への流れに抗い、逆行するもの。余韻を残す常套的手段ではありますが、使い方によって豊かな意味内容を持ちます。千尋も振り返りますし、かぐや姫も振り返る。神話的には、振り返ることは、〈見るなの禁〉に属してしまうことが多いんですけどね。
何はともあれ、本年もよろしくお願いいたします。