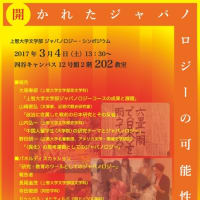以前に「四谷会談」で加藤幸子さんの新作小説を扱った際、かつては動物文学がもっと盛んで、書店にも「動物文学」の棚があった、という話をした。戸川幸夫や椋鳩十は当たり前で、海外文学はもちろん、幾つかの書名をいまも覚えている。そのときふと気になったのが、高橋健による児童文学『キタキツネのチロン』と、蔵原惟繕監督のサンリオ映画『キタキツネ物語』の関係だった。後者については今さらいうまでもないが、日本文化において培われてきた「ずる賢い」「陰惨な」キツネのイメージを、「健気な」「凜とした」印象へ塗り替えてしまった画期的な作品である。オホーツク海を埋め尽くした流氷の彼方から、北海道は釧路の雪原に降り立ったキタキツネのフレップ。彼は、その地の厳しい自然や人間との格闘のなかで、恋人と出会い、家族を作り、そして大切なものを失い/残し、再び流氷の彼方へ去ってゆく。筋立てとしては、蔵原が日活時代に撮っていた無国籍映画そのものなのだが、随処に使用されたドキュメンタリー・フィルムが、単なるフィクションに終わらない説得力を持っていた。映画が公開された1978年夏(なんと『スター・ウォーズ』とぶつかっていたのだ)、ぼくはまだ小学生だったが、サンリオ出版から出ていたフィルム・ブックと上記『チロン』を購入し、むさぼり読んだ覚えがある。『チロン』は、登場するキツネたちの名前こそ違うが、ストーリーはほぼ共通している。そこで気になったのが、同書は映画のノベライズなのか、それとも原案なのか、あるいはまったく関係なく作られたものなのか、ということである。これは、映画『キタキツネ物語』製作の経緯にも関わる。

 そこで、幾つか資料を集めてみた。まず『チロン』のあとがきを確認してみると、同書は単なるノベライズではなく、映画の原案を話し合うなかでまとめたものを、あらためて児童文学にリライトしたものだと分かった。しかし、あくまで児童文学なので、詳しい経緯は書かれていない。そこで、公開当時の『キネマ旬報』1978年7月下旬号をみると、当時のスタッフによる座談会とシナリオが採録されており、概ね製作の経緯と過程が明らかになった。まず、ドキュメンタリー部分の核になったのは、キタキツネの研究者として知られる竹田津実の記録で、これを自身が編集する動物雑誌『アニマ』に紹介した高橋健が、動物映画を撮ろうと動き始めていたサンリオへ話を持ち込んだらしい。サンリオ映画としての製作が決まってからは、高橋がキタキツネの1年を軸に原案を書き、4年かけて素材の撮影を行った。そうして蓄積された45万フィートに及ぶフィルムを、最終的に1本の劇場映画としてまとめてゆく際、蔵原が参加して脚本を書き、キツネの心情をヴォーカルとして表現すること、説明的な台詞を排し物語り的に構築することも決められていったという。恐らくこの段階で、脚本の流れから足りない素材を、飼育されたキタキツネを利用して撮影していったのだろう。なお、キツネの夫婦に目のみえない子供が誕生したことや、素材撮影の途中で多くのキツネが死んでいったことは、生態的な意味での事実であったようだ。ただし、追加撮影のいわゆる「作り」の段階で、飼育キツネにどのような演出が施されたのかは分からない。
そこで、幾つか資料を集めてみた。まず『チロン』のあとがきを確認してみると、同書は単なるノベライズではなく、映画の原案を話し合うなかでまとめたものを、あらためて児童文学にリライトしたものだと分かった。しかし、あくまで児童文学なので、詳しい経緯は書かれていない。そこで、公開当時の『キネマ旬報』1978年7月下旬号をみると、当時のスタッフによる座談会とシナリオが採録されており、概ね製作の経緯と過程が明らかになった。まず、ドキュメンタリー部分の核になったのは、キタキツネの研究者として知られる竹田津実の記録で、これを自身が編集する動物雑誌『アニマ』に紹介した高橋健が、動物映画を撮ろうと動き始めていたサンリオへ話を持ち込んだらしい。サンリオ映画としての製作が決まってからは、高橋がキタキツネの1年を軸に原案を書き、4年かけて素材の撮影を行った。そうして蓄積された45万フィートに及ぶフィルムを、最終的に1本の劇場映画としてまとめてゆく際、蔵原が参加して脚本を書き、キツネの心情をヴォーカルとして表現すること、説明的な台詞を排し物語り的に構築することも決められていったという。恐らくこの段階で、脚本の流れから足りない素材を、飼育されたキタキツネを利用して撮影していったのだろう。なお、キツネの夫婦に目のみえない子供が誕生したことや、素材撮影の途中で多くのキツネが死んでいったことは、生態的な意味での事実であったようだ。ただし、追加撮影のいわゆる「作り」の段階で、飼育キツネにどのような演出が施されたのかは分からない。
座談会を読んでいて興味深かったのは、製作陣が一致して、キタキツネの「子別れの儀式」を映画の最大の魅力としていることだった。蔵原は以下のように述べている。「生物学的には、あの儀式は本能の行為です。大昔とは型式は違ってきていますが、人間にも本能としての親と子の別れは、あるわけです。今は甘えの構造とか、断絶があるので、もっとプリミティブに見直してみようじゃないかと思ったし、ある種、信仰に近い形で、プリミティブなものは美しくて根源的だ、という思いが演出していく上での私のベースになっていた。そういった点で、"子別れの儀式"は僕自身、観て驚き、感動したし、この映画の現実といいましょうか、ドキュメンタリーの白眉ではないかという気がします」。土居健郎の『甘えの構造』。「過保護」という言葉が一般化したのも、この頃であったかもしれない。そして、「プリミティブ」という言葉。「何回も繰り返しますが、もっとプリミティブなものを見つめていくことが必要な時代でもあるんですね。そういうことを、われわれは日常の生活の中で、一切ぬぐいさっている。僕はドキュメンタリー撮影のため、ピグミー族とジャングルで二ヵ月程生活した時、そのことを痛感しましたね。ちょっとキザな話ですが、ホイットマンが死期が近付いた時、"単純なものはすごいんだぞ"ということをつぶやいたと、若い頃何かで読みましたが、ピグミーやインディアンと一緒に生活してみて、ああ、そうかなと、だんだん思うような年齢になってきた。そんな時に、この映画に出会えたのは、すごく幸せだった」(ともに64頁)。1978年といえば、レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』が川田順造によって翻訳された、その翌年に当たる。国立民族学博物館が開館したのも、1977年11月だった。近現代の芸術は、常に「プリミティヴ」なものに触発されていたが、この時代にもそうした思潮があり、『キタキツネ物語』成立の原動力になったと思うと、面白い。
それにしてもこの映画、『スター・ウォーズ』の向こうを張って興行収入59億円をあげ、『もののけ姫』に抜かれるまで20年日本映画のトップに輝いていた割に、公刊されている資料が少ない。日本動物映画史、あるいは動物文学史を考えるうえでも、またエコクリティシズムや環境人文学の対象としても、もっと言及されていい気がする。素材部分の撮影の苦労、演出部分の実態と困難、物語の確立までの具体的な議論など、現在も活躍されている関係者への聞き取りや諸資料の発掘を通じ、もっと公けに共有されるべきではなかろうか。

 そこで、幾つか資料を集めてみた。まず『チロン』のあとがきを確認してみると、同書は単なるノベライズではなく、映画の原案を話し合うなかでまとめたものを、あらためて児童文学にリライトしたものだと分かった。しかし、あくまで児童文学なので、詳しい経緯は書かれていない。そこで、公開当時の『キネマ旬報』1978年7月下旬号をみると、当時のスタッフによる座談会とシナリオが採録されており、概ね製作の経緯と過程が明らかになった。まず、ドキュメンタリー部分の核になったのは、キタキツネの研究者として知られる竹田津実の記録で、これを自身が編集する動物雑誌『アニマ』に紹介した高橋健が、動物映画を撮ろうと動き始めていたサンリオへ話を持ち込んだらしい。サンリオ映画としての製作が決まってからは、高橋がキタキツネの1年を軸に原案を書き、4年かけて素材の撮影を行った。そうして蓄積された45万フィートに及ぶフィルムを、最終的に1本の劇場映画としてまとめてゆく際、蔵原が参加して脚本を書き、キツネの心情をヴォーカルとして表現すること、説明的な台詞を排し物語り的に構築することも決められていったという。恐らくこの段階で、脚本の流れから足りない素材を、飼育されたキタキツネを利用して撮影していったのだろう。なお、キツネの夫婦に目のみえない子供が誕生したことや、素材撮影の途中で多くのキツネが死んでいったことは、生態的な意味での事実であったようだ。ただし、追加撮影のいわゆる「作り」の段階で、飼育キツネにどのような演出が施されたのかは分からない。
そこで、幾つか資料を集めてみた。まず『チロン』のあとがきを確認してみると、同書は単なるノベライズではなく、映画の原案を話し合うなかでまとめたものを、あらためて児童文学にリライトしたものだと分かった。しかし、あくまで児童文学なので、詳しい経緯は書かれていない。そこで、公開当時の『キネマ旬報』1978年7月下旬号をみると、当時のスタッフによる座談会とシナリオが採録されており、概ね製作の経緯と過程が明らかになった。まず、ドキュメンタリー部分の核になったのは、キタキツネの研究者として知られる竹田津実の記録で、これを自身が編集する動物雑誌『アニマ』に紹介した高橋健が、動物映画を撮ろうと動き始めていたサンリオへ話を持ち込んだらしい。サンリオ映画としての製作が決まってからは、高橋がキタキツネの1年を軸に原案を書き、4年かけて素材の撮影を行った。そうして蓄積された45万フィートに及ぶフィルムを、最終的に1本の劇場映画としてまとめてゆく際、蔵原が参加して脚本を書き、キツネの心情をヴォーカルとして表現すること、説明的な台詞を排し物語り的に構築することも決められていったという。恐らくこの段階で、脚本の流れから足りない素材を、飼育されたキタキツネを利用して撮影していったのだろう。なお、キツネの夫婦に目のみえない子供が誕生したことや、素材撮影の途中で多くのキツネが死んでいったことは、生態的な意味での事実であったようだ。ただし、追加撮影のいわゆる「作り」の段階で、飼育キツネにどのような演出が施されたのかは分からない。座談会を読んでいて興味深かったのは、製作陣が一致して、キタキツネの「子別れの儀式」を映画の最大の魅力としていることだった。蔵原は以下のように述べている。「生物学的には、あの儀式は本能の行為です。大昔とは型式は違ってきていますが、人間にも本能としての親と子の別れは、あるわけです。今は甘えの構造とか、断絶があるので、もっとプリミティブに見直してみようじゃないかと思ったし、ある種、信仰に近い形で、プリミティブなものは美しくて根源的だ、という思いが演出していく上での私のベースになっていた。そういった点で、"子別れの儀式"は僕自身、観て驚き、感動したし、この映画の現実といいましょうか、ドキュメンタリーの白眉ではないかという気がします」。土居健郎の『甘えの構造』。「過保護」という言葉が一般化したのも、この頃であったかもしれない。そして、「プリミティブ」という言葉。「何回も繰り返しますが、もっとプリミティブなものを見つめていくことが必要な時代でもあるんですね。そういうことを、われわれは日常の生活の中で、一切ぬぐいさっている。僕はドキュメンタリー撮影のため、ピグミー族とジャングルで二ヵ月程生活した時、そのことを痛感しましたね。ちょっとキザな話ですが、ホイットマンが死期が近付いた時、"単純なものはすごいんだぞ"ということをつぶやいたと、若い頃何かで読みましたが、ピグミーやインディアンと一緒に生活してみて、ああ、そうかなと、だんだん思うような年齢になってきた。そんな時に、この映画に出会えたのは、すごく幸せだった」(ともに64頁)。1978年といえば、レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』が川田順造によって翻訳された、その翌年に当たる。国立民族学博物館が開館したのも、1977年11月だった。近現代の芸術は、常に「プリミティヴ」なものに触発されていたが、この時代にもそうした思潮があり、『キタキツネ物語』成立の原動力になったと思うと、面白い。
それにしてもこの映画、『スター・ウォーズ』の向こうを張って興行収入59億円をあげ、『もののけ姫』に抜かれるまで20年日本映画のトップに輝いていた割に、公刊されている資料が少ない。日本動物映画史、あるいは動物文学史を考えるうえでも、またエコクリティシズムや環境人文学の対象としても、もっと言及されていい気がする。素材部分の撮影の苦労、演出部分の実態と困難、物語の確立までの具体的な議論など、現在も活躍されている関係者への聞き取りや諸資料の発掘を通じ、もっと公けに共有されるべきではなかろうか。