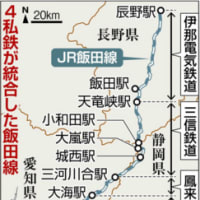本郷由美子 会員限定記事
北海道新聞2024年5月20日 10:00(5月21日 0:49更新)
海外の企業などで一定期間経験を積む海外インターンシップ事業などを手がける「タイガーモブ」(東京)は、「次世代リーダーの創出」を会社のミッション(使命)に掲げ、新型コロナ禍を機にオンラインや海外での教育研修事業も展開しています。2023年度の年商は3億円と、コロナ前の2019年度の約3倍に拡大。社長の菊地恵理子さん(35)はコロナが流行した2020年から釧路管内弟子屈町に自宅を構え、東京との2拠点生活で1歳から4歳までの子ども3人を育てています。公私ともにコロナが転機となった菊地さんに、同社の事業や弟子屈での生活などについて聞きました。(東京報道 本郷由美子)
きくち・えりこ 1988年、三重県生まれ。関西学院大在学中に中国に留学し、上海のホテルでインターンシップを体験。大学卒業後に就職した新卒採用支援会社で海外インターンシップ事業を立ち上げ、2016年に独立、タイガーモブを設立した。2017年、女性起業家大賞・スタートアップ部門特別賞を受賞。弟子屈町と東京の2拠点で生活する。
■途上国など「本物の現場」が舞台
「大事にしているのは、ままごとではない本物の現場を見て、体験してもらうこと。南アフリカのサバンナで野宿をするとか、バングラデシュのアパレル工場で商品を作るとか。アウェーの環境に身を置くことで参加者は心を動かされ、自分と向き合うようになります」。菊地さんは、同社のインターンシッププログラムの特色をこう語ります。
菊地さんは大学在学中に留学した中国でホテルのインターンを経験し、学生や社会人に海外でのインターンシップを紹介するタイガーモブを2016年に設立しました。コロナ禍以前は45カ国で350件以上の受け入れ先を紹介し、累計で計3千人以上を派遣しました。業績は右肩上がりで、自身も17年に全国商工会議所女性会連合会が主催する女性起業家大賞の「スタートアップ部門特別賞」を受賞しました。
■コロナ禍でインターン中止。オンラインでの教育事業に活路
しかし、2020年にはコロナ禍によって外国との往来が難しくなり、ほぼすべてのインターンシップが中止や延期に追い込まれてしまいました。
売り上げがゼロになる瀬戸際でしたが、社内で議論を重ね「コロナが終わるのを待つのではなく、新しいサービスを提供しよう」と前を向いたといいます。海外で活躍する人たちの話をオンラインで聞くイベントを企画し、毎日のように開催しました。
そんな中、2022年度から高校で導入される探究学習に向けて授業内容を模索していたクラーク記念国際高(本校・深川市)から「探究学習向けのプログラムをやってもらえないか」との打診があり、同校で世界各国の起業家を講師としたオンライン授業を2020年に24コマ実施しました。生徒や教員の反応が良く、「これはニーズがある」と実感。教育事業に参入するきっかけとなりました。
2022年10月に教育機関向けの海外研修事業を始め、東京都内の高校でアジアでの1週間の研修と事前、事後学習を行う探究プログラムを実施しました。「既存の修学旅行は『楽しかったね』で終わる消費型が多い。今後につながる内容にできればと思いました」。高校を中心に依頼が増えていき、現在は学生・生徒向けが主力事業となりました。需要に応えるため、2023年度当初に18人だったスタッフは、24年5月時点で35人と2倍に増えました。
学生・生徒向けに提供するプログラムには修学旅行など学校独自の研修を企画する「カスタマイズ型」のほか、同社が企画したプログラムにさまざまな学校の生徒らが個人で参加できる「一般公募型」もあります。渡航先はアジアやアフリカ、北欧などで、学ぶ内容は環境や貧困、ビジネスなどが用意されています。期間は5日間程度の短期から1カ月程度の長期まで。2023~24年にフィンランドやドバイで実施したプログラムには、オホーツク管内大空町立大空高の生徒計3人も参加しました。大学生向けのインターンシップを含め、2023年度は計233プログラムで計2190人を世界各地に送り出しています。
菊地さん自身がスタッフとして教育事業の研修に同行することもあります。学校では自分を押し殺していたような中高生が、海外の現場で表情が明るくなっていくのを何度も見て来たそうです。「生徒たちの生き方が変わっていく場に携われるのは、何度経験してもうれしい」と仕事の醍醐味(だいごみ)を語ります。
コロナ禍以前の主力事業だった海外インターンシップは費用や語学力など参加へのハードルが高く、大学生や一部の社会人向けで市場規模が限られますが、教育事業であれば学校単位のほか、中学生以上の幅広い年代の個人にも参加してもらえます。菊地さんは「コロナ禍が事業転換・拡大のきっかけになった」と振り返ります。
■「日本とは思えない」弟子屈でのびのび
コロナ禍は菊地さんの生活にも大きな変化をもたらしました。会社の勤務形態をフルリモートワークに変更。2019年に菊地さんの夫が趣味の釣りと狩猟のために設けた弟子屈の拠点が、コロナ禍の20年以降は自宅となりました。当時、マスクが必須の状況で閉塞(へいそく)感が漂っていた東京に比べ、のびのびと暮らせたといいます。「自然が豊かで移住者にも優しく、日本とは思えないような場所。自分が知らなかったアイヌ民族文化も身近に学べる。子供も現地の保育園に通うことになり、コロナ禍の3年間はほとんど弟子屈にいました」。現在は事業拡大のため東京で生活することが多くなりましたが、両方を行き来する生活を続けています。

屈斜路湖畔で、色づいた木々に囲まれて歩く菊地さんと長男=2021年11月(本人提供)
■道内でインバウンド向け事業を
・・・・・・・