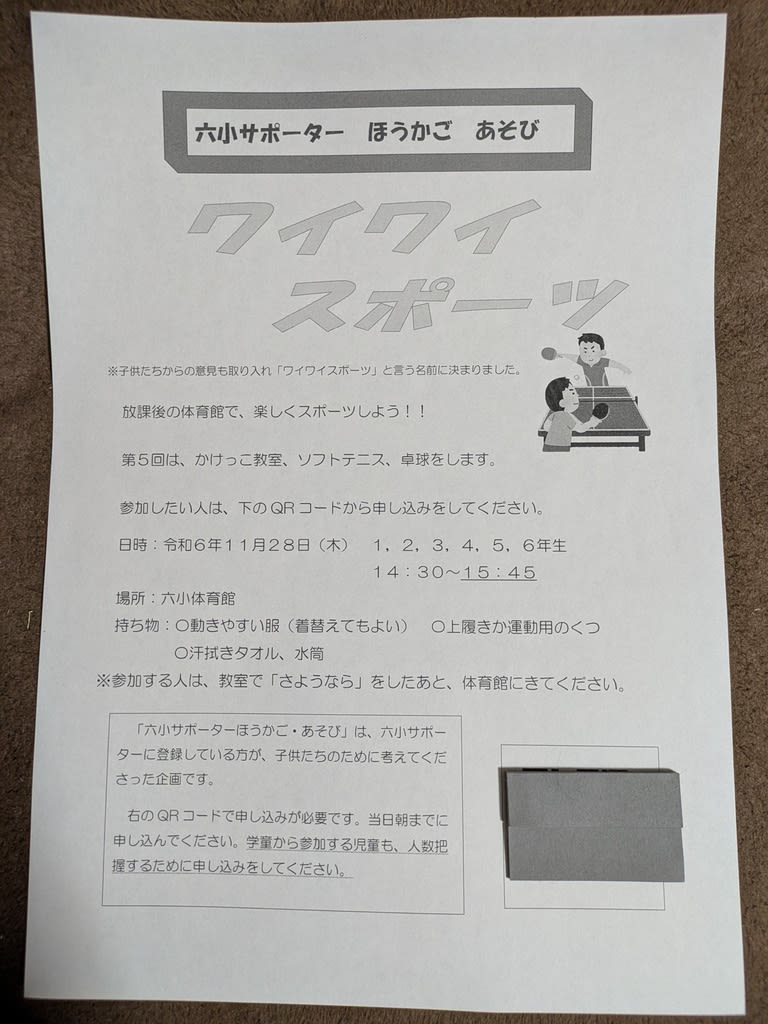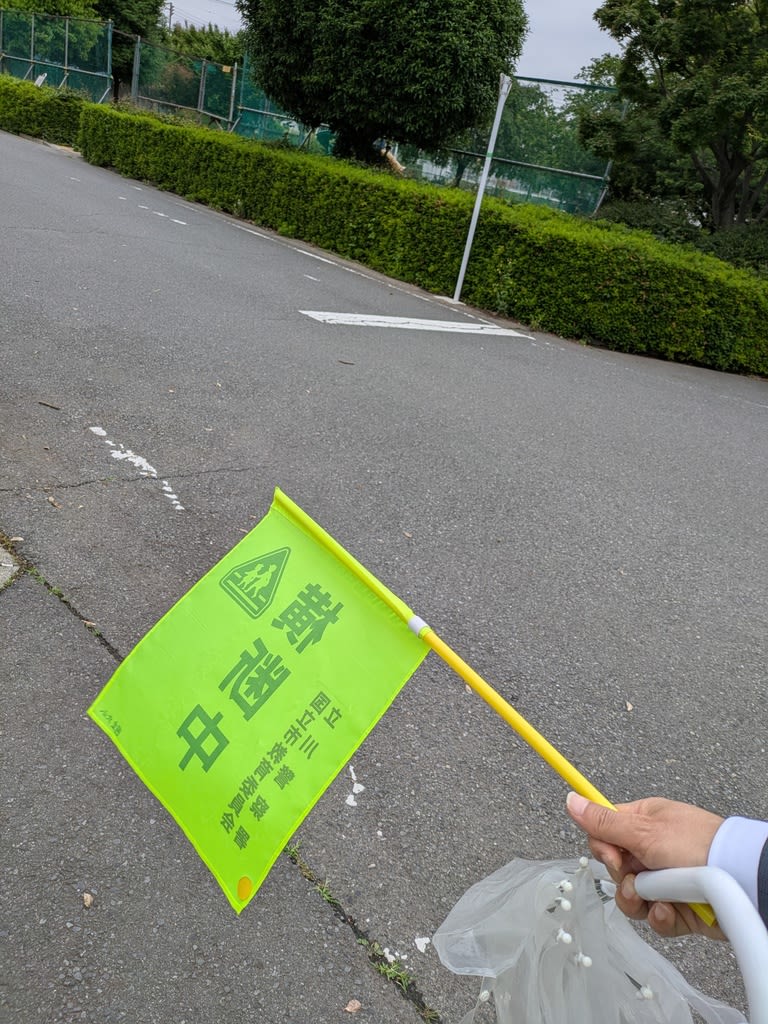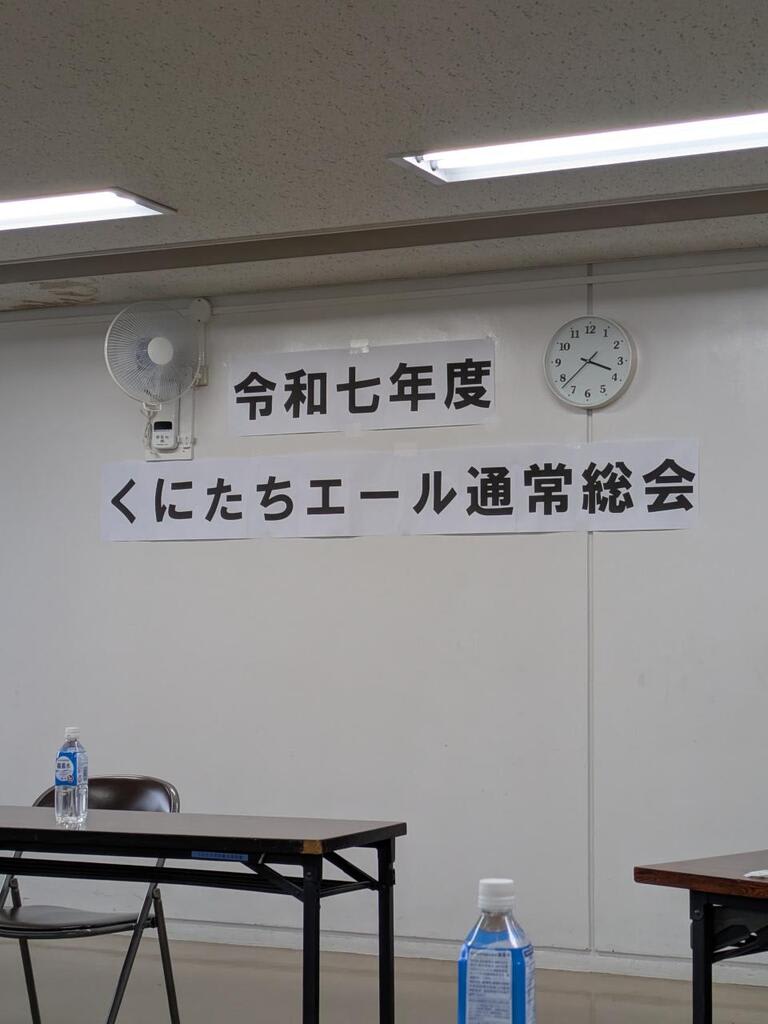こんにちは、子育て支援に向けて幼保小の連携が重要と考えている福祉保険委員会所属の石井伸之です。
本日は、午前中に石井伸之の市議会通信186号の入稿、午後2時30分からは幼保小の園長校長連絡協議会及び研修会への出席、午後7時からは矢川駅南口駅前広場における住民説明会、その後は消防団の操法訓練に参加して一日が終わりました。
午後2時30分から行われた幼保小の連携推進研修会は矢川プラスで行われます。
講師として大豆生田啓友(オオマメウダ ヒロトモ )氏(玉川大学教授)と寳來生志子(ホウライ キシコ)氏(東海大学准教授)にお越しいただきました。
内容としては、子どもの学びと育ちを繋ぐ為に「主体的、対話的で深い学び」「個別最適な学びと協働的な学び」に関するチャレンジテーマを各自が設定し、実践事例を持ち寄ることで子どもの学びと育ちを支える環境を幼保小の種別を越えて専門職同士が学び合う往還型研修です。
幼保で自由に「のびのび」とした自主性や主体性を育む教育が、小学校に入り机に座って45分間単純に詰め込むだけの授業に変わった時のギャップが一年生にとっての壁に感じられ、不登校になってしまうという事例が散見されます。
幼保で積み上げてきたものが、小学校で一瞬にして崩れ去る事例を改善する為にも、こういった幼保小の連携が重要です。
過去の学校が「大人の都合が良い子どもを育てる場所」になっていたのではないでしょうか?という自己批判から「子どもの主体性を育み、自主性を大切にする」教育が重要視されています。
幼保で培って来た広がりの上に、小学校での学びで更に広げていくことが出来るようにするべきです。
講演が終わった後に、各テーブルごとでのディスカッションに移ります。
その際にとある校長先生と幼保の先生方とのやり取りを聞かせていただきました。
そこで出て来たキーワードは「笑顔」だったことに私は興味津々です。
校長先生という立場は学校の最高責任者であり、間違いなく最高位の管理者です。
一歩間違えば近付きにくいオーラを発して、口を利くことも難しい相手と思われがちとなります。
この部分を「笑顔」で心の扉を開き、気さくな人間関係を築くことによって意見交換を重ねることの大切さを話されていました。
小川建設時代に素晴らしい笑顔の所長の元で次席(所長に次ぐ2番目の立場)として、とある現場に配属となりました。
工期と予算の非常に厳しい現場でしたが、〇〇所長の為ならばという形で職人さん方が大変協力的な現場であったことを思い出します。
所長が常に職人さんと何気ない会話を交わし、会話の最後に所長が職人の親方に対して「よろしく頼むよ」というと、親方からは「〇〇所長の頼みならば仕方ないか」という会話を何度も聞きました。
立場に関わらず会話と笑顔で心を通じ合うことの大切さを学んだことを思い出します。
腹を割って腹蔵無く話をすることが、子ども達の信頼感を勝ち取りることに繋がるのではないでしょうか?
そして、子ども達と話す時には膝を折り、同じ目線で真剣に話を聞くことが大切と考えています。
こういった研修会において学ぶ中で、今後とも幼保小のより良い連携に向けて学びたいと考えています。