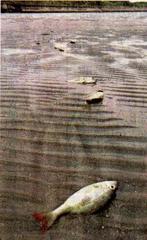▲<パワーポイントを使って話されている小濱氏>
1月23日、21:00~23:00に「語る会」の新年会を兼ねた会合に参加して来ました。
会場は、いつもの「けんぱーのすばやー」(おもろまち)。20:45くらいに着いたら、百人近く揃っていた。
今回のゲストスピーカーは、県北部で活躍している。ドクターヘリの「NPOメッシュ・サポート」理事長の小濱正博氏です。
初めて聞く、ドクターヘリの実態話は、知らない事がいっぱいあって、あっという間の2時間だった。
以下、要約です。
2009年6月15日再開後、約8ヵ月間で出動件数:105件
搬送患者数:92名
平均年齢:58.1歳
内訳:脳血管18、交通外傷15、外傷12、CPA11、循環器8、溺水6、減圧症6、他

▲<色んなデーターを使って説明して頂いた>
患者居住区:北部67、中南部16、県外9
北部53%、北部離島20%、中南部・県外27% 要請地域:国頭村33、本部町・今帰仁村14、伊江村12、名護市12、大宜味村10、他
北部地区におけるメッシュ運航対象地区12市町村の居住者:12万9246人
世帯数:5万3204、観光客300万人(美ら海水族館など)。
初期治療が大切で、心肺停止3分死亡、呼吸困難10分で50%死亡、大量出血30分で50%死亡。
よって、3~15分で到着する事が大切になる(特に、地震や台風など自然災害時は、車よりヘリが極めて有効である)。
救急病院が、県中南部に集中しているので、北部の患者を運ぶのには、ドクターヘリが北部に必要。
しかし、県のヘリは、中部の残波岬にあるのみで北部へ回り切れない。
また、ドクターが輪番制なので緊急時にはヘリに到着するのに30分くらいかかる。
全国的には、約100万都市に一つの救命救急センターが、沖縄本島では中南部に3カ所あり、北部にはない。
県からの補助が激減している状況下で、今後、サポーター制にして自力運営の方向へ。
そのために、ヘリに協賛企業の広告を貼ったりしている(ジャスコと我那覇精肉店のやんばる豚肉は、沖縄では有名な話)。
現会員数:1万3,453名
会費寄付:5,098万円、助成金4,200万円(地域医療再生基金申請中)。
「救急ヘリMESH」サポーター会員を急遽大動員の募集中との事。
今回わざわざ、那覇まで来られたのはこの事もあったからだ。
年間会費:1,000円、3,000円、5,000円、10,000円がある。
今後、会員と非会員の差別化やau携帯のGPSによる救急信号発信なども検討中。
★スイスでは、年会費2,700円を払えば国内外に飛んでくれる仕組みだとの事(スイス国民の40%、家族会員300万人)、それで15台のヘリと3機のジェット機を保有しているらしい。
沖縄県の現状で、人口集中地区(中南部)と北部の医療格差を見過ごせないので、民間のNPOでカバーせざるえないというのが、小濱理事長のご両親の出身地が「やんばる」という事もあり、この現状を放っておけないと思って立ち上がったらしい。
私も、今回話を聞いて、年間会員になって貢献したいと思いました。
※文中の数字などに間違いがあれば私の聞き間違い・記録間違いです。





 <居合道>
<居合道>







































 <横浜ベイスターズ、1月31日「那覇空港」にて、沖縄入り歓迎風景。>
<横浜ベイスターズ、1月31日「那覇空港」にて、沖縄入り歓迎風景。>







 <クバサーヌ御嶽>
<クバサーヌ御嶽>