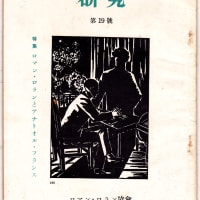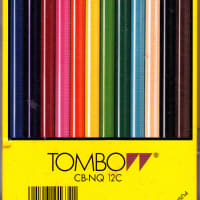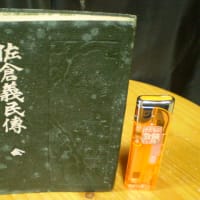天保7年甲斐国大騒動(1)
( 8) 01/07/01 16:49 コメント数:2
みなさん、こんにちは。
無宿大活躍(~~)の一揆の話です。無宿者が頭取になります。
無宿ツリーに続けてもよかったのですが、長くなったので、新規にします。
なにせ、この天保7年8月に起こった甲斐の大騒動は、大塩平八郎にも水戸斉昭
にも衝撃を与えた大騒動で、天保7年の最大の事件でしょう。
久しぶりに一揆観光でやります(^^)。
おふじ「みなさま、本日は一揆観光バスにようこそ。今回は、甲斐の国の大騒
動にご案内いたしまーす」
五郎「おばさん、甲斐の国って、どこだい?」
おふじ「甲斐といえば、山梨県。山はあっても山梨県よ。山に囲まれた土地
ね。でも、お客はあんた子ども一人?小僧を相手に一揆のガイドもさび
しいわね」
五郎「元気出してよ。ちゃんと聞いてあげるからさ。甲州ワインでもいっぱい
やりながら、話してよ。甲斐といえば、武田信玄だろ?」
おふじ「そうそう、信玄は甲斐のまんなか辺甲府盆地を根拠地にしていたの
ね。ところで、甲斐の国はこの甲府盆地を中心にした国中(くにな
か)地方と、今でいえば、大月市、都留市あたりの東部にあたる郡内
(ぐんない)地方の二つに分けられるの。この二つは、風土も気質もち
がっていたみたい。」
五郎「信玄の根拠地であった国中の方がプライドが高かったのかな」
おふじ「さあ、わからないけど、郡内地方は、田が少なく、ほとんど、絹の生
産をしていて、お米は国中からもっぱら買っていたそうよ。郡内の郡
内絹は全国的にも有名だったそうよ」
五郎「なるほど。郡内の人は、お米を作ってなかった。ということは、飢饉に
なると、郡内の人は困る。わかった!一揆は郡内の人がはじめたんだ
ね」
おふじ「するどい!おまえ、なん年生だい?大きくなったら、この一揆観光会
社で働かないかい。わたしももう歳だからね」
五郎「おばさん、たぶん、こんな筋書きだろう。まず、郡内の人が、国中(甲
府盆地)の富裕な米商人に米を貸してくれと要求するために一揆をおこ
すのでしょう?」
おふじ「その時の頭取が、下和田村の武七、犬目村の兵助なわけ。もちろん、
この二人は無宿ではないわよ。でも、郡内勢が、笹子峠を越えて、国中
に入ってから、国中の貧農、無宿たちが大勢参加し、一揆の当初の目的
が変わり、無宿者が頭取になって、甲斐国中、大暴れするのよ」
五郎「ねえさん、待った。話は急ぐ必要はねえよ。つづきは、ワインでもいっ
ぱいやってから、ゆっくりしなせえ」
つづく
おふじ「はーい。まず、下和田村の武七さんね。当時、70歳だったとか。
記録にはこうあります。『下和田村のいずこに和田武七とて近郷に知
られし、男伊達ありしが・・・・」(珍説見聞集)『下和田村の武七
という者、平生公事訴訟を好み、あるいは、無宿風来の長脇差などを
手訓付、仲間の中にては親方と称し、何の家職もつとめず、その日暮
らしの曲者なり』(応思穀恩編附録)」
五郎「男伊達だって?」
おふじ「そう、庶民のまあ、理想の男像よ。強きを挫き、弱きを守る男よ。
よくいえば、侠客、博徒。悪く言えば、遊び人、やくざもん。
武士道がすたれて、任侠道が盛んになったのかしら」
五郎「樋口一葉さんのじっちゃんも、こんなのじゃなかった?」
おふじ「博打をしたかどうかしらないけど、農業を嫌って、学問を好んで、公
事訴訟が得意だってことで、一風変わったところは似ているね。
ふつう、町や村の揉め事なんは、武士、町役人や村役人、庄屋さん、
寺の坊さんなどがあたるけど、だんだんと、そういう立場でない人
で、上や地域に対して口をきいてくれる頼りになる口利き屋さんが出
てきたんですね。国定の忠治親分だって、地元の人の頼りにはなった
かもしれないよ。あ、思い出した。こんなタイプの人は、明治までは
各地の村にいたようで、北村透谷も若い頃、多摩でこんな老侠客と
会って、影響を受けた、なんて言っています。」
五郎「ぼくらは、こんな人、映画かマンガでしか会えないよなあ。ところで、
ガイドさん、もう一人の頭取、兵助さんはどんな人なの?」
おふじ「ちょうど時間となりました。また、明日ね」
つづく
天保7年甲斐国大騒動(2)
( 8) 01/07/02 21:18 10520へのコメント
みなさん、こんにちは。
今回は、最初の頭取について
下和田村の武七、治左衛門
「下和田村のいずこに和田武七とて近郷に知られし男伊達ありしが」(「珍説
見聞集」)
「ここに、下和田村の百姓武七という者、平生、公事訴訟を好み、あるいは無
宿風来の長脇差などを手なれつけ、仲間の中では親方と称し、何の家職も務め
ず、その日暮らしの曲者なり」(「応思穀思編付録」)
天保7年甲斐国大騒動(3)
( 8) 01/07/03 21:58 10524へのコメント コメント数:1
おふじ「みなさまー、たたいまバスは甲州街道を走っておりまーす。甲州街道
といえば、いろんな人が歩いていますね」
五郎「えーと、椿三十郎、机龍之助、近藤勇、黒駒勝蔵!」
おふじ「そうですね。江戸から甲府勤番になる人も歩いたわ。なんでも、甲府
勤番になるのは、山流しといわれて、武士にとっては、左遷だったみ
たいですね。ろくな武士がこなかったとか(例外はもちろんあるで
しょう)。甲斐は天領で、代官所は甲府、石和、市川の3カ所にあっ
たそうだけど、ろくな侍はいなかったみたいよ。甲斐騒動のあと、代
官所の人はほとんどお役御免、逼塞などの処分を受けています。博徒
にとっては、稼ぎやすいところだったかも。
はーい、ここが、犬目村。頭取の兵助さんの村よ」
五郎「静かな所だなあ。あ、犬目村兵助の碑が建っている!」
おふじ「今は、静かだけど、昔は甲州街道の宿駅だったから、もっとにぎやか
だったでしょうね。兵助さんは、ここで、水田屋という宿屋も営業
し、犬目村の百姓代をしていたそうよ。」
五郎「村では、お金持ちのほうだね。」
おふじ「そうね。それに、天保7年は結婚して4年、はじめての赤ちゃんが生
まれたばかしなのよ」
五郎「家庭を捨ててまでして、なぜ頭取になったの?」
おふじ「ほほほ、そこが男の生きる道さ。兵助さんは、近くに住む下和田の武
七さんに私淑していたのかもしれない。一揆を起こす前に、家の後始
末の閣書き置きを残し、離縁状もわたしているの。生活力のある実務
的な感じの人だわ。読み書きはもちろん、そろばん、算術、顔相など
も得意で、逃亡中、それで生活しているのよ。」
五郎「え、逃げちゃうの?」
おふじ「こらっ。知ってるくせに(^^)。とぼけないで。兵助さんが逃亡中、日
記をつけていて、それが現存してることは有名よね。
下和田の武七さんに、わしは年だから自首する、おまえは、逃
げのびろ、と勧められたようよ。1年間逃亡し、天保8年には下総に
定着し、天保10年には妻子を呼び、幕末(嘉永ごろ)には、再び、
故郷に帰ったらしいわ。」
五郎「妻子と再会できたんだね。でも、よく逃亡生活ができたね。」
おふじ「兵助さんの愛読書はなんだと思う?西行四季物語だって。どんな話か
知らないけど、旅を苦には思わない人だったかもしれないわね」
五郎「ところで、のどかさんから教えてもらって、ぼくも中央公論の日本の歴
史「幕藩制の苦悶」で、郡内騒動のところを読んだのだけど、なんと、
磔562人と書いてあるね。これ、ちょっと多すぎると思う。562人も磔す
るだろうか」
おふじ「佐藤健一「真説甲州一揆」時事通信社も磔526人と書いてあったわ。で
も、図説百姓一揆では磔4人となっているの。よくわからないわ。で
も、いくらなんでも562人の磔はないでしょうね。みなさま、どう思われ
ます?」
つづく
。
( 8) 01/07/01 16:49 コメント数:2
みなさん、こんにちは。
無宿大活躍(~~)の一揆の話です。無宿者が頭取になります。
無宿ツリーに続けてもよかったのですが、長くなったので、新規にします。
なにせ、この天保7年8月に起こった甲斐の大騒動は、大塩平八郎にも水戸斉昭
にも衝撃を与えた大騒動で、天保7年の最大の事件でしょう。
久しぶりに一揆観光でやります(^^)。
おふじ「みなさま、本日は一揆観光バスにようこそ。今回は、甲斐の国の大騒
動にご案内いたしまーす」
五郎「おばさん、甲斐の国って、どこだい?」
おふじ「甲斐といえば、山梨県。山はあっても山梨県よ。山に囲まれた土地
ね。でも、お客はあんた子ども一人?小僧を相手に一揆のガイドもさび
しいわね」
五郎「元気出してよ。ちゃんと聞いてあげるからさ。甲州ワインでもいっぱい
やりながら、話してよ。甲斐といえば、武田信玄だろ?」
おふじ「そうそう、信玄は甲斐のまんなか辺甲府盆地を根拠地にしていたの
ね。ところで、甲斐の国はこの甲府盆地を中心にした国中(くにな
か)地方と、今でいえば、大月市、都留市あたりの東部にあたる郡内
(ぐんない)地方の二つに分けられるの。この二つは、風土も気質もち
がっていたみたい。」
五郎「信玄の根拠地であった国中の方がプライドが高かったのかな」
おふじ「さあ、わからないけど、郡内地方は、田が少なく、ほとんど、絹の生
産をしていて、お米は国中からもっぱら買っていたそうよ。郡内の郡
内絹は全国的にも有名だったそうよ」
五郎「なるほど。郡内の人は、お米を作ってなかった。ということは、飢饉に
なると、郡内の人は困る。わかった!一揆は郡内の人がはじめたんだ
ね」
おふじ「するどい!おまえ、なん年生だい?大きくなったら、この一揆観光会
社で働かないかい。わたしももう歳だからね」
五郎「おばさん、たぶん、こんな筋書きだろう。まず、郡内の人が、国中(甲
府盆地)の富裕な米商人に米を貸してくれと要求するために一揆をおこ
すのでしょう?」
おふじ「その時の頭取が、下和田村の武七、犬目村の兵助なわけ。もちろん、
この二人は無宿ではないわよ。でも、郡内勢が、笹子峠を越えて、国中
に入ってから、国中の貧農、無宿たちが大勢参加し、一揆の当初の目的
が変わり、無宿者が頭取になって、甲斐国中、大暴れするのよ」
五郎「ねえさん、待った。話は急ぐ必要はねえよ。つづきは、ワインでもいっ
ぱいやってから、ゆっくりしなせえ」
つづく
おふじ「はーい。まず、下和田村の武七さんね。当時、70歳だったとか。
記録にはこうあります。『下和田村のいずこに和田武七とて近郷に知
られし、男伊達ありしが・・・・」(珍説見聞集)『下和田村の武七
という者、平生公事訴訟を好み、あるいは、無宿風来の長脇差などを
手訓付、仲間の中にては親方と称し、何の家職もつとめず、その日暮
らしの曲者なり』(応思穀恩編附録)」
五郎「男伊達だって?」
おふじ「そう、庶民のまあ、理想の男像よ。強きを挫き、弱きを守る男よ。
よくいえば、侠客、博徒。悪く言えば、遊び人、やくざもん。
武士道がすたれて、任侠道が盛んになったのかしら」
五郎「樋口一葉さんのじっちゃんも、こんなのじゃなかった?」
おふじ「博打をしたかどうかしらないけど、農業を嫌って、学問を好んで、公
事訴訟が得意だってことで、一風変わったところは似ているね。
ふつう、町や村の揉め事なんは、武士、町役人や村役人、庄屋さん、
寺の坊さんなどがあたるけど、だんだんと、そういう立場でない人
で、上や地域に対して口をきいてくれる頼りになる口利き屋さんが出
てきたんですね。国定の忠治親分だって、地元の人の頼りにはなった
かもしれないよ。あ、思い出した。こんなタイプの人は、明治までは
各地の村にいたようで、北村透谷も若い頃、多摩でこんな老侠客と
会って、影響を受けた、なんて言っています。」
五郎「ぼくらは、こんな人、映画かマンガでしか会えないよなあ。ところで、
ガイドさん、もう一人の頭取、兵助さんはどんな人なの?」
おふじ「ちょうど時間となりました。また、明日ね」
つづく
天保7年甲斐国大騒動(2)
( 8) 01/07/02 21:18 10520へのコメント
みなさん、こんにちは。
今回は、最初の頭取について
下和田村の武七、治左衛門
「下和田村のいずこに和田武七とて近郷に知られし男伊達ありしが」(「珍説
見聞集」)
「ここに、下和田村の百姓武七という者、平生、公事訴訟を好み、あるいは無
宿風来の長脇差などを手なれつけ、仲間の中では親方と称し、何の家職も務め
ず、その日暮らしの曲者なり」(「応思穀思編付録」)
天保7年甲斐国大騒動(3)
( 8) 01/07/03 21:58 10524へのコメント コメント数:1
おふじ「みなさまー、たたいまバスは甲州街道を走っておりまーす。甲州街道
といえば、いろんな人が歩いていますね」
五郎「えーと、椿三十郎、机龍之助、近藤勇、黒駒勝蔵!」
おふじ「そうですね。江戸から甲府勤番になる人も歩いたわ。なんでも、甲府
勤番になるのは、山流しといわれて、武士にとっては、左遷だったみ
たいですね。ろくな武士がこなかったとか(例外はもちろんあるで
しょう)。甲斐は天領で、代官所は甲府、石和、市川の3カ所にあっ
たそうだけど、ろくな侍はいなかったみたいよ。甲斐騒動のあと、代
官所の人はほとんどお役御免、逼塞などの処分を受けています。博徒
にとっては、稼ぎやすいところだったかも。
はーい、ここが、犬目村。頭取の兵助さんの村よ」
五郎「静かな所だなあ。あ、犬目村兵助の碑が建っている!」
おふじ「今は、静かだけど、昔は甲州街道の宿駅だったから、もっとにぎやか
だったでしょうね。兵助さんは、ここで、水田屋という宿屋も営業
し、犬目村の百姓代をしていたそうよ。」
五郎「村では、お金持ちのほうだね。」
おふじ「そうね。それに、天保7年は結婚して4年、はじめての赤ちゃんが生
まれたばかしなのよ」
五郎「家庭を捨ててまでして、なぜ頭取になったの?」
おふじ「ほほほ、そこが男の生きる道さ。兵助さんは、近くに住む下和田の武
七さんに私淑していたのかもしれない。一揆を起こす前に、家の後始
末の閣書き置きを残し、離縁状もわたしているの。生活力のある実務
的な感じの人だわ。読み書きはもちろん、そろばん、算術、顔相など
も得意で、逃亡中、それで生活しているのよ。」
五郎「え、逃げちゃうの?」
おふじ「こらっ。知ってるくせに(^^)。とぼけないで。兵助さんが逃亡中、日
記をつけていて、それが現存してることは有名よね。
下和田の武七さんに、わしは年だから自首する、おまえは、逃
げのびろ、と勧められたようよ。1年間逃亡し、天保8年には下総に
定着し、天保10年には妻子を呼び、幕末(嘉永ごろ)には、再び、
故郷に帰ったらしいわ。」
五郎「妻子と再会できたんだね。でも、よく逃亡生活ができたね。」
おふじ「兵助さんの愛読書はなんだと思う?西行四季物語だって。どんな話か
知らないけど、旅を苦には思わない人だったかもしれないわね」
五郎「ところで、のどかさんから教えてもらって、ぼくも中央公論の日本の歴
史「幕藩制の苦悶」で、郡内騒動のところを読んだのだけど、なんと、
磔562人と書いてあるね。これ、ちょっと多すぎると思う。562人も磔す
るだろうか」
おふじ「佐藤健一「真説甲州一揆」時事通信社も磔526人と書いてあったわ。で
も、図説百姓一揆では磔4人となっているの。よくわからないわ。で
も、いくらなんでも562人の磔はないでしょうね。みなさま、どう思われ
ます?」
つづく
。