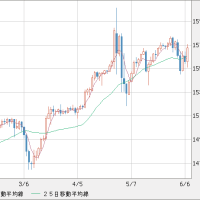今年もこの日が来た。9年もの歳月が流れたが、「復興」の実態は相変わらずである。
「国土強靭化」という虚名の下で進められた復興は失敗に終わり、
立派なインフラや急拵えの建物・住宅ばかりが残って
高齢化と人口流出は相変わらずである。
嘘つき安倍の言う「復興を加速」の実態はこのザマだ。
脱税した除染会社の有り様からも分かるように
加速したのは政策にたかる便乗主義と腐敗だ。
他方、復興の中で素晴らしい人間力、人材力も発揮されたが
殆ど全てが民間発であり、国会議員は時折申し訳のように来て
自分の手柄であるかのように自画自賛するだけなのである。
(空疎な嘘と欺瞞を垂れ流す安倍がその典型)
コロナ対策の件でも明らかになっているが、
日本社会は「政官は形だけ、民間発の活動の方が優秀」である。
震災復興でもありありとその病弊や民間活動の質の高さが示された。
南三陸で震災後に質の高い牡蠣養殖を実現させた事業者は
「若者はやりがいと誇りがあれば集まる」と語っている。
安倍自民が、若者にやりがいも誇りも与えられないから
被災地から若年人口が流出し復興が失敗し続けているのである。
▽ 政策面での「民度」はこの通り、政治主導での巨額の公共事業は確実に失敗する
当ウェブログの厳しい警告は、令和元年の陶酔が冷めた後に必ず浮上してくるであろう。
「元々、東日本大震災の被災地は過疎に苦しんでいた地域が多く、
多くの識者が当該地域からの人口流出が起きると予想しており
「復興」どころか「復旧」すら困難であることは予想されていた」
「加えて原発事故による壮烈な風評被害で
福島とその近隣の第一次産業・観光業が凄まじい打撃を受けており、
深刻な影響は後々まで残ることになる」
「知られているように被災地支援の熱意と活動は漸減するものである。
被災地での日常回復も個々の状況や資質によって「まだら模様」となり、
被災による打撃が甚大であった人々、復興の動きに取り残された人々は
経済的にも心理的にもより苦しい状況に追い詰められつつある」
「寄付金でも「買って応援」でも彼らの苦境は改善されない。
まして、自民党が票田にカネをばら撒き、選挙に勝つための方便である
「国土強靭化」では復興が永遠に不可能なのは明白である。
(せいぜい彼ら利益共同体の「利権回復」でしかない)」
「陛下が震災の影響が色濃く残っている被災地の現状に心を痛め、
深い気遣いをされているのを聞いてしみじみと心打たれた後に、
安倍首相のいつもの空々しい言辞を聞いて猛然と怒りが込み上げてきた」
「復興が進んでいる一部の見た目の良い場所だけで物見遊山し、
震災が「新しいステージ」に入ったなどととんでもない嘘を吐く政治家は、
天皇陛下のお気持ちを踏みにじる叛逆者に限りなく近い」
「今、被災地は復興どころか復旧も不可能になりつつある。
それは様々な理由に基づくものだが、最大の理由の一つは安倍政権である」
「「国土強靭化」などと愚劣なプロパガンダを展開して
公共事業予算を全国津々浦々にバラ撒いたために
被災地に向かう筈の資材も労働者も一気に分散し、コストも高騰した」
「自民党のお家芸である業界買収策の余波で、
ただでさえ困難な復興が遅れに遅れ、
自民党と癒着している建設業界が優先するのは「ハコモノ」である。
生活再建は業界に及ぼす恩恵が少ないので後回しにされる」
「このようなことは、自民党の通弊として、
これまでの「実績」から見て分かり切った話だった」
「権力の監視どころか「権力の犬」になっている御用メディアは恥さらしである。
こうした被災地の実情を知っていたら、「新しいステージ」が嘘八百である位はすぐ分かる筈だ」
「口ではいいことを言うが、相変わらず中身が伴っていない安倍首相。
状況がかなり良い場所ばかり視察し、子供と一緒に写真に収まって
自分のイメージだけ良くしようとする魂胆が見え見えである」
「あのバラ撒き民主党よりも自民党は6兆円の予算を上積みしていた。
この巨額予算が、人口流出した被災地の巨大な建造物に化けたのである」
「震災復興がうまくいかなかったことは、この速報を見れば明白である。
安倍政権による「被害」はこれにとどまらない。
建設業ばかりに労働者が集中した被災地は、二度と立ち直れなくなる。
自前の産業を失い、産業が空洞化する。政治家に予算を求めて生きるしかなくなる」
「被災地には穏和な人が多く、支援を受けて感謝している。
だからはっきりと言わないのだが、本音は以下の通りだ。
「安倍首相は大嘘つきで、「新しいステージ」になど入っていない」
「安倍政権や自民党は、被災地よりも建設業界のために行動している」
「震災復興は失敗しており、復旧すら不可能になった」」
「口だけ安倍政権が、経済ばかりか震災復興でも成果に乏しく、
寧ろ復興を妨害している様相が明らかになってきた」
「「被災地の復興に向けた取り組みを加速する」などとまた空々しい美辞麗句を語るが
映りの良い子供と一緒に御用メディアのテレビに映ってばかりで、
震災復興が思うように進んでいない苦い現実を誤摩化そうとしている」
「その見え透いた小細工も道理であり、人の少ない場所に巨大な土木工事ばかり進み、
自民党の票田である建設業界ばかりが儲かっているのが現実だからだ。
自民党の国土強靭化こそが震災復興を妨げる根源なのだから、誤摩化すしかない」
「国勢調査によれば、被災地の人口流出は加速している。
確かにインフラが失われてしまえば生活が困難になるから仕方のない面もあるが、
福島の深刻な人口減少をみれば、「復興に向けた取り組みを加速」などと大嘘をつくのは
とんでもない話であるばかりか、政権の重大な責任を認識すらしていない事実を示すものだ」
「また、岩手・宮城の人口減少トレンドは全く変わっていない。
「取り組みを加速」したつもりだけで、成果は乏しい低能の証拠であるのは明白だ」
「「復興を加速」と称した安倍首相の発言は嘘で、
投入した兆円規模の予算にもかかわらず
東日本大震災の被災地復興ははかばかしくない」
「矢張り「復興格差」が進んでおり、特に福島原発事故の悪影響が甚大である。
2020年に日本国民が東京五輪に束の間の熱狂を見せる時にも、
多くの被災地自治体は今と左程変わらない現実を痛感せざるを得なくなる」
「これも大方の予想通りであろう、
カネをいくら投入して公共事業を行っても、かつての生活が戻ってくる筈がないし
被災地には元々人口流出・減少が続いていた地域が多いこと、
そして福島原発事故は不可逆的かつ長年に及ぶ悪影響を与えていることから、
復興が容易でないことは初めから分かっていたことなのだが」
「軽々しく大言壮語した安倍首相と、
社員に対して「高く評価されている」と豪語する東電社長の言葉が、
かつての暮らしを取り戻せない被災地の現状の前で
白々しく響くだけなのは至極当然のことと言える」
「このままだと、建設業への降って湧いた特需と
仙台など一部の震災バブルに終わってしまいかねない。
多くの人々の命が失われ、コミュニティと生活が破壊された末に
そうした結果しか残らないのなら、「復興」という言葉に対する深い不信ばかりが残る」
「西日本の豪雨災害により、改めて確認できたことがある。
日本は「民度一流、議員三流以下」の国である」
「名もなき一般国民が、自前でボートを出して被災者を助けて廻ったり、
自らも被災しているにも関わらず真っ先に炊き出しを始めたり、
今回もまた諸外国が讃歎を惜しまない驚くべき事例が複数ある」
「しかし、この前例のない豪雨災害において一般国民の示した「民度の高さ」と、
与党議員の示した自己中や「程度の低さ」が真に驚嘆すべきコントラストだ」
「「赤坂自民亭」炎上の件も醜悪だが、それは実は本質ではない。
腐敗した自民党議員が大勢の犠牲者や被災者を「利用」して
「国土強靭化」と称した業界バラ撒きの謀略を巡らせているのが最悪なのだ」
「死者を利用して予算を出させ、自分の票に繋げるという
人間として最低最悪の行動と言っても過言ではない。
(勿論、議員としても最低最悪であるのは言う迄もない)
こうした「反社」議員の歳費を大幅カットして復興予算に投入すべきであろう」
「腐敗したこの連中の「業界バラ撒き」が地方自治体を衰退させ、
地方からの人口流出と高齢化を加速させてきたのである」
「論より証拠、東日本大震災でも今回の豪雨災害でも、
安倍の口だけ「国土強靭化」は殆ど効果を発揮せず、
防災・減災に役立った予算の方が遥かに少ない位である。
政策リテラシーが果てしなく低い安倍が何もしていないのは想定内だが、
自民党議員も国交省も防災の費用対効果や検証を碌に行っていない」
「腐敗している上に大勢の国民を無視し、
自分の選挙と票田への利益誘導しか考えていない
自民党議員はまさに「国賊」と言うべきなのだが、
こうした「国賊」を議員として選んだのが「民度」の高い国民なのだから不思議だ」
「考えられる結論はただ一つ、「日本国民の最悪の資質を反映したのが自民党議員」で、
日本国民の自己中心的で利益誘導ばかり求める体質が国会議員に集中的に体現されているのだ。
(実績や日頃の行動から見てそれ以外の結論は出ない)」
「国交省が治水計画の見直しに着手するとのことなので、
矢張り国交省も自らの見通しが役に立たず、想定が外れている事実を
認めざるを得なくなった訳である」
「しかし悲しいことに「業界」との関係が余りに深過ぎる官庁だけあって、
「堤防の高さやダムのかさ上げ」等という旧態依然の対処しかない」
「相変わらず、防災の実効性や費用対効果を無視して
防災事業の焼け太りのような非効率的状況を脱する見込みがない」
「諸先輩方に逆らえない組織というものは、正しい方向へ舵取りすることが非常に難しい、
そうした深刻な現実をまた改めて証明してしまったと言える」
「安倍自民の国土強靭化(という名前の選挙対策のバラ撒き)や省庁の防災対策の
非効率性を嘲笑うように、住民主導の防災対策と訓練で「一人の犠牲も出さなかった」
奇跡的な団地が広島にあるが、安倍も自民も霞が関の組織人間も何も学ばないのだろう」
「その「奇跡の団地」の合言葉は「自分の命は自分で守る」であり、
災害においては業界バラ撒きに必死の安倍や自民など信用してはならず、
緊急時には官庁や自治体が住民を救ってくれる訳ではないと教えてくれているのだ」
「それを理解できずに国土強靭化などという欺瞞的な標語を信じる地域住民は、
これまでの口だけ「復興」事業と同様に、故郷を衰退に向かわせることとなろう」
「自民党や政府の「復興」事業など信じてはならない。
これまでの被災地での「復興」の実態が明々白々に証明している。
奥尻島は地理的条件において著しく不利という点はあるものの、
東日本大震災の被災地でもそっくりの状況になっているのが何ともやりきれない」
「国土強靭化よりもハザードマップ、それに加えて住民の意識と行動だ。
災害の危険性の高い地域ではそれしかない。
また、国交省は自らの見通しが外れている事実を直視し、
機動的に社会インフラの復旧を行える仕組みを整えるべきであろう」
「東日本大震災から8年。追悼式で安倍は「復興を加速していく」と豪語したが、
実態は被災地の方々や殆どの国民がよく理解しているように、真逆である」
「「復興は加速していない」「ハコモノ等のインフラだけ(=土建だけ活況)」
「若者が戻って来ない」「政治家の言葉は空疎」が偽らざる真実なのだ」
「当ウェブログは公共事業や「国土強靭化」で復興を加速させようとしてはならない、
それはこれまでの震災を見れば明白であり、重要なのは人材であると指摘してきた」
「全く学習能力も自浄能力もない安倍と霞が関は、過去から学ばず
東日本大震災の被災地にインフラばかり整えようとし、
被災地からの若者の流出を招いているのである」
「人口統計から、「復興が加速」などしていないことは明白である。
ペースは緩慢で、二度と元には戻らない被災地も多いのだ。
特に困難に直面しているのは、若年層が流出して戻らない地域である」
「特に、安倍が国会で非常用電源を失うことはないと豪語したにも関わらず
(この劣化二世は、10年以上前から軽薄で嘘つきで無責任だったことが実証された訳だ)
実際は全く逆の結果となり歴史に残る過酷事故の直撃を受けた福島の被災地は深刻である」
「こちらは政策で対処しようとしても条件的に厳しいところではあるのだが、
エネルギー政策の転換をサボって福島の潜在エネルギー資源を活用せず、
大規模な除染事業で腐敗が黴のように広がっているのは間違いなく安倍の責任である」
「「日本は「民度一流、議員三流以下」の国である」と当ウェブログは指摘した。
安倍は三流以下なので(B層を騙す能力だけは一流)勿論例外はあるが、
残念ながら東日本大震災からの復興においては完全に正しかったと言える」
「三陸海岸の地理的条件を活かした「南三陸わかめ羊」や
三陸の陸前高田でしか養殖できない「エゾイシカゲガイ」のように
見事に復興に貢献している素晴らしい例はある」
「それらは皆、例外なく民間発の事業である。
安倍の手柄でも霞が関の貢献でも全くないのは言う迄もない」
「恐らく20世紀の世界でも有数の英明な君主であった昭和天皇。
満州事変勃発の際には軍需物資禁輸の恐れを予見し、
226事件では若い天皇を軽んじて日和見する陸軍幹部に決然たる姿勢を見せ、
終戦時の的確な見通しも人間宣言の決断も常人の遠く及ばないところだった」
「その余りに偉大な父から天皇の地位を引き継がれたこと自体が
筆舌に尽くし難い程に大変なことではなかったかと推察する」
「雲仙へ、神戸へ、東北へ、中国・九州へ。
そして沖縄へ、サイパンへ、ペリリューへも。
象徴天皇の新たな規範を陛下が築かれたと言っても過言ではない」
「陛下のお言葉は「国民に寄り添って」というものだったが、
「災害の時代」だった平成に被災地を見舞われる両陛下は
国民の方こそ自ら寄り添い申し上げないとと思わせる存在だった」
「国民の側も災害時において世界一と言っても過言ではない
「民度」の高さを随所で示しており、災害支援への恩返しや
過去の水害の伝承による迅速な避難など、改めて感服させられる例が複数見られる」
「政策面ではすっかり保守退嬰になっても
災害時になると高い倫理性が必ず示されるのが不思議だ」
「令和は経済面では殆ど良い話がないと運命付けられているが
(即位式に便乗して自己アピールに走った劣化二世のせいである)
日本社会自体は決してその高い資質を失うことはないだろう」
「災害大国日本では、過去の災害の教訓を生かして
驚くべき防災や避難を成功させた地域が必ず出てくる。
今後も貴重な教訓を無にしないよう、先進例から学ばなければならない」
「人口流出が進む被災地の現状は明白な復興の「失敗」を示している」と当ウェブログは警告した。
豪雨災害でもコロナ禍でも学習能力ゼロの与党と腐敗政治家が日本社会を蝕んでいる。
▽ 地方で重要なのは人材の「質」であり、政府の頭ごなしの施策で再生する自治体などない
「東日本大震災での「復興」の失敗は、西日本の豪雨災害でも繰り返されることとなろう」
とも当ウェブログは予言したが、悲しいことに予想通りの惨状だ。。
「台湾よりも遥かに劣る「後進国」並みの「全国で休校」という愚かな措置が行われ、
判断力に劣り実行が遅い泥縄な日本政府の体たらくが全世界に知れ渡っている」
「安倍が碌に効果のない一斉休校で見え透いたパフォーマンスするから、
民間事業者が凄まじい打撃を受けている。
愚かで利己的なトップがいる国はえてしてこうなるのだ」
「しかし震災時も豪雨災害時もそうだったが、非常事態においては
日本国民は驚くような民度の高さを示すものであり、今回も同様である」
「程度が低過ぎて寧ろ悪影響をもたらしている政治家とは違い、
民間では俊敏に、困っている人々を助ける活動が始まっている」
「愚かで空疎なパフォーマンスしか芸のない首相が一斉休校を宣言すると、
すぐさま保護者を助けるために子を預かる活動が始まっている。
静岡などでは学校に子の居場所をつくり、学童では必死の防疫対策の上で受け皿を作ろうとしている」
「また、劣化二世の愚劣な判断で大打撃を受けた給食業者は
食材を一気に買い求める消費者によって打撃を緩和させることが出来、
より独創的な活動としては経営難に追いやられた飲食店が受注して
低所得世帯に食事を届けるスキームをNPOが編み出した」
「ただ残念なのは、最近の選挙でのは日本の民度は明らかに低下しているので
事態を改善させるどころか悪化させる愚かな政治家が権力を握ってしまうことだ」
「感染者の出ていない地域は分散登校にすれば良かったものを。。
安倍は無意味な食品ロスを大量に生んだ点でも愚かで、恥晒しだ」
「悪しき官邸主導で政策を歪め、官僚機構を意気沮喪させ、
社会を腐蝕させる政治が行われるのはそれが元凶なのである」
「悲しいことに、東日本大震災や豪雨災害での失政、
地方創生の失敗と同じ様な現象がまた再び起きている」
安倍の「戦略上の大失敗を、戦術の巧妙さで取り返すことはできない」ということだ。
太平洋戦争は昔の話ではなく、今も完全に構図である。
↓ 参考
静岡で休校中の子どもを学校に受け入れ、大阪では保護者と飲食店を同時支援 - 政府より民間の方が賢い
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/88e447841597b64bcf896f0623e104814
被災地に戻らない若者、安倍の言う「復興加速」は土建業だけ - 政府や霞が関は予算をバラ撒くのみ
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/6f3779a1f9e6fed9b76d02dd6cd76e19
国交省の想定は外れてばかり、「国土強靭化」は予算の無駄と実証 - 命を守るのは住民主導の対策と訓練だ
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/a4a243e2925114b2cdeba8f29cd1b1ec
復興予算6兆円増額して人口減少が止まらず、安倍政権はもはや害悪 -「復興進んでいない」が住民の54%
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/d54f95e8d21729902e8ae49c5c25d54a
被災地の女性の貧困が深刻化、自営業者・パートの約7割が失業中 -「国土強靭化」で復興できる筈がない
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/af4ca12c6b88a24beb5dfa856ad6ee5f
▽ 地方創生が失敗したまま、令和に突入してしまった日本
福島の営農再開わずか3割 避難指示区域、帰還進まず 国の目標達成困難に(毎日新聞)
https://mainichi.jp/articles/20200305/k00/00m/040/245000c.html
何が「復興を加速」なのか、いい加減にしろと言いたい。
確かに震災復興のため多くの人が尽力したが、与党政治家はその中に入らない。
こうした不都合な事実を無視して自慢話をするしか能がない輩だ。
長く住めない「ついのすみか」 岩手・宮城復興住宅、居住継続5割強 岩手大調査(毎日新聞)
https://mainichi.jp/articles/20200301/k00/00m/040/313000c.html
復帰住宅はコミュニティ再生に失敗し、まさに「老人ホーム化」している。
ここから教訓を汲み取ろうとする動きはいまだにない。
戻らない住民多く、目立つ空き地…「遠い復興」震災9年(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200310-OYT1T50328/
安倍は福島原発事故の甚大な影響について申し訳のように言及するが、
福島での影響の大きさは安倍が口先で謝ったところで1ミリも改善しない。
そして「国土強靭化」という名の下の土建依存の復興事業は福島以外でも大失敗している。
被災地発、次世代のカキ養殖=「過密」避け味向上、時短も―東日本大震災9年(時事通信)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020030401014&g=soc
この通り、真の復興を果たすのは民間の人材だ。
過剰漁獲を繰り返して資源を蕩尽した今の日本漁業への警告ですらある。
安倍官邸は乗っかって自画自賛するだけの醜悪な存在で、
寧ろ衰退を加速させているのである。
「国土強靭化」という虚名の下で進められた復興は失敗に終わり、
立派なインフラや急拵えの建物・住宅ばかりが残って
高齢化と人口流出は相変わらずである。
嘘つき安倍の言う「復興を加速」の実態はこのザマだ。
脱税した除染会社の有り様からも分かるように
加速したのは政策にたかる便乗主義と腐敗だ。
他方、復興の中で素晴らしい人間力、人材力も発揮されたが
殆ど全てが民間発であり、国会議員は時折申し訳のように来て
自分の手柄であるかのように自画自賛するだけなのである。
(空疎な嘘と欺瞞を垂れ流す安倍がその典型)
コロナ対策の件でも明らかになっているが、
日本社会は「政官は形だけ、民間発の活動の方が優秀」である。
震災復興でもありありとその病弊や民間活動の質の高さが示された。
南三陸で震災後に質の高い牡蠣養殖を実現させた事業者は
「若者はやりがいと誇りがあれば集まる」と語っている。
安倍自民が、若者にやりがいも誇りも与えられないから
被災地から若年人口が流出し復興が失敗し続けているのである。
▽ 政策面での「民度」はこの通り、政治主導での巨額の公共事業は確実に失敗する
 | 『震災復興 欺瞞の構図』(原田泰) |
当ウェブログの厳しい警告は、令和元年の陶酔が冷めた後に必ず浮上してくるであろう。
「元々、東日本大震災の被災地は過疎に苦しんでいた地域が多く、
多くの識者が当該地域からの人口流出が起きると予想しており
「復興」どころか「復旧」すら困難であることは予想されていた」
「加えて原発事故による壮烈な風評被害で
福島とその近隣の第一次産業・観光業が凄まじい打撃を受けており、
深刻な影響は後々まで残ることになる」
「知られているように被災地支援の熱意と活動は漸減するものである。
被災地での日常回復も個々の状況や資質によって「まだら模様」となり、
被災による打撃が甚大であった人々、復興の動きに取り残された人々は
経済的にも心理的にもより苦しい状況に追い詰められつつある」
「寄付金でも「買って応援」でも彼らの苦境は改善されない。
まして、自民党が票田にカネをばら撒き、選挙に勝つための方便である
「国土強靭化」では復興が永遠に不可能なのは明白である。
(せいぜい彼ら利益共同体の「利権回復」でしかない)」
「陛下が震災の影響が色濃く残っている被災地の現状に心を痛め、
深い気遣いをされているのを聞いてしみじみと心打たれた後に、
安倍首相のいつもの空々しい言辞を聞いて猛然と怒りが込み上げてきた」
「復興が進んでいる一部の見た目の良い場所だけで物見遊山し、
震災が「新しいステージ」に入ったなどととんでもない嘘を吐く政治家は、
天皇陛下のお気持ちを踏みにじる叛逆者に限りなく近い」
「今、被災地は復興どころか復旧も不可能になりつつある。
それは様々な理由に基づくものだが、最大の理由の一つは安倍政権である」
「「国土強靭化」などと愚劣なプロパガンダを展開して
公共事業予算を全国津々浦々にバラ撒いたために
被災地に向かう筈の資材も労働者も一気に分散し、コストも高騰した」
「自民党のお家芸である業界買収策の余波で、
ただでさえ困難な復興が遅れに遅れ、
自民党と癒着している建設業界が優先するのは「ハコモノ」である。
生活再建は業界に及ぼす恩恵が少ないので後回しにされる」
「このようなことは、自民党の通弊として、
これまでの「実績」から見て分かり切った話だった」
「権力の監視どころか「権力の犬」になっている御用メディアは恥さらしである。
こうした被災地の実情を知っていたら、「新しいステージ」が嘘八百である位はすぐ分かる筈だ」
「口ではいいことを言うが、相変わらず中身が伴っていない安倍首相。
状況がかなり良い場所ばかり視察し、子供と一緒に写真に収まって
自分のイメージだけ良くしようとする魂胆が見え見えである」
「あのバラ撒き民主党よりも自民党は6兆円の予算を上積みしていた。
この巨額予算が、人口流出した被災地の巨大な建造物に化けたのである」
「震災復興がうまくいかなかったことは、この速報を見れば明白である。
安倍政権による「被害」はこれにとどまらない。
建設業ばかりに労働者が集中した被災地は、二度と立ち直れなくなる。
自前の産業を失い、産業が空洞化する。政治家に予算を求めて生きるしかなくなる」
「被災地には穏和な人が多く、支援を受けて感謝している。
だからはっきりと言わないのだが、本音は以下の通りだ。
「安倍首相は大嘘つきで、「新しいステージ」になど入っていない」
「安倍政権や自民党は、被災地よりも建設業界のために行動している」
「震災復興は失敗しており、復旧すら不可能になった」」
「口だけ安倍政権が、経済ばかりか震災復興でも成果に乏しく、
寧ろ復興を妨害している様相が明らかになってきた」
「「被災地の復興に向けた取り組みを加速する」などとまた空々しい美辞麗句を語るが
映りの良い子供と一緒に御用メディアのテレビに映ってばかりで、
震災復興が思うように進んでいない苦い現実を誤摩化そうとしている」
「その見え透いた小細工も道理であり、人の少ない場所に巨大な土木工事ばかり進み、
自民党の票田である建設業界ばかりが儲かっているのが現実だからだ。
自民党の国土強靭化こそが震災復興を妨げる根源なのだから、誤摩化すしかない」
「国勢調査によれば、被災地の人口流出は加速している。
確かにインフラが失われてしまえば生活が困難になるから仕方のない面もあるが、
福島の深刻な人口減少をみれば、「復興に向けた取り組みを加速」などと大嘘をつくのは
とんでもない話であるばかりか、政権の重大な責任を認識すらしていない事実を示すものだ」
「また、岩手・宮城の人口減少トレンドは全く変わっていない。
「取り組みを加速」したつもりだけで、成果は乏しい低能の証拠であるのは明白だ」
「「復興を加速」と称した安倍首相の発言は嘘で、
投入した兆円規模の予算にもかかわらず
東日本大震災の被災地復興ははかばかしくない」
「矢張り「復興格差」が進んでおり、特に福島原発事故の悪影響が甚大である。
2020年に日本国民が東京五輪に束の間の熱狂を見せる時にも、
多くの被災地自治体は今と左程変わらない現実を痛感せざるを得なくなる」
「これも大方の予想通りであろう、
カネをいくら投入して公共事業を行っても、かつての生活が戻ってくる筈がないし
被災地には元々人口流出・減少が続いていた地域が多いこと、
そして福島原発事故は不可逆的かつ長年に及ぶ悪影響を与えていることから、
復興が容易でないことは初めから分かっていたことなのだが」
「軽々しく大言壮語した安倍首相と、
社員に対して「高く評価されている」と豪語する東電社長の言葉が、
かつての暮らしを取り戻せない被災地の現状の前で
白々しく響くだけなのは至極当然のことと言える」
「このままだと、建設業への降って湧いた特需と
仙台など一部の震災バブルに終わってしまいかねない。
多くの人々の命が失われ、コミュニティと生活が破壊された末に
そうした結果しか残らないのなら、「復興」という言葉に対する深い不信ばかりが残る」
「西日本の豪雨災害により、改めて確認できたことがある。
日本は「民度一流、議員三流以下」の国である」
「名もなき一般国民が、自前でボートを出して被災者を助けて廻ったり、
自らも被災しているにも関わらず真っ先に炊き出しを始めたり、
今回もまた諸外国が讃歎を惜しまない驚くべき事例が複数ある」
「しかし、この前例のない豪雨災害において一般国民の示した「民度の高さ」と、
与党議員の示した自己中や「程度の低さ」が真に驚嘆すべきコントラストだ」
「「赤坂自民亭」炎上の件も醜悪だが、それは実は本質ではない。
腐敗した自民党議員が大勢の犠牲者や被災者を「利用」して
「国土強靭化」と称した業界バラ撒きの謀略を巡らせているのが最悪なのだ」
「死者を利用して予算を出させ、自分の票に繋げるという
人間として最低最悪の行動と言っても過言ではない。
(勿論、議員としても最低最悪であるのは言う迄もない)
こうした「反社」議員の歳費を大幅カットして復興予算に投入すべきであろう」
「腐敗したこの連中の「業界バラ撒き」が地方自治体を衰退させ、
地方からの人口流出と高齢化を加速させてきたのである」
「論より証拠、東日本大震災でも今回の豪雨災害でも、
安倍の口だけ「国土強靭化」は殆ど効果を発揮せず、
防災・減災に役立った予算の方が遥かに少ない位である。
政策リテラシーが果てしなく低い安倍が何もしていないのは想定内だが、
自民党議員も国交省も防災の費用対効果や検証を碌に行っていない」
「腐敗している上に大勢の国民を無視し、
自分の選挙と票田への利益誘導しか考えていない
自民党議員はまさに「国賊」と言うべきなのだが、
こうした「国賊」を議員として選んだのが「民度」の高い国民なのだから不思議だ」
「考えられる結論はただ一つ、「日本国民の最悪の資質を反映したのが自民党議員」で、
日本国民の自己中心的で利益誘導ばかり求める体質が国会議員に集中的に体現されているのだ。
(実績や日頃の行動から見てそれ以外の結論は出ない)」
「国交省が治水計画の見直しに着手するとのことなので、
矢張り国交省も自らの見通しが役に立たず、想定が外れている事実を
認めざるを得なくなった訳である」
「しかし悲しいことに「業界」との関係が余りに深過ぎる官庁だけあって、
「堤防の高さやダムのかさ上げ」等という旧態依然の対処しかない」
「相変わらず、防災の実効性や費用対効果を無視して
防災事業の焼け太りのような非効率的状況を脱する見込みがない」
「諸先輩方に逆らえない組織というものは、正しい方向へ舵取りすることが非常に難しい、
そうした深刻な現実をまた改めて証明してしまったと言える」
「安倍自民の国土強靭化(という名前の選挙対策のバラ撒き)や省庁の防災対策の
非効率性を嘲笑うように、住民主導の防災対策と訓練で「一人の犠牲も出さなかった」
奇跡的な団地が広島にあるが、安倍も自民も霞が関の組織人間も何も学ばないのだろう」
「その「奇跡の団地」の合言葉は「自分の命は自分で守る」であり、
災害においては業界バラ撒きに必死の安倍や自民など信用してはならず、
緊急時には官庁や自治体が住民を救ってくれる訳ではないと教えてくれているのだ」
「それを理解できずに国土強靭化などという欺瞞的な標語を信じる地域住民は、
これまでの口だけ「復興」事業と同様に、故郷を衰退に向かわせることとなろう」
「自民党や政府の「復興」事業など信じてはならない。
これまでの被災地での「復興」の実態が明々白々に証明している。
奥尻島は地理的条件において著しく不利という点はあるものの、
東日本大震災の被災地でもそっくりの状況になっているのが何ともやりきれない」
「国土強靭化よりもハザードマップ、それに加えて住民の意識と行動だ。
災害の危険性の高い地域ではそれしかない。
また、国交省は自らの見通しが外れている事実を直視し、
機動的に社会インフラの復旧を行える仕組みを整えるべきであろう」
「東日本大震災から8年。追悼式で安倍は「復興を加速していく」と豪語したが、
実態は被災地の方々や殆どの国民がよく理解しているように、真逆である」
「「復興は加速していない」「ハコモノ等のインフラだけ(=土建だけ活況)」
「若者が戻って来ない」「政治家の言葉は空疎」が偽らざる真実なのだ」
「当ウェブログは公共事業や「国土強靭化」で復興を加速させようとしてはならない、
それはこれまでの震災を見れば明白であり、重要なのは人材であると指摘してきた」
「全く学習能力も自浄能力もない安倍と霞が関は、過去から学ばず
東日本大震災の被災地にインフラばかり整えようとし、
被災地からの若者の流出を招いているのである」
「人口統計から、「復興が加速」などしていないことは明白である。
ペースは緩慢で、二度と元には戻らない被災地も多いのだ。
特に困難に直面しているのは、若年層が流出して戻らない地域である」
「特に、安倍が国会で非常用電源を失うことはないと豪語したにも関わらず
(この劣化二世は、10年以上前から軽薄で嘘つきで無責任だったことが実証された訳だ)
実際は全く逆の結果となり歴史に残る過酷事故の直撃を受けた福島の被災地は深刻である」
「こちらは政策で対処しようとしても条件的に厳しいところではあるのだが、
エネルギー政策の転換をサボって福島の潜在エネルギー資源を活用せず、
大規模な除染事業で腐敗が黴のように広がっているのは間違いなく安倍の責任である」
「「日本は「民度一流、議員三流以下」の国である」と当ウェブログは指摘した。
安倍は三流以下なので(B層を騙す能力だけは一流)勿論例外はあるが、
残念ながら東日本大震災からの復興においては完全に正しかったと言える」
「三陸海岸の地理的条件を活かした「南三陸わかめ羊」や
三陸の陸前高田でしか養殖できない「エゾイシカゲガイ」のように
見事に復興に貢献している素晴らしい例はある」
「それらは皆、例外なく民間発の事業である。
安倍の手柄でも霞が関の貢献でも全くないのは言う迄もない」
「恐らく20世紀の世界でも有数の英明な君主であった昭和天皇。
満州事変勃発の際には軍需物資禁輸の恐れを予見し、
226事件では若い天皇を軽んじて日和見する陸軍幹部に決然たる姿勢を見せ、
終戦時の的確な見通しも人間宣言の決断も常人の遠く及ばないところだった」
「その余りに偉大な父から天皇の地位を引き継がれたこと自体が
筆舌に尽くし難い程に大変なことではなかったかと推察する」
「雲仙へ、神戸へ、東北へ、中国・九州へ。
そして沖縄へ、サイパンへ、ペリリューへも。
象徴天皇の新たな規範を陛下が築かれたと言っても過言ではない」
「陛下のお言葉は「国民に寄り添って」というものだったが、
「災害の時代」だった平成に被災地を見舞われる両陛下は
国民の方こそ自ら寄り添い申し上げないとと思わせる存在だった」
「国民の側も災害時において世界一と言っても過言ではない
「民度」の高さを随所で示しており、災害支援への恩返しや
過去の水害の伝承による迅速な避難など、改めて感服させられる例が複数見られる」
「政策面ではすっかり保守退嬰になっても
災害時になると高い倫理性が必ず示されるのが不思議だ」
「令和は経済面では殆ど良い話がないと運命付けられているが
(即位式に便乗して自己アピールに走った劣化二世のせいである)
日本社会自体は決してその高い資質を失うことはないだろう」
「災害大国日本では、過去の災害の教訓を生かして
驚くべき防災や避難を成功させた地域が必ず出てくる。
今後も貴重な教訓を無にしないよう、先進例から学ばなければならない」
「人口流出が進む被災地の現状は明白な復興の「失敗」を示している」と当ウェブログは警告した。
豪雨災害でもコロナ禍でも学習能力ゼロの与党と腐敗政治家が日本社会を蝕んでいる。
▽ 地方で重要なのは人材の「質」であり、政府の頭ごなしの施策で再生する自治体などない
 | 『奇跡の村 地方は「人」で再生する』(相川俊英,集英社) |
「東日本大震災での「復興」の失敗は、西日本の豪雨災害でも繰り返されることとなろう」
とも当ウェブログは予言したが、悲しいことに予想通りの惨状だ。。
「台湾よりも遥かに劣る「後進国」並みの「全国で休校」という愚かな措置が行われ、
判断力に劣り実行が遅い泥縄な日本政府の体たらくが全世界に知れ渡っている」
「安倍が碌に効果のない一斉休校で見え透いたパフォーマンスするから、
民間事業者が凄まじい打撃を受けている。
愚かで利己的なトップがいる国はえてしてこうなるのだ」
「しかし震災時も豪雨災害時もそうだったが、非常事態においては
日本国民は驚くような民度の高さを示すものであり、今回も同様である」
「程度が低過ぎて寧ろ悪影響をもたらしている政治家とは違い、
民間では俊敏に、困っている人々を助ける活動が始まっている」
「愚かで空疎なパフォーマンスしか芸のない首相が一斉休校を宣言すると、
すぐさま保護者を助けるために子を預かる活動が始まっている。
静岡などでは学校に子の居場所をつくり、学童では必死の防疫対策の上で受け皿を作ろうとしている」
「また、劣化二世の愚劣な判断で大打撃を受けた給食業者は
食材を一気に買い求める消費者によって打撃を緩和させることが出来、
より独創的な活動としては経営難に追いやられた飲食店が受注して
低所得世帯に食事を届けるスキームをNPOが編み出した」
「ただ残念なのは、最近の選挙でのは日本の民度は明らかに低下しているので
事態を改善させるどころか悪化させる愚かな政治家が権力を握ってしまうことだ」
「感染者の出ていない地域は分散登校にすれば良かったものを。。
安倍は無意味な食品ロスを大量に生んだ点でも愚かで、恥晒しだ」
「悪しき官邸主導で政策を歪め、官僚機構を意気沮喪させ、
社会を腐蝕させる政治が行われるのはそれが元凶なのである」
「悲しいことに、東日本大震災や豪雨災害での失政、
地方創生の失敗と同じ様な現象がまた再び起きている」
安倍の「戦略上の大失敗を、戦術の巧妙さで取り返すことはできない」ということだ。
太平洋戦争は昔の話ではなく、今も完全に構図である。
↓ 参考
静岡で休校中の子どもを学校に受け入れ、大阪では保護者と飲食店を同時支援 - 政府より民間の方が賢い
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/88e447841597b64bcf896f0623e104814
被災地に戻らない若者、安倍の言う「復興加速」は土建業だけ - 政府や霞が関は予算をバラ撒くのみ
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/6f3779a1f9e6fed9b76d02dd6cd76e19
国交省の想定は外れてばかり、「国土強靭化」は予算の無駄と実証 - 命を守るのは住民主導の対策と訓練だ
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/a4a243e2925114b2cdeba8f29cd1b1ec
復興予算6兆円増額して人口減少が止まらず、安倍政権はもはや害悪 -「復興進んでいない」が住民の54%
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/d54f95e8d21729902e8ae49c5c25d54a
被災地の女性の貧困が深刻化、自営業者・パートの約7割が失業中 -「国土強靭化」で復興できる筈がない
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/af4ca12c6b88a24beb5dfa856ad6ee5f
▽ 地方創生が失敗したまま、令和に突入してしまった日本
 | 『地方消滅 - 東京一極集中が招く人口急減』(増田寛也,中央公論新社) |
福島の営農再開わずか3割 避難指示区域、帰還進まず 国の目標達成困難に(毎日新聞)
https://mainichi.jp/articles/20200305/k00/00m/040/245000c.html
”東京電力福島第1原発事故により、福島県内で営農を休止した農地のうち、再開した面積は約3割にとどまることが各市町村への取材で明らかになった。帰郷する住民が少ないことが理由だ。国は2020年度末までに6割の目標を掲げたが、達成は難しくなっている。
毎日新聞は2月、避難指示が出された福島県12市町村にアンケートを実施し、いずれの自治体からも回答を得た。
この結果、営農を休止したのは、国や自治体が避難指示を出した12市町村1万7298ヘクタール。このうち19年度までに再開したのは10市町村5487ヘクタールで、全体の32%にとどまった。再開率が最も高かったのは12年春に避難指示が解除された広野町の72%。19年春まで全町避難が続いた大熊町と、4日に全町避難が一部解除された双葉町はゼロ。両町を除き、最も低かったのは、17年春に解除された富岡町と浪江町の3%。
再開が進まない理由について「帰還した人が少ない」(富岡町、葛尾村、飯舘村など)という声が多かった。実際に、避難指示が出された区域の住民登録者数は事故当時7万4395人だったが、20年2月1日現在の居住者は1万6880人と23%に過ぎない。解除が遅れた市町村ほど再開率の低い傾向にある。
原発事故後、国は原発から30キロ圏内を中心に稲の作付けを制限。国や自治体は放射線量が高く、立ち入りが制限されている帰還困難区域を除き、18年3月までに内陸部を含む農地約3万9500ヘクタールを表土を入れ替えるなどして除染した。
国や県は帰還する住民が少ない中、避難指示解除から原則3年間、営農再開に備えた除草など農地の保全管理に補助を出しているが、楢葉町や葛尾村など4市町村で19年春までに一部を除いて期限が切れた。南相馬市や富岡町など5市町村では20年春に一部を除いて期限が切れる。
〔中略〕
福島大の林薫平准教授(農業経済学)は「農地保全の助成が終了しつつある中、少数の担い手で農地を保全管理しきれない実態が顕在化しつつある。営農再開のモデルを確立し、広げていくことが重要だ」と話している。【渡部直樹】”
何が「復興を加速」なのか、いい加減にしろと言いたい。
確かに震災復興のため多くの人が尽力したが、与党政治家はその中に入らない。
こうした不都合な事実を無視して自慢話をするしか能がない輩だ。
長く住めない「ついのすみか」 岩手・宮城復興住宅、居住継続5割強 岩手大調査(毎日新聞)
https://mainichi.jp/articles/20200301/k00/00m/040/313000c.html
”東日本大震災後、岩手、宮城両県に建設された大規模災害公営住宅(復興住宅)で、今の住宅に住み続けると明確に決めている人は5割強にとどまることが、岩手大学三陸復興・地域創生推進機構の船戸義和特任助教らによるアンケートで明らかになった。国の基準で政令月収(控除後の所得)が15万8000円を超え、入居3年を過ぎると、割り増し家賃を取られることが背景にある。
〔中略〕
調査は2019年12月から20年1月、コミュニティーの実態や課題を探るため、両県の集合型復興住宅で実施した。福島県は原発事故被災地への将来的な帰還を望む人も多いため、対象から外した。このうち、毎日新聞が整備戸数の多い上位3団地ずつ、計6団地を抽出して分析した。6団地では、13歳以上の入居者計2114人に配布し、半数近い988人から回答を得た。平均年齢は62歳で、約3割は1人暮らしだった。
「今の公営住宅に今後も住み続けるか」との問いに「住み続ける」と答えたのは56%。「分からない」は36%、「転居を考えている」は7%で、合計43%だった。働き手世代の15~64歳に絞ると60%に上昇する。「住み続ける」とした人の平均年齢が68歳であるのに対し、「分からない」「転居を考えている」を選んだ人を合わせた平均は53歳で、若中年層で永住意識が低かった。
生活の不安や課題を選択式で三つまで答える質問では「家賃・生活費」を選んだ人が46%で最も多く、「健康・運動」34%、「仕事・収入」23%と続いた。
国は19年12月、復興住宅の家賃を安く抑えるために自治体に出してきた特例的な補助を、21年度以降に見直す方針を示した。国の担当者は「毎年のように大災害が起き、公平性を保つ意味もある」と説明する。
〔中略〕
復興住宅で自治会の設立・運営を支えてきた船戸特任助教は「現役世代の永住意識が薄くなると、復興住宅が老人ホーム化する懸念が現実味を帯びてくる。コミュニティーの活性化につなげるため自治会活動への参加を条件に家賃を減免するなど、現役世代に住み続けてもらうための制度を作るべきだ」と提言する。【中尾卓英、三瓶杜萌】
◇災害公営住宅(復興住宅)
災害で自宅を失った人のために、都道府県や市町村が国の補助を受けて整備し、安い家賃で貸し出す住宅。集合型と一戸建て型がある。東日本大震災では岩手、宮城、福島の3県に約2万9000戸が建てられた。”
復帰住宅はコミュニティ再生に失敗し、まさに「老人ホーム化」している。
ここから教訓を汲み取ろうとする動きはいまだにない。
戻らない住民多く、目立つ空き地…「遠い復興」震災9年(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200310-OYT1T50328/
”東日本大震災から11日で9年となった。岩手、宮城、福島県では住宅再建が進んだものの、復興事業の長期化による人口流出は深刻で、再生された街に空き地が目立つ。東京電力福島第一原発事故に見舞われた福島は、避難指示の解除が遅くなった地域で住民帰還の動きが鈍い。政府が復興の総仕上げとする「復興・創生期間」の終了まで1年。
〔中略〕
高台や内陸部への集団移転事業は、残る16戸の宅地が今月内に完成予定で、計画された8389戸の造成が終わる。災害公営住宅も計画した約3万戸の99%が完成。最大約12万戸あった仮設住宅は、新年度中に原発避難者向けを除いてなくなる見込みだ。ただ、津波対策で大規模なかさ上げを行った中心市街地は、商店や住宅が戻っていない。
被災地の鉄道は今月、すべて復旧する。福島のJR常磐線富岡―浪江駅間は14日に運転を再開。昨春の復旧後、台風で再び被災した岩手の三陸鉄道リアス線も20日に運行再開となる。
一方、福島の苦境は続いている。避難者はいまだ4万人超。この9年で避難先での定住が進み、帰還意欲は低い。復興庁の調査で「戻らないと決めている」と答えた住民は、今月に避難指示が一部解除された双葉町や大熊町で6割に上る。
漁業は原発事故後、魚種ごとに安全性を確認しながら試験操業を続け、本格的な再開を目指してきた。しかし、原発の汚染水を浄化した処理水の処分方法を巡り、政府の有識者会議が海洋放出を含む2案を提言。漁業者の間に風評被害を懸念する声が広がっている 。
政府は、復興庁の設置期限を10年延長して2031年3月末までとした。福島で避難者の帰還促進や風評被害対策に取り組む一方、岩手、宮城では5年をめどに産業振興などを支援する事業の完了を目指す。”
安倍は福島原発事故の甚大な影響について申し訳のように言及するが、
福島での影響の大きさは安倍が口先で謝ったところで1ミリも改善しない。
そして「国土強靭化」という名の下の土建依存の復興事業は福島以外でも大失敗している。
被災地発、次世代のカキ養殖=「過密」避け味向上、時短も―東日本大震災9年(時事通信)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020030401014&g=soc
”宮城県南三陸町の戸倉地区にあるカキの養殖場が、東日本大震災後、養殖いかだを7割減らす画期的な方法で復活を果たした。成長と環境保護の両立が評価され、2016年に国内で初の水産養殖管理協議会(ASC)認証を取得、19年には農林水産祭の天皇杯も受賞した。主導した後藤清広さん(59)は「震災を経験したからこそ挑戦できた」と語り、若手への継承や地域的な広がりにも手応えを感じている。
県漁業協同組合の志津川支所戸倉出張所では、津波で船や養殖設備などを全て失い、12年、いかだを震災前の約1000台から約270台まで減らして養殖を再開した。当初は、いかだの所有権を手放さなければならない漁師からの反対が根強かったという。
仲間の説得に奔走した後藤さんを支えたのは、11年8~12月、試しに育てたカキが驚くほどのスピードで育ち、味も良くなったという結果だ。従来は、出荷の目安となるむき身の重さ約15グラムに達するまで2~3年かかっていたが、稚貝が減ったことで1年で30~40グラムまで成長。出荷サイクルを短縮できた。若いカキは甘みが強く、生食用に高値で売れるという。
後藤さんによると、志津川湾一帯は震災前もたびたび津波被害に見舞われた。その都度、養殖設備を強化して生産量を増やすことを繰り返した結果、約1000台がひしめく過密養殖となり、成長は遅く味の評価も下がっていたという。後藤さんは「何十年もやってきたが、自然の回復力に初めて気付いた。品質を上げれば、生産量を減らしても収入は増やせると思った」と振り返る。
いかだを減らして3年ほどたつと、機材が十分に整い、船の燃料代などの経費削減や労働時間の短縮と共に漁師たちの平均収入は伸び、現在では震災前の1.5倍に。ASC認証を受け対外的な評価が高まると、30代以下の就業者が震災前の2倍以上に増えた。
後藤さんの長男伸弥さん(35)もその1人。養殖の将来に希望が持てず、一時は別の仕事に就いたが、「味の違いにびっくり」し復帰。若手で試食イベントを企画するなど、地域の盛り上げにも積極的に取り組む。
〔中略〕
後藤さんは「若者はやりがいと誇りがあれば集まると痛感した。どん底を経験した戸倉でできたのだから、どこの地域でもできる可能性がある」と力を込めた。 ”
この通り、真の復興を果たすのは民間の人材だ。
過剰漁獲を繰り返して資源を蕩尽した今の日本漁業への警告ですらある。
安倍官邸は乗っかって自画自賛するだけの醜悪な存在で、
寧ろ衰退を加速させているのである。