エコノミスト合併号はインバウンド特集、
先週「「黄金時代」でなく「大迷惑時代」が正しい」と書いたが
極めて真っ当な内容でありこの合併号特集の冒頭は
スイスに倣って客数を制限し単価を上げるべきとの正論だ。
全く以てその通りで、暗愚な安倍・菅が推進したビザ緩和はやめ、
富裕層や高所得層以外をインバウンドから排除すべきである。
特区民泊と違法民泊は徹底的に排除しなければならないし
迷惑行為には罰金を科し悪質な外国人には罰則を定めネットで公表すべきだ。
高額な伝統工芸品がインバウンド客に売れ始めていること、
台湾からもワインツーリズム参加が出つつあること、
一部ではあるが良い兆しも見えるようになった。
エントリーのサブタイトルは98頁、市川繁男氏の連載から。
氏は日本の長期金利上昇を警戒しているのではあるが
50年間の長期金利とCPI上昇率を掲載しているので
日本の場合CPI上昇率と経済成長率は相関すらないという
極めて重大な事実が一目瞭然になっているのである。
つまり暗愚な安倍らが主張してきた「デフレ脱却」は大嘘で
日本は寧ろ物価が上昇すると70年代のようにスタグフレーションになることが分かる。
◇ ◇ ◇ ◇
東洋経済の保険特集はやや内向き、業界ものと言ってもよい。
矢張りサブの「80年目の戦争経済 総決算」が重要だった。
先週、「インチキ・アベノミクスと高橋財政は全然別物だから」と書いたが
日本経済をV字回復させた高橋財政は財政拡張も短期間であり
金融緩和でも、口ほどにもない黒田と違って買い入れた国債を市場売却している。
いまだにアベノミクスを信奉している愚か者はこの記事を熟読すべきだ。
いま財政拡張で景気回復すると妄信しているB層有権者が増殖しているが
そういう視野狭窄と独善こそ高橋是清の命を奪ったテロリストの本質なのだ。
(高橋是清は放漫な財政拡張に反対して凶弾に倒れた、というのが史実である)
佐藤優氏の連載は戦後の先鋭化した左翼の話になってきた。
まさか参政党に媚びているのだろうか?
AERAでは自分が大学で教えていて資本論を輪読させたら
学生が哲学書も読めるようになったと自画自賛を展開しているが
「どの程度」「どれほどの人数が」という肝心の点はぼやかしており
まるで全員が読めるようになったかのような自慢話として読者に受け取られるだろう。
社会科学を学んでそれこそ氏が重視する数学を用いた計量分析で実証すべきであろうに。
◇ ◇ ◇ ◇
ダイヤモンドは恒例の資格特集、「切り口を変えてきた」と
先週書いたが、士業支援AIツールの紹介は興味深い。
学歴ロンダなど相変わらずの記事もあるが
頑張って工夫した跡が見られ読者各位は詳細に読み込んでみても良いかも。
サブ特集の「マンション 最強の管理第2弾」は前回ほどではなかったが悪くない。
管理を考えると矢張りタワマンはどうも不利な条件が揃っているな。。
さて佐藤優氏の連載、選挙に無関心な層を動員した参政党とみらいに注目しているそうだが、
かつての民主党への政権交代の時と今回の参院選の投票率はほとんど変わらなかった。
無関心層の動員はこれがピークに近いと考えた方が妥当ではないか。
氏の見通しはこれまでの実績として精度が著しく低かったので
個人的には参政党とみらいのどちらか、或いは両方が失墜すると予想している。
参政党はいま勢いがあるように見えるが党首も議員もウソとデマカセが多すぎる。
古代ギリシャで言うところのデマゴーゴスであり政権を担う能力も資格もない。
実際にはばら撒きポピュリズムだがまだしも良識のある国民民主にすら負ける可能性があろう。
ところで氏は、公明党は大丈夫と言っておきながら大幅に議席を減らした事実をどう考えているのか。
参院選では議席を失い党勢は後退したが公明党は大丈夫という詭弁を弄するのだろうか?
◇ ◇ ◇ ◇
次週はダイヤモンドに注目、勿論メインではなくサブのホテルランキングの方である。
▽ コラム「2024年の国別AIランキングでの日本の順位」も重要
▽ 大袈裟なタイトルの多い東洋経済、本当に大変革なのかどうか。。
重要なのはせいぜい不動産関連だけだと思うのだが。
先週「「黄金時代」でなく「大迷惑時代」が正しい」と書いたが
極めて真っ当な内容でありこの合併号特集の冒頭は
スイスに倣って客数を制限し単価を上げるべきとの正論だ。
全く以てその通りで、暗愚な安倍・菅が推進したビザ緩和はやめ、
富裕層や高所得層以外をインバウンドから排除すべきである。
特区民泊と違法民泊は徹底的に排除しなければならないし
迷惑行為には罰金を科し悪質な外国人には罰則を定めネットで公表すべきだ。
高額な伝統工芸品がインバウンド客に売れ始めていること、
台湾からもワインツーリズム参加が出つつあること、
一部ではあるが良い兆しも見えるようになった。
 | 『週刊エコノミスト』2025年8/26・9/2合併号 |
エントリーのサブタイトルは98頁、市川繁男氏の連載から。
氏は日本の長期金利上昇を警戒しているのではあるが
50年間の長期金利とCPI上昇率を掲載しているので
日本の場合CPI上昇率と経済成長率は相関すらないという
極めて重大な事実が一目瞭然になっているのである。
つまり暗愚な安倍らが主張してきた「デフレ脱却」は大嘘で
日本は寧ろ物価が上昇すると70年代のようにスタグフレーションになることが分かる。
◇ ◇ ◇ ◇
東洋経済の保険特集はやや内向き、業界ものと言ってもよい。
矢張りサブの「80年目の戦争経済 総決算」が重要だった。
先週、「インチキ・アベノミクスと高橋財政は全然別物だから」と書いたが
日本経済をV字回復させた高橋財政は財政拡張も短期間であり
金融緩和でも、口ほどにもない黒田と違って買い入れた国債を市場売却している。
いまだにアベノミクスを信奉している愚か者はこの記事を熟読すべきだ。
いま財政拡張で景気回復すると妄信しているB層有権者が増殖しているが
そういう視野狭窄と独善こそ高橋是清の命を奪ったテロリストの本質なのだ。
(高橋是清は放漫な財政拡張に反対して凶弾に倒れた、というのが史実である)
 | 『週刊東洋経済』2025年8/23号 (保険 大転換) |
佐藤優氏の連載は戦後の先鋭化した左翼の話になってきた。
まさか参政党に媚びているのだろうか?
AERAでは自分が大学で教えていて資本論を輪読させたら
学生が哲学書も読めるようになったと自画自賛を展開しているが
「どの程度」「どれほどの人数が」という肝心の点はぼやかしており
まるで全員が読めるようになったかのような自慢話として読者に受け取られるだろう。
社会科学を学んでそれこそ氏が重視する数学を用いた計量分析で実証すべきであろうに。
◇ ◇ ◇ ◇
ダイヤモンドは恒例の資格特集、「切り口を変えてきた」と
先週書いたが、士業支援AIツールの紹介は興味深い。
学歴ロンダなど相変わらずの記事もあるが
頑張って工夫した跡が見られ読者各位は詳細に読み込んでみても良いかも。
サブ特集の「マンション 最強の管理第2弾」は前回ほどではなかったが悪くない。
管理を考えると矢張りタワマンはどうも不利な条件が揃っているな。。
![資格&学歴 裏ワザ大全(DiamondWEEKLY 2025年8/23号 [雑誌]) 週刊ダイヤモンド](https://m.media-amazon.com/images/I/41PBcNRKzcL._SL160_.jpg) | 『DiamondWEEKLY』2025年8/23 (資格&学歴 裏ワザ大全) 週刊ダイヤモンド |
さて佐藤優氏の連載、選挙に無関心な層を動員した参政党とみらいに注目しているそうだが、
かつての民主党への政権交代の時と今回の参院選の投票率はほとんど変わらなかった。
無関心層の動員はこれがピークに近いと考えた方が妥当ではないか。
氏の見通しはこれまでの実績として精度が著しく低かったので
個人的には参政党とみらいのどちらか、或いは両方が失墜すると予想している。
参政党はいま勢いがあるように見えるが党首も議員もウソとデマカセが多すぎる。
古代ギリシャで言うところのデマゴーゴスであり政権を担う能力も資格もない。
実際にはばら撒きポピュリズムだがまだしも良識のある国民民主にすら負ける可能性があろう。
ところで氏は、公明党は大丈夫と言っておきながら大幅に議席を減らした事実をどう考えているのか。
参院選では議席を失い党勢は後退したが公明党は大丈夫という詭弁を弄するのだろうか?
◇ ◇ ◇ ◇
次週はダイヤモンドに注目、勿論メインではなくサブのホテルランキングの方である。
▽ コラム「2024年の国別AIランキングでの日本の順位」も重要
![ガンダム ジークアクス(DiamondWEEKLY 2025年8/30号 [雑誌]) 週刊ダイヤモンド](https://m.media-amazon.com/images/I/51GZpD4i-aL._SL160_.jpg) | 『DiamondWEEKLY』 2025年8/30号 (ガンダム ジークアクス) 週刊ダイヤモンド |
▽ 大袈裟なタイトルの多い東洋経済、本当に大変革なのかどうか。。
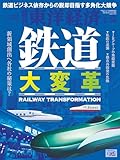 | 『週刊東洋経済』2025年8/30号 (鉄道 大変革) |
重要なのはせいぜい不動産関連だけだと思うのだが。












![5年後の業界地図(DiamondWEEKLY 2025年8月2日号 [雑誌]) 週刊ダイヤモンド](https://m.media-amazon.com/images/I/41s0xEB49TL._SL160_.jpg)

![大NTTの野心 (DiamondWEEKLY 2025年8月9・16日合併号 [雑誌]) 週刊ダイヤモンド](https://m.media-amazon.com/images/I/41tcxQQhxDL._SL160_.jpg)
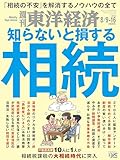

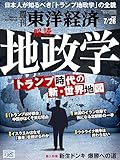


![公認会計士ランキング(DiamondWEEKLY 2025年6/21号 [雑誌]) 週刊ダイヤモンド](https://m.media-amazon.com/images/I/415ULR7HI6L._SL160_.jpg)

![マンション 最強の売買(DiamondWEEKLY 2025年6/28・7/5合併号 [雑誌]) 週刊ダイヤモンド](https://m.media-amazon.com/images/I/51URoATCWDL._SL160_.jpg)
![週刊エコノミスト 2025年7月1・8日合併号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51JPp-qF3IL._SL160_.jpg)

































