今週のダイヤモンドは驚きのガンダム特集だが
第二特集でホテルランキング、第三特集もと
矢張りメインだけではまずいと編集部が判断したようだ。
注目のホテルランキングはページが少なめで残念、
いつものダイヤモンドは顧客目線でのランキングだが
今回は珍しく経営側からの見方だったのが興味深い。
その意味で、ペット同伴可能なホテルが
経営側にメリットが大きいのは面白い視点で意外だった。
エントリーのサブタイトルは14頁、
「2024年の国別AIランキングでの日本の順位」より。
IMD世界競争ランキングでは日本は35位、
デジタル協同力ランキングでは31位、
AIランキングでは11位だそうだ。
著者はAI活用が日本経済復権の鍵と主張するが
人材に投入する資金も巨大な国内市場もないのだから
日本は米中に対して圧倒的に不利と考えるのが妥当ではないか。
◇ ◇ ◇ ◇
東洋経済の鉄道特集は可もなく不可もなくというところ。
「大袈裟なタイトルの多い東洋経済、本当に大変革なのかどうか。。」
と先週に書いたが、業界的には大変革かもしれないが
日本経済にとってはそうではない、という程度の話だった。
より気になるのは巻頭コラム「ニュースの核心」で、
内容としてはは寧ろ「ニュースの核心を外している」もので
医学部のいわゆる「地域枠」の問題を取り上げているのだが
制約の多い「地域枠」が学生には不人気であり
どうしても医学部にという層にとっては
寧ろ穴場、狙い目とされている実態すら知らないらしい。
執筆者の風間氏はリベラルで理想主義的な記事が多く、
(労働者の権利擁護では良い記事も多かったのだが)
国公立医学部に合格するために地域枠しかなかった受験生と
酷くなる一方の医師の偏在に悩む自治体や大学との、
互いの利害を巡る功利的な争いであることを全然分かっていない。
自治医大と愛知県が卒業者の医師に修学金の一括変換を求めるのは
分割払いのような配慮を見せれば制度が崩壊し僻地から続々と
自治医大出身の医師が流出するのを恐れているからである。
それだけ日本の医師偏在の問題は大きいし、医師は僻地に行かないのだ。
そもそも自由開業の特権を持つ日本の医師界に根本的な構造問題があり、
ドイツのように開業を規制して政府が医師の配置を統制し
医師の偏在を是正するよう診療報酬を地域別に調整すれば
地域枠など最初から必要なかったであろうに。
自治医大出身のこのA医師も公金を貰ってからゴネるから
問題になるのであって、最初から他の国公立医学部に行けば良かったのだ。
自分で自治医大を選択して自ら公費を受け取ったのだから
他の医師と同等の学費を負担するのが公平というものである。
これはコラムの言うような「お礼奉公」などではなく
単なるモラルハザードの問題に過ぎない。
A医師の訴訟のせいで修学金や奨学金の額が大幅減額される可能性すらあろう。
もし家庭の経済状況に制約されず医師になれるべきと医師側が主張するなら
欧州並みの間接税を負担するからと自ら申し出るのが理の当然である。
佐藤優氏の連載は引き続き戦後左翼の話。
チェコの話は矢張りウケなかったのだろうか。。
但し戦後左翼の話も脱線気味で「ソ連の介入前提」という
物騒な話が出ているので何だこれはとよく読んだら
何のことはない、単なる氏の恣意的断定だった。
氏は当該勢力から過去に嫌がらせを受けた経験があると告白しており
そうなるとただの私怨に基づく決め付けと判断されるであろうに。。
氏はAERAでは、アラスカでの米ロ会談で
トランプがプーチンの立場に近付いたとまた珍妙な説を展開している。
(因にイアンブレマーは「プーチンの勝利」と冷静に判断している)
以前は確か「プーチンと握った」と断定していた筈だが。。
聞く所ではかなり体調が宜しくないそうなのでそのせいかもしれない。
執筆も無理をしない方が読者の為にも良いのでは。。
◇ ◇ ◇ ◇
次週もダイヤモンドに注目、と言ってもメインではなくサブの「スキマバイト 光と影」の方。
▽ 三菱商事の撤退を受けて洋上風力のレポートもあるようだ
▽ 修正を迫られるホンダの電動化計画、次の大統領が民主党になってまたひと騒動になるかも。。
▽ エコノミストもマンション管理特集、それだけ問題が多いということでもある
サブ特集の「迫るマンションの廃虚化」も重要。
第二特集でホテルランキング、第三特集もと
矢張りメインだけではまずいと編集部が判断したようだ。
注目のホテルランキングはページが少なめで残念、
いつものダイヤモンドは顧客目線でのランキングだが
今回は珍しく経営側からの見方だったのが興味深い。
その意味で、ペット同伴可能なホテルが
経営側にメリットが大きいのは面白い視点で意外だった。
![ガンダム ジークアクス(DiamondWEEKLY 2025年8/30号 [雑誌]) 週刊ダイヤモンド](https://m.media-amazon.com/images/I/51GZpD4i-aL._SL160_.jpg) | 『DiamondWEEKLY』 2025年8/30号 (ガンダム ジークアクス) 週刊ダイヤモンド |
エントリーのサブタイトルは14頁、
「2024年の国別AIランキングでの日本の順位」より。
IMD世界競争ランキングでは日本は35位、
デジタル協同力ランキングでは31位、
AIランキングでは11位だそうだ。
著者はAI活用が日本経済復権の鍵と主張するが
人材に投入する資金も巨大な国内市場もないのだから
日本は米中に対して圧倒的に不利と考えるのが妥当ではないか。
◇ ◇ ◇ ◇
東洋経済の鉄道特集は可もなく不可もなくというところ。
「大袈裟なタイトルの多い東洋経済、本当に大変革なのかどうか。。」
と先週に書いたが、業界的には大変革かもしれないが
日本経済にとってはそうではない、という程度の話だった。
より気になるのは巻頭コラム「ニュースの核心」で、
内容としてはは寧ろ「ニュースの核心を外している」もので
医学部のいわゆる「地域枠」の問題を取り上げているのだが
制約の多い「地域枠」が学生には不人気であり
どうしても医学部にという層にとっては
寧ろ穴場、狙い目とされている実態すら知らないらしい。
執筆者の風間氏はリベラルで理想主義的な記事が多く、
(労働者の権利擁護では良い記事も多かったのだが)
国公立医学部に合格するために地域枠しかなかった受験生と
酷くなる一方の医師の偏在に悩む自治体や大学との、
互いの利害を巡る功利的な争いであることを全然分かっていない。
自治医大と愛知県が卒業者の医師に修学金の一括変換を求めるのは
分割払いのような配慮を見せれば制度が崩壊し僻地から続々と
自治医大出身の医師が流出するのを恐れているからである。
それだけ日本の医師偏在の問題は大きいし、医師は僻地に行かないのだ。
そもそも自由開業の特権を持つ日本の医師界に根本的な構造問題があり、
ドイツのように開業を規制して政府が医師の配置を統制し
医師の偏在を是正するよう診療報酬を地域別に調整すれば
地域枠など最初から必要なかったであろうに。
自治医大出身のこのA医師も公金を貰ってからゴネるから
問題になるのであって、最初から他の国公立医学部に行けば良かったのだ。
自分で自治医大を選択して自ら公費を受け取ったのだから
他の医師と同等の学費を負担するのが公平というものである。
これはコラムの言うような「お礼奉公」などではなく
単なるモラルハザードの問題に過ぎない。
A医師の訴訟のせいで修学金や奨学金の額が大幅減額される可能性すらあろう。
もし家庭の経済状況に制約されず医師になれるべきと医師側が主張するなら
欧州並みの間接税を負担するからと自ら申し出るのが理の当然である。
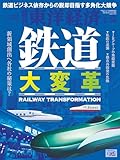 | 『週刊東洋経済』2025年8/30号 (鉄道 大変革) |
佐藤優氏の連載は引き続き戦後左翼の話。
チェコの話は矢張りウケなかったのだろうか。。
但し戦後左翼の話も脱線気味で「ソ連の介入前提」という
物騒な話が出ているので何だこれはとよく読んだら
何のことはない、単なる氏の恣意的断定だった。
氏は当該勢力から過去に嫌がらせを受けた経験があると告白しており
そうなるとただの私怨に基づく決め付けと判断されるであろうに。。
氏はAERAでは、アラスカでの米ロ会談で
トランプがプーチンの立場に近付いたとまた珍妙な説を展開している。
(因にイアンブレマーは「プーチンの勝利」と冷静に判断している)
以前は確か「プーチンと握った」と断定していた筈だが。。
聞く所ではかなり体調が宜しくないそうなのでそのせいかもしれない。
執筆も無理をしない方が読者の為にも良いのでは。。
◇ ◇ ◇ ◇
次週もダイヤモンドに注目、と言ってもメインではなくサブの「スキマバイト 光と影」の方。
▽ 三菱商事の撤退を受けて洋上風力のレポートもあるようだ
![アサヒ 王者の撤退戦(DiamondWEEKLY 2025年9/6号 [雑誌]) 週刊ダイヤモンド](https://m.media-amazon.com/images/I/51zFSi-Zj0L._SL160_.jpg) | 『DiamondWEEKLY』 2025年9/6号 (アサヒ 王者の撤退戦) 週刊ダイヤモンド |
▽ 修正を迫られるホンダの電動化計画、次の大統領が民主党になってまたひと騒動になるかも。。
 | 『週刊東洋経済 』2025年9/6号 (どうする!ホンダ) |
▽ エコノミストもマンション管理特集、それだけ問題が多いということでもある
![週刊エコノミスト 2025年9月9日号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/519SmTbAZRL._SL160_.jpg) | 『週刊エコノミスト』 2025年9月9日号 |
サブ特集の「迫るマンションの廃虚化」も重要。










![大NTTの野心 (DiamondWEEKLY 2025年8月9・16日合併号 [雑誌]) 週刊ダイヤモンド](https://m.media-amazon.com/images/I/41tcxQQhxDL._SL160_.jpg)
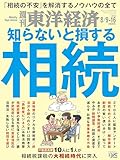

![霞が関官僚の危機(DiamondWEEKLY 2025年7/19・26合併号 [雑誌]) 週刊ダイヤモンド](https://m.media-amazon.com/images/I/51SQFQz4eQL._SL160_.jpg)

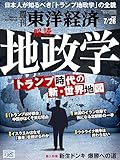

![保険大激変(週刊ダイヤモンド 2025年3/22号 [雑誌])](https://m.media-amazon.com/images/I/51pYBBesRIL._SL160_.jpg)
![週刊東洋経済 2025年3/22号(進撃のアクセンチュア)[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/41103UalfVL._SL160_.jpg)
![階級社会の不幸(週刊ダイヤモンド2025年3/29号 [雑誌])](https://m.media-amazon.com/images/I/51PQTX9vVDL._SL160_.jpg)
![週刊東洋経済 2025年3/29号(再来! 大倒産時代)[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51s+XSISDeL._SL160_.jpg)
![週刊エコノミスト 2025年4月1日号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WE7SvLlfL._SL160_.jpg)
![名門エスカレーター校(週刊ダイヤモンド2025年3/15号 [雑誌])](https://m.media-amazon.com/images/I/51436SZo8pL._SL160_.jpg)


![週刊東洋経済 2025年3/15号(株の道場 環境激変に勝ち抜く株)[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51uM32Jkd8L._SL160_.jpg)

































