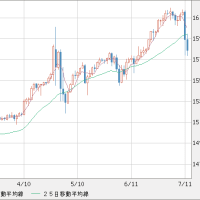菅義偉のもたらした害はコロナ対策の大失敗だけではない。
ライドシェアのような筋の悪い場当たりな政策案を出すことだけでもない。
そもそも根本的に、提唱する政策が殆ど例外なく有害なのだ。
携帯料金の値下げ圧力はまだしも害の少ない方であり、
(本来なら日本国民の所得を伸ばし、5G投資を促進する方が先決だった)
年々弊害が大きくなるのはもはや悪名高い「ふるさと納税」である。
ふるさと納税は発想としては悪くないが極一部の自治体にばかり
使い切れないカネが溜まって行く一方、しかも仲介業者が暴利を貪って
自治体に「ハゲタカ」と陰口を叩かれる始末である。
しかも地方創生どころか地方の少子高齢化と社会減(人口流出)は止まらない。
ふるさと納税は原発立地自治体の補助金のような「麻薬」のようになり果てたのだ。
▽ 長野県下條など卓越した自治体は、公務の人件費をカットして次世代育成に投資した
自民党の地方創生は、「バラ撒き」しかもたらさない。
最初から分かり切った、大失敗必至であったと証明されたことになる。
「「地方創生」と聞いてすぐ思い浮かべるのは、
バブル期に自民党政権が行なった愚劣な「ふるさと創生」である。
1億円をバラまいて今は寧ろ不良債権のようになっている自治体も多い」
「今回の「地方創生」も所詮は同じである。
支持率が下がっている安倍内閣の人気取り、姑息な地方選挙対策が本質である。
ふるさと納税の税制優遇拡大や地方企業の税負担軽減などが挙がっているが、
これまでの「ふるさと創生」や地方振興策がことごとく失敗に終わったという
「不都合な事実」を直視し真摯に反省することなしに成果が出る筈はない」
「本気で地域経済の梃入れを行なおうと考えるなら、
大企業正社員や公務員の退職金の税控除を大幅縮小し、
その全額を育児世帯への現物給付に移転するのが最も効果的である」
「また、原子力発電を半永久的に凍結し、環境税を引き上げて
税収を全額コージェネ推進と木質バイオマス熱利用に投入すべきである。
エネルギー需要地では一気に熱利用が進み、
化石燃料の輸入は大幅減少、その分は内需に還流する」
「農業では日本版AOC(原産地呼称)の導入、
漁業では漁獲枠の大規模導入、林業では国産材建築の推進、
木質バイオマス・コージェネの発電分の固定価格買い取り、
食産業ではMOF(国家最優秀職人章)の導入、
我が国の政府も官庁もこうした必要な施策を全く実行していない」
「非常に豊かな田舎がある欧州では地域資源の磨き方が巧みだし、
自らの地域の良さをよく理解しているし活用法も優れている」
「うまくいった活性化策に「視察者が殺到」するのは結構だが、
視察した後、何らかの成功に結びつけた事例が皆無に等しい。
公費を使った視察に明確な成果がなければ、行政訴訟の対象とすべきである」
「「地方創生」なるバズワードは、政治感覚の鋭い者ならすぐ分かるように、
自民党政権による有権者を丸め込む地方統一選向けのプロモーションに過ぎない」
「関係閣僚は「バラ撒きにはしない」などとほざいているが、
安倍内閣の「国土強靭化」そのものが明白な業界バラ撒きなのだから、
最初の第一歩から間違っている、もしくは有権者を騙そうとしているかのいずれかだ。
(自民党の体質から見て、その両方である可能性が極めて高い)」
「直近では「地方創生」と称して東京23区の大企業の本社機能を
地方に移転すれば税優遇という、シャープ亀山工場の失敗から全く学習していない
「次元の低い」政策案を大真面目で出してきた」
「確かに企業経営の観点から言えばリスク軽減のために地方移転も必要だが、
それは「地方創生」ではない。自分を安売りする租税競争の国内版でしかない」
「「地方創生」に寄与するのは、地域の実態や特性に根づいた
付加価値創造に長けている多様な中小企業の存在である。
そのような中小企業を政府が生み出したり育てたりすることはできない」
「ただ補助金や税軽減だけで釣られてくる大企業は
自治体からいくらカネを貰えるかしか考えず、すぐに出てゆく厄介者だ」
「エリック・シュローサーはアメリカの大企業が州政府を脅し、
移転をちらつかせて州政府から更なる恩典を脅し取る実態を書いている」
「ふるさと納税の上限引き上げは悪くないが、
この程度の軽減では大した効果がないだろう」
「どうせまた、「人口減や地方経済の衰退に歯止めをかけ」るのに失敗しても
政府も与党もキャリア官僚も、誰一人として責任を取らないのは間違いない」
「「ベンチャー企業への投資優遇税制」も、これまで死屍累々の政策だ。
これまでの失策を全く反省せず有権者のカネをバラ撒きに使う
政府や与党らしい腑抜けた政策案だ」
「投資庁によって対内投資を積極的に募るスウェーデンや、
観光プロモーションが巧みな欧州国から学ぶ能力が根本的に欠如している」
「日本財団の18歳意識調査では、安倍の地方創生が
「うまくいっている」と考える者が5%にも満たない。
安倍は碌な政策を行っていないのだから、当然の帰結と言えるだろう。
(それどころか菅が「ふるさと納税」バブルと大混乱を引き起こす始末)」
「しかも若者は安倍政権下ですっかり「劣化」しており、
魅力ある大学がない、経済的メリットがない、
官庁が移転してくればいいと我が儘放題、言いたい放題である」
「公立大学としては驚くべき成功を収めた国際教養大学で
地元出身者の比率が激減して大問題になっている事実すら理解していないのだ。
国際教養大学ができて、秋田県の人口流出が止まったとでも考えているのか?
かつてのバングラディッシュのように、自らの惨状を誇張して援助を乞うのは間違っている」
「ただ、地方の若者を責めるのは正しくない。若者達は
利己的で無責任な自民党議員の悪影響を受けて歪められただけであり、
都市圏でホテルが急増しただの、経団連に調査を求めるだの責任転嫁する片山や、
若者は高齢者のために地方に行って雪かきしろととんでもない暴言を放つ自民党政務官など
真に批判されるべき対象は自民党議員であり、無責任の元凶である安倍なのである」
「周知の通り、東京圏への人口流入は23年連続で転入超過。
転入が転出をおよそ14万人も上回るという状況で、
安倍の「地方創生」は予算の無駄、役立たずという結論になろう」
「文科省の官僚のクビを握った官邸は
大都市圏の大学定員管理厳格化を強行させたが、
加計学園のような地方私大の経営陣を潤すだけで人口流出は変わらず、
矢張り腐敗した安倍らしい「利益誘導政策」の一つに過ぎなかった訳である」
「おまけに地方創生担当相の片山はこの惨憺たる結果を
「東京圏でのホテル急増」のせいだとすぐさま責任転嫁し、
経団連など経済団体に「実態調査を求める」と言い放った」
「自民党の鈴木外務政務官に至っては「雪国で若者の就農を促し」
などと若年層を将棋のコマか何かのように扱う始末。
(このような増長議員の歳費をカットして予算に充当すべきであろう)」
「中共のように国民を思い通りに動かせると勘違いしているのか、
安倍自民はまさに「頭から腐る」状況になっていることがよく分かる」
「腐った頭からは腐った政策と予算の無駄しか生じない訳で、
大失敗した安倍や菅をクビにして権力の座から駆逐するのが信賞必罰なのだが
惰眠を貪るB層が保守退嬰のため日本を衰退させる現況を延命させてしまっている」
「その結果、「地方の中小企業で働いたらカネを払う」
「AIやIoTで地方創生」という碌でもない政策案ばかり出てきており、
日本の政策の劣化は太平洋戦争時と同じ様な壊滅的状況に陥っている。。
(大失敗した参謀の責任を問わず使い続けた大本営と全く同じである)」
「「地方創生」は惨憺たる失敗で
選挙でB層を騙すための売り文句に過ぎなかった、ということだ。
14万人の転入超を13万弱に減らしたところで手柄になどなるわけがない。
予算効率・費用対効果から言えば「役立たず」以外の何ものでもない」
「大学の定員厳格化は、受験生を散々犠牲にして地方私大を助けるだけ、
人口流出は変わっていないのだから「小手先」「糊塗策」である。
人口減が予想されていたのに大学を粗製濫造した自民党が責任を誤摩化しただけの話」
「B層を騙すための案を手を変え品を変え繰り出す様は
特殊詐欺グループの手口とそっくりである。
何一つ検証せず責任も取らない詐欺政党が政権に入るとこうなるのだ。
技術を活用すること自体は結構だが、政府が音頭をとって寧ろ失敗する例は余りに多い。
(過去の経産省の大プロジェクトが死屍累々であるのがその証拠)」
「地方でも驚くべき成功を収めている自治体は複数ある。
しかし、その共通点は「地域主導」であり「政府主導」ではない。
だから政府の詐欺的な「地方創生」は常に失敗する運命なのだ」
安倍政権下で少し進んだのは地理的表示保護制度(GI)ぐらいで、他は論外という状況だ。
▽ 自治体がカネを出しても、企業は「税金を安くしなければここから出ていく」と言うだけである
▽ 海外事例の研究もしない評論家は、地方企業に法人減税すれば出生率が上がると机上の空論
矢張り「「地方創生」と僭称する次元の低い政策案しか報じられず、
当ウェブログの指摘した通り、さもしい選挙対策に堕してしまうのは間違いない」結果である。
「日経記事の素晴らしいところは高齢化や少子化の影響が大きく、
観光客増の効果を打ち消してしまったと指摘している点である」
「地方創生は、真に効果があるのであれば勿論異論はないが、
安倍と自民の「地方創生」は完全に口だけのバラ撒きであり
実態は「地方衰退加速」でしかないのは厳然たる事実だ」
「これは勿論、保身と腐敗の塊である安倍自民の程度の悪さが主因だが、
政府が関わると必ずと言って良い程に地方振興策は失敗すること、
成功例を見ると悉く「政府や省庁が関わっていない地域主導型」であることから、
地方創生が失敗した理由は「政府や省庁が余計な政策で邪魔したから」なのだと言える」
「例えば日本ワインの隆盛は営々と品質改善を続けた生産者の努力と工夫のお蔭であり、
インバウンドで高い評価を受けている地域も全てボトムアップ型の成長である」
「ただ、そうした成功事例のある地域でも少子高齢化・社会減に苦しんでおり、
真の地方創生には長野県下條のような強力な人口政策が不可欠であることも
既にして明らかになっていると言えよう」
「観光で成功すること自体は良いのだが、
観光客は通常、住民よりも消費額が圧倒的に低い。
納税においても地域貢献度は低いのである」
「インバウンドでの成功例に挙げられる京都や高山の人口動態を見ても明らかなように、
人口政策なくして地方創生の成功はあり得ない」
地方衰退はそもそも自民党政権と地方自治体に原因があるのだから、
失敗に終わるのは最初から分かり切った話、戦略的・戦術的に「必敗」なのだ。
↓ 参考
「高齢化や人口減が観光客の増加を打ち消している」- 安倍の「地方創生」は大嘘、地方衰退が鮮明に
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/699090e435b39e67e95634d1e3f98c10
「地方創生はうまくいっている」僅か4.8%、安倍は嘘と失態ばかり - 自民党議員は責任転嫁に必死
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/63c62f00163729bbe3847305bbc2a024
本社移転の税優遇でも大学定員管理でも徒労に、地方創生を唱えて人口流出 - 安倍の政策は死屍累々
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/9f7064201ab6c145f6e4df28e7eec6e6
「奇跡の村」下條の出生率回復は住宅等の現物給付が主因、行政改革でも卓越 - 低次元の安倍政権と大違い
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/08bd9d382dd2624bd567b845d473189
▽ 政府の愚かな方針に従う地域は衰退へ、地方創生の失敗は過去の事実により容易に予想できる
ふるさと納税の倍増へ菅前首相「2兆円という目標は必要だ」(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20230819-OYT1T50154/
なぜこの人物が議員を辞めないのか不可思議だが、
総額2兆円に達すれば一部自治体が使い切れない資金が山積み必至だが
儲け倍増のふるさと納税仲介業者だけが大喜びであろう。
ふるさと納税の1人あたり受け入れ額で上位50自治体、積み立て残高が4年間で倍増…和歌山・北山村は税収20年分に(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/20231105-OYT1T50164/
菅とヒラメ官僚のお粗末な制度設計がこのような偏頗な結果をもたらした。
自治体ごとに受入額に上限を設定しないからこうなるのだ。
得をするのは富裕層と仲介業者だけ…ふるさとが潤わない「ふるさと納税」の歪んだ構図(president.jp)
http://president.jp/articles/-/76147
菅義偉の有害な制度改革のせいで「ハゲタカ」業者がたかってきて
ボロ儲けしている。こうした利益誘導政策は自民党のお家芸である。
ふるさと納税で被災地寄付、12%が経験 民間調べ(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC037G30T00C22A3000000/
ふるさと納税の制度自体には勿論、良い面もある。
災害支援はその筆頭であり、制度は公共性を考慮して改善しなければならない。
無思考で「2兆円」などと豪語し腐敗をより深刻化させるのは大罪である。
ライドシェアのような筋の悪い場当たりな政策案を出すことだけでもない。
そもそも根本的に、提唱する政策が殆ど例外なく有害なのだ。
携帯料金の値下げ圧力はまだしも害の少ない方であり、
(本来なら日本国民の所得を伸ばし、5G投資を促進する方が先決だった)
年々弊害が大きくなるのはもはや悪名高い「ふるさと納税」である。
ふるさと納税は発想としては悪くないが極一部の自治体にばかり
使い切れないカネが溜まって行く一方、しかも仲介業者が暴利を貪って
自治体に「ハゲタカ」と陰口を叩かれる始末である。
しかも地方創生どころか地方の少子高齢化と社会減(人口流出)は止まらない。
ふるさと納税は原発立地自治体の補助金のような「麻薬」のようになり果てたのだ。
▽ 長野県下條など卓越した自治体は、公務の人件費をカットして次世代育成に投資した
 | 『奇跡の村 地方は「人」で再生する』(相川俊英,集英社) |
自民党の地方創生は、「バラ撒き」しかもたらさない。
最初から分かり切った、大失敗必至であったと証明されたことになる。
「「地方創生」と聞いてすぐ思い浮かべるのは、
バブル期に自民党政権が行なった愚劣な「ふるさと創生」である。
1億円をバラまいて今は寧ろ不良債権のようになっている自治体も多い」
「今回の「地方創生」も所詮は同じである。
支持率が下がっている安倍内閣の人気取り、姑息な地方選挙対策が本質である。
ふるさと納税の税制優遇拡大や地方企業の税負担軽減などが挙がっているが、
これまでの「ふるさと創生」や地方振興策がことごとく失敗に終わったという
「不都合な事実」を直視し真摯に反省することなしに成果が出る筈はない」
「本気で地域経済の梃入れを行なおうと考えるなら、
大企業正社員や公務員の退職金の税控除を大幅縮小し、
その全額を育児世帯への現物給付に移転するのが最も効果的である」
「また、原子力発電を半永久的に凍結し、環境税を引き上げて
税収を全額コージェネ推進と木質バイオマス熱利用に投入すべきである。
エネルギー需要地では一気に熱利用が進み、
化石燃料の輸入は大幅減少、その分は内需に還流する」
「農業では日本版AOC(原産地呼称)の導入、
漁業では漁獲枠の大規模導入、林業では国産材建築の推進、
木質バイオマス・コージェネの発電分の固定価格買い取り、
食産業ではMOF(国家最優秀職人章)の導入、
我が国の政府も官庁もこうした必要な施策を全く実行していない」
「非常に豊かな田舎がある欧州では地域資源の磨き方が巧みだし、
自らの地域の良さをよく理解しているし活用法も優れている」
「うまくいった活性化策に「視察者が殺到」するのは結構だが、
視察した後、何らかの成功に結びつけた事例が皆無に等しい。
公費を使った視察に明確な成果がなければ、行政訴訟の対象とすべきである」
「「地方創生」なるバズワードは、政治感覚の鋭い者ならすぐ分かるように、
自民党政権による有権者を丸め込む地方統一選向けのプロモーションに過ぎない」
「関係閣僚は「バラ撒きにはしない」などとほざいているが、
安倍内閣の「国土強靭化」そのものが明白な業界バラ撒きなのだから、
最初の第一歩から間違っている、もしくは有権者を騙そうとしているかのいずれかだ。
(自民党の体質から見て、その両方である可能性が極めて高い)」
「直近では「地方創生」と称して東京23区の大企業の本社機能を
地方に移転すれば税優遇という、シャープ亀山工場の失敗から全く学習していない
「次元の低い」政策案を大真面目で出してきた」
「確かに企業経営の観点から言えばリスク軽減のために地方移転も必要だが、
それは「地方創生」ではない。自分を安売りする租税競争の国内版でしかない」
「「地方創生」に寄与するのは、地域の実態や特性に根づいた
付加価値創造に長けている多様な中小企業の存在である。
そのような中小企業を政府が生み出したり育てたりすることはできない」
「ただ補助金や税軽減だけで釣られてくる大企業は
自治体からいくらカネを貰えるかしか考えず、すぐに出てゆく厄介者だ」
「エリック・シュローサーはアメリカの大企業が州政府を脅し、
移転をちらつかせて州政府から更なる恩典を脅し取る実態を書いている」
「ふるさと納税の上限引き上げは悪くないが、
この程度の軽減では大した効果がないだろう」
「どうせまた、「人口減や地方経済の衰退に歯止めをかけ」るのに失敗しても
政府も与党もキャリア官僚も、誰一人として責任を取らないのは間違いない」
「「ベンチャー企業への投資優遇税制」も、これまで死屍累々の政策だ。
これまでの失策を全く反省せず有権者のカネをバラ撒きに使う
政府や与党らしい腑抜けた政策案だ」
「投資庁によって対内投資を積極的に募るスウェーデンや、
観光プロモーションが巧みな欧州国から学ぶ能力が根本的に欠如している」
「日本財団の18歳意識調査では、安倍の地方創生が
「うまくいっている」と考える者が5%にも満たない。
安倍は碌な政策を行っていないのだから、当然の帰結と言えるだろう。
(それどころか菅が「ふるさと納税」バブルと大混乱を引き起こす始末)」
「しかも若者は安倍政権下ですっかり「劣化」しており、
魅力ある大学がない、経済的メリットがない、
官庁が移転してくればいいと我が儘放題、言いたい放題である」
「公立大学としては驚くべき成功を収めた国際教養大学で
地元出身者の比率が激減して大問題になっている事実すら理解していないのだ。
国際教養大学ができて、秋田県の人口流出が止まったとでも考えているのか?
かつてのバングラディッシュのように、自らの惨状を誇張して援助を乞うのは間違っている」
「ただ、地方の若者を責めるのは正しくない。若者達は
利己的で無責任な自民党議員の悪影響を受けて歪められただけであり、
都市圏でホテルが急増しただの、経団連に調査を求めるだの責任転嫁する片山や、
若者は高齢者のために地方に行って雪かきしろととんでもない暴言を放つ自民党政務官など
真に批判されるべき対象は自民党議員であり、無責任の元凶である安倍なのである」
「周知の通り、東京圏への人口流入は23年連続で転入超過。
転入が転出をおよそ14万人も上回るという状況で、
安倍の「地方創生」は予算の無駄、役立たずという結論になろう」
「文科省の官僚のクビを握った官邸は
大都市圏の大学定員管理厳格化を強行させたが、
加計学園のような地方私大の経営陣を潤すだけで人口流出は変わらず、
矢張り腐敗した安倍らしい「利益誘導政策」の一つに過ぎなかった訳である」
「おまけに地方創生担当相の片山はこの惨憺たる結果を
「東京圏でのホテル急増」のせいだとすぐさま責任転嫁し、
経団連など経済団体に「実態調査を求める」と言い放った」
「自民党の鈴木外務政務官に至っては「雪国で若者の就農を促し」
などと若年層を将棋のコマか何かのように扱う始末。
(このような増長議員の歳費をカットして予算に充当すべきであろう)」
「中共のように国民を思い通りに動かせると勘違いしているのか、
安倍自民はまさに「頭から腐る」状況になっていることがよく分かる」
「腐った頭からは腐った政策と予算の無駄しか生じない訳で、
大失敗した安倍や菅をクビにして権力の座から駆逐するのが信賞必罰なのだが
惰眠を貪るB層が保守退嬰のため日本を衰退させる現況を延命させてしまっている」
「その結果、「地方の中小企業で働いたらカネを払う」
「AIやIoTで地方創生」という碌でもない政策案ばかり出てきており、
日本の政策の劣化は太平洋戦争時と同じ様な壊滅的状況に陥っている。。
(大失敗した参謀の責任を問わず使い続けた大本営と全く同じである)」
「「地方創生」は惨憺たる失敗で
選挙でB層を騙すための売り文句に過ぎなかった、ということだ。
14万人の転入超を13万弱に減らしたところで手柄になどなるわけがない。
予算効率・費用対効果から言えば「役立たず」以外の何ものでもない」
「大学の定員厳格化は、受験生を散々犠牲にして地方私大を助けるだけ、
人口流出は変わっていないのだから「小手先」「糊塗策」である。
人口減が予想されていたのに大学を粗製濫造した自民党が責任を誤摩化しただけの話」
「B層を騙すための案を手を変え品を変え繰り出す様は
特殊詐欺グループの手口とそっくりである。
何一つ検証せず責任も取らない詐欺政党が政権に入るとこうなるのだ。
技術を活用すること自体は結構だが、政府が音頭をとって寧ろ失敗する例は余りに多い。
(過去の経産省の大プロジェクトが死屍累々であるのがその証拠)」
「地方でも驚くべき成功を収めている自治体は複数ある。
しかし、その共通点は「地域主導」であり「政府主導」ではない。
だから政府の詐欺的な「地方創生」は常に失敗する運命なのだ」
安倍政権下で少し進んだのは地理的表示保護制度(GI)ぐらいで、他は論外という状況だ。
▽ 自治体がカネを出しても、企業は「税金を安くしなければここから出ていく」と言うだけである
 | 『ファストフードが世界を食いつくす』(エリック・シュローサー,草思社) |
▽ 海外事例の研究もしない評論家は、地方企業に法人減税すれば出生率が上がると机上の空論
 | 『日本の生き筋ーー家族大切主義が日本を救う』(北野幸伯,扶桑社) |
矢張り「「地方創生」と僭称する次元の低い政策案しか報じられず、
当ウェブログの指摘した通り、さもしい選挙対策に堕してしまうのは間違いない」結果である。
「日経記事の素晴らしいところは高齢化や少子化の影響が大きく、
観光客増の効果を打ち消してしまったと指摘している点である」
「地方創生は、真に効果があるのであれば勿論異論はないが、
安倍と自民の「地方創生」は完全に口だけのバラ撒きであり
実態は「地方衰退加速」でしかないのは厳然たる事実だ」
「これは勿論、保身と腐敗の塊である安倍自民の程度の悪さが主因だが、
政府が関わると必ずと言って良い程に地方振興策は失敗すること、
成功例を見ると悉く「政府や省庁が関わっていない地域主導型」であることから、
地方創生が失敗した理由は「政府や省庁が余計な政策で邪魔したから」なのだと言える」
「例えば日本ワインの隆盛は営々と品質改善を続けた生産者の努力と工夫のお蔭であり、
インバウンドで高い評価を受けている地域も全てボトムアップ型の成長である」
「ただ、そうした成功事例のある地域でも少子高齢化・社会減に苦しんでおり、
真の地方創生には長野県下條のような強力な人口政策が不可欠であることも
既にして明らかになっていると言えよう」
「観光で成功すること自体は良いのだが、
観光客は通常、住民よりも消費額が圧倒的に低い。
納税においても地域貢献度は低いのである」
「インバウンドでの成功例に挙げられる京都や高山の人口動態を見ても明らかなように、
人口政策なくして地方創生の成功はあり得ない」
地方衰退はそもそも自民党政権と地方自治体に原因があるのだから、
失敗に終わるのは最初から分かり切った話、戦略的・戦術的に「必敗」なのだ。
↓ 参考
「高齢化や人口減が観光客の増加を打ち消している」- 安倍の「地方創生」は大嘘、地方衰退が鮮明に
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/699090e435b39e67e95634d1e3f98c10
「地方創生はうまくいっている」僅か4.8%、安倍は嘘と失態ばかり - 自民党議員は責任転嫁に必死
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/63c62f00163729bbe3847305bbc2a024
本社移転の税優遇でも大学定員管理でも徒労に、地方創生を唱えて人口流出 - 安倍の政策は死屍累々
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/9f7064201ab6c145f6e4df28e7eec6e6
「奇跡の村」下條の出生率回復は住宅等の現物給付が主因、行政改革でも卓越 - 低次元の安倍政権と大違い
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/08bd9d382dd2624bd567b845d473189
▽ 政府の愚かな方針に従う地域は衰退へ、地方創生の失敗は過去の事実により容易に予想できる
 | 『反骨の公務員、町をみがく---内子町・岡田文淑の町並み、村並み保存』(森まゆみ,亜紀書房) |
ふるさと納税の倍増へ菅前首相「2兆円という目標は必要だ」(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20230819-OYT1T50154/
”自民党の菅前首相は19日、長野市で講演し、総務相時代に提唱した「ふるさと納税」の規模について、「総額2兆円という目標は必要だ。自然にそうなっていくことが望ましい」と述べた。〔以下略〕”
なぜこの人物が議員を辞めないのか不可思議だが、
総額2兆円に達すれば一部自治体が使い切れない資金が山積み必至だが
儲け倍増のふるさと納税仲介業者だけが大喜びであろう。
ふるさと納税の1人あたり受け入れ額で上位50自治体、積み立て残高が4年間で倍増…和歌山・北山村は税収20年分に(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/20231105-OYT1T50164/
”ふるさと納税制度で、2022年度に人口1人あたりの寄付受け入れ額が多かった上位50市町村の「特定目的基金」の残高(21年度末)が1905億円に上り、17年度末比で倍増していることが、読売新聞の調査でわかった。財政規模に対し、寄付金が多すぎることが理由で、多くが基金の具体的な使途を決めないまま積み上げ続けている。急増する寄付金を有効活用できていない実情が浮かぶ。
〔中略〕
総務省の公表データを分析すると、全1741市区町村の特定目的基金の21年度末残高は計8兆4857億円で、17年度末から6793億円(8.7%)増えていた。22年度に人口1人あたりの寄付額が多かった上位50市町村で見たところ、計1905億円で17年度末(計962億円)から98%増。全市区町村と比べ、伸び幅が際立っていた。
また、自治体の財政規模を示す地方税収と比較すると、50市町村は2年9か月分に相当する基金を積み立てていることになり、こちらも全市区町村(5か月分)を上回る規模だった。1人あたりの寄付額が229万円と最も多かった和歌山県北山村は、税収20年分以上の金額を積み立てている。
全国の自治体が受け入れた寄付総額は、22年度に9654億円に上り、3年連続過去最高を更新。50市町村は人口ベースで日本の0.4%にすぎないが、寄付総額の17%(1693億円)が集中している。
基金残高が増えているのは、財政規模に対し、寄付が多すぎるためだ。50市町村に取材したところ、具体的な使途予定を回答した自治体は7市町にとどまった。
総務省は「自治体には寄付金の使途を明確にするよう求めている。有効に使われていないのであれば問題だ」としている。”
菅とヒラメ官僚のお粗末な制度設計がこのような偏頗な結果をもたらした。
自治体ごとに受入額に上限を設定しないからこうなるのだ。
得をするのは富裕層と仲介業者だけ…ふるさとが潤わない「ふるさと納税」の歪んだ構図(president.jp)
http://president.jp/articles/-/76147
”■浮き彫りになった「ふるさと納税」の問題点
「官製ネット通販」と揶揄され、1兆円規模にまで膨れ上がった「ふるさと納税」。年末のかきいれ時を迎え、1000万人近くにまで広がった利用者が「おとくな返礼品」を探し求めて、あまたの「ふるさと納税サイト」をはしごしている。
地方自治体も、地場産業も、寄付者も、「三方一両得」の制度として始まったふるさと納税だが、市場の拡大とともに本来の趣旨が忘れ去られ、さまざまな問題点が浮き彫りになってきた。
今、利用者が寄付した税金のうち1500億円規模にも上る巨額のマネーが、全国の自治体とは無縁の東京の仲介サイト業者などに掠め取られている実態をご存知だろうか。善意の寄付が制度につけ込んだ民間業者の懐に入ってしまっているのだ。
もう一つ。高額所得者ほど寄付額の上限が高くなる仕組みを使って合法的な節税対策として利用されていることを承知しているだろうか。納めるべき所得税や住民税が肉や魚の返礼品にすり替わり、住んでいる自治体に納付されず住民サービスに支障をきたしているのである。
〔中略〕
ふるさと納税を主唱した菅義偉前首相は「2兆円」を目標に掲げたが、規模が大きくなることは弊害も大きくなることにつながる。
ふるさと納税が健全な制度として持続的に発展するためには、小手先の手直しではなく、原点に立ち戻る抜本的な改革を行わねばならないタイミングを迎えている。
〔中略〕
ふるさと納税は、「自分のふるさとや縁のある地域に寄付(納税)して、元気になってもらおう」という趣旨の寄附金税制の一つで、2008年にスタートした。
政策的に言えば、地方と大都市の格差是正や人口減地域における税収減対策を、自治体と庶民の間で進めようというもので、個人が納める税の一部移転ということになる。税法上は、寄付額を住民税から控除する仕組みで、当初の上限は住民税のおおむね1割、現在はおおむね2割。所得税も、税率に応じて一部控除される。ただ、寄付しようとすれば2000円の自己負担金が持ち出しになる。
税収の少ない地方自治体が自由に使える寄付金で少し財源が潤い、販路が限られていた地場産業は返礼品需要で少し活性化し、ふるさとに貢献したくてもなかなかできなかった利用者が少し満足感を味わい返礼品まで受け取って少し得した気分になるという、「三方よし」の制度といえた。
〔中略〕
知る人ぞ知る制度で、11年に東日本大震災で被災自治体への寄付が急増したものの、しばらくの間は、寄付者は10万人余り、総額も100億円余りで推移していた。
■寄付金の獲得競争が全国に広がった
ところが、地場の特産品を返礼品としてふるさと納税を募る自治体が現れるようになり、その動きはやがて全国に広がって寄付金獲得の競争が始まった。
いつのまにか、寄付金を集めること自体が目的化し、もともとの狙いが変質していったのである。
そして2015年。寄付できる金額の上限が倍増(住民税控除額の上限を1割から2割に引き上げ)し、確定申告が不要となるワンストップ特例の導入で手続きが簡略化されると、事情が一変する。
ふるさと納税がにわかに注目を集め、利用者の意識も様変わり。返礼品が税金の還元策になることがわかると、自らのふるさとへの貢献など置き忘れ、ネットに並ぶ返礼品の品定めに血眼になった。高額返礼品を受け取り実質的な節税にいそしむ高額所得者の姿も目立つようになった。
寄付者は100万人を超え、寄付総額は一気に1500億円規模にまで膨れ上がった。
そうなると、利用者の関心を誘うためには地場の特産品だけでは足りず、地場産業以外の返礼品や地場産業とは関係のない商品券や金券まで提供する自治体も現れ、「寄付金争奪戦」はますますエスカレートした。
■仲介サイト業者が続々と参入
とはいえ、ビジネスとは無縁の地方公務員が、十分な実務のノウハウを持ち合わせているわけもない。
そんな事情に目をつけたのが、ネット通販などに長けている中央の民間業者だった。最初に仕掛けたのはベンチャーの「ふるさとチョイス」で、IT企業アイモバイル系の「ふるなび」、ソフトバンク系の「さとふる」、「楽天ふるさと納税」の楽天など、大手業者が続々と「ふるさと納税サイト(仲介サイト)」事業に参入した。本来、自治体が行わなければならない実務を、業務委託として請け負い、仲介手数料を得るなど、さまざまな形で全国の自治体に関与していったのである。
どの仲介サイトも、自治体ごとの返礼品はもちろん、肉・魚・果物・民芸品などにジャンル分けされ寄付額に応じて整理された全国の返礼品が一目でわかる「ふるさと納税サイト」を展開し、利用者を寄付に誘った。
〔中略〕
■利用者は300倍、寄付総額は約120倍に急拡大
ふるさと納税の22年度の利用者は891万人で、スタートした08年度の3万人余りに比べると実に約300倍。寄付件数は5184万件と14年連続で過去最多を更新し、寄付総額は9654億円にまで膨れ上がった。08年は81億円だったから約120倍に膨張、この3年間に限っても倍増している。
寄付受入額トップの自治体は、宮崎県都城市で約196億円。北海道紋別市約194億円、同根室市約176億円、同白糠町約148億円、大阪府泉佐野市約138億円、佐賀県上峰町約109億円と、「100億円自治体」が続く。
昨今は過大に集まった寄付金の使い道に苦慮する「うれしい悲鳴」を上げる自治体も出ているという。
一方、利用者の大半を抱える大都市圏では、本来入ってくるはずだった多額の住民税が地方の自治体に流失し、住民サービスに支障が出始めるようになった。寄付に伴う23年度の住民税の減収総額(いわゆる「赤字」)は全国で6798億円となり、もっとも多い横浜市は272億円に達する。名古屋市、大阪市、川崎市も軒並み100億円を超える。こちらは、本当の悲鳴だ。
〔中略〕
こうなると、話は違ってくる。
当初は静観していた総務省だが、各方面からさまざまな問題点が指摘されるようになって、規制策を打ち出さざるを得なくなった。
まず19年に、「返礼品は地場産品に限り調達費は寄付額の3割以下」(3割ルール)、「返礼品+経費の総額は寄付額の5割以下」(5割ルール)という「御触れ」を出し、ルールを遵守した自治体のみがふるさと納税を実施できる制度(指定制度)を導入した。
たとえば、寄付金が10万円の場合、返礼品の調達費は3万円以下、送料や仲介サイトに支払う手数料、広告費などを含めた総経費は5万円以下に抑えなければならなくなった。寄付額のせめて半分は自治体に入るよう指導したのである。
ところが、仲介サイトのPR合戦にもあおられて、返礼品競争はヒートアップ。「御触れ」を無視するかのように、高額の返礼品を提供したり、多額の経費をつぎ込む自治体が続出。読売新聞の調べによると、21年度に「5割ルール」を超えた自治体は138市町村に上ったという。
さらに、新たな問題が露見する。仲介サイトが、「5割ルール」の枠外として、システム管理費や顧客情報管理費など「募集外(ボガイ)」と称するさまざまな手数料を、自治体から広く徴収していたことが判明したのだ。
■小手先の対策では不十分
また、これまで「5割ルール」の対象外だった、自治体が発行する寄付金受領証やワンストップ特例に関わる事務費も、無視できない額になってきた。
こうした「隠れ経費」を含めると、多くの自治体が「返礼品+経費」が5割を超えてしまうという。
このため、総務省は10月から、経費の算定基準を厳格化して「隠れ経費」をすべて加え、地場産品の基準も厳しくした「新5割ルール」の実施に踏み切った。
しかし、いずれも小手先の対策に過ぎず、とても抜本的な見直しとは言い難い。
あらためて、ふるさと納税の問題点を整理してみる。
①巨額の税金が仲介サイト業者に流出している
②業者に支払う経費の算定基準や内容が不透明
③高額所得者ほど実質的な節税効果が大きい
④返礼品や経費のコストが重く、寄付額の半分程度しか自治体に入らない
⑤地場産品の人気度によって寄付金受け入れの自治体間格差が大きい
⑥大都市圏の自治体は流出額が大きく、住民サービスに支障が出ている
⑦利用者の大半は返礼品目当てで、ふるさとへの貢献という理念がかすんでいる
⑧ふるさと納税に絡んだ不祥事が続発し、贈収賄のような刑事事件まで起きている
など、枚挙に暇がない。
ふるさと納税の寄付総額が100億円前後の10年前ならともかく、今や市場は1兆円規模となり、さらに拡大が見込まれるだけに、どれをとってももはや看過できなくなった。
■寄付額の15%抜き取られる…仲介業者に逆らえなくなった地方自治体
とくに、重要な問題点を深掘りしてみる。
まず①と②について。
「5割ルール」では、返礼品の調達額は3000億円程度、経費は2000億円程度になるが、経費のうちかなりの額が仲介手数料や決済手数料、顧客リスト管理費、販売促進費、広告宣伝費などの名目で、仲介サイトの運営業者に支払われている。
寄付金受け入れ額ランキングに名を連ねる九州のある自治体の担当者によると、あれやこれやで仲介サイト業者に支払う金額は寄付額の15%程度に上り、しかも手数料などの料率は仲介サイト業者から一方的に提示され、不満を感じても交渉の余地はほとんどないという。
担当者に言わせれば「無垢(むく)な自治体を食い物にするハゲタカ業者が巨額の税金をかすめとっている」となる。つまり、全国では1500億円にも上る税金が、ふるさととは無縁の仲介サイト業者の懐に収まってしまっているのだ。ふるさとへ寄付したつもりの利用者にすれば、実に不快で由々しき問題と言わざるを得ない。
〔中略〕
次に③について。
ふるさと納税における住民税の控除の上限(寄付金の実質的な上限)は、2割の定率のため、高額所得者ほど寄付の上限額が飛躍的に大きくなる。
ちなみに、22年の世帯平均年収546万円(厚生労働省・国民生活基礎調査)の場合、上限額は概算で6万円(夫婦の場合、家族構成により異なる、以下同じ)になる。
もっとも多いのは年収200万~300万円世帯だが、300万円世帯の上限額は概算で1万8000円だ。
これに対し、年収が1000万円なら約17万円、1500万円で約40万円、2000万円で約56万円、3000万円は100万円余り、5000万円になると200万円を超す寄付ができてしまう。寄付額の3割は返礼品となって戻ってくるので、その分が実質的な節税となる。
逆進性がきわめて高く、税の公平原則からみれば極端な不均衡が生じている。つまり、「金持ちほど得をする制度」なのである。当初から指摘されていた制度上の欠陥で、素直に受け入れられる利用者がどれほどいるだろうか。
④以下は、寄付金目当ての返礼品競争が招いた結果であり、自治体が税収を奪い合う構図は歪んでいるとしかいいようがない。
■富裕層の節税に歯止めをかけるべきだ
では、どうするか。
制度上の欠陥や抜け穴は、根本的に是正しなくてはならない。
まず、手がけやすいところでは、寄付額の上限(税額控除の上限)を「定率」に加えて新たに「定額」を設けることだろう。
約1000万人の利用者が約1兆円を寄付している現状から計算すると、1人当たりの平均寄付額はざっくり10万円。これは、年収約700万円の世帯の上限額に相当する。2割の上限率はそのままで、上限額としてたとえば10万円を設定すれば、全世帯の7割を占める年収700万円未満の世帯には影響がなく、一方で、節税にいそしむ高額所得者の多額寄付に歯止めをかけることができる。そうすれば、庶民の怨嗟の声も少しは鎮められるかもしれない。
〔中略〕
■最大の問題は、仲介サイト業者への税金流出
次に着手できるのが、経費の抜本的見直しだ。
総務省は、自治体に入る寄付金を寄付額の半分程度を目安にしているが、少なすぎる。経費などを差し引いて、少なくとも7割、できれば8割は残らないと、本旨に反するのではないか。「返礼品+経費」を「3割以下」に抑えるようにすべきだ。
仲介サイト業者への税金の巨額流出は、現在の最大の問題ともいえる。
民間の仲介サイト業者を規制することは容易ではないが、自治体の経費の使い方に厳しいガイドラインを設けることは難しくないだろう。
一つの方策として、地場以外の業者に支払う経費に上限を設けてはどうだろうか。たとえば、仲介サイトの大手業者に10%以上も支払っている仲介手数料の上限をクレジットカード並みの3%程度に抑えることが考えられる。
その結果、不満をもった仲介サイト業者が手を引いたとしても、ふるさと納税の仕組みが崩壊するわけではない。
〔中略〕
そして、できることなら、経費の支出先は地元の業者(自治体レベルにとどまらず県レベルも含む)に限るべきだろう。それは、地域が潤うことと同義語だ。
〔中略〕
■ふるさと納税サイトは「カタログ通販」になっている
仮に大手業者の仲介サイトがなくなった場合、総務省は、県や有力自治体が主導して県レベルのささやかな仲介サイトを地元業者に委託する代替策を推奨してはどうだろうか。
利用者には不便になるかもしれないが、「カタログ通販」化した「ふるさと納税サイト」を眺めて、ショッピング感覚で寄付している現状を見つめ直す契機になるのではないか。
〔中略〕
爆発的に拡大しているふるさと納税だが、あるべき姿は、「寄付金争奪戦」でもなければ、「官製ネット通販」でもない。
スタートから15年経った今、創設の趣旨に立ち戻る「勇気」が求められている。
----------
水野 泰志(みずの・やすし)
メディア激動研究所 代表
1955年生まれ。名古屋市出身。早稲田大学政治経済学部政治学科卒。中日新聞社に入社し、東京新聞(中日新聞社東京本社)で、政治部、経済部、編集委員を通じ、主に政治、メディア、情報通信を担当。2005年愛知万博で博覧会協会情報通信部門総編集長を務める。日本大学大学院新聞学研究科でウェブジャーナリズム論の講師。〔以下略〕”
菅義偉の有害な制度改革のせいで「ハゲタカ」業者がたかってきて
ボロ儲けしている。こうした利益誘導政策は自民党のお家芸である。
ふるさと納税で被災地寄付、12%が経験 民間調べ(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC037G30T00C22A3000000/
”ふるさと納税仲介のトラストバンク(東京・渋谷)はふるさと納税を活用した災害支援の実態調査をまとめた。地震や豪雨の被災地に寄付をしたことがある人は12%だった。このうち66%は2回以上活用しており、5回以上も14%いた。「今後してみたい」人は26%だった。
同社が2月下旬、20歳以上の全国1010人に聞いた。災害支援としてふるさと納税の寄付ができることを知っている人は54%だった。
寄付経験者に初めて被災地に寄付をした時期を尋ねると、東日本大震災があった11年が15%で最も多く、次いで熊本地震があった16年、西日本豪雨などがあった18年がそれぞれ11%で多かった。静岡県熱海市の土石流災害などがあった21年は10%だった。〔以下略〕”
ふるさと納税の制度自体には勿論、良い面もある。
災害支援はその筆頭であり、制度は公共性を考慮して改善しなければならない。
無思考で「2兆円」などと豪語し腐敗をより深刻化させるのは大罪である。