2014年7月9日、高級オーディオメーカーとして知られた山水電気が破産手続きを開始し、完全消滅した形になった。とはいえ同社は90年代には業界の第一線から退いており、ブランド名が残っていただけで、このニュースを聞いても今さら何の感慨も無い。
ただ、あらためて思うのは、企業の命運というのは各従業員が握っているものではなく、トップの資質次第だということだ。
同社は1944年に創業。当初は電源トランスの生産・販売を手掛けていたが、60年代末にリリースした海外向けオーディオ用レシーバー(アンプとチューナーが一体化したもの)が評判になり、それから事業の中心をオーディオ機器(特にプリメインアンプ)に移した。70年代から80年半ばまでが全盛期で、トリオ(現JVCケンウッド)やパイオニアと並んで“オーディオ御三家”と呼ばれ、一世を風靡したものだ。

ところが商品ラインナップをアンプに固定化したせいで、デジタル化の波に乗り遅れる。さらには目先の資金繰りのために海外ファンドの傘下に入るが、それらのファンドが次々に破綻。いよいよ経営が行き詰まっていく。世の中がバブルに踊ってどこの企業も好業績だった89年にはすでに赤字だったというのだから、呆れたものである。
とうとう90年代末には“本業”を見捨てるハメになってしまうのだが、この会社の経営陣は最後まで前向きなマーケティングを打ち出すことは無かった。
いくら特定分野で実績を出そうとも、常に世の中のトレンドを読み、それに合わせた提案を絶えずしていくことこそ企業の生き残る道だ。山水電気はそれが出来なかった。もちろん、特定のコアなユーザー向けに手の込んだ商品を少量作り続けるやり方もあっただろう。しかし、東証一部に上場を果たしたような企業に、そういうガレージメーカーみたいな小回りの利く方法論を採用することは出来ない。この会社が破綻したのは、まあ当然だ。
一番馬鹿げていると思ったのは、山水電気は87年に金を掛けてCI(コーポレートアイデンティティ)を実施し、ロゴを変更したことだ。CIというのは、アサヒビール等に代表されるように、新しい商品やサービス、または新しい企業理念や体制を打ち出す時に併用されるものである。ところが山水電気は単にロゴマークを変更しただけ。しかも、商品デザインやラインナップはほとんど変わらない。さらに言えば、その新しいメーカーロゴは全然垢抜けてはいなかった(前の方が良かった)。一体何のためのCIだったのか。

おそらく当時の経営陣は“CIというものが流行っているから、自分のところでもやってみよう”という安易な気持ちで実施したのだろう。その資金や労力を新しいコンセプトの商品開発に振り向けていれば、少しは違っていたのかもしれない。
さて、私はこのメーカーのアンプを使ったことは一度も無い。もちろん、歴代の製品は何度も試聴している。しかし、どれも好みに合わなかった。たぶんこの重々しい音が好きな人はけっこういたのだろう。ただし個人的には、安いクラスはONKYOに、上級機器はACCUPHASEやLUXMANの製品に、完全に負けていると思ったものだ。
余談だが、私はなぜかSANSUIのチューナーは保有していたりする(笑)。別にこのメーカーの製品が好きであったということではなく、たまたまチューナーの更改時期において手頃なモデルがこれしか店頭に無かったので買い求めただけの話。何度か故障して修理に出したが、今でもちゃんと動いてくれる。フルサイズのチューナーが市場にあまり存在しないことを考え合わせると、たぶん“寿命”になるまで使い続けると思う(^^;)。
ただ、あらためて思うのは、企業の命運というのは各従業員が握っているものではなく、トップの資質次第だということだ。
同社は1944年に創業。当初は電源トランスの生産・販売を手掛けていたが、60年代末にリリースした海外向けオーディオ用レシーバー(アンプとチューナーが一体化したもの)が評判になり、それから事業の中心をオーディオ機器(特にプリメインアンプ)に移した。70年代から80年半ばまでが全盛期で、トリオ(現JVCケンウッド)やパイオニアと並んで“オーディオ御三家”と呼ばれ、一世を風靡したものだ。

ところが商品ラインナップをアンプに固定化したせいで、デジタル化の波に乗り遅れる。さらには目先の資金繰りのために海外ファンドの傘下に入るが、それらのファンドが次々に破綻。いよいよ経営が行き詰まっていく。世の中がバブルに踊ってどこの企業も好業績だった89年にはすでに赤字だったというのだから、呆れたものである。
とうとう90年代末には“本業”を見捨てるハメになってしまうのだが、この会社の経営陣は最後まで前向きなマーケティングを打ち出すことは無かった。
いくら特定分野で実績を出そうとも、常に世の中のトレンドを読み、それに合わせた提案を絶えずしていくことこそ企業の生き残る道だ。山水電気はそれが出来なかった。もちろん、特定のコアなユーザー向けに手の込んだ商品を少量作り続けるやり方もあっただろう。しかし、東証一部に上場を果たしたような企業に、そういうガレージメーカーみたいな小回りの利く方法論を採用することは出来ない。この会社が破綻したのは、まあ当然だ。
一番馬鹿げていると思ったのは、山水電気は87年に金を掛けてCI(コーポレートアイデンティティ)を実施し、ロゴを変更したことだ。CIというのは、アサヒビール等に代表されるように、新しい商品やサービス、または新しい企業理念や体制を打ち出す時に併用されるものである。ところが山水電気は単にロゴマークを変更しただけ。しかも、商品デザインやラインナップはほとんど変わらない。さらに言えば、その新しいメーカーロゴは全然垢抜けてはいなかった(前の方が良かった)。一体何のためのCIだったのか。

おそらく当時の経営陣は“CIというものが流行っているから、自分のところでもやってみよう”という安易な気持ちで実施したのだろう。その資金や労力を新しいコンセプトの商品開発に振り向けていれば、少しは違っていたのかもしれない。
さて、私はこのメーカーのアンプを使ったことは一度も無い。もちろん、歴代の製品は何度も試聴している。しかし、どれも好みに合わなかった。たぶんこの重々しい音が好きな人はけっこういたのだろう。ただし個人的には、安いクラスはONKYOに、上級機器はACCUPHASEやLUXMANの製品に、完全に負けていると思ったものだ。
余談だが、私はなぜかSANSUIのチューナーは保有していたりする(笑)。別にこのメーカーの製品が好きであったということではなく、たまたまチューナーの更改時期において手頃なモデルがこれしか店頭に無かったので買い求めただけの話。何度か故障して修理に出したが、今でもちゃんと動いてくれる。フルサイズのチューナーが市場にあまり存在しないことを考え合わせると、たぶん“寿命”になるまで使い続けると思う(^^;)。













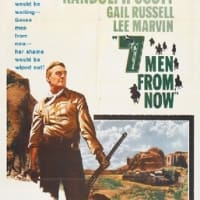














なんと言いますか、某漫画風に言えば「~年前からずっと瀕死だったサンスイが、今やっと死んだのだ」というところでしょうか
>いくら特定分野で実績を出そうとも、常に世の中のトレンドを読み、それに合わせた提案を絶えずしていくことこそ企業の生き残る道だ
まさにガラパゴス化の典型でしょうか
ピュアオーディオはずっとホームシアターに食われ続けているわけですから
ここでスマホ並みのブレイクスルーが必要なのかもしれません
私はピュアオーディオは「世界観」そのものだと思います
「まさにその場に居合わせている」というのも世界観でしょうし
WEやALTEC愛好家の「こまかいことはいいから魂を直撃する音楽を追究」というのも世界観でしょう
そういえばブログ主様は、最近価格で誰かに噛みつかれませんでしたか?
でも、あの人たちももう終わりなんじゃないかと思います
本当に求めているものは「銀箱」でモノラルジャズを浴びるように聞く、と言うことなんだと思いますが
「まがいもの」や奇怪な道具で、似て非なる世界を作ってしまいましたから
すなおにヴィンテージ礼賛して、ケーブル売りながら出物が出たら融通して、「こういう世界もあるんだ」という姿勢ならまた違った展開もあったんでしょうが・・・
ある時代の終わりをしみじみ感じます
長文失礼しました
どちらかというとTechnicsやSONY、VICTOR、Lo-Dといった“御三家”以外のブランドの方が積極的な新規提案をしていました。PIONEERやKENWOODが今でもかろうじて生き残っているのは、カーナビというピュア・オーディオではないプロダクツのおかげです。思えば、この3社の業界内でのガラパゴス化は往年のオーディオ全盛期に端を発していたのでしょう。
それにしても、昔はこの“御三家”のように一部上場を果たした規模の大きな企業が、(いくらブームだったとはいえ)オーディオに特化したような商品ばかりを揃えていたというのは、ある意味無謀でしたね。ピュア・オーディオ機器というのは(今の内外の専門メーカーがそうであるように)小回りが利く程度の事業規模の企業体が手掛けるものなのかもしれません。
>最近価格で誰かに噛みつかれませんでしたか?
あそこの掲示板ではしょっちゅう誰かに噛みつかれていますが(爆)、こっちも調子に乗って相手していると、互いに書き込み削除の憂き目にあうというパターンが多いですね(苦笑)。
時折思うのですが、“ALTECのユニットを銀箱に入れて鳴らす”とか“JBLの4343をマルチで駆動する”とかいった昔ながらのマニアのやり方を、今でも“至高のもの”か何かのように信じ、その方法を他人に無理に奨めてくる人がいますけど、あれって一種の迷惑ですよね。
確かに良い音で鳴っている銀箱入りのALTECのシステムに遭遇したこともありますが、すべての人があの音で満足するかというと、そうではないわけで・・・・。ましてやJBLなんて、もろに聴き手を選びます。昔は国内で販売されているスピーカーの音色の多様性が小さかったせいで、自分好みの音を追求しようとすると、いきおい“ユニットと箱とを個別調達してのマルチドライブ”に行かざるを得なかったのかもしれませんけど、ヴァラエティに富んだ音色を持つブランドが多数入っている現在においては、それは古いやり方だと感じます。
そういえば、山水電気はJBLの輸入代理店として名を馳せました。すでにブランドが有名無実化していたとはいえ、同社の存在が今回消え去ってしまったのは、ひとつの時代の終わりを象徴していたのかもしれません。
それでは、今後ともよろしくお願いします、
いつも興味深い投稿をありがとうございます。
山水のロゴ変更、私もはっきり覚えています。前の方が良かったというのも全く同じ印象でした。私の友人がα607LEXを所有していた(ロゴ変更から少し経って出たもの?)ので聴いたことはあるのですが(20年前ですが)、この頃私はオーディオ初心者ということもあり、高級機器は良い音がするなぁと思ったと記憶しています。音楽をいい音で聴く喜びを教えてくれた機器の一つですので、個人的には思い入れがあるメーカーでした。
元副会長さまも以前から書かれていますが、国内大手メーカーで長らく生き残っているメーカーでさえ、省電力、省スペースの方向性を打ち出したピュアオーディオは相変わらず出ないですね。
常に世の中のトレンドを読み、それに合わせた提案を絶えずしていくこと、企業にとってこのことはますます重要性が増していると思います。今やそれをガレージメーカーがやってくれているので本当に有り難いです。
ロゴ変更といえば、PIONEERも98年に実施しているんですよね。“創立60周年”という名目でしたが、こっちも個人的には前の方が良かったような気がします。
本文にも書きましたが、CIというのは顧客や市場に対する新しいアクションやアピールを伴ってこそ意味があるもので、単に“ハヤリだから”とか“創立○○周年だから”とかいう自分たちの都合だけで断行しても、効果は薄いでしょう。
省電力・省スペースのピュア・オーディオ機器は、なかなか品目数が増えませんね。大手ではわずかにTEACがトライしているようですが、その試みは他社には広がっていないように思います。
そういえば、SANSUIに籍を置いていた技術者が主宰するガレージメーカーに「イシノラボ」がありますが、あそこのアンプはコンパクトサイズですね。型番もSANSUIと同じ「AU」が使われていて、興味をそそられます。何とか一度は聴いてみたいと思います。
それでは、今後ともどうかよろしくお願いします。