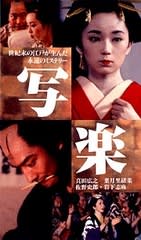95年作品。江戸・寛政年間に突如あらわれ、100余枚の革新的な浮世絵を残し、わずか1年で消えた謎の絵師・東洲斎写楽の人物像に迫ろうとする篠田正浩監督作品。原案と製作総指揮はフランキー堺で、35年以上あたためた企画とか。
冒頭、歌舞伎「蘭平物狂」の舞台で、脇役を演じる主人公とんぼ(真田広之)が足にケガをするくだりが描かれるが、この場面だけで観るのがイヤになった。歌舞伎のわくわくするような高揚感とエロティシズムがまったくない。役者の顔の上から無粋なタイトルを載せるという暴挙も相まって、作者は歌舞伎を全然愛していないことがわかる。
大手版元の蔦屋(フランキー堺)の儲け話に乗ってとんぼは“写楽”という名で役者絵を描き始めるのだが、致命的なことに、絵を描くシーンの盛り上がりはない。どうして主人公が特異な画風を身につけたのかの説明もないし、なぜ絵を描きたいのかも示されない。歌麿(佐野史郎)や北斎(永澤俊矢)など他の絵師の描写も通り一遍で、深く突っ込もうという気もないらしい。「美しき諍い女」「マルメロの陽光」など、画家が絵を描く際の切迫感を描いて圧倒させる欧米の秀作群と比べて、何と無神経でいいかげんな処理だろう。作者は絵画も愛していない。
岩下志麻扮する大道芸人の女座長、葉月里緒菜演じる花魁、片岡鶴太郎扮する十遍舎一九など、当時の江戸町民を代表させるキャラクターは、ほとんど真面目に描く気もないと思うほど印象が薄い(特に葉月はヒドイ。どこが花魁だ。ファッション・ヘルス嬢にしか見えないぞ)。作者は江戸町民文化も愛していない。
そして行きあたりばったりなドラマ展開、演技指導の不在、工夫のかけらも見られないカメラワーク、ド下手な合成処理など、そもそも映画を撮る気があるのか疑わしい。しかも2時間20分というバカ長さ。何考えてるんだ。ホントに何考えてるんだよ。
「北斎漫画」(81年)とか「歌麿/夢と知りせば」(77年)などの過去の力作とは比べようもない超低レベルの映画だ。篠田正浩監督は出来不出来が激しいけど、これは最低の部類だろう。