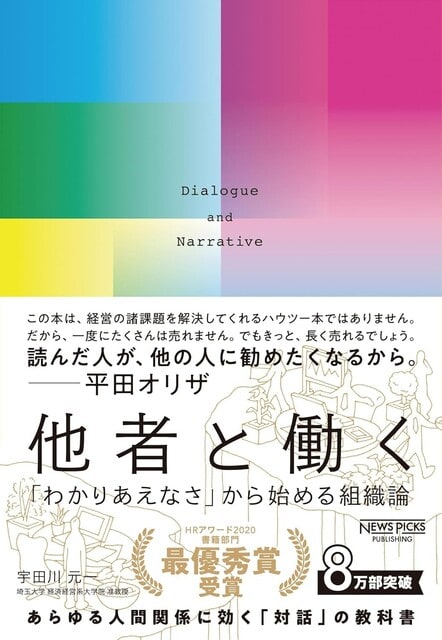30年近く前の刊行でいささか古いが、16世紀以降、砂糖がいかに世界商品化されていったかが分かりやすく記述されている名著。大航海時代、植民地のプランテーションと奴隷制度の仕組み、三
角貿易の構造、産業革命などに触れられ、世界経済史の絶好のケーススタディといえる。
現代社会では、本書で取り上げられた砂糖やチョコレートのみならず、あらゆる製品、食品、サービスが世界商品化され、まさにグローバルバリューチェーンの中で生産され、消費されている。世界商品化は光と影の部分が常にセットであり、現代においても、影の一面として児童労働や強制労働などの問題もあり、砂糖のプランテーションの例と相似形ともいえる。現代との連続性を意識させられる。
グローバライゼーションは、これからも不可逆的に進行していくだろうから、影の部分をどう克服していくのかというのが課題になる。
教科書的なことを言ってもしょうがないかもしれないが、ステークホルダーとして企業の責任は大きく、様々なSDGsにおける行動目標を地道に実直に進めて行くことが大切だろう。
余談だが、過去記事になるが、2011年2月に、好きなビートルズの聖地巡礼目的でイギリス・リバプールを訪れた。その際に、偶然「International Slavery Museum | National Museums Liverpool (liverpoolmuseums.org.uk)」(国際奴隷博物館)という博物館があることを知り、立ち寄ったのだが、そこでは本書で言うリバプールを起点とした奴隷の三角貿易について、かなり詳しく展示されていた。
アフリカの黒人文化の紹介、奴隷貿易の実態、リヴァプールとの関わり、プランテーションでの奴隷の生活、黒人開放の歩み、そして現代での黒人の活躍ぶりが、模型やコンピュータグラフィックも活用して、物語、歴史的遺品、フィルム、パネルなどによって語られている。なかなか行く機会は少ない都市だとは思うが、もし訪ねる機会があったら、奴隷博物館訪問もお勧めしたい。ロンドンからも2時間ちょっとで行ける。
(付録)以下、印象に残った部分を引用。
・1)さとうきびの栽培には、膨大な人数の、命令の行き届きやすい労働力が必要と言う事と2)それが地味、つまり、土地の植物を育てる能力を急速に失わせる作物であったと言うことが、・・・さとうきび栽培は、早くから奴隷のような強制労働を使い、プランテーションの形を取る大規模な経営が取られ、新しい土地と労働力を求めて、次々と移動していったのです。(p.28)
・イギリスのリバプールを出発した奴隷、貿易船は、奴隷と交換するために、アフリカの黒人王国が求める鉄砲やガラス玉、綿織物などを持っていきました。それらを西アフリカで奴隷と交換したわけです。ついで、獲得した奴隷を悲劇の中間航路に沿って輸送し、南北アメリカやカリブ海域で売り、砂糖(稀に綿花)を獲得して、リバプールに帰るのでした。奴隷貿易を中心とする三角貿易によって、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカの3大陸は、初めて本格的に結びつけられたのです。(pp55-56)
・ 砂糖入り紅茶の朝食は、いわば地球の両側から持ち込まれた、2つの食品によって成立しました。言い換えれば、イギリスが世界商業の(中核)の位置を占めることになったからこそ、このようなことが可能になったのです。都市から始まったイギリス風朝食は、やがて農村にも広がっていきます・・・イギリス国内の農民の作る穀物などより、奴隷の作る砂糖の方が、地球の裏側から運んできたとしても、安上がりになったということです(p170)
・ カリブ海にいろいろな産業が成立しなかったのは、・・・この地域が世界商品となったさとうきびの生産に適していたために、ヨーロッパ人がここにプランテーションを作り、モノカルチャーの世界にしてしまったことが、大きな原因だったのです。カリブ海で砂糖のプランテーションが成立したことと、イギリスで産業革命が進行したこととは、同じ1つの現象だったのです。(p206)