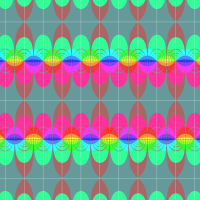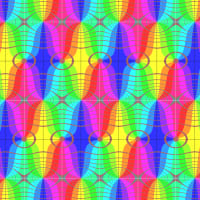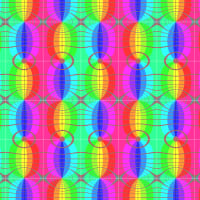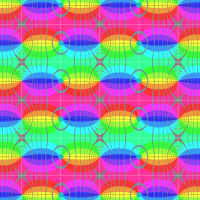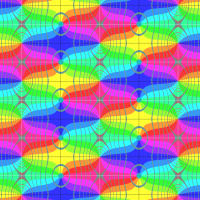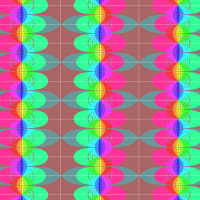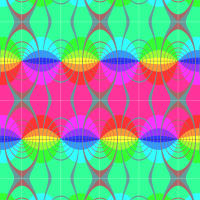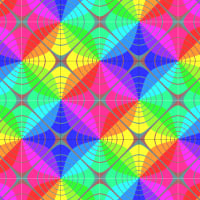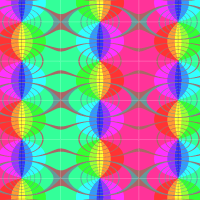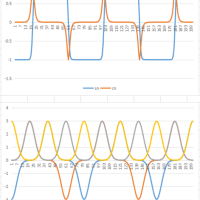本日は午前出張で、作業自体は普通。しかし交通の接続が良くなくて昼休みがたっぷりと取れて、帰社時間が遅れてほぼそのまま帰宅しました。
その昼休みの時間に20年前の自作のポリゴン表示の幾何学模型のプログラムを見直して、と。
正20面体と正八面体の頂点座標は簡単に算出できます。しかし、どの点とどの点が辺になっていて、どの辺がどの面に属していて、両隣はどの面が接していて、などは自明ではありません。なので紙で模型を作って接続を確かめ、それを数値表に置き換えて行きます。
この作業が強引に思えたのか、開発ノートが同梱されている(作者は私)のですが、かなりやけ気味の文章になっていて笑えます。今から考えると、確かにもう少々は数学的に洗練された言い方になるものの、作業自体は同様と思えるからです。
ですから、プログラムを見直してもOpenGLの本当に基礎部分しか使っていません。一応、プログラミングガイドは読み返す予定ですが、ちょっと気になっていた部分を追加する程度になると思います。
こうした、学習用分子模型程度のグラフィックの需要はそれなりにあると思えます。が、先に指摘したように新しい解説書はなかなか見当たりません。本ブログが適切な場所とは思えないので、どうするか思案中です。
ちなみに、1980年代に一応グラフィックが出てくる程度の8bitパソコンが流行した頃には、普通の行番号BASICで簡単なグラフィックを楽しむ本がいくつか出ていました。
最近も表計算ソフトで図形表示をする本が出版されましたが、あっという間に店頭から消えてしまいました。表計算ソフトは便利ですが、ちょっと便利すぎて図形表示には手軽とは言えない部分があるような気がします。
今私が取り組んでいる古典的Windowsプログラミング+OpenGL 1.1の表示部分は、上述のようにワンパターン化することが出来る感じです。このひな形に普通のC言語の数値計算を入れるだけでかなりの絵が出てくる気がします。