 標高 トマの耳1963m オキの耳1977m 群馬県・新潟県
標高 トマの耳1963m オキの耳1977m 群馬県・新潟県
2008年7月20日(日) 晴れのち曇り  →
→
メンバー 山の神と私
コースタイム 8:05谷川岳ロープウェイ駐車場8:40--熊穴沢避難小屋--9:50天狗の留まり場10:00--10:35肩の小屋10:40--トマの耳--11:05オキの耳(昼食)11:45--西黒尾根--12:45休憩12:55--ガレ沢の頭--ラクダの背--13:48休憩13:58--15:20駐車場
再び8年前の山行記録。この年の海の日3連休に訪れた谷川岳は、すごい人出だったが、谷川岳ロープウェイの利用者は昨年同期の4倍と書かれた読売新聞の切り抜きが保存されていた。どうりで、人だらけだったわけだ。ガソリンが高騰し、日帰り圏のここが好まれたのではとの見方もあったようだ。またその切り抜きには、ミネウスユキソウの写真も掲載されていた。自分が撮影したカットにも同じ花が写っていて、これはミネウスユキソウというのかと、ちょっと勉強になった(下のほうに写真)。


左:天神山へ架けられたリフト 右:熊穴沢避難小屋
4:50珍しく予定よりも早く山の神と自宅を出発する。ガソリンを満タンにし、コンビニで買出しをし高速道へ向かう。関越に入って、まず上郷SAで朝食をとった。その後も順調に走って、8:05予定より早く、予想外に空いている谷川岳ロープウェイの駐車場に入る(¥500)。まだ時間が時間だから、観光客がいないせいだろう。
さてロープウェイに乗って、らくらくと1319mの天神平に到着する。駐車場は空いていたものの、登山者はもう、そこここにいる。天神山でも登って来たのか、軽装で荷物の少ない登山者も見かける。そろそろ行くかと、やおら山の神と天神平駅を後にした。しばらくは楽チンな横移動だけだ。やがて熊穴沢避難小屋の赤い建物が目に入る。日が差さない薄暗い小屋の中を覗くと、休憩している人でいっぱいだった。座れないなと、小屋の外で山の神と水分補給して、先へと進む。


2点とも:登山者でいっぱいの天狗の留まり場
9:50休むにはうってつけの天狗の留まり場に到着する。名前のとおり、岩が積み重なった小高い場所で、天狗が実際にいたら、留まりたくなるような(?)場所だ。よじ登ると、見晴らし良好で風も抜けていき、非常に心地いい。山の神と休憩し、さて登山道に戻ろうかと、降り口を見ると、どっかりと年配のおばちゃんが居座っていて微動だにしない。やれ困ったなと思っていると、誰かが「どけ、どけ」とばかりに念を送ったのか、奇跡的に腰を上げた。



左:西黒尾根への分岐 右:大賑わいだったトマの耳、オキの耳。残念ながらガスっていて展望なし
谷川の双耳峰が近づいてくるにつれ、ところどころで渋滞が発生した。肩の小屋近辺はとくにひどく、登山者でごった返していた。早く行こうと山の神を急かして、まずトマの耳、そして谷川の最高地点、オキの耳に登頂した。記念撮影するのもたいへんなほどの混みようだ。
オキの耳でそそくさと昼食をとり、11:45下山開始する。


左:ミネウスユキソウとピンクのハクサンフウロ 右:ケルンもガスに巻かれる
昼を食べているときから、だいぶガスってきてはいたが、ケルンのあたりで大量のガスが流れてきて、辺りは真っ白になった。かなり視界は悪い。


左:西黒尾根下降中 右:ガレ沢の頭
西黒尾根を下降していくと、だいぶガスがはれてきた。ガスがはれてしまうと、谷がよく見え、結構な高度感だ。高所恐怖症の人は厳しいコースかもしれない。


鎖場嫌いの山の神、必死に下降中
下山を始めて最初の休憩をとった後は、鎖場が連続する。なぜ鎖場嫌いの山の神がこのコースをOKしたのかは、思い出せないが、ついさっき山の神に谷川岳のことを聞くと、あの鎖場だらけのところでしょ、もう2度と行かないときっぱり断言していた。


左:樹林帯まで来てホッと一息 右:蒸し暑い、鬱蒼とした森を進む
鎖場を越えて、樹林帯に入り2度目の休憩をとる。あとは下るほどにどんどん蒸し暑くなり、汗でシャツがネバつく不快さに耐えながら、鬱蒼とした森の中をひたすら歩くことになる。ようやく林道に出て、やれやれとなり、そしてクタクタになって駐車場にたどり着く。目の前にあった自販機で山の神とともに梅ジュースをゲット。一気にほてった体をクールダウンする。
本日のお宿は、湯の小屋温泉、民宿やぐら。 なぜか2人なのに15畳の大部屋に通され、広すぎて落ちつかない。そうはいいながらも、温泉にゆったりつかれば、気分も変わり、まったりとくつろげた。明日は、武尊山麓にある、田代湿原・花咲湿原のお散歩だ。













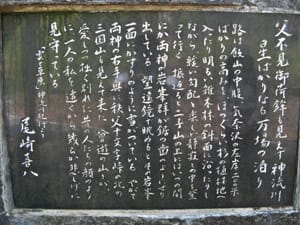























 標高 2,228.1m 群馬県
標高 2,228.1m 群馬県




















