
中公新書の『ふしぎな県境』を読んでいたら、飯豊山(飯豊本山)は福島県であるとのページが出てきた。でも飯豊本山は登っているけれども、たしか山形ではなかったかと思って、自分のブログの記録にあたることにした。検索すると、2001年6月1日に訪れていて、もう18年も前かあと感慨に浸って記録を隅から隅まで読んでしまい、はて何のために検索したんだっけ?となった。そうそう山形県かどうかを調べるためだった。
見ると山形県と福島県と書かれていた。
書いたときのことは何ひとつ覚えていないが、ろくに地図を見もせずにWebで検索して山形県と福島県だと書いたのだろう(山形側の大日杉から入山している)。
『ふしぎの県境』に戻ろう。著者の西村氏は県境フリークで、なぜこうなっているのだろうとだれもが疑問をもつような変わった県境を発掘して本を書いた。なかでも圧倒的にすごいのは、この飯豊山だろう。西村氏が盲腸県境と呼ぶほど、奇妙奇天烈なのだ。新潟県・山形県・福島県の三つの県境にある三国小屋から西へ尾根づたいに1m幅で種蒔山、切合小屋、草履塚、飯豊本山(2105.1m)を経て、尾西小屋まで全長8kmが福島県になっている。
つまりたったの1mの幅で帯状に新潟県と山形県の隙間に福島県が割って入っているのだ。
なぜかといえば、こんな歴史があったからだ。江戸時代に入る直前、会津側の一の木村(いちのきむら)、現在の喜多方市山都町(やまとちょう)からの飯豊の登山道が整備され、飯豊神社の表参道とされた。時代は下って明治。福島県は県庁所在地で揉め、その余波で飯豊山一帯は新潟県に編入されることになる。
しかし福島の一の木村は黙っていなかった。その後新潟側と福島側で綱引きがあり、話し合いでは決着せず、最終的には調停が入って現在の県境が確定したようだ。

この本の著者、西村氏は山のぼらーでもないのに、この県境を自分の目で確かめるために飯豊のお山を目指す。一般登山者はまず行かない鎖場いっぱいの剣ヶ峰を通ってこの尾根に突入していくのだ。


ここまでやるのは、やはり絶対見たい、そこに行ってやろうという執念からだろう。でも彼はこの経験で登山の楽しみを知ったようだから、もうわれわれ山仲間の一員になっているのかもしれない。













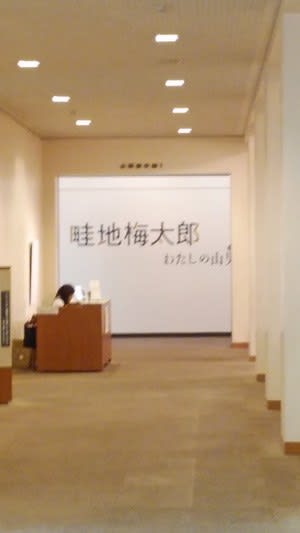
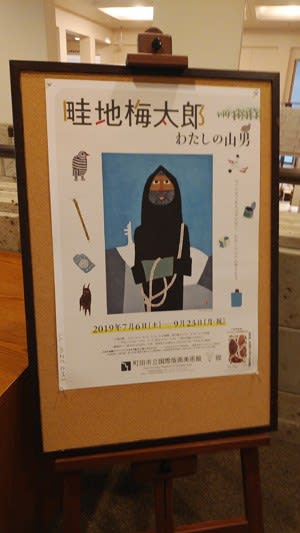
 1Fにはカフェがある。雨が降っていなければテラス席も
1Fにはカフェがある。雨が降っていなければテラス席も











