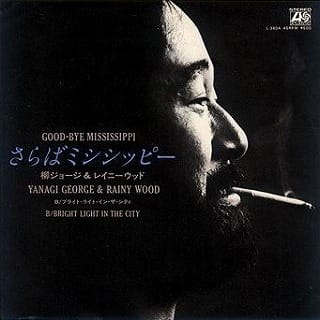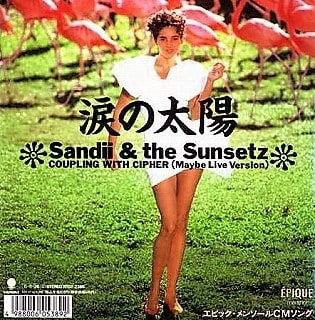■津軽じょんがら節 c/w 黒い瞳 / 三橋美智也&寺内タケシとバニーズ (キングレコード)

大物スタアの夢の競演は、どのようなジャンルでもファンにとっては絶対嬉しいはずで、例え周囲に何と言われようとも、素直に受け入れなければバチアタリだと思うのがサイケおやじの立場ですから、昭和42(1967)年末に発売された本日掲載のシングル盤は、まさにそれっ!
なにしろ、今も人気の津軽三味線を一般に広めた大功労者にして、もちろん津軽三味線の名手たる歌謡界の大スタア! その三橋美智也とエレキギターの世界的名手として知らぬ者もない寺内タケシが、なんとっ!
津軽三味線の所謂曲弾きとして最も有名な「津軽じょんがら節」で競演するというのですから、たまりませんっ!
ご存じのとおり、寺内タケシはエレキギターばかりか三味線やマンドリンをも自在に弾きこなすテクニックと世界を俯瞰した幅広い音楽性を有する天才ミュージシャンであり、また三橋美智也は日本民謡を基調した歌謡曲を十八番にしながらも、実は洋楽センスに満ちた楽曲を多数吹き込み、大ヒットさせた事は、例えば昭和歌謡曲のスタンダード「星屑の町」だけでも、凄過ぎる説得力だと思いますから、「津軽三味線 VS エレクトリックギター」という新旧和洋折衷の大企画にも、なんらの問題はありません。
むしろ、寺内タケシのレコーディングキャリアでは昭和40(1965)年秋に出したブルー・ジーンズ名義のLP「レッツ・ゴー・エレキ節」において、既に「津軽じょんがら節」をエレキギターで弾きまくり、これは翌年春にはシングルヒットもした大名演になっていますし、掲載シングル盤を出す直前にはクラシックの名曲をエレキ化した傑作「レッツ・ゴー・運命」で世界中を驚嘆させていたのですから、いよいよ三橋美智也との夢の対決には、血沸き肉躍るのが当然でありましょう。
ちなみにバックの演奏メンバーは荻野達也(key)、黒沢博(g)、鈴木義之(g)、小野肇(b)、井上正(ds,per) という顔ぶれのバニーズなんですが、アレンジはしっかり寺内タケシ!
そして演奏は、あらためて三橋美智也の三味線のド迫力に圧倒されるのがサイケおやじの最初っからの印象で、それは今も変わりありません。
全然、エレキに負けていないんでよねぇ~~~!?!
しかし、寺内タケシも、やっぱり凄いですっ!
基本的には前述ブルー・ジーンズのバージョンに準じたスタイルではありますが、例の「Terry-sh」なリックの圧巻な響きが野太い録音によって、最高の迫力が感じられる「ロックの音」になっていますよ♪♪~♪
このあたりは互に相手を打ち負かそうという意識よりも、競演を楽しみ、それをリスナーに最良の雰囲気で伝えんとする本物のプロの証かと思うばかりです。
その意味でB面に収録された、これまた有名なロシア民謡を演じた「黒い瞳」は、些かアイディアが空回りしたような、失礼ながら、ちょいと違和感のある仕上がりと思います。
う~ん、津軽三味線でロシア民謡ってのも、なかなかオツなもんですから、もうちょっと正調でもイケたような……。
ということで、最後の最後で不遜の極みも吐露してしまい、反省しきりのサイケおやじではありますが、真夏はエレキ!
なぁ~んて、覚悟(?)を決めてしまえば、グッタリしちゃ~、なんにもならないっ!
ビシッと心身ともにエレキを注入して、明日っからもシビレていこうと思います。