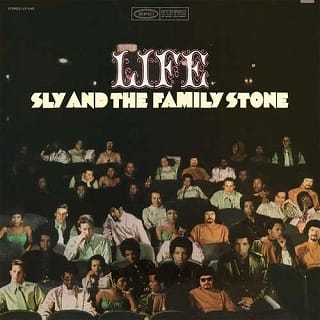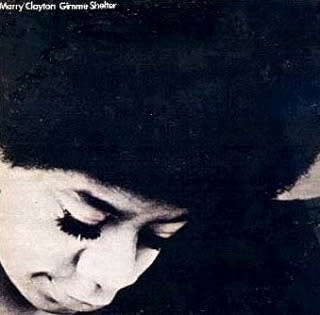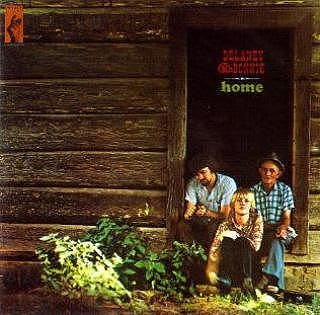■Trying To Live My Life Without You / Otis Clay (Hi)
サイケおやじの洋楽歴は結局、ベンチャーズからのエレキブームとビートルズを端緒とするロックやポップスを源にしているので、所謂黒人ソウルミュージックに関しては同時代に流行っていたモータウンサウンドやその他のR&Bよりも、サイケデリックブームからダイレクトに続いたと思われるニューソウルにシビレていたのが真相です。
もちろんオーティス・レディングやアレサ・フランクリ、レイ・チャールズやサム&デイヴあたりは相当に夢中になって聴いていましたし、ジェームス・ブラウンも、またしかりです。
しかしそれは洋楽ヒットパレードという表の世界の出来事で、実は裏の世界にはディープソウルと呼ばれる黒人R&Bの深~~い奥の細道があり、中でもアメリカ南部系の所謂サザンソウルは恐ろしいほどの魅力!?
それをサイケおやじに気づかせてくれたのが、1973年に世に出たという、本日ご紹介のLPでした。
歌っているオーティス・クレイはミシシッピ生まれというコテコテの南部黒人で、少年時代からゴスペル歌手として活動していたところから幾つかのレコーディングも残しているようですが、世俗のR&Bを歌うようになったのは1960年代中頃、二十代前半の時期だったそうです。
しかしその頃に発売された楽曲はアメリカでも小ヒットでしたから、日本でレコードが出ていたのか否かは知る由もありません。それでもコアなマニアから熱い注目を集めていたのは間違いなく、実は1970年代末になって我国でオーティス・クレイが局地的にブレイクした時、サイケおやじはラジオでそうした初期の録音を聴くことが出来たのですが、そこに強く残されるストロングな余韻からは、まさに本物の良さが痛感されました。
で、サイケおやじがこのアルバムを始めて聴いたのは1975年の事で、既に述べたように当時は黒人音楽といえばニューソウル系に夢中だったんですが、そんなところから知り合いになった年上の友人から、こういうのも凄いもんだよ、と教えられたのが、ディープなサザンソウルの世界でした。
しかも件の友人が私に聴かせてくれたのは、本場アメリカで売られていた45回転のシングル盤がメインのホットなコレクションでしたから、その音の迫力と本物に接しているという感動は筆舌に尽くし難いものがあったのです。
う~ん、思わず唸るサイケおやじ◎!■▲?★♪~♪
当然、忽ち夢中にさせられる世界でした。
しかし、そうしたレコードはその頃、容易に入手出来るものではありません、
そこでアドバイスされ、まずはゲットしたのが、当時は全く知らなかった本日ご紹介のアルバムだったのです。
A-1 Trying To Live My Life Without You
A-2 I Die A Little Each Day
A-3 Holding On To A Dying Love
A-4 I Can't Make It Alon
A-5 That's How It Is
B-1 I Love You, I Need You
B-2 You Can't Keep Running From My Love
B-3 Precious Precious
B-4 Home Is Where The Heart Is
B-5 Too Many Hands
おぉ~、まずはいきなりシビレさせられるのが、A面ド頭収録の「Trying To Live My Life Without You」です。
なにしろ針を落とした瞬間、低い重心のソリッドなドラムスが鳴り響き、完全にツボを刺激してくれるホーンリフに導かれ、グッと苦みの効いたオーティス・クレイのボーカルが表現するのは、所謂メンフィスのスタックスサウンド直系という真っ黒な世界です。
しかも意外なほどにしなやかなリズム隊のグルーヴ、また甘さを含んだギターやキーボードの隠し味が、聴くほどに緻密で力強く、また女性コーラスの華やかな猥雑性も良い感じ♪♪~♪
そして全体から強く滲んでくるゴスペル風味は、隠しようもありません。
もう、この1曲だけで完全KO状態は請け合いですっ!
ちなみに以前にも書いたことがありますが、サイケおやじがこのアルバムに出会ったのと同時期、ロッド・スチュアートがワーナー移籍後の日本独自初シングルとして出した「Three Time Loser」が、なんとこの「Trying To Live My Life Without You」とクリソツな雰囲気!?
結論から言えば、その該当曲のみならず、当時のロッド・スチュアートの元ネタは、このアルバムといって過言ではないほどです。
そのあたりは「Holding On To A Dying Love」や「Home Is Where The Heart Is」でさらに顕著ですし、ストリングスの使い方までも含めて、実はロッド・スチュアートが前述のワーナー移籍後のレコーディングセッションを、その一部ではありますが、メンフィスで敢行されたという経緯も理解出来るところじゃないでしょうか。
ただしオーティス・クレイの歌手としての実力が、完全にロッド・スチュアートを凌駕しているのは、人種的な壁なんか問題にするまでもなく、このアルバムを聴けば納得する他はありません。
特に粘っこいスローグルーヴにおけるハードボイルドな泣きの表現は絶品で、「I Die A Little Each Day」や「I Love You, I Need You」といった、幾分露骨な愛の表現を含む歌詞の世界を苦い悔恨のパラードに仕立て上げる、そのボーカルの力量は最高ですよ♪♪~♪
また、タメの効いたビートを活かす唱法も素晴らしく、「I Can't Make It Alon」や「You Can't Keep Running From My Love」の何気無さを当たり前だと思ったら、完全にバチアタリでしょう。
ですから如何にもサザンソウルらしさが充満した「That's How It Is」や「Precious Precious」に思わずこみあげるものを感じたとしても、それはオーティス・クレイの思うツボ♪♪~♪
ちなみに演奏を担当しているのはティーニー・ホッジス(g)、チャールズ・ホッジス(key)、リロイ・ホッジス(b)、ハワード・グリムス(ds) といった、所謂ハイ・リズムに加えて、1960年代からのメンフィスソウルのキモを作り出していたウェイン・ジャクソン(tp) とアンドリュー・ラプ(ts) が主体となったメンフィスホーンズなんですが、ここではゴリゴリした表現よりも既に述べたように、しなやかさを大切にした、なかなか繊細なバッキングも成功の秘密かもしれません。
と同時に、ストリングの使い方がニューソウル風味に傾いている瞬間が要注意じゃないでしょうか。
そんなところからオーラスの「Too Many Hands」が、かなりファンキーに歌われるのは次回へ続くお楽しみの予告篇だったのかもしれず、実にジャストミートの締め括り♪♪~♪
ということで、全く捨て曲無しの大名盤!
極言すれば、これだけ充実した内容のサザンソウルアルバムは、そう簡単に見つかるものではありません。まさに完全無欠!
ですから1970年代末頃になって我国にサザンソウルのブームが到来した時、このアルバムが「愛なき世界で」の邦題で紹介され、いきなりの優良推奨盤になったのもムペなるかなではありますが、そのきっかけは昭和53(1978)年の来日公演だったと言われています。
残念ながらサイケおやじはそれに接していませんが、実はこの時は既に人気を集めていたO.V.ライトの代役だったという瓢箪から駒!? 真摯で熱いステージは完全に観客を圧倒し、そこから作られたライプアルバムも決定的な名盤になっているほどです。
ちなみに日本でのそうした流行は、やはり局地的というか、ロックファンに比べれば明らかにマニア性感度の高いものでした。
しかしそこに火がついたのは、昭和52(1977)年頃に突如として我国で復刻されたジェームス・カーという黒人歌手が1967年に出したアルバム「ユー・ガット・マイ・マインド・メスド・アップ(Goldwax)」で、これはもう、サザンソウルの全てが集約されている聖典なんですが、ご存じのように、その頃の黒人大衆音楽はブルースにしろ、R&Bにしろ、最初からLPメインで作られていたのは極わずかです。つまりシングル曲の寄せ集めというのが、アルバムの正体でした。
それが1970年代になると、一発のヒットが出ればもちろんのこと、有能な歌手やグループは完全にアルバム中心主義に移行し、例えばニューソウル系のミュージシャンになると、シングル盤を軽んずる傾向さえ表れていたのですから、そんな中で実直にひとつの歌と曲を大切する姿勢が強いオーティス・クレイがブレイクするのは、まさに温故知新だったのです。
そして以降、オーティス・クレイは何度かの来日公演も行い、驚いたことには「いとしのエリー」なんていう歌謡曲さえ歌うほどの人気者になるのです。
まあ、このあたりはレイ・チャールズもやっていますから、なんとも言えませんが、それを非難するファンが多いのも事実です。しかし今も元気で巡業活動をやっているらしいオーティス・クレイが、サザンソウルの魅力を我国に伝えた貢献は否定出来ないでしょう。
そういう分野をこれから聴いてみようと思われる皆様には、本日の1枚を強く推薦させていただきます。